『焔』、『陰謀の日本中世史』、『わたしの信仰』、『先史学者プラトン』……
2018年12月27日
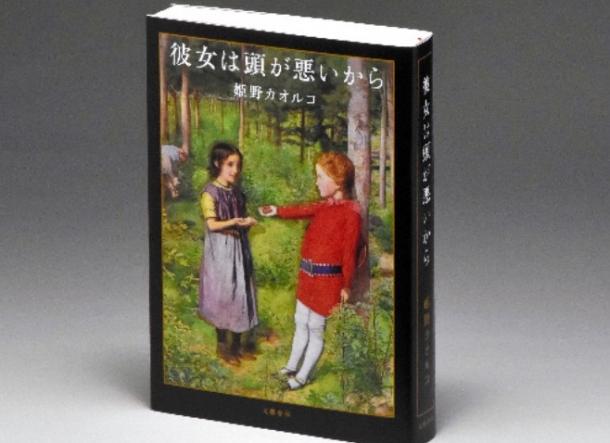 姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』(文藝春秋)
姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』(文藝春秋)大槻慎二(編集者・田畑書店社主)
読書界のみならず、世はドキュメンタリー・ノンフィクションの時代のように映ります。それらの言葉/表現は、ある事件・事態がなぜ出来したかをきめ細やかに〈説明〉してはくれますが、肌が粟立つほど〈感じさせて〉くれるのはやはり小説の言葉だと、今年は以下の3冊によって改めて思い知らされました。
星野智幸『焔』(新潮社)
今年度の谷崎潤一郎賞も受賞して世評高い本書ですが、賞にはおさまりきらないある切迫感を覚える小説群でした。それは現時点の「リアル」が、過去にも、また未来にもどこまでも増殖していくような不気味な強度を備えて目の前に差し出されているからでしょう。
姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』(文藝春秋)
本の立ち姿が「シュッとしている」ので一見そうは見えませんが、43字詰め20行組で本文480頁。およそ1000枚に届く大長編です。そしてこれが「大長編」たる理由は、現代日本においてエスタブリッシュメントというのはすべからく〈ミソジニー〉という1点において成り立っているという事実を、全編を通じてまさに〈感じさせて〉くれるからでしょう。本書を読めば、今年随所で見られた政治家の木で鼻をくくったような態度も、官僚の醜態、なぜにあそこまで卑屈になって忖度するかも、ローラさんへの執拗なバッシングも含めて、辺野古がなぜあんなことになってしまったのかも、同じ1点から来ていることがよく分かります。
辺見庸『月』(KADOKAWA)
『彼女は頭が悪いから』が、実際に起こった東大生5人による強制わいせつ事件を下敷きにしているように、本書は相模原の障害者施設で起こった大量殺人事件に触発されて書かれています。たまに日中の住宅街を歩いていると、あまりの静けさにぞっとすることがあります。そうした静謐のなかにうごめく狂気をこれほどに正確に捉えている作品は他になく、近年の詩作によってますます磨きがかかった語彙のほとばしりがかえって沈黙を、その語彙がもたらす色彩の豊かさがかえって乳白色の怖さを表出しています。
[書評]『月』
奥 武則(ジャーナリズム史研究者)
今年は岩波新書が生まれて80年。関連の企画広告などを目にした。いまや「新書」を名乗る出版物は世にあふれている。当然、玉石混淆である。以下の3冊は間違いない「玉」である。その道の専門家が研究の蓄積を踏まえて一般読者向けに執筆した力作といっていい。こういう本を比較的安い定価で手に入れられるのだから、新書花盛りは悪くない。ただし、量からすれば、「石」の方が断然多いのでご注意を。
呉座勇一『陰謀の日本中世史』(角川新書)は、『応仁の乱――戦国時代を生んだ大乱』(中公新書)が大ヒットした中世史家の著作。世にはびこる似非歴史家たちの数々の陰謀論を確かな史料によって論破する。本物の歴史学の強さを教えてくれる。「本能寺の変」に“黒幕"はいなかったし、関ケ原合戦は家康の陰謀ではないのである。終章「陰謀論はなぜ人気があるのか?」は、一つの学問論としても読める。
 服部龍二『高坂正堯――戦後日本と現実主義』(中公新書)
服部龍二『高坂正堯――戦後日本と現実主義』(中公新書)井手英策『幸福の増税論――財政はだれのために』(岩波新書)は、「弱者を助ける社会」から「弱者を生まない社会」への転換を構想する財政社会学者の渾身の書である。「はじめに」に本書執筆のねらいが端的に述べられている。「自由を愛し、リベラルな社会を追い求めるあなたへ」と題された部分に共感した。「僕はみなさんの仲間だ」と言いつつ、著者は「自由の条件整備を棚あげにしながら、自由を語る僕たちとはいったいなんなのだろう」と自問する。生きていくためにだれでもが必要とするベーシック・サービスを提供するために必要な財源を国民みんなで担う社会。これが著者の目指す社会のあり方である。歴史家の安丸良夫の「通俗道徳」論から出発し、多くの国際比較のデータを参照しつつ展開される著者の未来構想に、私はほぼ納得した。
駒井 稔(編集者)
アンゲラ・メルケル著、フォルカー・レージング編、松永美穂訳『わたしの信仰――キリスト者として行動する』(新教出版社)
EU最強の国家・ドイツを率いるメルケル首相とはどんな人物か。彼女は原発からの離脱をいち早く宣言し、難民を積極的に受け入れることを表明してきました。今、その去就が注目されるメルケルの行動は我が国でも広く報道されてきましたし、東ドイツ出身であり、牧師の娘であることもよく知られています。しかし、本書を読むまでは、メルケルの拠って立つ思想的基盤について、何も知らなかったことに驚きました。キリスト者(プロテスタント)として、その内面の深奥から生みだされる言葉は、政治家のものとは思えない誠実さと深さを湛えています。ひと言で言えば、メルケルは現代には珍しい理想主義者なのです。講演やインタヴューなど16編を収録した本書では、高齢化社会のあるべき姿、新自由主義経済の限界、デジタル社会の未来など喫緊の課題が取り上げられ、ヨーロッパの、そして世界の未来を考えるすべての人たちにとってたくさんの学びがある一冊と言えるでしょう。
貴堂嘉之『移民国家アメリカの歴史』(岩波新書)
他国で抑圧された人々を受け入れ、その多様性を生かして繁栄してきたのがアメリカである――。本書を読むと、そういう「移民国家」としてのアメリカは、いささか美化されてきたきらいがあることがよく分かります。従来から語られてきたヨーロッパからの移民の物語とは大いに異なる、中国や日本などのアジア系移民に焦点を当て、専門家以外にはほとんど知られていなかった彼らの苦難に満ちた歴史を克明に描いていく様は、まさに圧巻の一語に尽きます。詳細なデータを基に展開されるアジア系移民の歩みを読み進むうちに、移民とは何か、アメリカとはどういう国かという、きわめて根源的な問題が語られていることに気づかされるのです。
内田樹編著『人口減少社会の未来学』(文藝春秋)
日本の総人口は21世紀末には6000万人になるという予測もあります。大量の外国人労働者の受け入れが必要となり、移民についても、ついに具体的に語られる時代になってきました。しかし本書で内田樹さんが警鐘を鳴らすように、私たちは確実に起こる将来の事態に対して、きちんと考えることができているのでしょうか。「破局的事態」は考えないことにするという日本人の持つ思考的欠陥から自由になったのでしょうか。政治学的、経済学的アプローチはもちろん、建築家や演劇人まで、さまざまな分野の専門家たちが、急激に進む少子高齢化社会の未来について語る本書は、実に貴重な示唆に満ちています。
[書評]『人口減少社会の未来学』
松本裕喜(編集者)
メアリ・セットガスト『先史学者プラトン――紀元前一万年―五千年の神話と考古学』(山本貴光・吉川浩満訳、朝日出版社)
ほとんど知らないことばかりの先史時代の考古学の面白さもさることながら、石器や土器、岩壁画や洞窟画などから切り抜いた図像の見せ方がすばらしい。註(本文の解説)と注(出典)の扱い、図版のページも示した索引など、よく工夫された本づくりに感心した。
[書評]『先史学者プラトン』
池内了『司馬江漢――「江戸のダ・ヴィンチ」の型破り人生』(集英社新書)
目次に続けて「司馬江漢略年譜」「著作一覧」を置き、各章の扉に江漢の自画像、熱気球や天動説・地動説のスケッチを掲載するなど、行き届いた編集だと思った。油絵・銅版画から窮理学・天文学まで、まさにダ・ヴィンチ的な江漢の活動が生き生きと描かれている。新書タイプの評伝の一つのスタンダードとなる本ではないだろうか。
[書評]『司馬江漢』
鹿野政直『沖縄の戦後思想を考える』(岩波現代文庫)
2011年に出た本の文庫化だが、戦後の沖縄の人びとの思想的営為について多くのことを教えてくれる本である。普天間基地撤去の問題を前にして著者が法政大学沖縄文化研究所で行った講義がもとになっている。20万人余が犠牲になった沖縄の戦闘、日本国憲法の埒外に置かれ自治も人権も無視された米軍の沖縄支配、1960年代から盛り上がった復帰運動の中から生まれた「日本を問い返す」思想、「反復帰の思想」、「沖縄の根の意識化」、そして1972年の占領の終結と現在までの沖縄の人びとの声(思想)が、おびただしい文献の紹介とともに丁寧にたどられている。しかし復帰後、基地の島としての沖縄の位置はどれぐらい変わったのだろうか。沖縄に戦後はあるのか、米軍による沖縄占領は復帰後弱まるどころかむしろ強化されているとの議論もあるようだ。いま現在も辺野古には大量の土砂が投入され、海は黄色く染まっている。ほかに選択肢はないとして辺野古への新基地建設が次々に進められてゆく現状に違和感を覚える人に、ぜひ読んでいただきたい1冊だ。
ほかに谷岡亜紀『言葉の位相――詩歌と言葉の謎をめぐって』(KADOKAWA)は、あまり編集がなされていない(と言っていい構成の)本だが、文語と口語、旧仮名と新仮名など短歌・俳句の実作者が直面する日本語の表記をめぐっての考察が面白かった。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください