『私はすでに死んでいる』、『除染と国家』、『みな、やっとの思いで坂をのぼる』……
2018年12月29日
中嶋 廣(編集者)
長谷川郁夫『編集者 漱石』(新潮社)
著者の長谷川郁夫さんは、およそ10年前に自ら編集者学会を立ち上げ、初代会長に就いた。その意味が解っているのは長谷川さんだけだった。それは『編集者 漱石』を読めばわかる。数頁読んだとき、私は思わず横っ面を張られる思いがし、頭がくらくらした。長谷川さんによれば、「近代文学の出発から二十年。成熟期に向う文藝の新時代にもとめられるものは何か、を漱石は知悉していたのである」。そしてそれは漱石だけが知っていた。漱石が死んで100年たったとき、長谷川さんが現れて、そういうことを読み解いたのだ。用いたのは、荒正人の『漱石研究年表』、あるいは夏目鏡子の『漱石の思ひ出』といったよく知られたテキストだ。それが読みに応じて、これほども変わるものか。そういう点でテキストの読み方は、実は創造性に富むものなのだということがわかる。これは何度も読み返すに値する本だ。
[書評]『編集者 漱石』
内田洋子『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』(方丈社)
本を売ることを稼業にした、イタリア・モンテレッジォ村の歴史。エッセイだがメルヘンの趣もある。謎は謎を呼び、ではないけれど、深みにはまっていくミステリー仕立ての濃厚な香り、もうたまりません。しかし最後まで読んだとき、著者が最も気にかけているのは、モンテレッジォの魂が、日本の出版人になお宿っているかどうかなのである。この本はカラー図版満載だがネームはない。本文と図版が実に微妙に絡み合っていて、こんなことは初めてだ。本作りにも冒険がある。
[書評]『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』
アニル・アナンサスワーミー著、藤井留美訳『私はすでに死んでいる――ゆがんだ〈自己〉を生みだす脳』(紀伊國屋書店)
現代の神経科学者に突きつけられる問い、「私はもう死んでいます。精神は生きているけど、脳は自殺未遂をしたときに、死んだのです」。コタール症候群においては、デカルトとは逆に、「我思う、ゆえに我なし」なのである。あるいは身体完全同一性障害(BIID)では、患者はとにかく手や足を死ぬほど切り落としたいのだ。つまり身体の内部感覚と、現実の身体にズレが生じている。こんな例が全部で8章分、読み終わると、人間の輪郭が少しボヤけて違って見える。
[書評]『私はすでに死んでいる』
堀 由紀子(編集者・KADOKAWA)
スティーブン・レビツキー、ダニエル・ジブラット著、濱野大道訳『民主主義の死に方――二極化する政治が招く独裁への道』(新潮社)
今年もっとも印象深かった本。本欄でも紹介したが、民主主義が「相互寛容」と「組織的自制心」の2つという、言ってみれば心の持ちようのようなものに護られているという事実に衝撃を受けた。現在、世界各地で見られる自国第一主義政党のカリスマ的な指導者が台頭しているが、わずか100年の間にもそういった事例はあちこちにあった。歴史は繰り返すという当たり前の事実を本書は多くの事例とともに教えてくれる。歴史から学び、それをどう生かすかを考え続けたい。
[書評]『民主主義の死に方』
原雄一『宿命――警察庁長官狙撃事件 捜査第一課元刑事の23年』(講談社)
オウム真理教の一連の犯罪のなかでも、あやふやな結末だった警察庁長官狙撃事件。そこにこんな事実があったとは! 元刑事による、当事者だからこそ書ける極上のノンフィクション。本文では、事件を追っていたときの著者の感情や考えは、あまり書かれていない。淡々としたその筆致が物足りない気もしたが、一転、あとがきは短いながらも情熱があふれている。本文の書きぶりは「事実を提示するので公平な視点で読んでほしい」という著者からのメッセージだったのかもしれないと思うと、より感慨深かった。警察という権力組織についても思いを巡らせた。警察は「犯人」とした人を犯人にするために「証拠集め」をする組織なのだろうかと暗澹たる思いがした。清水潔さんの『殺人犯はそこにいる――隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件』(新潮社)でも書かれていたが、警察は、「犯人」を犯人にするのに全力を尽くし、その後真犯人が見つかっても見つかったと言わない。本書の著者のように、現場に真実を追いかける刑事がいることがわずかな希望だと感じた。
日野行介『除染と国家――21世紀最悪の公共事業』(集英社新書)
福島第一原発事故の除染に懐疑的な思いを持っていた。本当に効果があるのだろうか、と。その疑問に答えをくれ、除染という公共事業の幻想を書き切っているのが本書だ。著者は毎日新聞で原発報道をリードしてきた記者。非公開の資料を独自のルートで手に入れ、匿名の関係者から証言を得て、隠された真実を掘り起こしていく様は、推理小説を読んでいるようにおもしろい。また、取材相手に直当たりし、核心の事実をぶつけるというハードボイルドさにもしびれてしまった。本書では、行政が公文書を意図的に作成しなかったり、改ざんしていることが明らかにされている。あれ? どこかで聞いた話だ。日本は中央のみならず、地方でもこんなことが普通になってしまっているのだろうか。2016年末までに2兆6000億円もの国費が投じられ、いったん終了した除染。その結果として、福島県には東京ドーム18杯分の汚染土があるが、行き先は決まっていない。本書の中で著者は、問題の風化を危惧しているが、一市民としてこの問題に関心を持ち続けたいと思う。
渡部朝香(出版社社員)
今年、石牟礼道子さんが亡くなられた。多くの人と同じく、私も『苦海浄土』に水俣病を教えられた……つもりでいた。永野三智さんの『みな、やっとの思いで坂をのぼる――水俣病患者相談のいま』(ころから)を読み、自分の無知に打ちのめされた。私よりだいぶ年下の永野さんは、水俣病の患者さんや家族の相談を受ける仕事をしている。家族にも病を言えぬ人。申請をためらう人。40代の患者もいる。症状は年々悪化する。2010年代の今現在のことだ。永野さんは無力を痛感しながら、石牟礼さんの「悶え加勢する」という言葉を励みに、彼らとともにあろうとする。交感を記録する永野さんの言葉は、ゆらぎも含め、確かな感触をもって届く。誰しもが水俣病と、近く遠く接している。
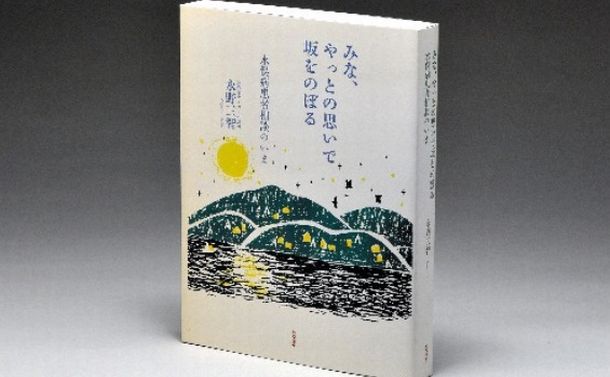 永野三智『みな、やっとの思いで坂をのぼる――水俣病患者相談のいま』(ころから)
永野三智『みな、やっとの思いで坂をのぼる――水俣病患者相談のいま』(ころから)巧みな創作だからこそ、真実に迫る言葉もある。三浦しをんさん『ののはな通信』(KADOKAWA)は、60年代末生まれの少女二人による、書簡体小説だ。お嬢様学校での恋。秘密。繊細な描写と、驚きの展開。そして、別離を経て、二人はメールで交流を再開する。ライター、外交官夫人となった中年の彼女たちは、それぞれのやり方で大きな世界に立ち向かう道を選ぶ。彼女たちだけではない。私たちはみな、個人的な経験を重ねながら、自分だけが知る傷や慰めを胸に、この世界に対峙せざるをえない。誰のものでもない自分を生きるしかない。
チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子訳、筑摩書房)は、多重人格症を発症したかに思われる33歳のキム・ジヨンの半生を描く。そこで露わになるのは、女性が直面するあらゆる差別や困難。一人の女の中に、多くの女の声がこだまする。韓国でベストセラーとなった本書に、日本でも多くの読者が、自分を、母を、親戚の女たちを、知人や友人を、見いだしている。帯の松田青子さんの言葉が素敵だ。「女性たちの絶望が詰まったこの本は、未来に向かうための希望の書」。今年報じられたいくつかの女性差別は、これまであったものの一部が可視化されたにすぎない。でも、もう、あともどりはない。女たちが声をあげ、女たちを励ます本が多く出版されたことは、2018年の大きな特徴だろう。今年、私が原稿をいただいた方を数えてみたら36人。そのうち女性が22人だった。そこからも何かの兆しを読みとれるかもしれない。女性が生き難さを負わせられていることに向きあうことは、さまざまな困難を抱える人たちとともに生きることにつらなっている。私たちは一人だけど、一人じゃない。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください