やまとことば(和語)による造語
2019年06月18日
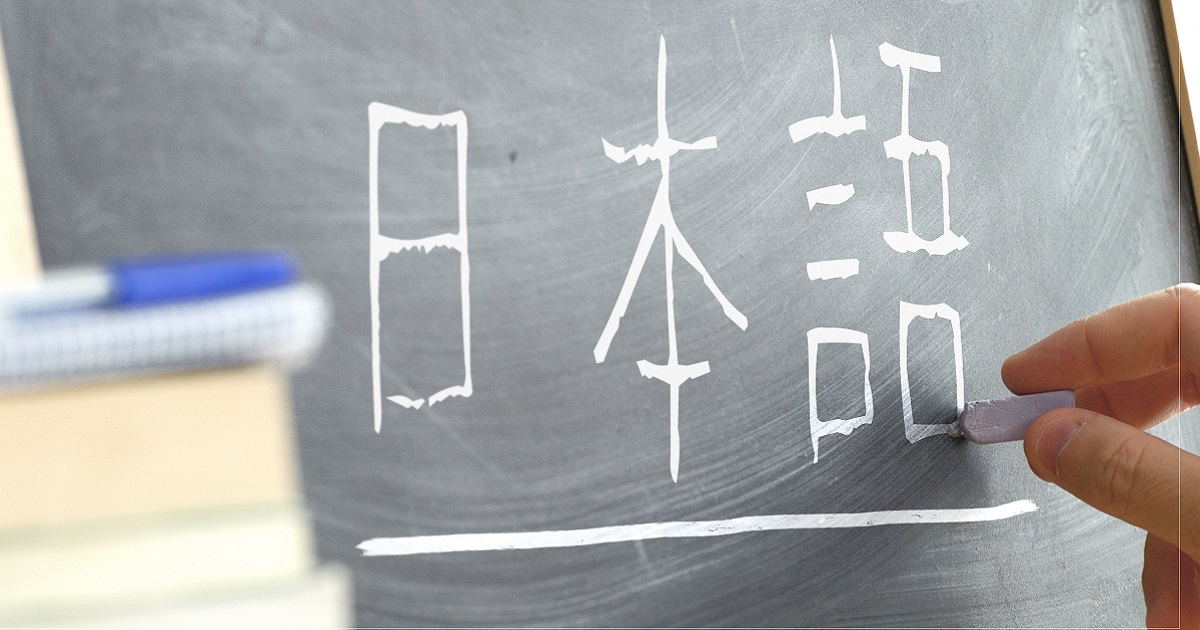 日本語は「国際語」としては問題が多い Photo: Juan Ci/Shutterstock.com
日本語は「国際語」としては問題が多い Photo: Juan Ci/Shutterstock.com日本語については歴史的な事情から、まず文字について論じなければならなかった。だが言語を問う場合、音の側面こそ重視されなければならない。文字をもたない(もたなかった)言語はあるが、音をもたない言語はない。
すでに漢字の問題性として論じたが(前稿)、増えすぎた同音異義語を聞いてわかるように区別できるのでなければならない。いまそれらを、ますます増える外国人・移民のために、全面的もしくは部分的にやまとことば(以下「和語」と記す)に置きかえる必要がある。漢語(音読み)の単語・合成語についても同様である。
この150年、私たちは造語のほとんどを漢字に頼ってきたが、和語自体の造語力を高める努力をすべきであろう。
これを論じた人は少なくない。井上ひさしは「アカルイ」という形容詞がどのように名詞、動詞になったかにふれ、かつ同じ語源と思われる単語を列記し、それらから造られた熟語を示しつつ、日本語の造語力の「旺盛」さにふれていた(井上「国語事件殺人辞典」、『國語元年』新潮文庫所収、26-7頁)。また田中克彦は、日本語をローマ字書きすることで、造語法がもっと広がる可能性があることを示唆した(田中『漢字が日本語をほろぼす』角川SSC新書、93頁)。
いま私たちは、可能なかぎり和語で造語をし、漢語を和語に置きかえる努力をおしむべきではなかろう。これなしには日本語は「国際語」にならない。
私は現時点にあって、和語の造語法のうち、前稿の「ふりこみ」「わかちがき」等に見られる造語法を重視したい。つまり動詞の連用形は、名詞となって他の名詞・動詞等との造語に利用できる。
例えば「防波堤」「盲導犬」。この方式で造語すれば、それぞれ「ふせぎづつみ」「みちびきいぬ」である。
私たちがこれらの言葉を初めて聞いた(見た)ときのことを、思い出してもらいたい。それぞれ「波を防ぐつつみ」(若い人なら「つつみ」ではなく「堤防」か?)、「目の見えない人を導く犬」と、漢語を訓読み(和語)で読んで理解したはずである。それなら始めからそう言えばよい。
ただし和語は、音韻構造が単純なため長音節語となる傾向がある。だから先のように核心のみをとりだした。あるいは前者は、少し特定して「なみのつつみ」でもよい(何やら近松の『堀川波鼓(ほりかわなみのつづみ)』を思い出しそうな)。またいずれも動詞連体形を用いて「ふせぐつつみ」「みちびくいぬ」でもよいが、その発音には2カ所に高い音が現れ、熟語としての安定性に欠ける(金田一春彦『日本語』岩波新書、92、94頁)。
上の例で連用形が純然たる名詞につくのは奇妙に感じられたかもしれないが、これが可能なのは、連用形自体が名詞として機能しているからである。実際この種の語法は、古くから広く見られる。思いつくままにあげる。「入り鉄砲に出女」「ぬれ手」「生き地獄」「書きことば」「悩みごと」「たかり屋」「いじめ(っ)子」「共働き世帯」「落ちこぼれ研究者」(最後3例の連用形は野村雅昭『新版 漢字の未来』三元社、136頁から)。
なお、類似した単語が和語にあれば漢語は不要である。「ねたみ」があるのに「嫉妬」を使う必要はなく(「女偏・女部を含む漢字や日本語にひそむ女性差別」)、また「つれあい」という、多少古めかしいが分かりやすく、かつ男女平等を含意する言葉を使えば、「(ご)主人」はいらない(後述)。
漢語は一部分を和語化するだけでも、外国人に分かりやすくなる。
例えば、最近目(耳)にする例で言えば「見える化」。「化」は、「可視化」のように一般に漢語につくが、これを和語の動詞終止形――名詞には漢語・外来語が多いが動詞の基本は和語である――につけたのは、和語による造語の可能性を広げた点で秀逸である。
これが一般に応用できるかどうか不明だが、動詞の連用形(前述)を使うことはできる。「老い化」、「変わり化」、「浄(清)め化」、「退き化」、「進み化」、「鈍り化」、「弱り化」等。今は奇妙でも、使い始めればすぐにふつうの熟語になるだろう。
日常生活に不可欠な例でいえば、歯(し)科、眼科、小児科は、「は科」、「め科」、「こども科」がよい(田中前掲『漢字……』28頁)。これは漢語の和語への置きかえによるが(耳鼻科も「みみはな科」でよい)、いずれも自然でありかつ分かりやすい。
可能なら「化」も「科」(これは生物種を示すカテゴリーでもある)も和語にしたいが、どちらも造語単位として長きにわたって用いるしかないのかもしれない。
イギリス語(英語)の国際化は、20世紀後半以降ますます顕著である。だが英語には、「国際語」としてふさわしくない女性的・人種差別的な単語・表現が多すぎる。
ことばは人がつくったが、一方ことばは人をつくる。ある言語を母語として身につけると、それに含まれる見方・感じ方を話者は内面化する傾向がある。そこから自由な人もいようが、一般にはそれは容易ではない。
英語を自覚なしに身につければ、何事かを悪く評価する場合、blackやyellowという扇情的で人種差別的なことばが往々口をついて出る。日本でも最近その悪影響が
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください