2019年07月05日
今年4月からこの「神保町の匠」も中身が変わった。2008年に三省堂書店の書評サイト「神保町の匠」(2014年から「三省堂書店×論座 神保町の匠」)としてスタートして10年余、書評のスタイルではネットではあまり読まれないので出版・書店・書き手など本の周辺の話題を書くことにしてはどうかとの「論座」担当者の提案を受けてのリニューアルである。
ネットで検索してみると、「書評ブログは読まれない」という記事が結構ある。
ネットだけではない。新聞書評もそれほど読まれないという。2003年から設けられていた毎日書評賞(2013年からは毎日出版文化賞書評賞)も2016年にはなくなっている。本そのものが読まれなくなっている現状が背景にあるが、本好きにとって書評は大切な読書の指針であるはずだ。なぜ書評は読まれないのだろうか。
丸谷才一『快楽としての読書 日本篇』(ちくま文庫)によれば、新聞・雑誌の書評の目的は第一に読者がどんな本を買い・買わないかを決めるための買物案内である。そのため書評はまず信頼されなければならない。そして信頼されるためには書評者の知名度などの要素もあるが、何よりもしっかりした文章、芸のある語り口、バランスの取れた評価など、その書評の書き方から受け取る感じが大事だという。
不特定多数の人が書く書評ブログはこの信頼感に欠けるかもしれない。
では新聞書評はどうか。
今年4月27日付の「朝日新聞」に目を疑うような書評があった。
見出しは「重ね刷りがアートに昇華する時」。『美術は魂に語りかける』(アラン・ド・ボトン、ジョン・アームストロング著、ダコスタ吉村花子訳、河出書房新社)という本の横尾忠則の書評である。書評文の上にわざと印刷の工程で出てくるヤレ(重ね刷り)を重ね、読めない状態にしている。どんなことが書かれた本なのか、全くわからない。ふつうに読める状態で印字された「好書好日」でその書評を読んでも、美術理論の本なのか、哲学的な本なのか、癒し系の本(原題は「セラピーとしてのアート」)なのか、もう一つわからなかった。
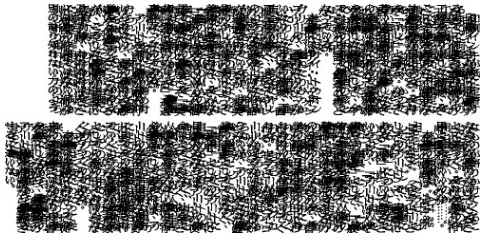 『美術は魂に語りかける』(アラン・ド・ボトン、ジョン・アームストロング著、河出書房新社)の横尾忠則氏による書評=2019年4月27日付「朝日新聞」
『美術は魂に語りかける』(アラン・ド・ボトン、ジョン・アームストロング著、河出書房新社)の横尾忠則氏による書評=2019年4月27日付「朝日新聞」丸谷も指摘するように新聞の読者は、まず読書案内として書評を読むのではないだろうか。そういう読者にとって、どんな本なのかわからない書評は困る。何人かにこの記事を見せて意見を聞いてみたが、知らないか気にかけていない人が多かった。この書評は書評欄に耳目を集めようとする思いきったパフォーマンス(美術家と編集者の合作?)とみるべきなのかもしれないが、それほど注目を集められなかったようだ。
 本が好きな人にとって、書評は本来愉しい読み物なのだが…… Photo: Rawpixel.com/Shutterstock
本が好きな人にとって、書評は本来愉しい読み物なのだが…… Photo: Rawpixel.com/Shutterstock同じ日の書評欄の『平成の終焉――退位と天皇・皇后』(原武史、岩波新書)の呉座勇一の書評は新鮮だった。この本の中身を評価したうえで、「天皇皇后らの考えをうかがえる資料は限られるため、踏み込みすぎに思える解釈も幾つか見られた」と最近の書評欄では珍しく批判があったからだ。
いつ頃からかわからないが、批判的に本を紹介することが少なくなったような気がする。
30年ぐらい前の話だが、勤めていた会社の女性編集者が自分の編集した本の「編集がずさん」と指摘した「朝日ジャーナル」の書評の執筆者に電話して、「どこがずさんなんですか」と問いつめていた。いきなり電話をかけてこられた書評者は困っただろうが……。
豊﨑由美『ニッポンの書評』(光文社新書)を読むと、新聞書評では批判は許されず、批判しても差し替えられるという(巻末の大澤聡との対談)。また新聞書評の分量は800字から1200字で、根拠をあげて批判するには字数が足りないとも指摘する。
呉座の書評でも「踏み込みすぎに思える解釈」の具体例は示されていないが、それを書いていてはこの本の中身を紹介できなかったろう。
「神保町の匠」でも初めのころ取り上げた本の著者から抗議を受けたことが二度あった。いずれの書評にも文中に著者をからかうというか揶揄するような文言があったためと思える。正面からの批評・批判なら、抗議は来なかったのかもしれない。
少し古い話だが、2004年冬から2014年夏にかけて出た『いける本・いけない本』(21号まで、非売品)は「どうも新聞書評が面白くない、それならいっそ……」と人文系の編集者が集まって出した書評誌だった。メインの記事は「いける本・いけない本アンケート」で、20人前後のメンバーが半年間に出たおすすめの3冊、異議のある3冊をあげ、100字前後でコメントした。
このアンケートで面白かったのは、「いける本」であがった本を別の人が「いけない本」にあげていることがよくあったことだ。
以下、「いける本」「いけない本」で重複した本をあげてみる(年度は「いける本・いけない本」で紹介された年)。
2005年、柴田哲孝『下山事件―最後の証言』(祥伝社)
2006年、カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』(早川書房)
2007年、東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』(講談社現代新書)、パオロ・マッツァリーノ『つっこみ力』(ちくま新書)、東浩紀・北田暁大『東京から考える――格差・郊外・ナショナリズム」(NHKブックス)、四方田犬彦『先生とわたし』(新潮社)
2008年、(重複なし)
2009年、水村美苗『日本語が亡びるとき――英語の世紀の中で』(筑摩書房)、鶴見俊輔・上坂冬子『対論・異色昭和史』(PHP新書)、小熊英二『1968―(上)若者たちの叛乱とその背景、(下)叛乱の終焉とその遺産』(新曜社)、川上未映子『ヘヴン』(講談社)、加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(朝日出版社)
2010年、橋本治『失われた近代を求めてⅠ――言文一致体の誕生』(朝日新聞出版)、柄谷行人『世界史の構造』(岩波書店)、村上春樹『1Q84 BOOK3』(新潮社)
2011年、中井久夫『災害がほんとうに襲った時――阪神淡路大震災50日間の記録』(みすず書房)、山本義隆『福島の原発事故をめぐって――いくつか学び考えたこと』(みすず書房)、金原ひとみ『マザーズ』(新潮社)
2012年、三浦しをん『舟を編む』(光文社)、井上理津子『さいごの色街 飛田』(筑摩書房)、佐藤信『60年代のリアル』(ミネルヴァ書房)、ドナルド・キーン『正岡子規』(角地幸男訳、新潮社)、孫崎享『戦後史の正体――1945―2012』(創元社)
2013年、開沼博『漂白される社会』(ダイヤモンド社)、村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋)
2014年、田澤耕『〈辞書屋〉列伝――言葉に憑かれた人びと』(中公新書)、佐々木健一「辞書になった男――ケンボー先生と山田先生」(文藝春秋)
以上だが、「いけない本」にあげた理由は、テーマや著者に期待して読んだものの期待が外れたというもの、本の仕立てかたに疑問を呈するものが多かった。
本の仕立てかたで言えば、2011年の『災害がほんとうに襲ったとき』『福島の原発事故をめぐって』を私はこの著者の本としては安易な本づくりと批判したが、3・11東日本大震災を目の前にして、版元も著者もあまり厚くない本で、値段を安くし、早く出版することを選択したのだろう。いまとなってみると、その判断のほうが正解に思える。
このように「いける本」「いけない本」の分かれ目も微妙なところがある。長田弘は『本という不思議』(みすず書房、品切)で、「本というものはおもしろいもので、どんな本も読み手とおなじ背丈しかもたない。読み手がこれだけであれば、本もまたこれだけなのです」という。確かにその本をどう理解するか、どう味わうかは読み手にかかっている。また同じ本を読んでも読む時期によって本の印象がガラッと変わることもある。
現役の編集者だったとき、一番つまらないのは、自分が手掛けた本が褒められも貶されもせず、無視されることだった。本を出す側から見れば、たとえ批判があっても書評に取り上げられること自体が一つのパブリシティー(広報)である。
新聞・雑誌の書評はよく本になっている。本好きには書評そのものが愉しい読み物なのだ。ただ取り上げられた本自体が古くなってしまうので、ロングセラーになる本は少ないようだ。その中で、いま読んでも面白い本を紹介してみよう。
丸谷才一『快楽としての読書 日本篇』『快楽としての読書 海外篇』(ちくま文庫)は「週刊朝日」「毎日新聞」に載った丸谷の書評からなり、書評の醍醐味を十分に味わわせてくれる本である。内容紹介がうまいので、書評だけで読んだ気になってしまいがちだが……。
 新聞や週刊朝日などで多くの書評を書き続けた丸谷才一氏=1968年
新聞や週刊朝日などで多くの書評を書き続けた丸谷才一氏=1968年角幡唯介『探検家の日々本本』(幻冬舎文庫)は雑誌やブログに載せた読書日記をまとめたものだが、「人生をつつがなく平凡に暮らしたいなら本など読まない方がいい。しかし、本を読んだほうが人生は格段に面白くなる」とまっすぐに本と向きあう。本との出会いは、人との出会いに似て、どこでつながって来るかわからないという。読書についていろいろ考えさせてくれる本である。
荒川洋治『過去をもつ人』(みすず書房)は「毎日新聞」の書評と読書にかかわるエッセイを収める。「高見順の文章は、簡明だ。ことばを飾らない。だいじなところでは、数少ないことばだけをつかう。それを向きあわせたり回転させたりして進む。文の節理が、とてもきれいだ」という具合。磨きぬかれた言葉による鑑賞が心地よい。「本らしい本を読む人は少ない。読書が消えた時代だ」との批判もある。
津野海太郎『最後の読書』(新潮社)では晩年の鶴見俊輔の読書が紹介されている。2011年脳梗塞で鶴見は話すことも書くこともできなくなったが、それから3年半本を読み続けた。津野はこれを「なにかのためではなく、じぶんひとりの『習う手応え』(幸田文のことば)や『よろこび』を得るためだけの読書」という。なんとも素敵な読書ではないだろうか。
本を探しやすい中規模の書店が減って、書店にふらりと入って気に入った本を見つけることが難しくなってきている現在、水先案内人としての新聞書評の役割は大きくなっている。批判も遠慮なく盛り込んで、魅力あふれる書評欄をつくってほしいものである。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください