問題非公開の民間試験、透明性に疑問
2019年09月25日
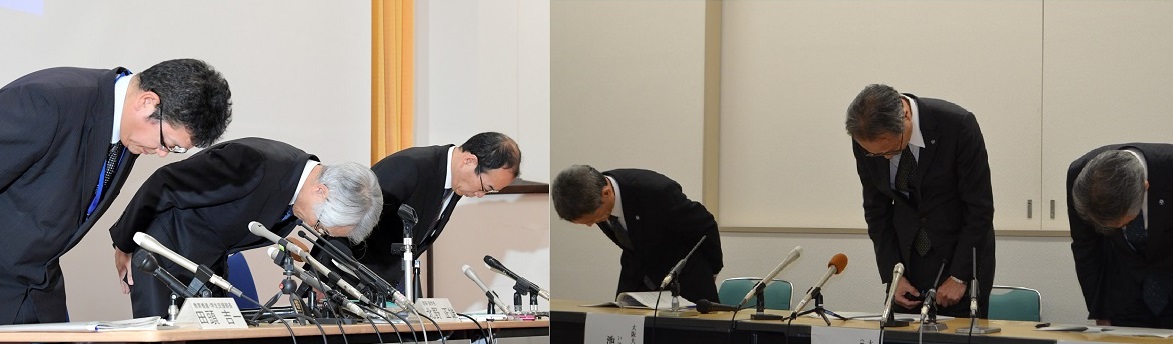 入試問題にミスがあったことを認め、謝罪する京都大学(左)と大阪大学の記者会見=2018年
入試問題にミスがあったことを認め、謝罪する京都大学(左)と大阪大学の記者会見=2018年新しい大学入試での英語民間試験の導入は問題が多すぎる。あまりに多すぎて、一つひとつ扱っていると、かえってわからなくなってしまいそうだ。ここではざっくりと、私たちが掲げる社会の価値観から、いやいや、そんな硬い表現ではなく、「当然だよね」と思っているところから考えてみたい。
前回は公平性の観点から疑問を提示した。今回は公開性、透明性の観点から。
覚えている方も多いと思うが、一昨年、大阪大学と京都大学の入試で相次いで出題ミスがあった。両大学はミスを認め、追加合格者を出し、新聞やテレビは大きく報道した。入試における出題ミスの重さ、責任の大きさ、事後の対応の大事さをあらためて知る出来事だった。
なぜ出題ミスがあったとわかったのか。
それは、阪大と京大が実際に出題した入試問題をすぐに公開していたからだ。そのため高校や予備校の先生たちが公開された問題を検証することができ、ミスを見つけ、大学側に指摘したからだ。もし大学が問題を公開していなかったら、ミスは見つけられないままで、本当は合格していた受験生が落ちたままだったかもしれない。
問題が公開され、社会の目にさらされることで保証される、試験の透明性。英語の新入試では、そこに疑問がある。
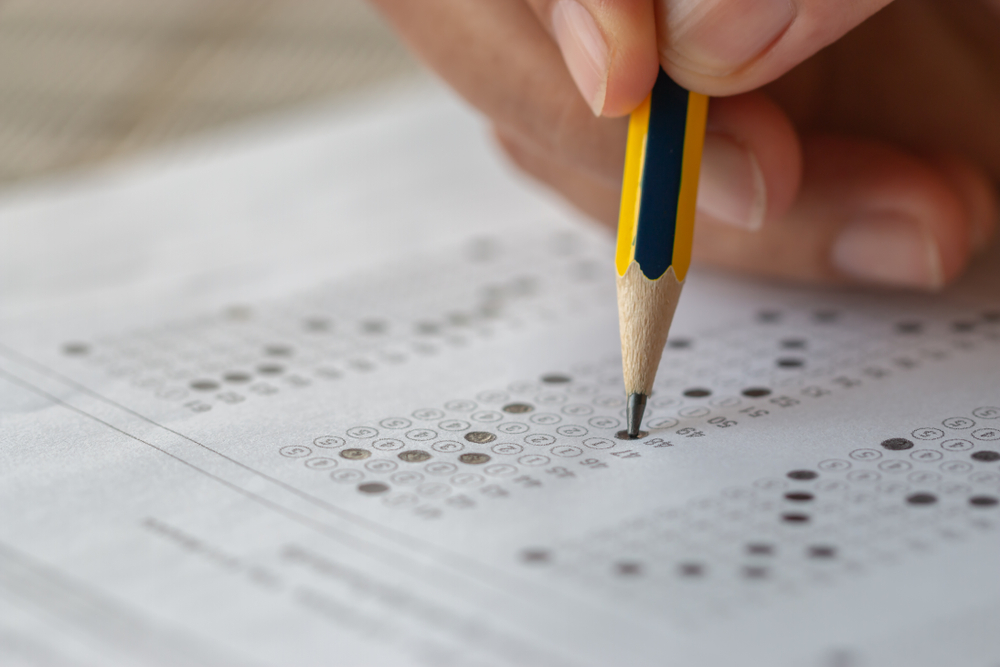 Photo: smolaw/Shutterstock.com
Photo: smolaw/Shutterstock.com2021年度から大学入試は大きく変わる。その中でも英語の変化は大きい。
受験生は4月から12月までの間に英検(大学入試用に新しく作るバージョン)やTOEFL、GTECなど、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能を扱う七つの民間試験のどれかを受け、そのスコアが試験業者から大学入試センターに送られる。最初の受験生は現在の高校2年生で、すでに七つのうちの一つ、英検の事前登録の手続きが始まっている。
気になるのは試験問題だ。出題内容は適切だったか、ミスはなかったか。答えのない問題や正解が複数あるような問題はなかったか。問題そのものが日本の高校生が受験するのにふさわしい内容やレベルだったか……。
終わったあとに高校の先生や予備校の先生たちが検証して判断するためには、実際に出された試験問題が公開されることが必須だ。
これは試験の世界に限らない。実施する側がいくら「大丈夫だ」「ちゃんとやっている」「任せてほしい」といってもだめで、判断するのは客観的な第三者、というのが現代の世の中の、いわば共通了解だろう。
人間のやることだ。ミスは避けられない。だからこそ、テスト後に見つけ、対応できるシステムを最初から埋め込んでおくこと。たくさんの人の目にふれられるようにして、見つけられるようにすること。これが大事なはずだ。まして受験生たちの人生を左右しかねない大学入試なのだから。
では、これから導入する英語民間試験はどうか。
9月中旬、記者は個々の試験を実施する団体や会社に問い合わせ、受験生が受けた試験問題は公開するのか、さらに解答あるいは解答例は公開するのかをたずねた。
答えは以下の通り。
ケンブリッジ英検=問題は公開しない 解答も公開しない
英検(S-CBT)=問題は公開しない 解答も公開しない
TOEFL iBT=問題は公開しない 解答も公開しない
IELTS=問題は公開しない 解答も公開しない
TEAPとTEAP CBT=問題は公開しない 解答も公開しない
GTEC=現在検討中。どうするかは10月中に発表の予定
公開すると答えた試験業者は一つもなかった。
なかには記者の問いそのものを理解するのに時間のかかった業者もあった。「ホームページにサンプル問題を出しているので形式や難易度はわかっていただけるはず」とか「過去の問題を一部公表しています」といった答えが返ってくることもあった。これがかみ合わない回答ということはわかっていただけると思う。
もっとも、試験業者だけを責めるのは気の毒というものだろう。7月に撤退したTOEICを含め、これまでも試験業者の多くは問題も解答も非公開でやってきた。それが業界のいわば常識であり、受験する側も特に疑問をもたなかった。
民間の資格・検定試験ならばそれでもいいだろう。だが、大学入試となると話は違うはずだ。
4技能を測る民間試験を導入するにあたって、大学入試センターは「参加要件」としていくつかの項目を掲げた。たとえば国内で2年以上実施しているとか、入試に使われた実績があるとか、1回の試験で4技能の全てを評価するとか、学習指導要領と整合性が図られているとか、4月から12月までの間に複数回の試験を実施するとか。
だがこの参加要件に「実施した試験問題を公開する」は、ない。
この点で業者を100%信用するということか。それでは試験はブラックボックスに入ったまま。第三者があとから検証することができない。高校や予備校の先生たちが取り組むことができない。
大学入試センターは、自分たちが試験を実施した後には問題を公開してきた。毎年、新聞各社が掲載するので見たことがある人は多いだろう。
だがそのセンターがつくった参加要件からは、問題の公開はきれいになくなっている。
 Photo: TypoArt BS/Shutterstock.com
Photo: TypoArt BS/Shutterstock.comなぜ「試験問題の公開」を要件に入れなかったのか。入れたら、要件を満たせない、つまり参加しない試験が続出してしまい、「民間試験の活用」が成り立たなくなるからか。はじめに民間試験ありきで、出題ミスから受験者を守るために欠かせない、第三者による検証の可能性や必要性は、当初から除外していたのではないか。その疑念がぬぐえない。
繰り返すが、パソコンやタブレットで試験を行っても、問題をつくるのは人間だ。事前にどれだけ注意し点検しても、ミスを100%避けることはできない。
そのことは過去が証明している。阪大や京大ですら避けられなかった。さらにミスがあった翌年、注意に注意を重ねたはずの京大で問題削除という事態が起きた。センター試験も、失礼ながらミスとは無縁ではない。何度もあったし、中には第三者に見つけてもらって、ほっとしたことだってあったはずだ。
出題ミスはテストの宿命と考えたほうがいい。出題した側を責めるのではなく、大事なのは、少なくとも大学入試においては、出題ミスを見つけられるようにすること、そして出題ミスがわかったらその試験を受けた受験生が不利にならないようにすることではないか。
事後に第三者が検証できない。出題ミスがあったかどうかがわからない。たとえ不適切な問題があってもわからない。これまでのミスの教訓が生かされない。そういう試験制度がまもなく始まろうとしている。制度の根本がおかしいのではないか。いくら4技能が大事だからといって、これでいいとはとても思えない。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください