【6】「石狩挽歌」「小樽のひとよ」
2019年12月12日
場所:小樽/余市
昭和50年(1975)「石狩挽歌」(作詞・なかにし礼、作曲・浜圭介、唄・北原ミレイ)
昭和42年(1967)「小樽のひとよ」(作詞:池田充男、作曲:鶴岡雅義、唄:鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
 「ニシン御殿」と呼ばれた旧花田家番屋。現在は国の重要文化財に指定されている。=北海道小平町鬼鹿広富
「ニシン御殿」と呼ばれた旧花田家番屋。現在は国の重要文化財に指定されている。=北海道小平町鬼鹿広富 いうまでもないが、歌謡曲は大衆の大衆による大衆のための唄である。したがって普通の暮らしぶりの人々の関心事がテーマに選ばれる。大衆のほとんどが知らない、聞いたこともない事象が歌詞にされることはまずない。仮に歌詞にされても支持されヒット曲となることはない。これが流行歌の「公理」である。
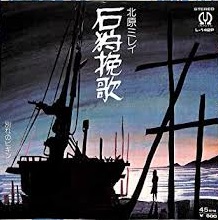 北原ミレイ「石狩挽歌」 作詞:なかにし礼、作曲:浜圭介
北原ミレイ「石狩挽歌」 作詞:なかにし礼、作曲:浜圭介 私もそうだったが、おそらく読者も、歌詞を確認して、ニシン漁師たちの間で海猫が「ごめ」と呼ばれていたこと、「つっぽ」とは漁師たちが羽織る筒袖の刺子半纏のようなものらしい、と知ったのではなかろうか。それにしても、これほどジャーゴン(業界用語)がちりばめられた唄はない。
 1946年撮影のニシン漁。この頃、北海道のニシン漁獲高は30万トンほどだったが、1990年代以降は毎年2000~3000トン程度で推移している。
1946年撮影のニシン漁。この頃、北海道のニシン漁獲高は30万トンほどだったが、1990年代以降は毎年2000~3000トン程度で推移している。 ジャーゴンといえば、高倉健の「網走番外地」(昭和41年、作詞:タカオ・カンベ、作曲者不詳)の「♪きすひけ、きすひけ」(渡世人用語で「酒を飲むこと」)、三橋美智也の「おんな船頭唄」(昭和30年、作詞・藤間哲郎、作曲・山口俊郎)の「♪おもいだすさえ、ざんざらまこも」(利根川下流・潮来地方の言葉で「風でざわつく真菰」)が思い浮かぶが、その2曲ですら、「きす」と「ざんざらまこも」以外は〝普通人が耳で聞いて理解できる歌詞〟である。
ところが「石狩挽歌」ときたら、「ごめ」「つっぽ」に加えて「やんしゅ」「といさしあみ」「かさどまる」「おたもいみさき」「こだいもじ」そして謎の呪文「オンボロロ」。耳で聞くかぎりはまるで「判じ物」である。
しかも、バブルを前にした時代のわれら「一般大衆」にとって「ニシン御殿伝説」は遥か忘却の彼方にあった。これほど時空を超えた異界の物語にもかかわらず、大ヒットしたのはなぜか。それは作詞家なかにし礼の物語を紡ぎ出す創造力と想像力の合作の賜物だろう。
意味不明のジャーゴンが次々と繰り出される中で、不遇だが気丈な女性の生き様が浮かびあがってくる。背景に流れる言葉が意味不明であればあるほど、ヒロインの立ち姿がいっそう鮮明になる。かつて安井かずみらと〝軟派〟な詞を量産していた同じ男の詞なのかと(〝軟派〟な詞はそれはそれでいずれも素晴らしい出来なのだが)、正直いって驚かされたものだった。
さらに、たんなる想像力の産物ではなかったことが、この唄をいっそう魅力的にしている。なかにし礼は、自伝的小説『兄弟』(文藝春秋、1998年)で描いた兄との私小説的相克を下敷きにしているが、そのままでは伝わらないので作劇的工夫をこらした、と由紀さおりとの対談でも語っている(「ミュージック・ポートレイト」NHKオンライン、2013.4.19)。リアルな物語に裏書きされていたのである。
また、歌い手もよかった。この楽曲は八代亜紀、森昌子、石川さゆりなど複数の歌手に提供されたが、北原ミレイの捨てばちな歌いぶりが歌詞にはぴったりだった。これがこの唄をさらに魅力的にしたことは間違いなかろう。
 北原ミレイ(1976年撮影)
北原ミレイ(1976年撮影)文芸にたとえれば、本来直木賞の大衆小説ジャンルへ芥川賞の私小説が持ち込まれたような衝撃的事件で、音楽業界がその年の「日本歌詞大賞」を授与したのは当然であった。
「石狩挽歌」のヒットの理由についてはこれぐらいにして、そろそろ本稿の通しテーマである「歌枕」に論を進めよう。その中でこの唄のたぐい稀れな魅力もさらに明らかになることだろう。
さて、「石狩挽歌」の舞台となったのは、歌詞の2番にある「朝里の浜」である。小樽の中心市街から東寄り、石狩湾に面した夏は海水浴で賑わう温泉保養地だが、かつてはニシン漁で栄え、なかにしの家もそうだったが、〝一網千両〟で成り上がった御殿が立ち並んでいた。したがって、普通ならここを「歌枕」とするのが妥当だろうが、私としてはこの唄にある正体不明ジャーゴンの一つである「古代文字」をとりたい。
それは、「かわらぬものは古代文字」がこの唄の「結語」にされているからである。「古代文字」は「ごめ」にはじまる強烈で個性的なジャーゴンに比べると耳への響きは至って地味で聞き流してしまいそうだが、追究していくほどに、そこに込められているメタファーとメッセージは奥深い。
 手宮洞窟の「古代文字」の模写図。実物は岩肌に刻まれている
手宮洞窟の「古代文字」の模写図。実物は岩肌に刻まれている
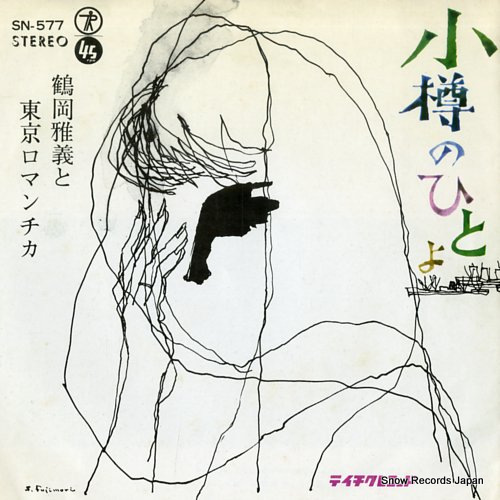 鶴岡雅義と東京ロマンチカ「小樽のひとよ」作詞:池田充男、作曲:鶴岡雅義
鶴岡雅義と東京ロマンチカ「小樽のひとよ」作詞:池田充男、作曲:鶴岡雅義この2番の歌詞を耳にしたとき、私は違和感をもった。1番の歌詞がかもしだすいかにも鶴岡正義と東京ロマンチカらしいムード歌謡には、なんとなくそぐわないからだ。調べているうちに事情がわかった。当時テイチクの東京ロマンチカのディレクターで、後に石原裕次郎のアシスタントディレクターになる高柳六郎が
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください