165万部のあの写真集を担当した元上司に聞いてみました[2]
2019年12月12日
編集者・赤井茂樹さんインタビューその2です。
東日本大震災の翌日、東大病院で開かれた会合に呼び出されて――
「本をつくっているとさ、事前には予想できない、没頭する時間って生まれるじゃない? 自分がこんなものに興味を持ってるって知らない。やってみて初めて気づく。それから、人との関係で、その課題を自分に投げられれば引き受けないわけにいかない、みたいなこともあるしね。のりかかってみると、楽しいことに負けてがんがんやってしまう」
そう語る赤井さんが、原発事故から8年後、安東量子さんの『海を撃つ――福島・広島・ベラルーシにて』(みすず書房)という本をつくるまでのお話です。
 震災当時の福島県相馬郡飯舘村=撮影・安東量子氏
震災当時の福島県相馬郡飯舘村=撮影・安東量子氏――原発事故が起きてから、長いこと休んでなかったですよね。赤井さん、足が痛くなってたりして。出先に届けものをしたら、足をひきずりながら出てきて、びっくりして、休んでくださいよ!ってしつこく言ったけど休まなくて……。
そうそう、足は痛かったねえ。なんだったんだろう。
俺があのとき、放射線関連の仕事をやるようになっていくのは、(前回話した)自分の父親のこともあるけど、もうひとつは中川恵一先生との関係だよね。『がんのひみつ』(朝日出版社、2008年)っていう本で、中川先生と仕事してたから。
中川先生は放射線治療っていう分野の専門家なんだけど、放射線治療って、医者以外の専門家のアシストによって成り立ってるのね。医学物理士って言ったかな。お医者さんじゃない、核物理学をやった人たちが、放射線治療のグループに入ってるんだ。その人たちが、放射線をどの強さで、どの角度から、どのぐらいの時間照射して、患部のがん細胞、腫瘍を攻撃すればいいかって計算して設計する。
だから彼らは、放射線の危険性も効用も、両方知ってる。被曝についても、日常的な感覚として知ってる。僕はそういう人と知り合ってよかったな、とは思ってるんだけど、それがあの事故と結びつくとは思っていなかった。
事故があってすぐ、中川先生から連絡が来て、専門家が何人もお見えになるから東大病院に来てほしいって。
――いつぐらい?
翌日だったか……、2011年3月11日から何日も経ってなかったと思う。理学部、工学部、他の大学の研究者、放射線防護っていう分野の専門家とか、20人ぐらいいた。そこに行って、自分たちにできることはないか、みたいな議論があった。
何回か会合が行われて、会合後のタクシーでの移動中だったか、原発とものすごく関係の深い研究分野のある先生が、「最悪でもチェルノブイリ」って言ったんだ。俺、これね、ほんと忘れがたい。せいぜいチェルノブイリだって言ってるわけだよ。チェルノブイリを軽視しているわけじゃないけど、最悪でもチェルノブイリっていう言い方のなかに、ものすごい傲慢な感じとか、被害っていうものの見積もり方の、ちょっとグロテスクな、専門家ならではの俯瞰しすぎている感じとか、にじんでるわけね。俺、こういう人とは仕事できないなと思った。
放射線治療チームの医学物理士たちは、ものすごく勉強していて、事故から数日のうちに、国際放射線防護委員会(ICRP)の文書を教えてもらった。“ICRP Publ. 111”っていうんだ(正式題名は「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」2009年)。ICRPのジャック・ロシャールさんという人が書いたものなんだよね。
ICRPは、放射線を使うとき、これこれの人体影響があるので注意しましょうっていうことを、現在わかっている範囲で、国際的に標準の考え方をつくろうという民間の団体なんだ。ロシャールさんはフランス人で、放射線防護が専門、今はICRPの副委員長。
――『海を撃つ』を書いた安東さんが2011年の秋に読んで、「堅物のはずの専門家集団が執筆したこの文章が、私たちの『望み』を語り、『願い』に注意を払っている」と驚いた文書ですね。赤井さんは、放射線治療チームの人たちに教えてもらったんですね。
うん、今、頼りになるのは、この文書だけなんだって。日本語訳がないから、訳して伝えたほうがいいかなって医学物理士の一人が言うので、中川先生とやろうということになって「team nakagawa」というアカウントでTwitterを始めたり、ブログをつくって、ICRPの文書の概要を紹介する連載を始めた。
事故からしばらくは、個人的にも仕事の上でも気持ちに余裕はなかったけど、いくつか印象に残ることがあったな。まず、早野龍五先生のTwitterでの発信が心強かった。先生の発信に接して、どういうデータを見ればいいのかはじめてわかったんだよ。いま思い出すと、俺はすがるように読んでいた気がする。
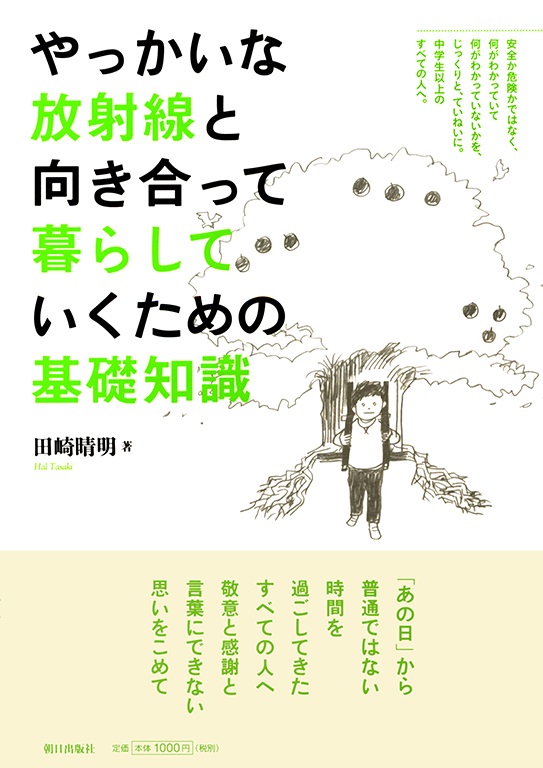 田崎晴明『やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識』(朝日出版社、2012年9月刊)
田崎晴明『やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識』(朝日出版社、2012年9月刊)田崎先生には「やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識」というページもあって、単行本にする際、担当させてもらった(朝日出版社、2012年9月刊行)。当時、俺は50代半ばで、慢心してたんだなと思う。ウェブサイトを活字化するだけと思いきや、じつに厳密で公平・正確なご指導を受けて、その意味でも忘れられない。
ICRPは国際的な非営利団体(事務局・カナダ)で、各国から専門家が手弁当のボランティアで参加してるんだよ。彼らがつくったものが絶対の真理ではないけど、他にそういう知見を提供するところがないので、いわばグローバルスタンダードになってる。当然、反対意見もあるけど、多くの場合、ICRPの見解は、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)とか、世界保健機関(WHO)の専門家たちからも支持されているんだ。
安東量子さんは、「もやもやとした思いを抱えるよりは、きちんと状況を把握した方がいい」と考え、SNSで発信したり、当事者の対話集会に尽力していくなかで、いろんな批判にさらされたんだけど、なかには「安東量子は、原発を推進するジャック・ロシャールに洗脳された人だ」みたいに言う人もいる。
――そういう感じなんですか。
うん、ロシャールさんは、原発があるなかで、自分のやれることをやってる人なので、訊いたことないけど、原発反対は表明したことがないんじゃないかな。
実際、ICRPって、ものすごく頑固な原発推進派がたくさんいる組織だから。線量基準ももっと緩めるべきだという専門家だっている。放射線利用を推進するために、放射線量をこういう範囲でコントロールしませんかって勧告する立場の組織だからね。
でも、チェルノブイリであれだけの事故が起きたってことは、事故が起きるっていうことなので、これからも。事故が起きることに対して、起きたらどうするかを書いておかないといけない。それで、ロシャールさんは、安東さんの表現を借りれば「人びとの望みを知り、当局と専門家は放射線量の低下を目指しながら、それを支える手段を共に考え、実施せよ」と言ってるわけ。
 ジャック・ロシャールさん=撮影・宮井優氏
ジャック・ロシャールさん=撮影・宮井優氏彼自身、ものすごい魅力的なんだよ。論文の冒頭にハンナ・アーレントを引いたり、立場の違う人の話をじっと聞くことができる。チェルノブイリ事故から10年後のベラルーシに入って、徹底的な喪失を経験した人たちと長く接したことも関係あるかもね。
それに、日本の議論だけ見てると、日本でしか話題にならないこととか、とくに関心が集中するトピックとか、ローカルであるっていうのが、わからなくなっちゃう。ロシャールさんみたいなフランス人で、かつ専門家で、ベラルーシで活動した人ならではのものの見方は、あまり聞けないことだよね。
――安東さんが本に書いていますけど、チェルノブイリの事故の被害があった、ノルウェーのヴァルドレス地方に行ったとき(この地域は、比較的最新の調査結果によれば、体内の放射性物質摂取量が、他の地域の平均的ノルウェー人の10倍)、ノルウェーで、この地方が忌避されたりしないのって、安東さんが案内人の女性に尋ねたら「一切ない、なんでそんなこと聞くの?」って不審そうだったから、日本では福島産の食べ物が忌避されたり、福島出身の人が嫌がらせを受けたりすることもあるって説明したら、驚かれたって書いてあって。あ、びっくりするんだっていうことに……。
うん、びっくりすることに対して、びっくりするよね。
 福島県南相馬市原町区=撮影・安東量子氏
福島県南相馬市原町区=撮影・安東量子氏事故から時間が経って、原発の中で演じられた修羅場とか、東電と官邸の確執とか、報道の延長でドキュメンタリーの類は出てくるようになって、やがて国会、政府、東電の事故調査委員会ができて、その報告書ができるようになったでしょう。
でもさ、ああいうのって、読んでも……。もちろん、絶対に必要な仕事だよ。でも、誰に向けて書いているのかがわからないし、あれをふつうの人が読んで、なにかこう……事故と、その影響を受けた人の生活に、どういう影響があったか、その核心みたいなものは伝わらないじゃん。統計とかデータの集積、それをもとにした分析、論文集のようなものなので、対策を練るとか、今後の展望、今回の事故の教訓っていうことでまとめられるわけだよね。
いろんな経験があったはずだけど、どうもあの福島固有の雰囲気が書かれない。わかりやすく言うと、石牟礼道子『苦海浄土』が出てこないって感じ。
安東さんのツイッターを見ていると、一時、攻撃的な誹謗中傷やデマ、彼女が間違いだと思うものに対して、激しく食ってかかったりしたこともあった。でも、彼女のブログを読むと、この人は文学的素養があって、放射線がとか、防護基準がとか、そういう畑の人じゃないんだってわかって注目するようになったんだ。
安東さんに会ったのは、2012年のはじめで、本の依頼は、最初からしたわけじゃないんだけど。
――赤井さんしか、ああいうかたちの本は頼まないんじゃないかな。
わからない、依頼はあったかもしれない。でも、安東さんの文章に愛着を持っていない人は駄目だと思う。愛着と、一部、注文を持ってないと。
――注文?
うん、安東さんって、ちょっとこう、歌うような文章を書いてしまうから。本の中にも詩が載ってたりするけど、それって、過剰になるか、ぎりぎりのところじゃない?
大災害とか大惨事とか大きな不幸が起きたとき、悲しみを歌う人っているでしょう。悲しみを歌うことは、あって、もちろんいい。必要でさえあるっていうか、止められないよね。でも、それでは安東さんのいいところは伝わらないわけ。
――具体的に、どういうところが良いと思ったんですか?
うーん……文章。語彙。抒情。毅然としたところ。腹が据わっていて失うものはないという覚悟、みたいなことだね。
メディアもいろいろだけど、たいがいのメディアは、ヒーローをつくってみたり、糾弾してみたり、科学的な知識も不十分なままに煽(あお)りを書いてしまったり。誤りを指摘されても直さない。まあ、とにかく記者も解説をしている人たちも信用ならないってことがわかって、ここに乗るまいって。
 バックホーを操作する安東量子さん
バックホーを操作する安東量子さん安東さんが言いたいことは、科学的に正しいか正しくないかの判断を、一人ひとりが持つような世界に僕らは住んでいないということが大前提なわけ。で、正しいとか正しくないに沿って生きてるんじゃないぞっていうことを、彼女自身がそう思っているのと同時に、彼女が接して親しくなってきた人たちは誰一人、それに沿って生きてないって、体験上、知ってる。
安東さんは夫婦で植木屋さんをやってるから、地元のおじちゃん、おばちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃんと親しいので、彼女は通訳の必要を強く感じてきたと思う。この人たち、そんなこと思ってないだろうって。そういう、メディアに加工されない声と俺たちをつなぐ通訳がいない。
それから、安東さんは、自身が甚大な被害をこうむったわけじゃないでしょう。原発からの直線距離を考えると、風向きなどが幸いして、放射性物質の量も、いわきは多くない。
――住めなくなるような場所に住んでいたら、違う経験になりますよね。でも、その微妙なところがね。安東さんが、宙ぶらりんって書いてるけど「数値を、高いといえばいいのか、低いといえばいいのか。私は会話のたびに、『高い』と『低い』のあいだを揺れ動いていた」「この数字は低いのだ。けれど事故前よりは高い。そして避難先よりも高い。低いけれど、高い」って。
そうなんだよ、あの、線量の高低が、暮らしの良し悪し・優劣に直結されてしまうことをなんとか乗り越えたいってところの葛藤がね、選挙の争点とかにはならなさそうなところがいい。
原発事故後、意見が違って対立するってあるでしょう。安全か危険か、みたいな。ちゃんと暮らしてますよ、なんて言うと、政府や御用学者の片棒を担ぐのか!なんて怒られたり。でもねぇ、測定を無視しない、同時に数値に振り回されない、数値は生活の中でコントロールできる場合もある。自分の暮らしを自分で選び、工夫し、地元であろうと避難先であろうと、生きていくってことが大事ということだと思うね。
他にも、ここで安東さんが書かなければなかったことにされちゃう、みたいなことがいっぱいあるって感じる。
安東さんのご主人、鎌田さんも、すっごいいい人なんだよ。歳は還暦くらい。彼も詩が好きで、中原中也が好きって聞くと小難しい人かと思うでしょう。でも、ぜんぜんそうじゃない。穏やかな、大事なものだけ見てる白熊みたいな感じ。
――白熊はいいです。鎌田さんは『海を撃つ』を読んだんですか?
うん。読んでくれて、最後の、タイトルに関連する場面がなければ、ただのドキュメントみたいに思われただろうけれど、最後に反転というか、寓話の向こうに突き放したところに驚かされた、その組み立てが最大の長所だって言ってた。
――寓話の向こうってなんだろう……? あの場面、涙が出そうになりましたよ。なんであそこ、ぐっとくるんだろう。
 近所に咲いていた花=撮影・安東量子氏
近所に咲いていた花=撮影・安東量子氏*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください