『北斎』『9条入門』『夏物語』『原子力時代における哲学』……
2019年12月17日
*本や出版界の話題をとりあげるコーナー「神保町の匠」の筆者陣による、2019年「わがベスト3」を紹介します(計4回シリーズ)。
小林章夫(帝京大学教授)
エドモン・ド・ゴンクール『北斎――十八世紀の日本美術』(隠岐由紀子訳、平凡社・東洋文庫)は、いち早く葛飾北斎の才能を評価した書物。18世紀イギリスを勉強してきた人間にとって、18世紀日本の天才画家を見いだしたゴンクールの眼力に感心すること多かった。
高橋裕史『戦国日本のキリシタン布教論争』(勉誠出版)は、日本での布教活動に、イエズス会、フランシスコ会がどのように関わり、いかなる対立をしたかを、一次資料を丹念に読み込み、多角的に検討した快著。しかしまあ、宗教界にも激しい派閥争いがあったのだな。それはそうだろう、自分の信じるものを巡って意見が分かれれば、俗世界よりも命がけの争いになるのは古今東西の真実である。
マークマン・エリス他『紅茶の帝国――世界を征服したアジアの葉』(越朋彦訳、研究社)は、紅茶がイギリスの国民的飲み物となった経緯を詳細に跡づけた名著。紅茶の研究には不可欠の資料となるだろう。ちなみに著者の一人エリスにはコーヒー文化を巡る名著がある。
今野哲男(編集者・ライター)
1. 加藤典洋『9条入門』(創元社)
今年の5月に逝去した文芸評論家・加藤典洋氏の遺作。優れた文芸評論家の最後の一策が、文学ではなく、むしろ政治に関するものであったことを悼む一方で、加藤氏にはその二つをつなげるに足る、戦後を生きる者としての稀な文学的倫理感があったことを強調しておきたいと思う。かつて、この国では孔子的な「中庸」が、ときに「どっちつかず」や「風見鶏」などの負のイメージをもってとらえられる傾向があった。『イソップ物語』で言えば「こうもり」のような扱いを受けていたのだ。政治の舞台では殊にそうで、これは東西冷戦下で生まれた保革両陣営の対立が、両者の間にある存在や立場の影をゆえなく薄くする面があったからだと思う。加藤氏は『敗戦後論』(1997年)以来、保革いずれにも与しない形でこの国の戦後のとらえ直しに力を注ぎ、返す刀で保革双方の憲法観にある不全性をラジカルに指摘してきた。本書が、「中庸」が最もラジカルだった時期の大事な記念碑として、長く保存されることを祈りたい。
2. 大澤真幸『三島由紀夫 ふたつの謎』(集英社新書)
わたしは、三島由紀夫という男は、ギリシャ文化へのひとかたならぬ傾倒に見られるように、フランスにのめり込んだ森有生などと同じく、西欧化した近代日本人の最も典型的な人物の一人だと思ってきた。その思いは、割腹自殺した後も変わっていない。たとえば寺山修司など西欧で評価された多くの日本人は、エキゾチシズムがその主因だったと邪推するが、この二人は日本にとってよりも、西欧にとってこそわかりやすかったのではないかと思う。その彼が、なぜ、ことさらに「日本」などという逆向きなことを言ったのか。本書はこの困難な課題に、三島の特異な「死」と、擱筆の日付が自決の日と重なる『豊饒の海』の不可解な結末部分に光を当てて、「謎解き」の形でスリリングに、大澤流の三島理解を展開している。
3. 吉本隆明『ふたりの村上――村上春樹・村上龍論集成』(論創社)
吉本隆明は生前、『ふたりの村上』という春樹と龍の両村上についての書き下ろしの論考を準備していたらしい。本書は書かれぬままに終わったその論考の題名を借りて、吉本の二人に関するさまざま論考を、丹念に拾い集めたもの。1924年生まれの吉本隆明には、49年生まれの春樹と52年生まれの龍とが、「現在」と切り結ぶ中でどう見えていたのか。肯定と否定が相半ばするそのアンヴィバレントな実相が明らかになる。
○番外
加藤典洋『完本 太宰と井伏――ふたつの戦後』(講談社文芸文庫)
掟破りの文庫ものだが、加藤氏の服喪のためにも是非。
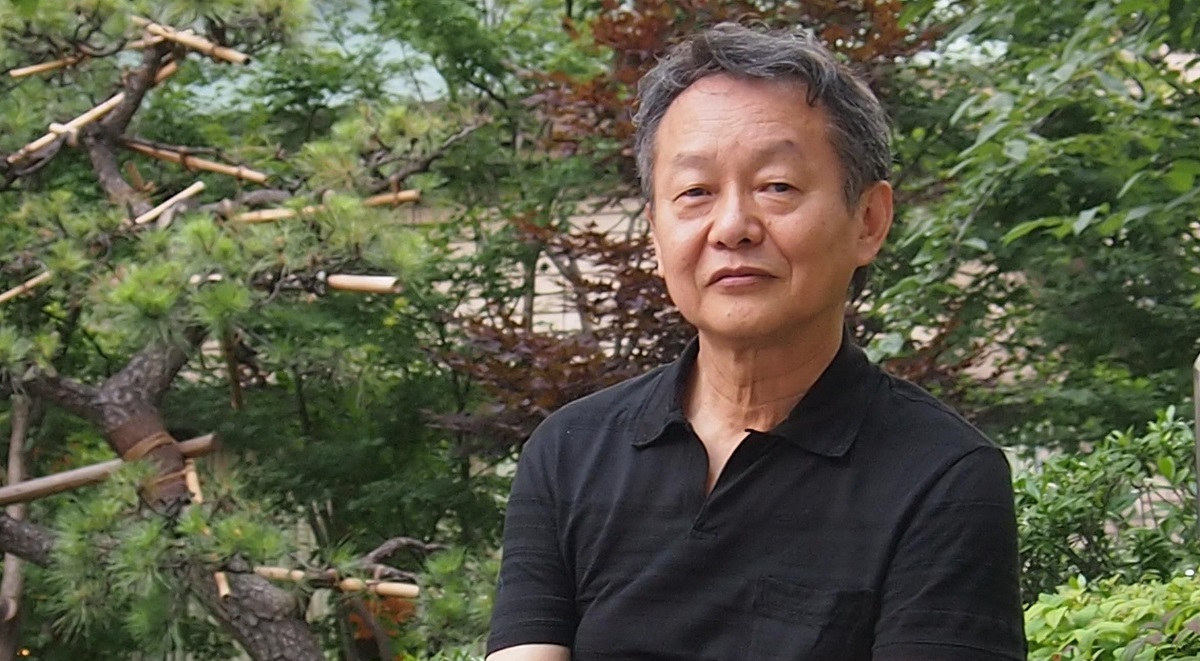 加藤典洋(1948―2019)
加藤典洋(1948―2019)中嶋 廣
川上未映子『夏物語』(文藝春秋)
この作品は、芥川賞を受賞した『乳と卵』の第2バージョンが第一部で、それから8年後の、2016年夏から19年夏までの3年間が、第二部である。この物語を読むと、日本の若い女性が置かれているギリギリのところがよく分かる。主人公の夏子が、バイト先で同僚だった紺野さんと再会する場面。そこで紺野さんは「わたしらは『産む機械』的な物ですらなくて、『まんこつき労働力』だ」と言う。女と男がここを突破できないと、日本人はどんどん少なくなり、いずれ消滅してしまう。もちろん、だからどうしたと言うわけではないが。この大著は今現在の問題を、これでもかと詰め込む。それでもとにかく、めちゃくちゃ面白い。これはほとんど奇跡である。
 川上未映子
川上未映子山田詠美『つみびと』(中央公論新社)
これは親子4代にわたる系譜のうち、2代目の「琴音(ことね)」、3代目の「蓮音(はすね)」、4代目の「桃太(ももた)」を主人公に、それぞれの悲惨を描く。時代や時間は、それぞれ主人公に応じて行ったり来たりするが、それで錯綜して読みにくいということはまったくない。見事なものだ。事件は「蓮音」がマンションの一室に、二人の子を置き去りにして死なせたというもので、実在の事件をモデルにしている。山田詠美の文章には暖かみがある。小説の内容に救いがないところでも、文体に救いがある。思わず涙腺が決壊しそうになるが、厳しく迫力ある文体がそれを許さない。
望月優大『ふたつの日本――「移民国家」の建前と現実』(講談社)
この本は私たちを覚醒し、外国人のいる日本の風景を、というよりも、その風景を見る私たちの「視線」を変えてしまおう、というのが著者の目論見である。入管法改定の後、2019年4月に新設された「特定技能」は、ある段階まで進むと、「技能実習」や「留学」の後も、日本に残って職に就くことが可能になる。それだけでなく「特定技能」2号まで進むと、家族を呼ぶことも可能になり、さらに年数を重ねることによって永住権の取得も可能になってくる。しかしこれは、まだ絵に描いた餅である。そうではなくて、私たちが、外国人労働者を見る目を変えられるかどうかなのだ。
○番外の一冊
L・M・モンゴメリ『赤毛のアン』(松本侑子訳、文春文庫)
50年前に読んだ村岡花子訳は、少女小説の名作だと思った。今度の松本侑子訳は本格的な大人の文学である。翻訳を読んで圧倒されたのは、実に久しぶりである。訳註も訳者あとがきも充実している。中学生の時は続編を読まなかったが、今度は全部読もう。
松澤 隆(編集者)
國分功一郎『原子力時代における哲学』(晶文社)
震撼。著者の単著で最も耽読。核の平和利用に関するハイデッガーの問題意識を射程に、人間が原子力に惹かれる理由を哲学的に追究した快著。文体は平易だが、構成は周到、性急な結論を斥ける。とはいえ、旋回する何かを思わせるような叙述は、時に極上のミステリを読む快感に近く、高まる動悸に慌ててしまう。ハイデッガーが重視した「技術」の読解には、文字通り「震え」が来た。
 國分功一郎『原子力時代における哲学』(晶文社)
國分功一郎『原子力時代における哲学』(晶文社)奥武則『黒岩涙香――断じて利の為には非ざるなり』(ミネルヴァ書房)
圧倒。「赤新聞」の先駆ともされる「萬朝報」を起こし、「まむしの周六」と仇名された稀有の新聞人の虚実を丁寧な史料分析で描き出した傑作評伝。分析途上で現れる同業体験者(元・毎日新聞)ならではの評語、いや隻語もよい。鶴見俊輔の高評と三宅雪嶺の酷評を引きつつ、両者は「新聞人」を貫いた涙香の〈本質を見誤っている〉と断ずる一文も説得力がある。今年は、中野目徹『三宅雪嶺』(吉川弘文館)という労作にも出逢った。また、昨年の黒川創『鶴見俊輔伝』(新潮社)の余韻も響き続ける。3人3冊の優劣を量るのではなく、個性の輝きと近代の陰翳を改めて見つめ直したい。
池内紀『ヒトラーの時代――ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(中公新書)
哀悼。久々に手にした著作が、遺作となってしまった。2年前の同じ新書『闘う文豪とナチス・ドイツ――トーマス・マンの亡命日記』の姉妹篇として読める一方、刊行直後に起きた「正誤表」騒動のせいもあり、「池内さんの最後の本がこれ……」という捉え方をした読者もいるかもしれない。興味関心により、それぞれの「池内本」があって当然で、個人的には複数のカフカ本が愛しい。しかし、いまという「時代」だからこそ文学者ではなく独裁者を採り上げ、この男を選挙で選び救世主のように称えたこの「時代」を描きたかった真意を、かみしめたい。永年の愛読者の一人として、感謝とともに。
ほかには、アニエス・ポワリエ『パリ左岸――1940-50年』(木下哲夫訳、白水社)。その表題副題にまず、畏敬と憧憬。この時空間を生きた多くの著名人の〈本業を離れた素顔〉(訳者あとがき)を垣間見るためだけでも、460頁4800円の価値はある。池内さんなら、〈ナチの毒が我々の思考そのものを害したため、自由な思考は何であれ勝利だった〉(サルトル)なんて一節を、どう読んだろうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください