ちゃんと動けば伝わる。10代の2人は声をあげ、社会の中で学んだ
2019年12月20日
大学入学共通テストへの英語民間試験の導入の問題点を指摘し、広く発信してきた高校2年のクリス君、こばると君へのインタビュー。東京都内にある別の高校に通っている彼らが、声をあげた動機や、定期テストや教科書の枠組みの中で「お利口さんゲーム」を強いられる学校教育への違和感を述べた「高校生の僕は英語民間試験に異議を唱えた【上】」に続き、自分の考えを鍛え、社会と関わる手応えを語る。
 クリス君(手前)、こばると君=中井征勝氏撮影
クリス君(手前)、こばると君=中井征勝氏撮影――2人は文部科学省前の抗議活動や国会内の野党の集まりで話したり、あるいはメディアに出たりもしました。学校での反応はどうですか。
クリス 先生たちはツイッターで僕のを見かけて「暗躍しているね」って。悪い意味じゃなくて「やってるでしょ」みたいなのが、うちの学校の先生たち。「やめておきなさい」と言われたことはない。うちの高校は自由だから、個々人で、というスタンス。先生たちもどっちかというと入試改革反対派で、「あ、やってくれてるね」って。延期が決まった時は「クリぴょん、おめでとう」って。クラスラインで「延期されたよ」と送ったら、「クリぴょんテレビ出てたよね」みたいな反応が多かった。
こばると 授業のあとで先生から呼び止められて何かなと思ったら「記事見たよ」。「あ、見たんですか、どうもどうも」。ツイッターやっている先生が何人かいて、「こばると君とかいうツイッタラーがいますね」と言われたこともある。やるぶんには自由という雰囲気はあるのかな。自分の中で意見や思うところがあるなら、黙認するし、生徒の与えられた自由の範囲でしょ、みたいな雰囲気の学校なので。
それから、柴山さん(柴山昌彦・前文科大臣)の「高校生の政治 適切でしょうか」のツイッターの直後ぐらいですが、社会科の先生が「社会科教員としては、生徒に与えられた自由の範囲内で、学業のさまたげになるような活動、たとえば授業中に放送を使ってとかはだめだけれど、ある程度の条件を満たしていれば、どんな思想を持つのも表現するのも生徒に与えられた自由の範囲内だし、18歳で有権者になるんだから君たちは」みたいな。「そういう活動をするのは高校生として問題はないし、安心してください」って。
クリス それ、こばるとに言っている。
こばると 対象1人みたいな説明があった。
――みんな聞いているわけでしょ。わかった生徒はこっち向いたり?
こばると 柴山さんの話が出たあたりから、みんなこっち向いたり。
クリス ははは。
こばると 自由に関する意識が高いというか、器が大きい学校に通っていて幸せだと思います。生活指導でも、自分の自由を制限することをしてはいけないと。そういう土壌があったことはありがたいと思います。
――ところで、2人は発言は積極的だけれど、仲間を増やそうとしているようには見えなかった。あれはなぜですか。
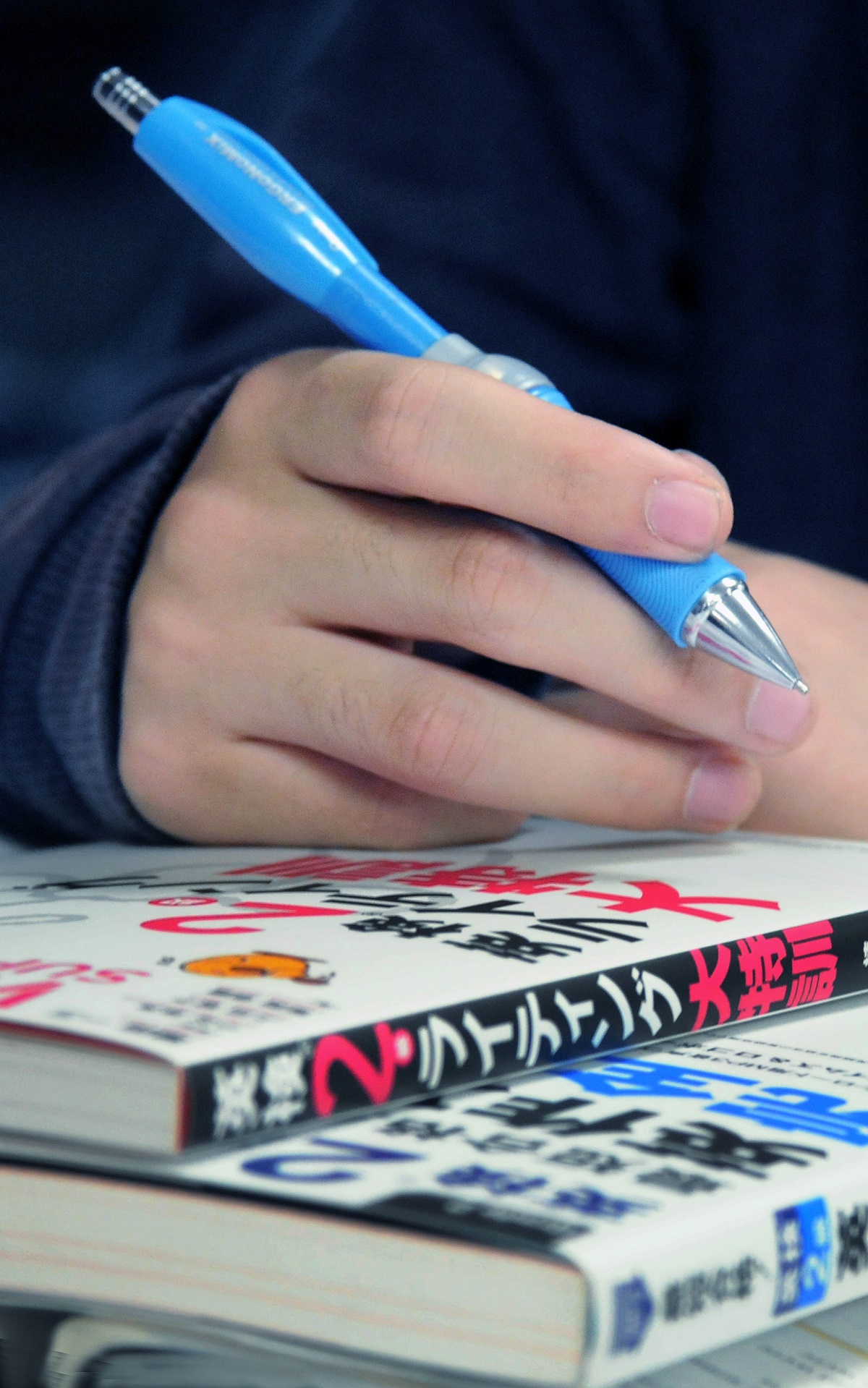 こばると君=中井征勝氏撮影
こばると君=中井征勝氏撮影クリス 僕も問題意識を広げるというところで動いていたところがあります。なぜかというと、8月1日のシンポジウムで言いたいことを文科省の人に「お願いします」と言ったあとに、「AERA」の記者に取材してもらってそれが記事になった経験をしたので。言いたいことが記事になってメディアに出るし、外にも広がる。学校のなかで仲間を集めるよりツイッターとかメディアとか不特定多数の人が見る。だから、記事とかテレビとか全然OKです、フリー素材にしてください、ぐらいの勢いで。
ツイッターがあったから。そこに仲間がいたから。ツイートするとリツイートする人がいる。それが広がれば、ツイッターやっている人なら参加しようかと思うと思ったし。(ネットで)集団にはなっていた。あとになって気づいて、けっこう反対している人、多くねって。
こばると 仲間を増やすというよりは、おかしいところも反対している人たちも、すでにあったので。いろいろな方向に一人でたらたらつぶやいていたら、それは聞こえないじゃないですか。あるものをどうやって集めて可視化させるかを意識していた。ツイッターならハッシュタグをつくってトレンドに載せるとか、ネット署名ならたくさん集めるとか。数という観点でいえば、そういう発想が多かった。
――それはどこかで学んだのですか、それとも自分で気づいたのですか。
こばると たぶん自分の意識がそうだったのかなという気がします。まともな意見で批判を述べている人たちが、ここにたくさんいる。それが知れ渡っていないだけ、みんなが興味をもっていないだけ。生徒や教師や大学関係者の声が世間一般に届きにくいのはあるから、集めて可視化しようっていう。それをしていけば、おかしいことをおかしいと言っているだけなので、気づいてくれる人は気づいてくれる。あとは声をどうやって伝えるか、届けるか、集めるか、ということだと思います。
――文科省の前や国会内で話すことは大変じゃなかった?
クリス 全然大変ではなかった。むしろチャンス。
こばると 言っていることはふだんと変わらない。その場に立ってナマで話さなければならない。それは努力があったけれど、ふだん言っていることと同じことを言っているだけなので。文科省前だったり野党のヒアリングだったり、場や形はいろいろ変わったけれど、疑問や批判や議論は同じことを言ってきただけ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください