『団地と移民』『つみびと』『カザアナ』『都市空間の明治維新』……
2019年12月23日
大槻慎二(編集者、田畑書店社主)
今どき世代論なぞ流行らないかもしれないが、以下の3冊をひとつのキーワードで括るとすれば、まぎれもなく「世代」である。
斎藤真理子 責任編集『完全版 韓国・フェミニズム・日本』(河出書房新社)
今年も出版界には諸々の話題があったが、明るい方の話題の代表選手を挙げるとすれば「文藝」秋季号(特集「韓国・フェミニズム・日本」)の異例の増刷だろう。創刊以来86年ぶりの3刷、しかも続く冬季号も増刷が決まり、2号連続の増刷は「文藝」史上初という。その「文藝」秋季号が増補されて単行本になった。こちらも売行き好調とのこと。これら雑誌や単行本をいったい誰が買っているかと言えば、それは圧倒的に若い世代だろう。書店にはヘイト本が溢れるこの御時世にあって、非常に見えにくいのはこういった若い読者の存在だ。若い引きこもり世代だと思われていたネトウヨの正体が、どうやら50代60代のいい歳をしたオヤジやオバサンだったと判明してきた昨今、日本の右傾化やヘイト問題の本質は、実は世代間闘争なのかもしれない。少なくとも「感性としての」世代間の。それにしても、河出書房という会社の遺伝子の強さを思う。
「文藝」編集部に訊く。再起動する文芸とは何か
「文藝」編集部に訊く。「紙の雑誌」を出す意味
安田浩一『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)
ヘイトスピーチ、外国人労働者問題、沖縄問題……と、近年、鋭敏なアンテナと確かな取材力で充実した仕事を重ねてきた著者の、いわばすべての問題意識が切り結ぶ「団地」という存在。「団地生まれ第一世代」を自認する著者が、フランスにまで飛んで取材するフットワークのよさ、モチーフを深く掘り下げる執念に、この問題が日本のみならずユニバーサルなものだと納得させられた。絶望の極みである「団地」を描き、しかしそこにひと筋の「希望」を置くことも著者は忘れない。それは「若い世代」の無償の介入であり、久しく忘れていた「人間力」の発露だった。
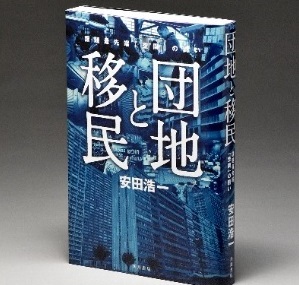 安田浩一『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)
安田浩一『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)多田尋子『多田尋子小説集 体温』(書肆汽水域)
「ポスト2020。出版ジャーナリズムの新しい潮流」でも書いたことだが、ごく個人的な意味合いもあって今年忘れがたい一冊となった。広い意味でもその出版形態の新しさ、そして何よりも多田尋子という作家の世代を超えた「言葉の命」の強さは特筆すべきだと思う。そしてその「言葉の命の強さ」はもしかしたら『韓国・フェミニズム・日本』の示すベクトルに通底しているかもしれない。
佐藤美奈子(編集者・批評家)
平然と行われる公文書の廃棄、現政権に不都合な語の隠ぺい(その語義は超短期間で「定義困難」と化した)、ベストセラー作品におけるWikipediaからの大量コピペ等々……。言葉の環境をめぐって、文字通り「底が抜けたような」状況が加速する一年だったと感じる。このような世相のもと、言葉が限りなく軽んじられていく趨勢にすでに慣らされ、麻痺しているかもしれない自身に、ゴリゴリした言葉の感触と生きるよすがを与えてくれた3冊を挙げたい。
カロリン・エムケ『なぜならそれは言葉にできるから――証言することと正義について』(浅井晶子訳、みすず書房)
タイトル中にある「それ」とは、ナチスの強制収容所やユーゴ戦争、アブ・グレイブ刑務所等でみられた暴力、恐怖、戦慄、虐待などを指す。しばしば人は、体験した「それ」を言葉にできない。生の極限状態が人間から言葉を奪うありようを考察し、理解したうえで、なおも著者は、人が「それ」を語り出す過程を鮮やかに視覚化する。支配層や多数派が見たいもの・聞きたいものだけが「ある」とされる状況下で、「それ」は、あっても「無い」と見なされがちだ。だからといって暴力からの生還者は「それ」を語れないと断じてはいけないと、著者は強く戒める。聞く側の人間と社会が「それ」を聞けるか否かが、生還者が言葉を回復できるかどうかの鍵なのだ、と。
山田詠美『つみびと』(中央公論新社)
日本で実際に起きた、母親による幼児への虐待事件から着想された小説。まさに要となるのが、生の極限状況を白日の下にさらす当事者の「語り」だ。語られることで、「陰惨な」「凶悪な」というマスメディアによる紋切り型のフレーズで括られ消費されていく事件が、他所の世界でなく、私が生きる「ここ」という日常で起きている手触りが得られるのだ。「語り」は同時に、登場人物自身と読者の両方に、「無い」ようにされる暴力や貧困の内実を確かめさせもする。
 山田詠美
山田詠美鶴ヶ谷真一『記憶の箱舟――または読書の変容』(白水社)
言葉は、記憶と深く、強く結びついている。そして人類の記憶の蓄積が「知」「叡知」であり、その収蔵庫こそ書物であることを、美しく澄みきった文章とともに改めて認識させてくれるのが本書である。東西における読書の歴史を辿った著者は、書物の絶対視はしない。だからこそ本書が示す現代のネット環境の輪郭――私たちを「無秩序な混沌に引き戻」しかねない――は説得的だ。
野上 暁(評論家・児童文学者)
中島京子『夢見る帝国図書館』(文藝春秋)
三度の洋行から帰った福沢諭吉の「ビブリオテーキがないことには近代国家とは言えない」という提言から、明治新政府によって建設が始まった日本最初の図書館が帝国図書館。現在は国会図書館分館の国際子ども図書館となっているが、その取材できた作家のわたしは、喜和子という老女と会い、「図書館が主人公の小説」を書くことを勧められる。戦後間もない頃の図書館の孤児だった喜和子と、わたしの奇妙な交流の中に、話中話として「夢見る帝国図書館」が挟み込まれ、永井荷風の父・久一郎の開館に向けての悪戦苦闘から始まり、図書館が若き樋口一葉に恋したり、一高時代の菊池寛と芥川龍之介、宮沢賢治の恋など、帝国図書館の眼から見た数奇な物語が披歴されて本好きにはたまらない一冊である。
森 絵都『カザアナ』(朝日新聞出版)
京の都で森羅万象を読み取り、その怪しい力をもてはやされた「風穴」という異能の徒たち。貧しい庶民が分け合っていた風穴の力を貴人たちが必要として「風穴囲い」が始まるが、武士の時代の「風穴狩り」によって力が封印。ところが、風雨の動きを読み天気に通じる「空読」、土地の記憶を読み取る「石読」、虫たちと通ずる「虫読」ら風穴の末裔が、「(株)カザアナ」という造園業者になって850年後に蘇る。近未来の日本を舞台に、父親を他国のテロで亡くした中学2年生の里宇と弟の早久と、母親でフリー記者の由阿とともに、嘘っぽいジャポニズムで塗りこめられた観光立国となり、格差が広がり管理と監視が強化される社会とテロ集団ヌートリアとも対決する。特定秘密保護法以降、管理と監視が進み、貧富の差も拡大している日本の現状をカリカチュアライズしてユーモラスに描いてみせた痛快なエンターテインメント作品だ。
 森絵都
森絵都赤坂憲雄『ナウシカ考――風の谷の黙示録』(岩波書店)
著者が30代半ばに出会ったという、アニメ版とマンガ版の二つのナウシカとの遭遇体験以来、その両者の違いにこだわり続け、執筆に取り掛かってから四半世紀の試行錯誤と思索を経て、マンガ版が秘めている思想の到達点とその可能性を鋭く解読した原稿用紙600枚の大作。「西域幻想」を第一章に、マンガ版の前史ともいえる『シュナの旅』から検証し、第二章「風の谷」、第三章「腐海」、第四章「黙示録」そして終章「宮崎駿の詩学へ」と続く全編から、ナウシカの物語が喚起する衝撃力と共に、極めて今日的な課題をも読み取ることが出来る。
松本裕喜(編集者)
井田太郎『酒井抱一――俳諧と絵画の織りなす抒情』(岩波新書)
新書とは思えない情報の詰まった本だ。琳派の絵師として名高い酒井抱一だが、その俳諧(連句)を正面から取り上げた本はあまりなかった。この本の魅力は、其角の俳風を慕った抱一句を掘り起こし、難解な句の意味を読み解いた点にあるだろう。俳句は余白の文芸であるという。著者は句の典拠や詠まれた場、地域性、習俗、人間関係のあや、当時の俳壇の趨勢などを一つ一つ手繰り寄せてゆくなかで、その余白の世界を再現しようとした。それは抱一の絵画の世界にも通じる通路だ。抱一は、宗達、光琳、若冲などの絵に学びつつ、自らの画技に俳諧の「脇起(わきおこし)」や「反転」などの手法を活用したと著者はみている。抱一の俳諧と絵画創作のバックボーンに迫った渾身の力作だと思った。
 酒井抱一「八ツ橋図屏風」(右隻部分)=出光美術館(門司)諸富氏提供
酒井抱一「八ツ橋図屏風」(右隻部分)=出光美術館(門司)諸富氏提供松山恵『都市空間の明治維新——江戸から東京への大転換』(ちくま新書)
江戸から明治に移り変わる時代の明治新政府や東京府の都市政策が生き生きと描かれた本である。首都東京の拠点は郭内(江戸城を取りまく外濠の内側)で、太政官、神祇官などの政府組織が置かれた。郭外(外濠の外側で、東は平井・亀戸、西は代々木・角筈、南は品川、北は千住・板橋までの範囲)の再編にあたって東京府は住民を貧富の差に応じて区分けしようとしたと著者はみる。銀座から築地にかけての煉瓦街計画、空き地になっていた武家地に桑と茶を植えて殖産興業の道を探った桑茶政策、麹町・三田・高輪の救育所などの貧窮民対策、小商人・芸能者による広場の再生など、都市再編にまつわる興味深い話が随所に盛り込まれていて面白かった。
高山れおな『切字と切れ』(邑書林)
平安末・鎌倉期の短連歌から長連歌への展開、十八切字の成立、俳諧の連歌から近現代の俳人たちのさまざまな切字説、国語学者・俳文学者の切字論まで、よくもここまで調べて書いたものだと感心した。「註」も充実している。連歌では発句に切字は必須とされ、句のなかの切れよりも平句と区切るための発句の切れ=句切れが重視された。芭蕉も発句の切れを重視し、上五末の「や」+体言止めの句(「古池や蛙飛び込む水の音」など)がよく詠まれるようになったという。しかし著者は、俳句にとって「や」「かな」「けり」などの「切字」は本当に必要なのか、また「切れ」は句の解釈によってどうともとれる曖昧なものではないかと問いかける。当たり前と思われていたことに根本的疑義を呈していて、説得力のある本だ。俳句界はこの問題提起に対して真剣に答える必要があるのではないだろうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください