2019年12月27日
1960年代の「異議申し立て」がピークを迎えたのは1968年である。「1968」に向かってあらゆる反体制運動が急坂を駆けのぼっていった。
だが、当時の(私を含めた)高校生たちの正念場は「1969」だった。1966年から1968年にかけて盛り上がった「全国学園闘争」は主に大学の出来事であって、多少そっちの気配のある高校生でも、まだ指を加えて見ているしかない隣の火事だった。
その「火事」がこちらへ燃え広がったのは1969年の春である。3月に各地で起きた「卒業式粉砕闘争」が発火点になった。4月~6月の一連の街頭行動にはこれまでにない数の高校生が参加した。そして夏休み明けから本格的な学内活動が始まる。10月以後は、毎週のように高校のバリケード封鎖や全学集会などが報じられた。小林哲夫によれば、この年、「高校紛争」は琉球政府と35都道府県で176校、208件に上った(『高校紛争1969-1970――「闘争」の歴史と証言』、2012)。
 卒業式闘争で東京駅八重洲口をデモする高校生たち=1969年3月19日
卒業式闘争で東京駅八重洲口をデモする高校生たち=1969年3月19日私の通った東京都立井草高校では、12月9日に校舎の一部がバリケード封鎖され、それをきっかけに生徒総会やクラス討論が連日行われた。校則や制服などの管理問題から定期考査や成績評価などの教育問題まで、多彩なテーマが議論の俎上に上った。
途轍もない高揚感があった。全校集会では、ふだんは大人しい女子生徒が教師に食ってかかった。つきあいのないクラスメートの破天荒な意見に聞き惚れたこともある。それまではほぼ無知だった私自身が、一番舞い上がっていた。
この「井草闘争」は、翌週の期末考査実施によって強制的に「収束」させられていったが、かかわった者たちのその後の生き方に大きな影響を与えた。むろん私もそのひとりだ。
「1969」から50年目の今年、当時の記憶や心境が多少でも再現できたらという想いから、1学年上の先輩や同期の仲間たちと小冊子をつくることになった。
冊子のタイトルは、一緒に世話人を務めてくれたT先輩と相談して、『1969 それぞれの記憶』とした。一人ひとりの寄稿者の立場や視点によって見えたものは違うだろうし、むしろその多様な(“それぞれの”)記憶の集合の中から何かが見えるかもしれないと考えたからだ。寄稿者は活動家やシンパに限定しない、「意見が異なっていても何かを感じていた」と思える人物に書いてもらおうということになった。
9月末に原稿が集まった。いったん引き受けながら、「棄権」を申し出た人もいた。それはそれで仕方がないと思った。結果的には、1970年卒業の9人と1971年卒業の9人が寄稿してくれた。ちなみに70年卒が学校群制度の1期生、我々71年卒が2期生である。
揃った原稿のタイトルは以下のようなものだ。
[一九七〇年卒]
あの時代から受け取ったもの
「クロノス」としての一九六九
遠い日々、遥かな日々
十二月までのこと
青春ドロドロ
こわいものなしだった
凍えた夜
ベトナム戦争と向き合った高校時代
五〇年前の記憶
[一九七一年卒]
もうひとつの世界が見えた頃
「委員会活動報告」と私の記憶
ずっと「夢」の中にいる
見た、聴いた、そして考えた
他者の論理に搦めとられることなく
一九六九年 ワタシのつたない備忘録
井草青春記
生涯一補欠
一九六九年の体験は世界とつながっていた
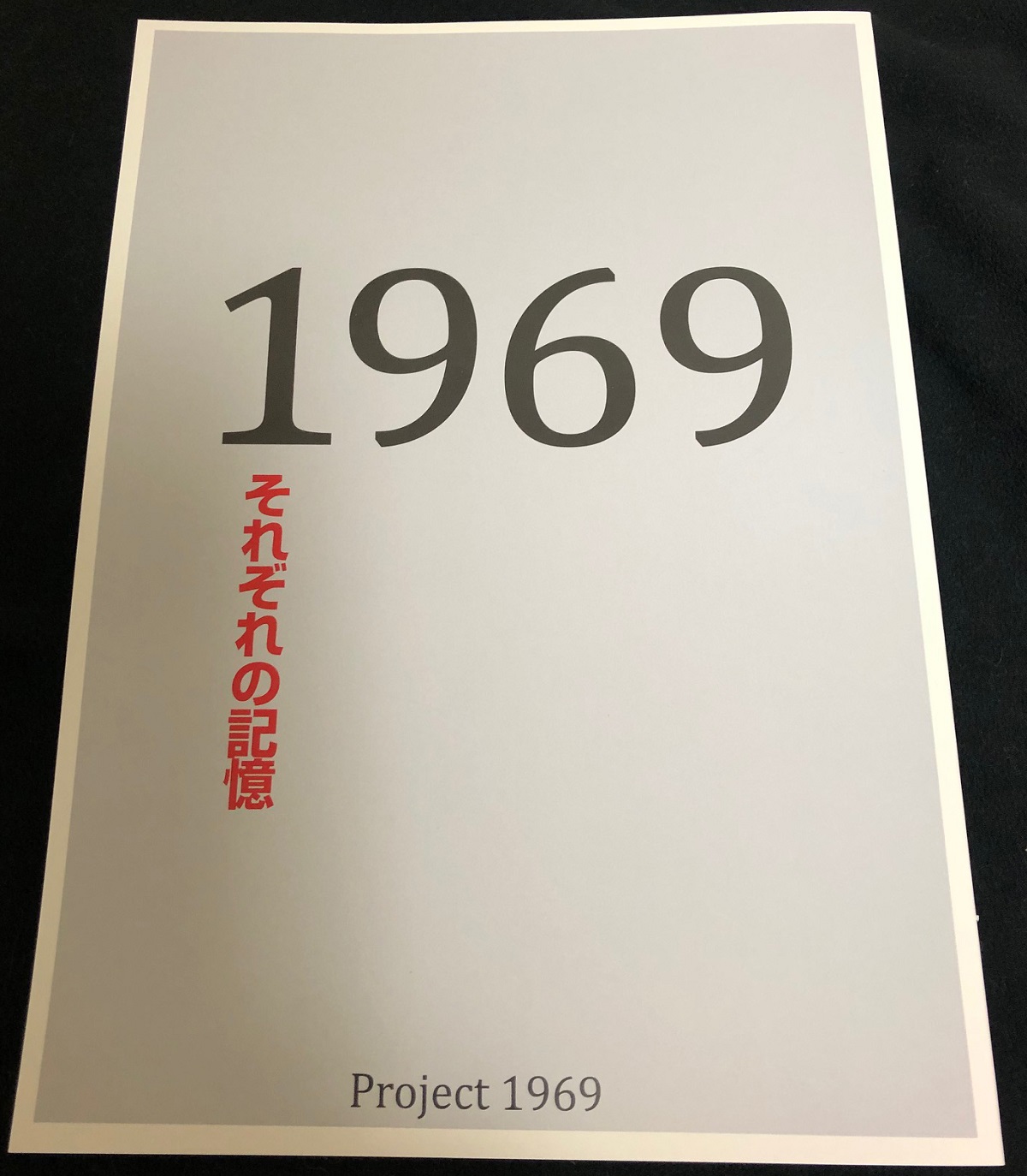 『1969 それぞれの記憶――Memories of 1969 in IGUSA Highschool』(2019)
『1969 それぞれの記憶――Memories of 1969 in IGUSA Highschool』(2019)それはいったい何なのか。
都立井草高校は、どのような意味でも有名校ではない。日比谷、西、戸山など名だたる都立進学校の知名度には遠く及ばない。スポーツなど課外活動でも(かつてはサッカーやハンドボールでならしたことはあったようだが)目立つものはなかった。1967年に始まった学校群制度によって、大泉・石神井高校と共に第34群を形成した結果、一番人気のない学校に転落し、振り分けで井草へ回された者たちの多くはわが身の不運を呪った。
井草高校の前身は、旧制の井草高等女学校である(1941年創設時は東京府立第18高等女学校)。1948年に新制都立高校として設置され、50年に完全な男女共学校になった(男女比率は約1対2)。この手の「旧高女」系の都立高校には、白鴎・竹早・駒場・富士などの「老舗名門校」もあるが、井草はそれら一桁ナンバースクールの威光を持つこともなかった。
ただ井草には、独特なリベラリズムの伝統があったという。『五十周年記念誌』(1991)は、その自由の気風について年代を追いながら繰り返し書いている。戦時中も英語の授業を続けたという伝説に始まり、敗戦後には民主主義の追い風を生徒も教師も存分に受けて、さまざまな改革運動に取り組んだと記している。政治動向に無関心だったわけではなく、60年安保闘争の国会デモに参加した先輩の話を聞いたこともある。
「自由の気風」は当時の都立高校に広く共通するものだが、井草の場合はデカダンスやシニシズムの雰囲気をまぶした大人っぽさもあった。それはたぶんに進学校受験に失敗した生徒が入る学校という「落ち校文化」によるものと考えられる。
私が1年生だった頃の3年生は学校群以前の最後の学年だった。男も女も実に成熟感のある大人に見えた(童貞も処女もあまりいなさそうだった)。圧倒的に恰好よく存在感漂う「2個上」の先輩は
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください