2019年12月31日
ぼくが2018年のベスト5の1冊に選んだ『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)は、多くの読者の賛同・評価を得、2019年ビジネス書大賞、山本七平賞など7つの賞を受賞し、すでに刊行部数30万部を突破している。
同書の中で著者の新井紀子は、「東ロボ」君プロジェクト(の「失敗」)の結果、意味を理解する力・読解力において、AIは人間を超えることはできないことを実証、説明した。
が、同時に、AIの弱点を探るべく作成したリーディングスキルテスト(RST)の実施により、AIが苦手とする読解問題を、同様に解けない人間が増えてきていることも明らかになった。これでは、AIの劇的な進化によってではなく、人間の退化によって「シンギュラリティ」が到来する。
今年9月刊行の続編、『AIに負けない子どもを育てる』(東洋経済新報社)で新井は、人間の読解力の減退の原因を、「ゆとり教育」だ「アクティブ・ラーニング」だと「新しい時代の教育」が喧伝されるたびに揺れ動く文科省とともに迷走を続けてきた、小学校教育の現場の混乱に見る。
たとえば、最近の教室では、「黒板を写させる活動は、アクティブ・ラーニングではなく、一方的な教え込みだから」と、ノートをあまり取らせないらしい。その代わりに、教師は生徒たちに穴埋めプリント、ドリル類を次々に与えているという。
だが、新井によれば、穴埋めプリントなどによってキイワードを覚え込み、それでテストの点を稼ぐ手法は、機械学習が膨大なデータからパターンを見出すのと同じであり、そうした習慣が土台となった「AI読み」は、人間が本来得意であった読解力の育成にはつながらない。そして、ある段階で、穴埋めプリントやドリルから子どもたちを徐々に卒業させ、板書をリアルタイムで写せるように指導するべきだと、新井は言う。
その提言に、ぼくも大いに賛同する。板書をノートに写すという作業は、機械的に見えて実は生徒一人ひとりの工夫が必要な作業だからだ。かつて学習雑誌の新学期号には、「ノートの取り方」という特集が必ず組まれていた。
 新井紀子
新井紀子ただ、国語以外の教科書をきちんと読めない状況を憂うる新井が、国語の教科書教材の大半が文学作品であることをあまりに問題視するのは、理解はできるが危険も感じる。全教科で学習の基礎となる「論理読み」の大切さは十分に認めるが、新井自身が「『正確に説明する』活動はまさに『プログラミング教育』の基本なのです」と(ここではいい意味で)言っているように、行き過ぎると再びコンピュータ至上主義、AI礼賛という、本来新井がそこから逃れようとした道に、再び引き込まれる可能性があるからだ。
その点、文学世界、芸術世界、人間の主観のすべてが、自然科学が記述する「客観的世界」と同様に実在すると説くマルクス・ガブリエルの「新実在論」は、自然主義=自然科学至上主義を根底から批判、AI礼賛を退ける。
『「私」は脳ではない――21世紀のための精神の哲学』(講談社)においてガブリエルは、人間の「意識」を、客観的「物」と関わりそのことを通じて他者と関わる「志向的意識」と、意識的で純粋に主観的な体験の質感であるクオリアを伴う「現象的意識」のコンビネーションと捉える。そして、記号の連鎖からなるAIは「現象的意識」を持ち得ず、人間になり変わることはできない、と言う。
「私」を脳という物であるとする自然主義の根底には、「自分が自由であること、そして他者もまた自由であることを直視するのは、とてもしんどい。できることなら、誰かに決定を委ねたい」という〈解放幻想〉がある。AIが全ての能力において人間を凌ぐ、人間よりも正しい判断をする転換点=「シンギュラリティ」を待望する現代の人間は、自らが自由に判断するよりも、より優れた誰か、何かの判断に従うことを志向しているのだ。
それを、実に危険な状況と見るガブリエルは、本書の目的を、「自己決定という精神の自由の擁護」と宣言する。
 マルクス・ガブリエル
マルクス・ガブリエルそんなガブリエルに、ドイッチャー賞を獲得して凱旋した気鋭の哲学者斎藤幸平が「日本でも落合陽一という研究者が、身分制の復活、あるいは技術を操ることのできる1%の人間による支配という将来像を肯定的に描き、人気を博すなど、悲惨な事態になっています」と語る『未来への大分岐――資本主義の終わりか、人間の終焉か?』(集英社新書)は、今最も気になる3人の知識人と対峙する、実に嬉しい、贅沢な対談集だ。
対談相手はまず、〈コモン〉の民主的な共有と管理を求める社会運動の興隆、発展を追い求める、『<帝国>』『コモンウェルス』のマイケル・ハート。
そして「〈世界〉は存在しないが、すべては存在する」と主張しながら、同時に「但し、存在するものがすべて真実であるわけではない」と喝破、社会構築主義⇨「ポスト真実」という今日の潮流に対抗するため、啓蒙やカント的倫理の有効性を唱えるマルクス・ガブリエル。
そして最後に、情報技術の発展が「限界費用ゼロ」をもたらし、価値を生み出さなくなることで資本主義は自ずと終焉すると主張する、『ポストキャピタリズム』のポール・メイソン。
彼らに、そして斎藤に共通するのは、現代の危機に、真っ向から立ち向かい、あるべき未来を志向、構想しようとする、諦めることなき姿勢である。
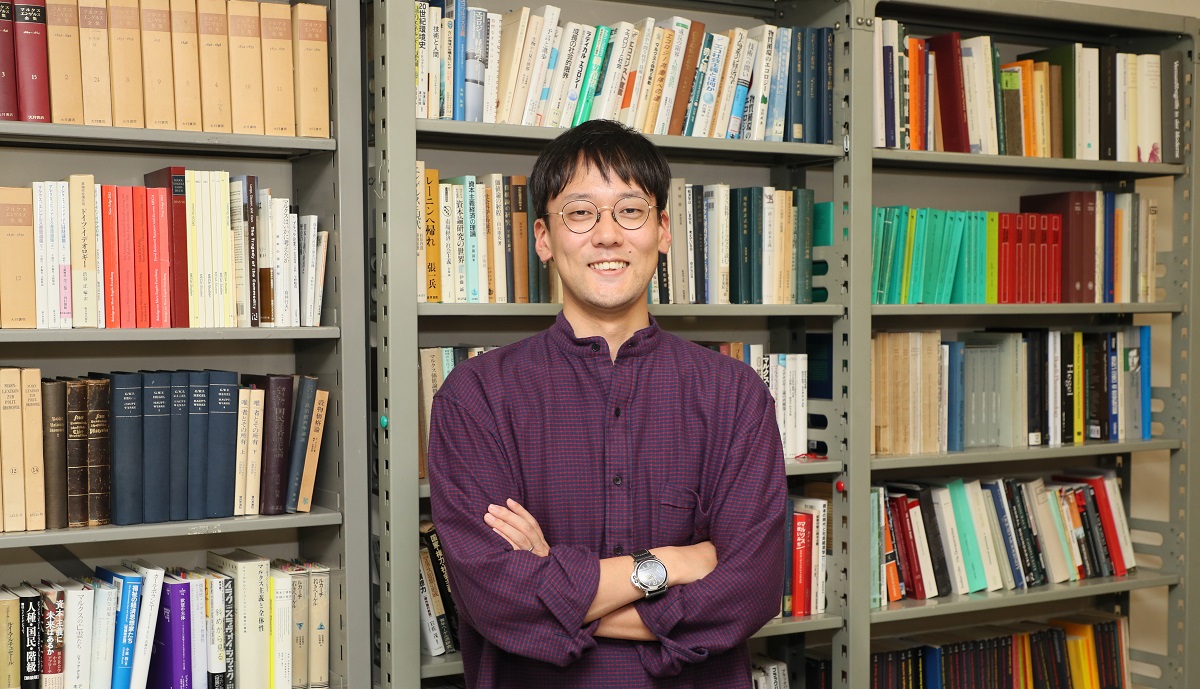 斎藤幸平
斎藤幸平斎藤はそれぞれの言説に、ただ肯うだけではない。ハートのBI(ベーシック・インカム)への期待には「貨幣こそ資本主義の根幹的な問題」ではないか、と疑念を表し、ガブリエルの〈新実在論〉が意に反して相対主義を招来する危険を指摘、モリスンの「資本主義終焉」のプロセスが情報技術の進化に期待しすぎており、「加速主義」に親和的でさえあるのではないか、と疑問を突きつける。
そうした斎藤の対峙姿勢による各々の主張の「衝突」こそが、更なる議論を生み出し、「次の段階を考えるヒント」を掘り出していく。
更に斎藤は、決して「議論の人」に留まらない。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください