『夢も見ずに眠った。』『8050問題の深層』『分解者たち』『セロトニン』……
2019年12月30日
鈴木久仁子(編集者・朝日出版社)
川上未映子『夏物語』(文藝春秋)
最も圧倒された本。一人でここまで考え、どのページにも目が貼りついて離れない引力ある物語で、今、そして未来の人間に足下から問いを突きつける人がいることに圧倒されました。
いろんなものの色、かたちがバッと頭にこびりつき(主人公の夏子の姉、巻子の乳首が銭湯の湯から現れる場面が大好き)、至るところで投げかけられる問い(なぜ大人は酒を飲むか/会ってみたいという気持ちの不思議など)に惹きつけられ、やがて私たちが立つ根本を揺らがす問題にぶちあたります。
ぬぼっと生きてる私には(たとえば、いないほうがよかったということはないんじゃないか、いいわるいも理由もないと、大多数の人と同じように思っている)ここで問われていることに何があるのかわからないところも。光と闇をももたらすエネルギーの塊みたいです。「間違うことを選ぼうと思います」と夏子が震える声で伝えたこと、それを抱えて広げていければいいのでしょうか。
絲山秋子『夢も見ずに眠った。』(河出書房新社)
最も読んでいる時間が愛おしかった本。
(以前ご紹介した詳細はこちら)
最後の場面で起きていること、こういう瞬間を人と分かち合うことは、めったに訪れないことかもしれませんが、きっと誰にでも開かれているとも思いました。
 絲山秋子『夢も見ずに眠った。』(河出書房新社)
絲山秋子『夢も見ずに眠った。』(河出書房新社)小川さやか『チョンキンマンションのボスは知っている――アングラ経済の人類学』(春秋社)
最も現実が力をくれた本。
世界各地から商売人が香港を訪れ、中国製品を買い付け、インターネットで通信し、母国へ輸出する。そんな国境を越えるインフォーマル経済の台頭に胸躍らせ、小川さんが訪れたチョンキンマンションという複合ビル。そこで出会ったボス・カラマとタンザニア人たち。しょぼくれた顔で仲間から金を借り、ネットの面白動画を探してばかり、そんなカラマと同行するうちに見えてくる経済、助け合い、信頼構築の仕組み。
現在進行形の瑞々しいレポートから導き出される論理は、日本で暮らす私たちが直面する問題を地続きで捉える。具体例の一つひとつに驚かされ、知るとなぜだか何ともいえない楽しさが湧いてくる。心とからだを開き、未知のものに賭けてみること。その軽やかさと力強さが本から届き、先の見えない未来を楽しく感じ始め、小川さんと共にカラマたちを好きになっていくのです。
堀 由紀子(編集者・KADOKAWA)
ブレイディみかこ著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)
各賞を次々に受賞している本書。当たり前だと思っていることに静かに問いかけてくる内容で、私にとっても大切な一冊になった。イギリスに住む著者と中学生の息子の日常を描く。難解な記述はどこにもなく、お風呂上がりにソファに横になりながら気楽に読める。なのに人物の行動が、言葉が、激しく揺さぶりをかけてくる。
なかでも「多様性」という言葉は鮮烈だった。多様性はない方が楽だけれど、楽ばっかりしていると無知になる――この言葉が強く印象に残った。
「おめえ、ちょっとアンプの音量を落としてくれねえか」と、べらんめぇ調のアイルランド人の夫がまた素敵。何度も読み返したくなる本。
 ブレイディみかこ
ブレイディみかこカルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』(冨永星訳、NHK出版)
タイトルから懐疑的な気持ちで手に取ったのだが、読み進むうちに引き込まれた。
本書では「今」という概念に意味がないと述べる。何光年か先に移り住んだとき、地球の家族は「今」なにをしているのか、と問うこと自体に意味がない、と。とはいえ私たちは時間の概念から離れられない。後半でその理由を考えていくのだが、進化や脳科学、ブッダ、詩人や哲学者などが次々に話題を展開する。難解なところもあったが、時間と空間を超えた思索の旅をさせてもらった。
川北稔著『8050問題の深層――「限界家族」をどう救うか』(NHK出版新書)
今年、ひきこもり状態だった人が関連する事件があり手に取った。本書では61万人超いる40~60代のひきこもり状態にある人とその親の問題を取り上げる。
就職の失敗や交通事故など、ひきこもりのきっかけは他人事ではない。親たちもいつまで続くのかと苦悩する。そこには恥の意識からくる孤独がある。
もっと早く社会が手を打っていたならば。そのとき何もなくても、20年後に顕在化してくるのだ。未来を今、考える必要性を思い知らされた。
プライベートな時間は物語の世界に逃避行している私だが、なぜか読んでも頭に入ってこない時期があった。そんなときに出会った若松英輔さんの『本を読めなくなった人のための読書論』(亜紀書房)。寄り添うような文章に励まされた。小説は、8年ぶりに新刊が出た大沢在昌さんの『暗約領域 Ⅺ 新宿鮫』(光文社)を愛おしく読んだ。前作で最大の理解者を失った主人公にとって、新しいフェーズに入ったかのような今作。30年間、鮫を活躍させ続けている著者の仕事ぶりにも感動。
渡部朝香(出版社社員)
猪瀬浩平『分解者たち――見沼田んぼのほとりを生きる』(生活書院)
いまこの時代に言葉を受け取れることを心から感謝する書き手のひとりに、藤原辰史さんがいる。藤原さんが今年上梓した『分解の哲学――腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社)は、生産をよしとする価値を転倒させ、統治をすりぬける「分解者」を描いた、愚直にして鮮やかな叛逆の書だった。その志と「分解」という言葉を共有する『分解者たち』も、猛烈な魅力をそなえた一冊だ。著者・猪瀬さんの兄には障害があり、一家は障害者運動と埼玉の見沼田んぼの開発問題が交錯する場で模索を続けてきた。猪瀬さんは家族の歴史を見つめなおすのと同時に、研究者として調査を踏まえ、見沼田んぼと周辺地域に生きるものたちの来し方を掘り起こす。障害のある人や朝鮮半島をルーツにする人もいれば、野宿者もいる。人間ではない生きものもいる。「とるに足らない」とされたものたち、どこにでもありそうな世界の、かけがえのなさ。論文とエッセイの間で揺れるかのような表現は、言葉にしがたいものを言葉にする悶えのようでもあり、だからこそ切実に届く。自分が生きる場所の分解者たちを感知せよとの呼び声が聞こえる。
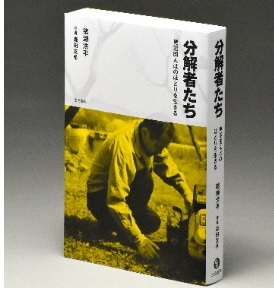 猪瀬浩平『分解者たち――見沼田んぼのほとりを生きる』(生活書院)
猪瀬浩平『分解者たち――見沼田んぼのほとりを生きる』(生活書院)レベッカ・ソルニット『迷うことについて』(東辻賢治郎訳、左右社)
移民だった曾祖母、酷いことに遭った幼少期の家、早世した友人、かつて愛した男――。個人の経験と歴史を撚り合わせて論を展開するソルニットの著作のなかでも、この本はとりわけ私的な語りとポエジーが際立つ。青についての論考も収められ、ブルーな憂愁が立ち込めているが、そこに貫かれているのはジョン・キーツの思考、「偉大な達成をつくりだす資質は〔略〕不確実な状況や謎や疑いのうちにとどまっている能力、消極的能力(ネガティブ・ケイパビリティ)」だ。ソルニットはいう、個人的な小さな物語は世界の大きな物語とマトリョーシカのような入れ子になっている、と。「作家、歴史家、アクティビスト」というソルニットのプロフィールを敬愛する。わたしも、だれしも、そうであれたら。
[書評]レベッカ・ソルニット『ウォークス』
エドゥアルド・ガレア―ノ『日々の子どもたち――あるいは366篇の世界史』(久野量一訳、岩波書店)
出会ったばかりの本だが、すっかり魅了された。1月1日から366日、その日にまつわる一話が収められている。はるか古代からごく最近まで、隠された蛮行、顧みられることのない出来事、勇敢に抗った人たちなどの、小さな歴史の数々。ウルグアイ出身のガレアーノは、ジャーナリストとして投獄され、亡命に追い込まれた。ローザ・ルクセンブルクの命日の1月15日には、こう書かれている。「ローザは、自由の名のもとに正義がないがしろにされたり、正義の名のもとに自由がないがしろにされたりすることのない世界を望んでいた。毎日、誰かがその旗を拾い上げる。泥に落ちた、その靴のように」。
高橋伸児(「論座」編集部)
ミシェル・ウエルベック『セロトニン』(関口涼子訳、河出書房新社)
農業食糧省に勤務する中年の「ぼく」は、交際している日本人女性が乱交パーティーに出ていたことを知る。これを一つのきっかけに彼女から“蒸発”し、抗鬱薬を服用しつつ、フランス国内を彷徨する。絶望の闇を抱えた道行きの途中、かつて関係をもった女性たちを回想し――性的な快楽の記憶も交えて――再会を求めさえするが、むろん彼女らも人生の澱を抱えながら生きていた。そこに欧州の一体化とともに衰退する農業を営む旧友の自暴自棄が錯綜する。フランスにイスラム政権が樹立される近未来を描いた前作『服従』は、シャルリー・エブド襲撃事件の日に発売され、「予言の書」として衝撃を与えたが、本作も、人間の個人主義、ニヒリズム、孤独、退廃とグローバル社会の行き着いた果てを活写したリアルと「予言」に満ちている。読んでいて陰々滅々となるが早々に再読したくなるほど魅惑的なのはなぜなのか。
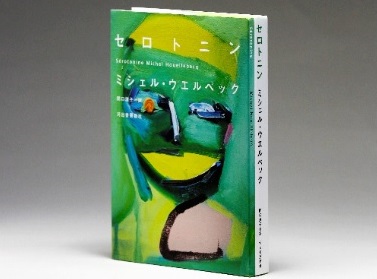 ミシェル・ウエルベック『セロトニン』(関口涼子訳、河出書房新社)
ミシェル・ウエルベック『セロトニン』(関口涼子訳、河出書房新社)横田増生『潜入ルポ amazon帝国』 (小学館)
上記『セロトニン』の一つの軸であったグローバル化の表象がアマゾンだ。今や買えない商品がないほどで社会的インフラとさえ言えるだろう。創業者ジェフ・ベゾスが大河にちなんだ社名そのまま、世界の資本主義市場をのみ込んでいるのだ。著者は15年ぶりにアマゾンの物流センターで働き、配送トラックに同乗し過酷な労働を実体験する。さらに、この巨大企業の租税回避の方策やフェイクレビューのからくりも暴露しつつ、アマゾンプライム、マーケットプレイス、アマゾン・ウェブ・サービスという経営3本柱の実態を検証する。読みながら、この会社の凄まじい強欲体質に驚きながらも、もはや現代人は「アマゾンとともに生きる」しかないと観念する(著者自身がアマゾンのヘビーユーザー)。ではどう生きるか、そのための膨大な情報と方策が本書にある。
労働現場に潜入取材した海外の優れたルポを読む
湯澤規子『7袋のポテトチップス――食べるを語る、胃袋の戦後史』(晶文社)
いくらアマゾンで生鮮食料品まで買えるようになっても、「食べる」という人間の根源的な行為は綿々と続いていく。しかし、かつて五感を総動員して味わってきた食が、栄養素やエネルギー、カロリーという数値に還元され、「頭で食べる」人たちが増えているのだ。戦前から現在まで、貧しかった食生活から飽食に至る食の風景を味読しつつ、「GAFA」という怪物が、人々の行動様式や感覚の変容を強いていることまであらためて考えさせられた。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください