2020年02月03日
昨年(2019年)は中山祐次郎さんと山本健人さんという、二人のお医者さんの本の編集を担当した。中山祐次郎さんの本は『泣くな研修医』という小説、山本健人さんの本は『医者が教える 正しい病院のかかり方』という新書だ(ともに幻冬舎)。
中山さんは郡山の総合南東北病院の勤務医、山本さんは今は京都大学大学院に在籍している。二人とも専門が消化器外科で30代ということに加えて、大きな共通点がある。「一般の人たちに向けて、正しい医療情報をわかりやすく発信する」ことに、並々ならぬ使命感をもって、エネルギーを注いでいる点だ。
 山本健人さん(左)と中山祐次郎さん=2020年1月11日、幻冬舎大学主催のトークイベントで 筆者提供
山本健人さん(左)と中山祐次郎さん=2020年1月11日、幻冬舎大学主催のトークイベントで 筆者提供ウェブ上の健康・医療情報には科学的根拠がない間違ったものが多いことはかねがね指摘されていた。それが広く知られるようになったきっかけは、2016年のWELQ(ウェルク)事件だ。WELQという医療健康情報サイトに「肩こりは幽霊が原因のことも?」などのトンデモ記事が多数掲載されていることが問題視され、運営会社の社長が謝罪し、サイトは閉鎖された。
この頃から、医師をはじめとする医療関係者や医療ジャーナリストによる、SNSでの情報発信が盛んになった。中山さんは「発信する医師団」、山本さんは「SNS医療のカタチ」といったゆるやかなネットワークを立ち上げ、ウェブでの情報発信だけでなく、リアルでもイベントを行うなどして、啓蒙活動に励んでいる。これらの活動はすべて忙しい本業の合間を縫って行われ、基本的に手弁当だ。
間違った医療情報の影響がとくに大きいのは、やはりがんに関する情報だ。「二人に一人ががんになる時代」と言われ、圧倒的に関心が高いし、間違った治療法の選択は命の危機に直結する。
お二人と仕事をしていた関係で、昨年後半は、医療関係のイベントにも何度か参加した。9月に開かれた朝日新聞withnews主催の「やさしい医療がひらく未来」というイベントでは、大須賀覚さんというアメリカ在住のがん研究者から、驚くべき、そして書籍編集者として猛省させられる発表があった。
2019年9月のある時点で、大須賀さんがAmazonの「ガン関連」ジャンルのランキング上位12位までに入る書籍を調べたところ、科学的に裏付けられた正確な内容が書かれたものは、たった3冊だったというのだ。
がん治療について、中山さんや山本さん、大須賀さんが主張するのは、決して難しいことではない。きわめてシンプルだ。すなわち、がんが見つかったときの治療法の選択は、「標準治療」一択だということ。
標準治療とは、手術・化学療法(抗がん剤)・放射線等、がんの部位と進行度に応じて効果があると検証され、学会が発表する「ガイドライン」に記載された治療法のことだ。
中山さんの言葉を借りれば、松竹梅の「竹」(中くらい)ではなく「松」(最上級)の治療であり(『がん外科医の本音』SB新書)、山本さんの言葉を借りれば、保険診療の範囲内で提供してもらえる「最も有効な治療」(『医者が教える 正しい病院のかかり方』)。
国立がん研究センターの「がん情報サービス」というサイトでは、「科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療」と説明されている。
この原稿を執筆中にチェックしたAmazonの「ガン関連」ジャンルのランキング上位には、素人の私が見ても明らかにアヤシイ食事療法や代替療法や医療否定の本がまだ多くある。だが、心あるお医者さんたちの献身的な情報発信により、医療本をとりまく空気は、この1~2年で大きく変わった。
昨年11月には、朝日新聞で大きな広告が掲載されたがん治療本について、腫瘍内科医の勝俣範之さんがSNS上で「科学的根拠がない」と指摘、朝日新聞社広報部が「広告表現には疑念があり、十分な検討を行うべきだった。掲載判断にあたっては、慎重なチェックに努めていく」という主旨のコメントを発表した。
中山さんの著書『医者の本音』『がん外科医の本音』(ともにSB新書)、極端な主張も不安を煽る記述もない、まっとうな医療本だが、多くの人に読まれている。私が担当した、山本さんの『医者が教える 正しい病院のかかり方』も、自分で言うのもなんだが、タイトルといい、テーマといい、内容といい、とてもまっとうだ。で、自分のこれまでの編集者的経験則で言えば、「医療もので、こういうまっとうな本は売れない」。だが、結果としてこの本も多くの人に読んでいただいている。
トンデモ本が売れるという状況はまだあるが、「まっとうな医療本」を求め、応援する読者は確実に増えているのを実感する。風向きは確実に変わりつつある。
 がん治療のトンデモ本が数多あるなか、「まっとう本」を求める読者も増えている=長野県立図書館
がん治療のトンデモ本が数多あるなか、「まっとう本」を求める読者も増えている=長野県立図書館そんなこんなで、中山さん・山本さんとの仕事を通して、がんの予防や検診や治療について、患者予備軍として知っておいたほうがいい、ひととおりの知識は身についた。個人的には、当分こういった本は読まなくていいだろう。入っている生命保険の更新で「先進医療特約をつけたほうがいいですよ」と勧められたときも、「私は保険診療で受けられる医療だけでいいです」ときっぱり断われた。実際がんに罹ったらそれはショックだろうけれど、治療法で大きく悩むことはないだろう……そんなふうにさえ、思っていた。
ところがだ。そんなわかった気分、ある種の達観した気持ちは、あえなく打ち砕かれてしまった。2冊の本、坂井律子さんの『〈いのち〉とがん――患者となって考えたこと』(岩波新書)、宮野真生子さんと磯野真穂さんの『急に具合が悪くなる』(晶文社)を読んだからだ。
坂井さんはNHKのディレクター・プロデューサーとして、福祉・医療・教育などの番組制作に携わってきた。2016年に膵臓がんと診断され手術。その後の、再発、抗がん剤治療、再手術、再再発という闘病の日々を綴っている。
 宮野真生子・磯野真穂著『急に具合が悪くなる』(晶文社)
宮野真生子・磯野真穂著『急に具合が悪くなる』(晶文社)『〈いのち〉とがん』を読んでショックを受けたのは、闘病は身体的にこんなに苦痛を伴うのかということ。手術後の後遺症や、抗がん剤の副作用。そんなところで読者を怖がらせるのは坂井さんの本意でないと思うのだが、感情を排して細部まで具体的に綴られる描写が壮絶で、「これ以上読み進めるのはつらい」と思うほどだった。
坂井さんが強く訴えていることのひとつは「何を食べたらいいのか」問題だ。それは糖質を摂らないとか肉を食べないとか野菜ジュースを飲むとかといった、世間に出回る食事療法の話ではない。食欲不振や副作用の味覚障害などにより、生きるために必要な最低限のエネルギーと栄養すら摂れなくなってしまうという問題だ。
病院では栄養指導も受けた。だが、「何だったら食べられるのか」がわからなくなっていた坂井さんにとって、「食べられないときは食べたいときに食べたいものを少しずつ」といったざっくりとした指導は、ほとんど役に立たなかったという。
たとえば高栄養で必須食品として薦められる卵なら、生か卵焼きかゆで卵か、ゆで卵なら半熟か固ゆでか、こんな症状がある人はこうすれば食べられる、という「具体的工夫のディテイル」が知りたかったという。そのような個々の患者さんたちの体験を集積したデータベースが必要だと坂井さんは述べる。
これは現代のがん医療に欠けていること……というより、手が回っていないことなのだと思う。中山さんや山本さんと仕事をしてあらためてわかったことだが、とにかく現場のお医者さんは忙しい。看護師さんも当然忙しい。
患者さんが「何だったら食べられるのか」がわからなくて困っていることを、医療関係者は決して軽んじているのではないと思う。ただ、そこまではなかなか手が回らない、責任をもってケアできない、ノウハウも足りない。だから、コアとなる標準治療の周辺を補完する情報とその発信者が必要で、それには、当事者である患者さんの協力も欠かせないだろう。
そして、『急に具合が悪くなる』を読んで突きつけられたのは、標準治療をやり尽くしたあとの時間がある、ふつうに仕事をして生活をする「日常」があるということだ。宮野さんと磯野さんの往復書簡はまさにその時期、宮野さんの受けられる治療が終わり、緩和病棟に入るほど体調が悪化していないときに始まった。
宮野さんは再発がわかり、多発転移という状態になった2018年の秋に、主治医から「急に具合が悪くなるかもしれない」と言われた。その後主治医は、「念のため、早めにホスピスを探しておいてほしい」と話を続け、宮野さんは「急に具合が悪くなる」とは何を意味しているのかを悟ったという。本のタイトルはそこから来ている。
宮野さんは、「いつ死んでも悔いのないように、という言葉は美しい。でもそれでは未来のために今を使うみたいではないか。そこには欺瞞があるのではないか」「がんになった自分は不幸なのか。不運だけれど不幸ではないのではないか」等々の剛速球の問いを投げ続ける。磯野さんはそれを真正面から受け止め、往復書簡の後半では、返信を書くたびに「魂の抜け殻」のようになっていたという。
体調が悪化し、大量のモルヒネを摂取しながら生活するようになっても、宮野さんは磯野さんに書き続けた。「痛みと死において自分を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す。これを哲学する者の業と言わずして何と言うのでしょうか」。
 TORWAISTUDIO/Shutterstock
TORWAISTUDIO/Shutterstock宮野さんは強い。坂井さんも強い。でも自分はどうだろう。受けられる治療がなくなり、遠からず死ぬことは確かで、あとは緩和病棟に入るのを待つだけ、という状況に耐えられるんだろうか。「なぜ私が?」という理不尽に、怒り悲しむことしかできないんじゃないだろうか。
本を読んで、宮野さんと磯野さんの、いのちの極限状況での言葉の応酬に感動しながら、「そんなことはできない、耐えられない」「そんな状況になりたくない」と、すっかり怯み、脅えている自分がいた。
だが、そこで思い至るのは、「急に具合が悪くなる」とは、決して極限状況ではなく、今この瞬間の自分もまさにそうなのだということだ。明日の予定も、著者と約束した刊行のスケジュールも、果たされる保証はどこにもない。その点では私だって、「自分が磯野さんとする『約束』とは何なのか」と問い続けた宮野さんと同じだ。
だとしたらどうするか。「がんにはなりたくない」とビビりながら、できるのは、今やりたいこと、今やらなくてはいけないことを、自分にできるだけウソをつかず、誠実にこなしていくこと。今を大切に生きること、という、ごくごく平凡な答えにたどりつく。
さらに、がんになるのが怖いなら、がんを100%予防することはできないわけだけれど、効果が実証されているがん検診を受けるとか、予防に効果があると実証されている生活習慣を守るとか(お酒は飲みすぎない!)など、中山さんや山本さんから学んだことを実践する。「振り出しに戻る」だ。
そもそも中山さんや山本さんが、誰から頼まれてもいないのに現在の活動を始めたスタート地点には、救えなかった多くのいのちに対する無念な思いがあった。「白衣を着て病院にいるときは、私は淡々とがん患者さんの手術や治療を行います。……しかし、思うことは山ほどある。悔しくて眠れぬ夜があり、恐怖を酒と飲み下す夜があります」と、中山さんは著書の冒頭で書いている(『がん外科医の本音』)。
どんなに手を尽くしても、がんで死んでいく患者さんをゼロにはできない。でも、間違った医療情報のせいでいのちを落とす人を減らすことはできる。中山さんは、自分と志を同じくする医療関係者に、どんどん情報発信し、本を書いてもらい、「良貨が悪貨を駆逐する戦略でいく」と言っている。
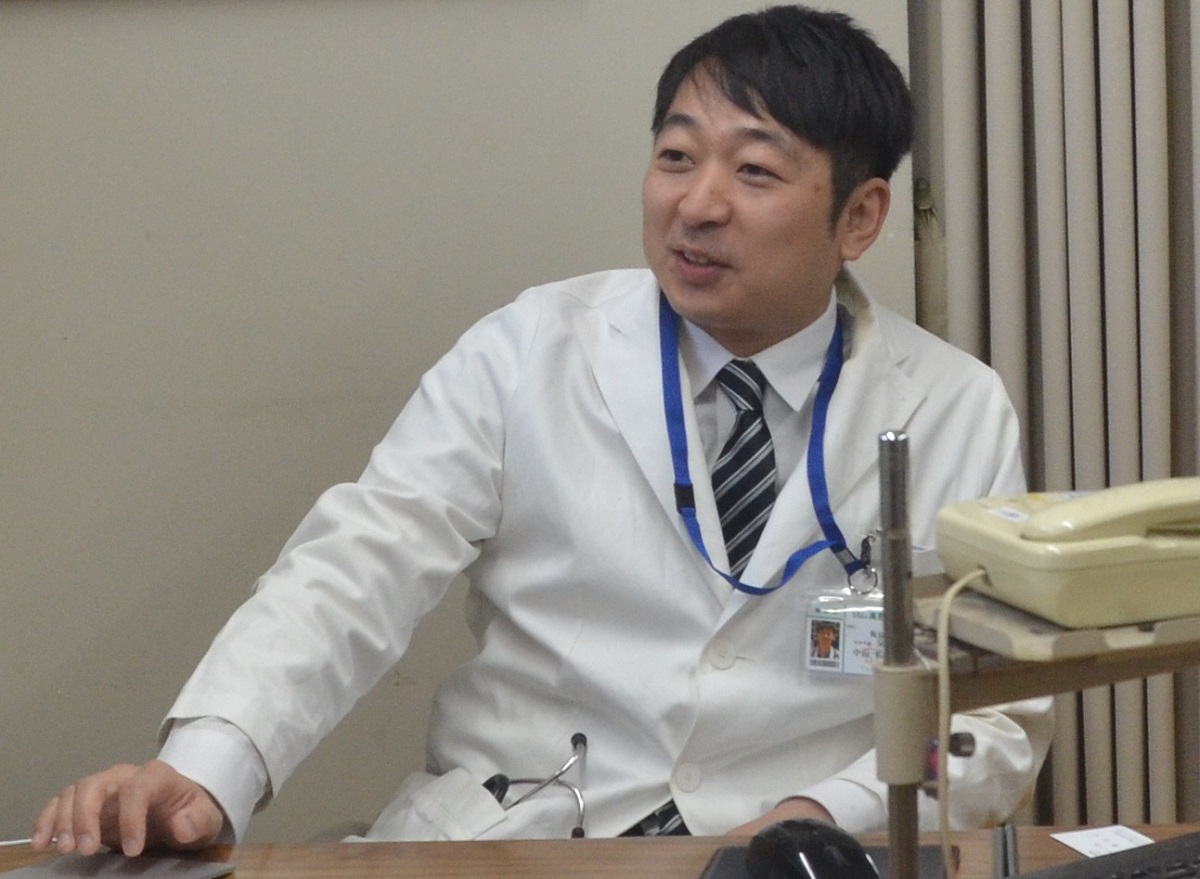 「良貨が悪貨を駆逐する戦略でいく」という中山祐次郎医師
「良貨が悪貨を駆逐する戦略でいく」という中山祐次郎医師私も編集者として、「まっとうな医療本」を出そうとする中山さんや山本さんのような書き手、そして、それでも医療だけでは救いきれない、生きることと死ぬことの理不尽さについて、いのちが尽きるぎりぎりまで語ってくれた宮野さんや坂井さんのような書き手の言葉を、世界に届けるお手伝いをしていきたいと思う。
宮野さんは、磯野さんとの往復書簡を続ける「約束」についてこう記している。
「『死なない』ことの約束じゃない。磯野さんが希望し、私も見たいと望む未来に対する賭けであり、そこに向かって冒険の道をくじけず歩んでゆくということの覚悟であり、なによりも、そんな言葉を投げかけてくれた磯野さんと私の今の関係への信頼なのです」
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください