2020年03月06日
20世紀後半のフランス映画音楽の第一人者、ミシェル・ルグラン(1932~2019)。彼が楽曲を手がけた数々の映画の中から、選(よ)りすぐりの7本が東京・YEBISU GARDEN CINEMAで上映中だ(特集上映「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」)。
演目は、ジャック・ドゥミ監督(1931~1990)の『ローラ』(1961)、『シェルブールの雨傘』(1964)、『ロシュフォールの恋人たち』(1967)、『ロバと王女』(1970)、ジャン=リュック・ゴダール監督 (1930~) の『女は女である』(1961)、『女と男のいる舗道』(1962)、アニエス・ヴァルダ監督(1928~2019)の『5時から7時までのクレオ』(1961)。いずれも見逃せない逸品だが、本稿では、ミシェル・ルグランと計11本の映画を“共作“し、互いが「双子の兄弟のような関係」と公言していたジャック・ドゥミの前記4作品を2回にわたって取り上げたい。
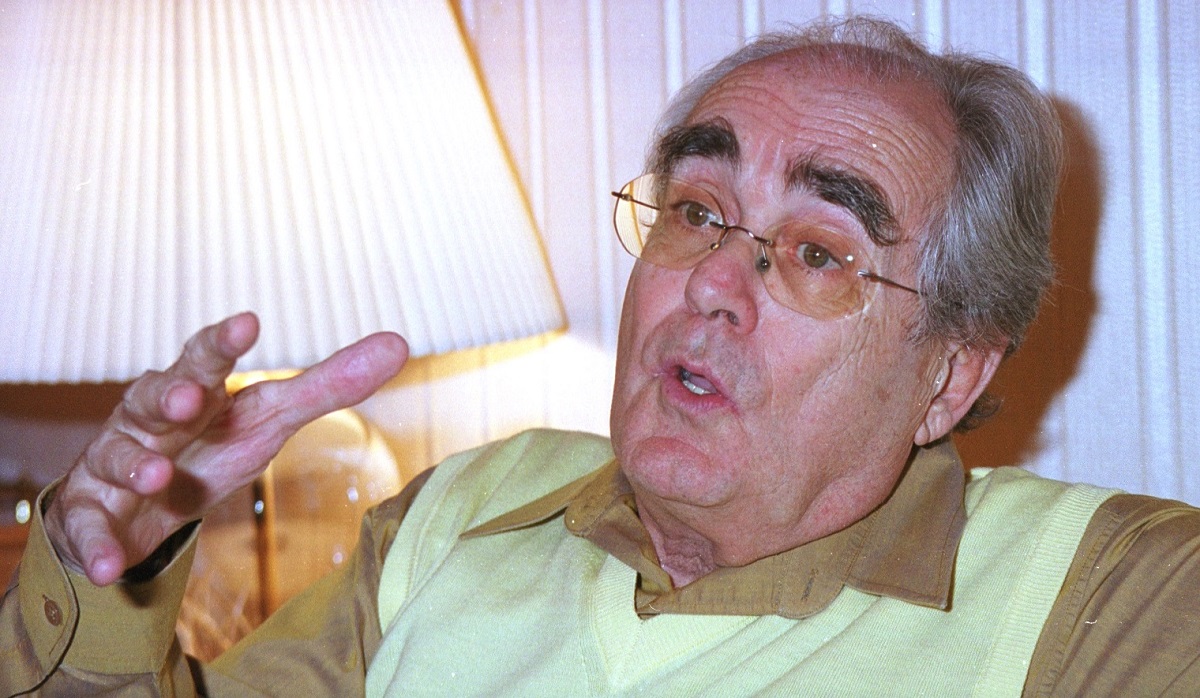 ミシェル・ルグラン(1932―2019)
ミシェル・ルグラン(1932―2019)なおフランスの「ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)」は、厳密には1950年代末~60年代初頭の、ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロルらを旗手とする、ロケーション撮影・低予算早撮り・即興演出を重視した“映画革命”をさす呼称だが、今回の特集タイトルのように、大まかに1960~70年に撮られたフランス映画をさすこともある。
そして、ドゥミや1962年に彼と結婚したアニエス・ヴァルダは、ヌーヴェルヴァーグの中心的存在であったゴダール、トリュフォー、シャブロルらが「カイエ派」――事務所がセーヌ河右岸にあった「カイエ・デュ・シネマ」誌を拠点とした――と呼ばれたのに対し、セーヌ河左岸を交友の場としたことから「左岸派」と呼ばれたが、両者は敵対するグループではなく、協力関係・共闘関係にあった“同志”だった。ちなみにトリュフォーの長編第1作『大人は判ってくれない』(1959)には、ドゥミがワンシーン、友情出演している。
では、ドゥミの作家的特徴はといえば、映画史に亀裂を入れたゴダールの過激さや、鮮烈で痛切な子供映画や恋愛映画の名手トリュフォーの先鋭さ、あるいはサイコスリラー風の犯罪映画を偏愛したクロード・シャブロルの異形さとも異なる、恋愛ドラマを甘美で儚(はかな)く辛辣なお伽話調のミュージカルに昇華する作風や、しばしば男女の出会い・すれちがい・別れの連鎖をロンド(輪舞)のごとく描く作劇、あるいは19世紀の文豪オノレ・ド・バルザックの「人間喜劇」のような、複数の作品にまたがって何人かの人物を登場させる<人物再登場>の手法に、それは顕著である。
■『ローラ』(1961、モノクロ)
「ヌーヴェルヴァーグの真珠」と呼ばれるドゥミの処女長編。ドゥミが少年期を過ごしたフランス西部の港町ナント――彼にとっての特権的な土地/トポス――を舞台にした3日間のドラマだが、数人の男女を代わる代わる前景化し、彼、彼女らが出会い・すれちがい・別れを繰り返すというドゥミ的な作風を確立した傑作だ。
 『ローラ』=「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」のサイトより
『ローラ』=「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」のサイトより――おもな登場人物は、一人息子を育てながら7年前に姿を消した初恋の男/息子の父親、ミシェル(ジャック・アルダン)を待ちつづける、切れ長の大きな目が蠱惑的(こわく)な踊り子ローラ(アヌーク・エーメ)、ローラに片思いする彼女の幼なじみロラン・カサール(マルク・ミシェル)、元踊り子のデノワイエ夫人(エリナ・ラブールデット)、その10代の娘セシル(アニー・デュペルー)、アメリカ人水兵のフランキー(アラン・スコット)。――ロランは、放浪癖のある世間知らずの文学青年だが、コケットリー(媚態)を振りまく快活なローラは、初恋の男ミシェルを忘れられず、ロランの愛を受け入れない。だがローラは、純情一辺倒ではなく、ミシェルと似ている水兵フランキーとは時おりベッドを共にする(細身だが骨格がしっかりしたアヌーク・エーメの身体は、たまらなく官能的だ)。
そんな踊り子ローラは、終始、プラスの意味で深さを欠いた表面だけの存在として、軽やかに儚(はかな)げに漂いつづける。水兵フランキーも、血肉をそなえた人間というより、白いセーラー服を着た記号的存在のように軽妙に振る舞う(本作以後、<水兵>はしばしば、ドゥミの登録商標のようにドラマの背景に見え隠れする)。
未婚の母デノワイエ夫人も、ロランにかすかな恋情を抱くかに見えるが、ほとんど喜怒哀楽を表さない。やや陰気なロラン/マルク・ミシェル一人が内面の起伏を表すが、それとて、ごく控えめなものであり、つまるところ『ローラ』で紡がれるのは、軽やかに儚くスクリーンをよぎっていく人間模様だ。そして、名カメラマン、ラウル・クタールの露出過多のカメラが美しくとらえた、白くまばゆい陽光に満ちたナントを舞台に、そうした儚げな描法によって浮かび上がる男女のドラマが、なんとも魅力的なのだ。
『ローラ』における運命的なロンドのような男女のドラマは、さらにフランキーとセシルの出会いと別れ――バッハの平均律クラヴィーアが流れるなか、二人が回転木馬で戯れるシーンの無重力的な超スローモーションは忘れがたい――、ローラにふられたロランの旅立ち、家出し父親の住むシェルブールへ向かうセシル、彼女を追って旅立つデノワイエ夫人、ローラとミシェルの再会……というふうに続いていく。
なお、セシルという娘の名前は、少女時代のローラの名前でもあり、つまりセシルは若き日のローラの姿であることや、ロランに扮するマルク・ミシェルが、同じ役名の宝石商として3年後に撮られる『シェルブールの雨傘』(1964)に再登場することも、ドゥミのいわば円環状の作劇法の一端を示している。そういえば、水兵フランキーが向かうのも新しい駐屯地、シェルブールで、したがってセシルが父親の住むその港町へと旅立つのは、フランキーを追うためでもある。
ところで『ローラ』は、メロドラマ的艶笑譚の名匠、マックス・オフュルス監督に捧げられていて、冒頭ではオフュルスの傑作『快楽』(1952)第二話の主旋律が流れるが、『ローラ』の描く男女の出会いと別れの連鎖/ロンドは、文字どおり『輪舞 La Ronde』という題名のオフュルスの傑作(1950)に霊感を得たものだろう(ただし、ドゥミ映画のカメラは流れるような見事な動きを見せるが、オフュルスのそれのような目まぐるしい流動感はない)。
また『ロ―ラ』には、ドゥミの敬愛するもう一人の偉大な映画作家、ロベール・ブレッソンへのオマージュが刻印されているが、若きドゥミを震撼させた、女の復讐を冷徹かつ戦慄的に描くブレッソンの恐るべき傑作、『ブローニュの森の貴婦人たち』(1944)のヒロイン/踊り子役のエリナ・ラブールデットがデノワイエ夫人を演じているのは、けだし、ドゥミのブレッソンへの讃辞なのである(作中では、『ブローニュの森の貴婦人たち』のダンサー姿のラブールデットを写したスチール写真が引用される!)。空間描写の点では、ナントの海沿いの光り輝く風光とともに、カメラが画面の奥行を活かした縦の構図でとらえる、パサージュ(passage)と呼ばれるアーケード商店街の通路が印象深い。
ちなみに『ローラ』では、ローラ/アヌーク・エーメが長い煙管(キセル)をくわえて踊り唄うくだりが、ほとんど唯一の、しかし目を見張るような艶やかなミュージカル・シーンだが、全編をミシェル・ルグランの音楽に伴奏された本作は、やはり、れっきとしたドゥミ&ルグランのミュージカル映画だ(ルグランは、撮影後のアヌーク・エーメの口の動きに合わせて作曲する離れ業をやってのけた!)。
急いで付言すれば、モノクロ・フィルムで撮られた低予算で多焦点的な『ローラ』は、最も(狭義の)ヌーヴェルヴァーグ的ドゥミ作品であり、ロラン/マルク・ミシェルが「たったひとりの友だちだったミシェル・ポワカールも殺された」と言い、ゴダールの『勝手にしやがれ』(1959)でジャン=ポール・ベルモンドが演じた主人公(ミシェル・ポワカール)に言及する場面や、街頭撮影のシーンで、マーク・ロブソン監督、ゲイリー・クーパー主演の『楽園に帰る』(1953)を上映中の映画館が映る瞬間がある(初期ヌーヴェルヴァーグ作品の街頭ロケでは、しばしば映画館が撮られた)。さらに、ゴダールが『ローラ』の「製作顧問」であったこと、ラウル・クタールが『勝手にしやがれ』の撮影監督であったことを付け加えておこう。<星取り評:★★★★★+★/DVDあり>
■『シェルブールの雨傘』(1964)
登場人物全員がすべてのセリフを歌ってしまう(!)、しかしオペラの芝居がかった重厚さはみじんも感じられない、フレンチ・ミュージカル映画の独創的な傑作で、ジャック・ドゥミの名を世界に知らしめ、第17回カンヌ国際映画祭で最高賞パルム・ドールを獲得し(当時のカンヌのレベルは何と高かったことよ!)、ミシェル・ルグランの作曲した甘く切ない主題歌も大ヒットし、ヒロインを演じたカトリーヌ・ドヌーヴの出世作ともなった。
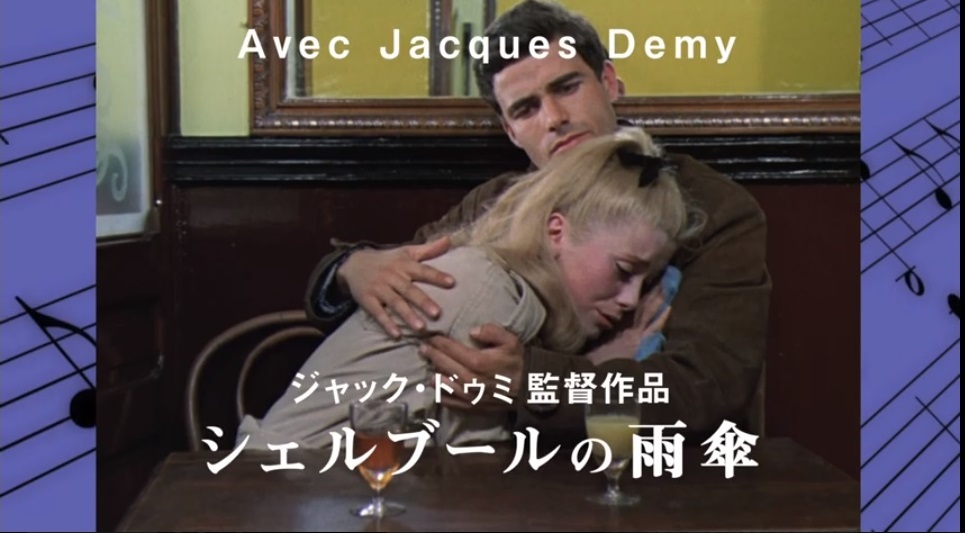 『シェルブールの雨傘』=「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」のサイトより
『シェルブールの雨傘』=「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」のサイトより描かれるのは、アルジェリア戦争下のフランスの港町、シェルブールを舞台にした、若い男女の別れと新たな出会いであるが、物語の大筋はこうだ。――傘屋を営むシングルマザーの女主人、エムリー夫人(アンヌ・ヴェルノン)の娘ジュヌヴィエーヴ(カトリーヌ・ドヌーヴ)は、自動車工のギイ(ニーノ・カステルヌーヴォ)と恋仲だったが、ギイは戦争に召集される。妊娠し孤独の身となったジュヌヴィエーヴは、宝石商ロラン・カサール(マルク・ミシェル)と出会い、葛藤の末、経営難に陥っていた傘屋の状況と母親の懇願によって、彼と結婚し、シェルブールを去る。ギイは負傷して戦地から帰還するが、傘屋は閉まっていた。しかし、ギイも新たな伴侶を得て再出発する……。
というふうに、この映画では、焦点人物が入れ替わっていく多焦点的な『ローラ』とは対照的に、ひとりのヒロインの葛藤を中心に、いわば求心的に悲恋のメロドラマが――成瀬巳喜男ふうに――展開されることも、興行的に成功した大きな要因の一つだっただろう。ただし前述のように、『ローラ』でナントを去ったロラン・カサール/マルク・ミシェルが、宝石商になって再登場する『シェルブール』は、『ローラ』の密かな続編でもあるのだ。
ジャック・ドゥミは、自作における<男女の出会い・すれちがい・別れ>について、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください