2020年05月15日
カミュの『ペスト』を読む(1)――コロナ危機の驚くべき予言の書
カミュの『ペスト』を読む(3)――人間もウイルスも神の被造物!?
アルベール・カミュの『ペスト』では、ペストの感染が広がるなか、仏領アルジェリアのオラン市は外部から遮断された隔離状態に置かれる。いわば、市全体が病原体の巣窟のような巨大クルーズ船状態になるのだ(強権発動によってロックダウン(封鎖)された、中国・武漢市や西欧の諸都市が連想される)。
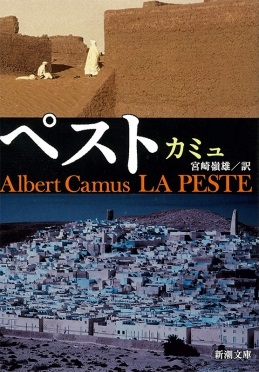 アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)
アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)
 MikeDotta/Shutterstock.com
MikeDotta/Shutterstock.comさらに、ペスト流行の第6週には、感染による死者は345名を数えたが、その時期に及んでもなお、危機感を持てない市民たちの奇妙な様子はこう書かれる――「〔死者数の〕相次ぐ増加はともかく雄弁であった。しかし、それも十分力強いものであったとはいえず、市民たちは不安のさなかにも、これは確かに憂(うれ)うべき出来事には違いないが、しかし要するに一時的なものだという印象を、依然もち続けていたのである。/彼らはそんなわけで相変わらず街頭を練り歩き、カフェのテラスで卓を囲んでいた。〔総じて彼らは〕……愚痴よりも冗談のほうを多くいい合い、(……)一時的なものとわかっているさまざまの不自由を機嫌よく受け入れようとするそぶりを示した。外観だけはともかく保たれていたのである」(113頁)。
とりもなおさず、市民たちの楽観的な言動が、不安の裏返しという無意識の防衛機能を含んでいることを、カミュは巧みに描いているが、こうした不安と楽観の入り混じる市民たちの集団心理も、目下の――“自粛”を“要請”されるという相反状況(ジレンマ)に置かれた――私たちのそれと大同小異だろう(「自粛の要請」とは、人命より経済を優先する、巧妙な自己責任論にもとづく施策ではないか)。
だが一方で、ペスト禍の深刻化は、市民の生活と町の外観を一変させてしまう。食料やガソリンの補給は制限され、電気の使用も制限され、必需品だけが陸路と空路によってオランに届けられる。車の運行は皆無に近くなり、商店も次々と閉じていく。映画館はフィルムの配給網が絶たれたため、いつも同じ映画を映写することになり(113~114頁)、さらに旅行者がオランに寄りつかなくなったことが、観光業の息の根を止める(168頁:リアル/現在的な状況だ)。
市民の間では、ただの不機嫌だけが原因の喧嘩も起こり、その不機嫌は慢性的なものになっていく(174頁)。また、当局は市民の暴動を恐れて警備隊による警戒を強め、市民が市外へ出ることを固く禁止し、違反者には投獄の刑が処せられる旨が布告される(163頁)。そして、6月の終わりには死者数はうなぎ上りに増加し、週700名を数えるに至る(162頁)。
しかしこうした状況は、ペスト流行のまだ序の口であった。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください