2020年05月20日
新型コロナウイルスの蔓延で小中学校が長期休校になったこともあって、子どもの本がよく読まれているという。もっとも、出版全体の売り上げ激減の中で、児童書は多少の凸凹はあるものの、横ばいもしくは微増で推移してきたから、平時でもそれなりに読まれているのだ。
ちなみに、全国学校図書館協議会(全国SLA)による第65回学校読書調査(2019年6月)によれば、昨年(2019年)5月に読んだ本の冊数が、小学生(4年生から6年生)は11.3冊、中学生は4.7冊、高校生は1.4冊。1か月間に1冊も本を読まない不読書率は、小学生が6.8%、中学生が12.5%、高校生は55.3%と年齢が上に行くほど激増する。
この傾向はずいぶん前から変わらない。2000年と比較してみると、読んだ本の冊数は、小学生6.1冊、中学生2.1冊、高校生1.3冊だったから、この19年間で高校生を除き倍増している。不読書率は、小学生16.4%、中学生43.0%、高校生58.8%で、小中学生は激減しているが高校生は微減。つまり、ほぼ20年前と比べ小中学生はずいぶんよく本を読むようになったものの、高校生は相変わらず半数以上が月に1冊も本を読んでいないということがよくわかる。
その要因として、小学校では全校一斉読書活動が約97%の実施率に対し、中学校で90%前後、高校では約40%と小学校の半分以下だというから、学校内における読書活動の影響が大きい。
また「朝の読書」運動の成果も小中学生の読書人口を増やしてきたに違いない。つまり、小中学生に関しては、子どもの本離れなどはないのだ。それに比べ高校生は、以前から部活や受験のための勉強に時間がとられて、本を読む時間などとれないのだろう。年齢が上がるほど、様々な情報を、本よりもスマホなどから得ている今日ではなおさらだ。
 「朝の読書」運動は小中学生の読書人口を増やしてきた
「朝の読書」運動は小中学生の読書人口を増やしてきたそんな中で、新潮文庫が企画している「中高生のためのワタシの一行大賞」の受賞作品を見ると、昨今の中高生の読書の在り様と、作品の中から一行を切り取る着眼点や文章表現力の巧みさには驚かされる。
「ワタシの一行大賞」は、今回が第7回目。新潮社が発行する2019年「中学生に読んでほしい30冊」「高校生に読んでほしい50冊」「新潮文庫の100冊」の対象図書の中から、心に残った作品の一行を選び、なぜその一行を選んだかを100~400字で書いて応募する。締め切りは9月30日で、第2次選考の後に角田光代が最終選考をして、大賞1名、優秀賞と佳作数名(今回は各2名)に、賞状と図書カードを贈呈。受賞作品は、『波』2020年1月号と、新潮社ホームページに全文掲載されている。
今回の応募総数は2万2154通だというから、青少年読書感想文全国コンクールの約400万には及ばないものの、中高校生がこれだけ参加するというのも驚きだ。読書感想文コンクールは、毎年夏休みの宿題に課せられたものを学校単位で応募し、市区町村・都道府県別の審査で選ばれた感想文が中央審査会に回されて、受賞作品が決まるのだが、今や全国的な学校行事の一環のようにもなっているから比較にならない。
昨年で65回を迎えた読書感想文コンクールの方は、歴史が長いこともあって常連入賞校もたくさんあり、指導教諭の力量も大きく影響しがちな上、感想文を書くために本を読むことを強いられるので、本来の読書の楽しみがそがれるという批判も絶えない。一行大賞のほうは、読後の感想文ではなく、気に入った一行を引き出して、それに関わる思いをエッセイとして綴るから自由度が広いのだろう。入選作のそれぞれが個性的でおもしろい。
 小中高校生の読書には自由が漲っている=rongyiquan/Shutterstock.com
小中高校生の読書には自由が漲っている=rongyiquan/Shutterstock.com今回の大賞は、たまたま選考委員の角田光代の『さがしもの』から、「目先のことをひとつずつ片づけていくようにする」を選んだ聖ヨゼフ学園中学校の宮下恵さん。海外に語学研修で出かける荷物作りをしていて、さっきまで手の中にあったはずの大事な鍵をどこに入れたのか見つからない。ちょっと視線をずらしたら見つかって気持ちが落ち着き、昨晩読んだ『さがしもの』の一行が思い出された。
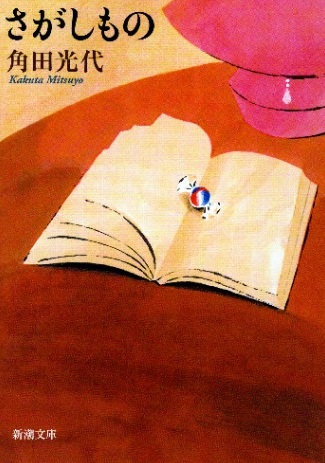 角田光代『さがしもの』(新潮文庫)
角田光代『さがしもの』(新潮文庫)これを大賞に選んだ角田は、さがしものとなくしものの違いについて自分で書きながら考えた事がなかったと言い、「ない」ことを振り返るのではなく、今より先に目を凝らしていくのが「さがしもの」なのかと教えられ、希望をもらった思いだと選評で述べる。
優秀賞は、王城夕紀『青の数学』から、「同じ問題を見ていても、誰も同じものを見ているわけじゃない」を取り出し、小学校の頃のテストで×印をもらった納得できない思いを語る横浜富士見丘学園高等学校の福本桃子さん。
テストに、鳥獣戯画の一場面を取りあげて蛙の気持ちを読む問題が出た。福本さんは「驚いていた」と記し、友だちは「悔しがっていた」。で、正解は「喜んでいた」だったという。出題者と同じように見なければ間違いになるというのは納得いかない。同じことは高校生になった今でも続いている。だから「教科書の物語は読めるのに、国語を読むことは難しい」。「大人は表現の自由だなんだというけれど、私は国語に見方の自由が欲しい」と。まさに紅野謙介の『国語教育の危機――大学入学共通テストと新学習指導要領』(ちくま新書)で批判されている新学習指導要領の問題点にも通底する、文学作品の読解についての疑問である。
優秀賞のもう一人は、山田詠美『ぼくは勉強ができない』から、「良い人間と悪い人間のたった二通りしかないと思いますか?」を引き出した、広島工業大学高等学校の丸山拓人さん。人間を善悪2通りのテンプレートにあてはめたがる性癖を、小学校の給食のときのエピソードを例に紹介し、「物事の善し悪しの裏にあるものにこそ、本当に目を向けなければならないのかもしれない」という。一冊の本が惹きつける言葉は人それぞれだが、なるほどここに目をつけたかと、このしなやかな感性がみずみずしく感じられる。
佳作の山田真亜沙さん(福岡常葉高等学校)は、伊坂幸太郎『ゴールデンスランバー』から、「個人的な生活と、世界、って完全に別物になってるよね。本当は繋がってるのに」を。「繋がっているのなら自分が世の中に関心を持つことで自分を取り巻く環境は何かが変わるのかもしれない」と山田さんは思う。同じく佳作の大沼乙寧さん(神奈川県立橋本高等学校)は、ハリエット・アン・ジェイコブズ『ある奴隷少女に起こった出来事』から、「あの希望を失いかけた日々と共に心によみがえってきたのは、年老いた善き祖母に愛された、おだやかな思い出だった」を引き、幸せや愛について考える。
新潮社のホームページには、これまでの受賞作も掲載されていて、選ばれた一行の多様性とそれに付された思いのそれぞれが興味深い。前年度(第6回)は、サン=テグジュペリ『星の王子さま』、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』、吉本ばなな『キッチン』、辻村深月『ツナグ』などからの一行を選んだエッセイが入賞している。
今回の選評で角田光代は、「小説は、物語は、読んだ人のものだ。どんなふうに読み、どんなふうに解釈してもかまわない。どんな一行を選んでもいいのだし、その一行に感化されても、怒りを覚えても、かなしくなっても、反発しても、明日には忘れてもかまわない。正解のない、いや、読んだ人のぶんだけ正解が広がっていくのが、読書のたのしみであり、自由さだ」と述べている。中高生が選んだ一行には、この自由さが漲(みなぎ)っている。
 「読んだ人のぶんだけ正解が広がっていくのが、読書のたのしみであり、自由さだ」と角田光代さん=撮影・三原久明
「読んだ人のぶんだけ正解が広がっていくのが、読書のたのしみであり、自由さだ」と角田光代さん=撮影・三原久明中学生はともかく、不読書率が5割を超える高校生もが、自分の体験に引き寄せ、好きな本から抜き出した一行に託して、思いのたけを語る文章はそれぞれ個性的で読み手の心にしみる。何の変哲もない一行であっても、人それぞれの思いに重なり、深く心に刻まれるのだということが、これらの短文の中から読み取れる。それは、読書を通しての自己発見であり、自分との対話でもある。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください