2020年06月29日
今回の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)には驚いた。2019年12月に中国武漢の海産物や生きた動物を売る市場にかかわる人のあいだで集団発生した後、この肺炎に似た症状の急性呼吸器疾患は中国国内から世界へ広がり、3月11日には世界保健機関(WHO)からパンデミック(世界的大流行)宣言が出された。6月28日現在、国内の感染者は1万8522人、死者は972人、世界の感染者は1000万人超、死者は49万人超とされる。
重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)と同様、最初は私にとって新型コロナは他人事の世界の話だった。病気にはそういうところがある。身内や親しい者に罹患者がいない場合には、もう一つ実感がわかないのである。
4月半ばに友人から紹介されて読んだ藤原辰史「パンデミックを生きる指針――歴史研究のアプローチ」は私の目を覚まさせてくれた。目の前で起こっている歴史的事態にまともに向き合う気持ちになったのである。
 藤原辰史・京都大学人文科学研究所准教授(農業史)
藤原辰史・京都大学人文科学研究所准教授(農業史)以下、この小論文を要約してみよう。
まず藤原は、「目の前の輪郭のはっきりした危機よりも、遠くの輪郭のぼやけた希望にすがりたくなる」人間の性向を指摘する。しかし、ペストの猛威、スペイン風邪、東京電力の原発事故などの重大な危機が到来したとき、歴史はそうした希望を冷酷に打ち砕いてきた。
いま参照すべき歴史的事件は100年前の「スペイン風邪」だという。アメリカを震源地とするこのインフルエンザは、1918年から1920年にかけて3度のパンデミックを繰り返し、最大1億人の命を奪った(後出の『人類と病』によると、1918~23年の犠牲者は7500万人とする統計もある)。第一次世界大戦の死者よりも多くの死者を出したスペイン風邪だったが、その割には教科書などの歴史叙述からも人々の記憶からも消え失せ、歴史的検証が十分になされてこなかったようだ。
藤原によれば、本当に怖いのはウイルスではなく、ウイルスに怯える人間である。そして「パンデミックを生きる」指針として以下の5項目を提唱する。
第一に、うがい、手洗い、歯磨き、洗顔、換気、入浴、食事、清掃、睡眠という日常の習慣を守ること。よく食べ、よく笑い、よく寝ることは免疫力をつける重要な行為なのだ。
第二に、組織内、家庭内での暴力や理不尽な命令には異議申し立てをすること。
第三に、戦争、五輪、万博など簡単に中止や延期ができないイベントに国家が力を入れすぎないこと。
第四に、経済のグローバル化のなかで弱い立場にいる人にとって、新型コロナ感染の危機がもたらすものをよく考えること。
第五に、危機の時代であっても、情報を抑制したり、的確に伝えなかったりする人たちへの異議申し立てをやめないこと。これは政治家への注文ばかりではない。個人の生命にかかわるようなインターネット上の記事は無料配信するのが、新聞・放送などメディアの社会的責任とも指摘する。
最後に、武漢での封鎖の日々を日記につづって公開した作家・方方(ファンファン)の言葉が紹介されている。
一つの国が文明国家であるかどうか(の)基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である。(王青訳)
武漢封鎖から2日後の1月25日から3月24日までSNSに投稿された方方の「武漢日記」は、英語版・日本語版などの出版が予定されているようだが、「中国の負の面を西側諸国に売り渡した」と国内では激しい批判にさらされているという(『朝日新聞』6月10日)。
日本政府の抱いた「遠くの輪郭のぼやけた希望」は今春に予定されていた習近平の来日と、7月に予定されていた東京オリンピックの開催であったが、両者とも延期を余儀なくされた。山本義隆「コロナとオリンピックに思うこと」は、自分の通院体験を通してブラックな医療現場の危機を指摘しつつ、「1月~3月の過程で何を間違えたのか」「商業主義と国家主義丸出しのオリンピック」「人類の生存が地球のキャパシティを越えつつある」と、コロナ後の世界がどう変わるべきなのかを問いかけている。「途方もない税金を使って一部の企業だけが潤うオリンピックは、もうこれを機会に終わりにすべきでしょう」との呼びかけには説得力があると思った。
そもそもウイルスとは何か。山内一也『ウイルスの意味論――生命の定義を超えた存在』(みすず書房)によると、牛の伝染病である口蹄疫やタバコの葉に斑点のできるタバコモザイク病の原因として、ウイルスが19世紀末に発見された。天然痘やエボラ出血熱、インフルエンザやノロウイルスが代表的なものだ。
ウイルスは、数十億年にわたり生き物とともに歩んできた「生物」ではあるが、細胞の外では活動できない「物質」でもある。外界では感染力を失ってすぐに死ぬが、条件さえ整えば数万年の凍結状態の後でも復活する不思議な存在である。
ウイルスは生物と無生物の境界に位置し、現行のコロナウイルスのように世界的流行を引き起こす病原菌であるとともに、人間のDNAにもその遺伝情報が組み込まれ一部は生命活動にもかかわっている。人間との敵対と共生の境界に位置しているのがウイルスなのだ。
人間の「体にも、腸内細菌や皮膚常在菌などに寄生する膨大な数のウイルスの存在することが明らかになりつつあり、一部はわれわれの健康維持にかかわっている可能性がある」「われわれは、ウイルスに囲まれ、ウイルスとともに生きている」と著者はいう。
また感染症については、山本太郎『感染症と文明――共生への道』(岩波新書)がウイルスをはじめ細菌や寄生虫のもたらす感染症を文明史的に考察、素人にも面白い話が数多く紹介されている。
 山本太郎・長崎大学熱帯医学研究所教授(国際保健学、熱帯感染症学)
山本太郎・長崎大学熱帯医学研究所教授(国際保健学、熱帯感染症学)農耕による定住と集団生活が人の感染の機会を拡大し、さらに野生動物の家畜化によって、天然痘は牛から、麻疹は犬から、インフルエンザは水禽(アヒル)から、人に感染していった。インドのカースト制は感染症を防ぐシステムだったのではないかとみる見方もあるらしい。ぺストは中国が起源で、シルクロードを通ってユスティニアヌス帝下の東ローマ帝国を襲い、またインカ帝国は旧世界の持ち込んだ感染症で崩壊した、等々。感染症を撲滅するよりは共生をとの提言にも説得力があった。たとえばエイズウイルスの場合、もし潜伏期間を100年にまで延長できれば、新たなウイルスに対する防波堤になるというのだ。
2003年のSARSの記述では、「3月24日、アメリカ疾病管理センター及び香港の研究者は、新型のコロナウイルスが患者から分離されたと報告」とある。そして、「SARSを引き起こしたウイルスは永遠に消えてしまったのか、あるいは、自然界のどこかで深い眠りについているだけなのか。物語は終わったのか、次の舞台が開くのを待っているのか、現時点では、誰にもわからない」と新型コロナの未来を推し量っている。実際、このコロナウイルス(SARS)は17年後、今回の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)として変容しつつ復活したのである。
今年4月に出版された託摩佳代『人類と病――国際政治から見る感染症と経済格差』(中公新書)は国連の保健機関WHOについて詳しい。第一次世界大戦の塹壕にいた兵士たちにマラリアとインフルエンザ(スペイン風邪)が蔓延したことから国際保健協力の必要性が国際政治の場で自覚されるようになった。第二次世界大戦では、サルファ剤、ペニシリン、抗マラリア薬クロロキン、DDTなどの感染症対策薬が開発され、戦場で活用された。二つの世界大戦のあと、1948年に世界保健機関(WHO)がジュネーブに設立され、天然痘、ポリオ、マラリアなどの感染症の根絶がめざされたが、成功したのは天然痘のみである。
近年のパンデミックには、エイズ(HIV)、SARS、エボラ出血熱、新型コロナウイルスがあり、これら新しく認識された感染症は「新興ウイルス感染症」、最近日本で流行したデング熱やはしか(麻疹)など既に知られていたウイルスによる感染症は「再興ウイルス感染症」と呼ばれる。新興ウイルス感染症の流行はウイルスの突然変異(性質が変わること)によるものだという。1970年代ストレプトマイシンやペニシリンなどの抗生物質やワクチンの登場で感染症はもはや脅威ではないと思われていた時期もあったが、その後も新興・再興ウイルス感染症は人類社会に深く浸透していった。われわれは感染症の時代を生きているのである。
コロナ後の世界はどうなるのだろうか。イタリアの若い作家パオロ・ジョルダーノが本年2月29日から3月4日までの日々を『コロナの時代の僕ら』(早川書房、飯田亮介訳)にまとめた。あとがき「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」は、ネットでも公開されている。ジョルダーノはフランスのマクロン大統領が国民に対する声明で使い、政治家やジャーナリスト、医師まで用いるようになった「戦争」という言葉に強い違和感を表明する。
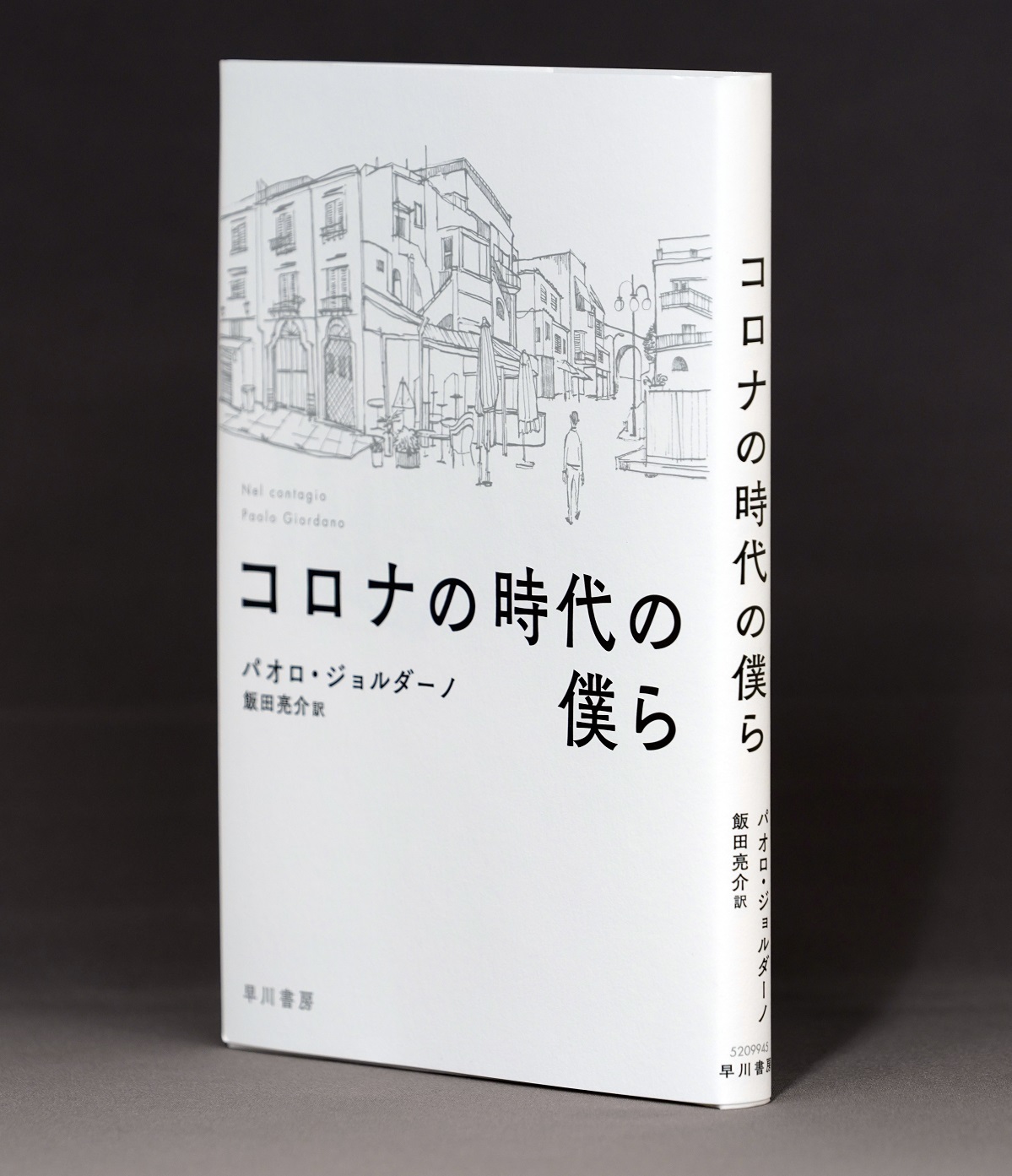 パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』(早川書房、飯田亮介訳)
パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』(早川書房、飯田亮介訳)この後ジョルダーノは「僕は忘れたくない」のフレーズに続けて、「ルールに服従した周囲の人々の姿を。そしてそれを見たときの自分の驚きを」「頼りなくて、支離滅裂で、センセーショナルで、感情的で、いい加減な情報が、今回の流行の初期にやたらと伝播されていたことを」「政治家たちのおしゃべりが突如、静まり返った時のことを」と畳みかけ、「僕には、どうしたらこの非人道的な資本主義をもう少し人間に優しいシステムにできるのかも、経済システムがどうすれば変化するのかも、人間が環境とのつきあい方をどう変えるべきなのかもわからない。……でも、今のうちから、あとのことを想像しておこう。『まさかの事態』に、もう二度と、不意を突かれないために」と語りかける。この作家のナイーブな声はどこまで届いたのだろうか。
歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、現在人類が直面している世界的危機には、重要な二つの選択肢があるという。第一に、全体主義的な監視社会を選ぶのか、それとも個々の市民の権利拡大を選ぶのか。第二に、ナショナリズムに基づく孤立か、それともグローバルな団結をとるのか(「新型コロナウイルス後の世界」柴田裕之訳)。
 CKA/Shutterstock.com
CKA/Shutterstock.comまた内田樹は、新型コロナウイルスが民主主義を殺すかもしれないと危惧しつつ、コロナ以後の日本で民主主義を守るには一人ひとりが「大人」に、できるなら「紳士」にならなければならないという。「紳士」とは、カミュが『ペスト』で描いた下級役人グランのように「電車で老人に席を譲るようなカジュアルさで」レジスタンス活動に参加する市民だという(インタビュー「コロナ後の世界」)。
「コロナ後の世界」については悲観的な見方が強いようだが、コロナ禍で起こった二つの市民運動に私は勇気づけられている。
一つは5月に日本で起こったネット上の反対運動で、「#検察庁法改正案に抗議します」のツイートがまたたく間に470万を超え、安倍政権は検察庁法改正案の国会での成立を断念した。集団的自衛権の容認など憲法解釈まで私(わたくし)に変更し、東京オリンピックの開催に邁進してきたこの政権に対して、とにかく「ノー」を突き付けることができたのである。コロナ禍の最中でなければ、この法案も数の論理で押し切られたのではないだろうか。
もう一つは5月25日に米ミネソタ州ミネアポリスで起きた黒人男性ジョージ・フロイド殺害事件に対する抗議デモである。撮影した女子高生がSNSに投稿した8分46秒の白人警官の暴行映像はまたたく間に世界に広まり、全米を揺るがす人種差別反対デモとなった。
自らを「戦時大統領」と呼んだ(3月18日)トランプ大統領はコロナウイルス対策に失敗した。アメリカの感染者数は現在251万人を超え、死者は12万5000人に達している。貧しい人は医療保険に加入できないアメリカの保険制度の問題も大きい。「ブラック・ライブズ・マター(BLM、黒人の命は大切)」とも呼ばれるこのデモには、「命の格差への不満」も込められているのだ。このデモの鎮圧に連邦軍を導入しようとしてトランプ大統領は大きな批判にさらされた。
 ホワイトハウス周辺で=2020年6月6日、米ワシントン、撮影・ランハム裕子
ホワイトハウス周辺で=2020年6月6日、米ワシントン、撮影・ランハム裕子グローバルな協力が欠かせない新型コロナ対策にアメリカも中国も指導力を発揮できず、国連もG7も存在感が薄いままだ。その後も北南米を中心に感染者数は急増、北京は感染第2波に襲われ、この新型ウイルスがいつ収束するのか、全く見通しは立っていない状態である。しかし「コロナ後の世界」に向けて、公正さと平等をもとめる市民・住民の力はこれからも試され続けるのではないだろうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください