2020年08月19日
最近、大きな歴史的潮流を考えることが難しくなったと若い友人がしきりに嘆いていました。確かに毎日、新型コロナウイルスの感染者数がさかんに報道され、移動の自粛ばかりを言われると、やがて、この病気の流行が終わり、人々が正常な活動を再開した時に、未来の世界がどのように変わっていくのか考える機会が失われている印象は否めません。
本質的な知見に基づく、未来に向けた洞察があってもいいのではないか。そう考える人々がいるのは自然なことです。個人的には、これから世界で大きな変化を引き起こすことが予想される要素の一つに、アフリカという主題があるのではないかと考えています。
そんな時に、書店でこの新刊『アフリカ出身 サコ学長、日本を語る』(ウスビ・サコ、朝日新聞出版)を手に取りました。著者のウスビ・サコさんは、アフリカのマリ出身。サコさんが学長になるまでの経緯から、コロナの時代の生き方まで、見事な「語り口」で紹介されているのでびっくりします。「なんやねん」はもとより、印象的な「なんでやねん」というフレーズを交えて、ざっくばらんに語られているのは、サコさんの自伝であり、日本論、アフリカ論、そしてヨーロッパ論でもあります。
 ウスビ・サコ京都精華大学長
ウスビ・サコ京都精華大学長中国への留学を経て、日本に来たサコさんは、中国と日本の違いも十分に理解しています。天安門事件の半年前に、留学先の南京で中国人学生と留学生たちが、衝突する事件にも遭遇。その中国留学中の1990年の夏に初めて日本を訪れますが、ジェットコースターに初めて乗った描写などは抱腹絶倒です。怖さのあまり数キロ先まで届くような大声で叫び続けたというのですから。
日本に留学することを決め、日本語学校に入学した大阪で、四畳半一間の下宿生活が始まります。大阪の街区は極度に発展しているのに、用を足すのは、なんと、ボットントイレ。最初のバイトは、伝説のディスコ「マハラジャ」のドアマンでした。サコさんの専門は建築設計です。
そんなサコさんですが、自らの「自由論」の授業で学生たちの自由に対する考え方に驚きます。学生たちに「自由」を実現するための必要な条件は、と問うと、なんと「スクールバスを増やしてほしい」から始まって「授業を減らしてほしい」まで「ほしい」のオンパレード。誰かが自分に自由を与えてくれると誤解しているとサコさんは思う。ここは、本書に秀抜な解説を書いている内田樹さんも取り上げている印象的な箇所です。
本書でも引用されているように、総務省の推計では2050年には日本の人口は9500万人に減少、うち40パーセントが65歳以上の高齢者になると予想されています。サコさんは、同時にこの時期に、世界の人口100億人の4分の1に相当する25億人以上がアフリカに居住、さらには、都市人口の半分くらいがアジアの諸都市で生活する予測を紹介します。
このような認識を背景に、サコさんは、これからの時代の真のグローバル教育は、いわゆる英語教育などではなく、アフリカやアジアの地域との関わりを考えることだと言います。日本人にとって、なかなか困難な課題であることは確かですが、サコさんのように、アフリカから来た教育者だからこその、未来への提言であると思います。
だらだらできないような国民性、常に将来につながることをやっていないとダメだという空気。何かの役に立っていなければ生きられないようなプレッシャー、就職が全てだという思い込みや、社会のシステム。それらのことと、引きこもりや自殺というのは、全てつながっているのではないか。
日本人よ、もっと肩の力を抜こうぜと、私は言いたい。
「なんでやねん!」というサコさんの声が聞こえてきます。しかし、深く日本文化に根差した考え方や行動規範を根本から変革することは可能でしょうか。
もう一冊、アフリカの新しい事情を描いた本を紹介しましょう。『アフリカを見る アフリカから見る』(白戸圭一、ちくま新書)です。2019年8月の刊行ですから、最新のアフリカ事情が盛り込まれています。著者の白戸圭一さんは、元毎日新聞社のヨハネスブルク特派員。現在は立命館大学国際関係学部で教鞭をとっています。他にもアフリカに関する優れた著作があります。
帯に「それ、いつの時代のアフリカ観?」とあり、思わず手に取ってしまいました。確かに、アフリカは、まだ多くの日本人にとって、遠いのは間違いありません。著者が大学の探検部の一員としてニジェールに足を踏み入れたのは1991年。以来30年に及ぶアフリカとの関わりからもたらされる記述は、目から鱗とはこのことかというくらい衝撃的です。
私の印象に強く残ったのは、著者が数年前から感じていた「昔とは何かが違う」という言葉です。アフリカの都市部は、人が増え、日本以上の過密になっていて、以前のような開放感がない。また、ラッシュ時の交通渋滞は凄まじい。これだけでも私たちの旧来のアフリカ観をひっくり返すに十分なインパクトがあります。
 アフリカ最大級の都市ラゴス(ナイジェリア) Ogunpitan Adeyemi/Shutterstock,com
アフリカ最大級の都市ラゴス(ナイジェリア) Ogunpitan Adeyemi/Shutterstock,comサコさんの本でも人口問題には触れられていましたが、本書によれば、サハラ砂漠以南のアフリカ49カ国(サブサハラ・アフリカ)では、かつて人類が経験したことのない勢いで人口が増えていき、国連の予測では、2100年のこの地域の人口が、人類の3分の1以上に相当するという記述に衝撃を受けました。
人口爆発するアフリカと、人口が減り続ける日本。両者は今後、それぞれが直面する課題の解決に向け、協力することができるだろうか。
これは長い射程を持った考え方を日本人が獲得することができるかという重大な問いかけだと思います。アフリカと日本の将来を見据え、ビジョンを描くことのできる政治的指導者は、果たして現れるのでしょうか。
「もう援助は必要ありません。日本企業の皆さん、ぜひ投資してください」。ここ数年、アフリカ諸国の政府関係者から、そんな言葉を聞く機会が増えた。
本書によれば、過去10年、世界はアフリカ投資ブームに沸いてきたということですが、日本企業も、ナイジェリアを中心に「味の素」が、ケニアでは「日清食品」がインスタントラーメンの販売で名を馳せたということです。
著者はまた、日本人について、そのまじめさについて、期せずしてサコ学長と同じ意見を述べるのです。
サービス産業の常態化。異様な長時間労働の末の過労死。学校でいじめられても学校に行くことをやめられず、挙句の果てに自ら命を絶ってしまう子供。こうした日本社会の様々な悲劇の根底に、我々の過剰な「まじめさ」が生み出す「余裕の欠如」があるのではないかということを、私はアフリカの人々との付き合いの中で感じてきた。
アフリカが問いかけてくる問題は、深く日本の本質に関わってくることが分かります。再度問います。この問題に解決策はあるのでしょうか。
最後に1970年代の初頭のアフリカについて書かれたエッセイ集をご紹介しましょう。『花のある遠景――東アフリカにて』(青土社、増補新版)。文化人類学者・言語学者である西江雅之さんの筆になる作品です。
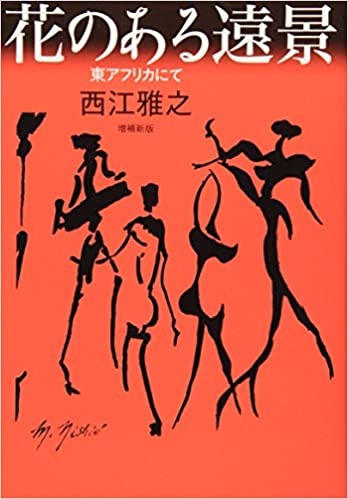 西江雅之『花のある遠景――東アフリカにて』(青土社、増補新版)
西江雅之『花のある遠景――東アフリカにて』(青土社、増補新版)著者の西江さんは英語はもとより、スワヒリ語など、現地の言葉にも精通していましたから、それまでのアフリカ旅行記とはまるで違う、等身大のアフリカが描かれているのです。もちろん、出会う人々は善人ばかりではありませんが、アフリカ人を一人も知らない私にも、登場人物たちがすべて隣人のように思えてくる筆力に圧倒されました。
特に好きだったのは「三人の女」。ケニアの首都、ナイロビの「夜の女」である3人の女性との交友を描いたものです。3人の女性のうち二人には子どもがいます。そのうちの一人、ンジェリが聞くのです。「この子の父親は、何処の国の人だか教えて下さいよ」と。西江さんは答えます。「顔つきから見ると、イタリア人だよ」。さりげない会話ですが、このやりとりに西江さんのアフリカ人との付き合い方の原型があるように思います。
文化的他者をあるがままに受け入れて、付き合っていくことは案外難しいことではないでしょうか。アフリカという日本から遙か遠い土地で、こんな風に自然体で振る舞えることが、若い私にはとても素敵に思えたのです。今回久しぶりに読み直してみて、さらにその感を深くしました。
 西江雅之=1992年
西江雅之=1992年ケニアのモンバサという港湾都市に住むインド人の友人、バルデヴさんとの交際のエピソードを綴った「ある友人」も心に残ります。アフリカにはインド人がたくさん住んでいること、インド人の微妙な立ち位置も書かれています。著者とバルデヴさんは、キリマンジャロに登るために宿泊したホテルで偶然、知り合い、友人になるのですが、便りの交換がないので、モンバサを訪問する度に会っているだけです。しかし、行けば必ず会いに行く「友人」なのです。アフリカにこんな友人がいる。とても羨ましく思ったことを思い出しました。
わたしは、裏町の人びとの生活を調べて、何かの報告書を書くためにあの場所で暮らしたわけではない。この一連の物語は、わたしが人生の一時期を過ごした“異郷”での個人的な思い出を綴ったものである。
西江さんの言葉は、アフリカのみならず、異国で人々と付き合うことは、このようなことではないか、と問いかけてきます。21世紀はアフリカの世紀だとよく言われます。しかし、政治や経済だけではない付き合い方もあるはずです。いえ、それが一番大切なのかもしれません。
*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください