2020年09月07日
ムダな仕事。無意味な仕事。バカバカしい仕事。
 デヴィッド・グレーバー著『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(酒井隆史・芳賀達彦・森田和樹訳、岩波書店)
デヴィッド・グレーバー著『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(酒井隆史・芳賀達彦・森田和樹訳、岩波書店)わたしは発行元の出版社に勤めているが、この本が刊行される過程には関わってはおらず、邦訳を心待ちにしていた。読み終えたいま、今年の人文書を代表する一冊になると強く予感している。このような重要な本を世に送り出した同僚への敬意とともに、一読者として本書の魅力の一端を紹介したい。
20世紀末までに週15時間労働が達成されるだろうと、ケインズは1930年に予言した。それから90年。実際、テクノロジーはめざましく発達した。にもかかわらず、なぜ、わたしたちはこんなにも忙しいのだろう。
まず思いあたるのが事務仕事だ。行政の官僚だけでなく民間でも管理部門が増大し、人びとを追い立てている。そのしくみはグレーバーの前著、『官僚制のユートピア――テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』(酒井隆史訳、以文社)に詳しい。
今回の本ではさらに、そうしたしくみのなかで拡大している、「ブルシット・ジョブ」――その仕事をしている当人が、世の中に役立たない、害悪ですらあるかもしれないと思っていながら、意味があるかのように取り繕って従事せねばならぬ仕事について、分析されている(この言葉が最初に掲げられた2013年の小論が本書の冒頭に引かれていて、その一文が考察の見取り図としてわかりやすい)。
部分的にブルシットな仕事は、いたるところにあるだろう。本書で図解されている大学のシラバスの煩わしい登録手続きのように。だが、この本では、個別の仕事ではなく、職が圧倒的にブルシットであるものを主な対象としている。
 sirtravelalot/Shutterstock.com
sirtravelalot/Shutterstock.com英国での調査によれば、37%の人が自分の仕事には意味がない=ブルシット・ジョブだと答えたという。そうした仕事は、金融サービスやマーケティング関連事業、企業の顧問弁護士、あるいは業種を問わず役位が目的化した仕事など、比較的高給な場合が多く、人に羨まれもする。でも、当人はつらい。無意味と思いながら仕事をすることは、グレーバーによれば「精神的な暴力」なのだ。
仕事は我慢してこそという道徳は、日本ばかりでなく英国でも根強いらしい。これで生活できているのだから。いずれ別の部門に配属されることもあるのだから。そんなふうに我慢を続けることは、自分以外の人の意味ある仕事や喜びある仕事への反感を醸成する。
世の中には、人の役に立つことがたしかな、実質のある仕事(リアル・ジョブ)もある。コロナ禍で光があてられた、医療従事者、清掃作業員、教員や保育士、小売販売員などの仕事がそれにあたるだろう。だが、キツくて待遇が悪い仕事が多い。グレーバーはそのような仕事をブルシット・ジョブと区別して、「シット・ジョブ」と呼んでいる。労働者たちは容赦なく苦しめられ搾取される。そうしたなかで、失業者の反感や、したり顔のリベラル・エリートへの反感が醸成される。
無意味だけれど待遇が良い仕事。有用だが低報酬の仕事。そして失業者。グレーバーは、そこにさまざまな反感が交錯していると読み解く。そして、それはあくまで政治的なものなのだ、つまり分断によってわたしたちは統治されているのだ、と。
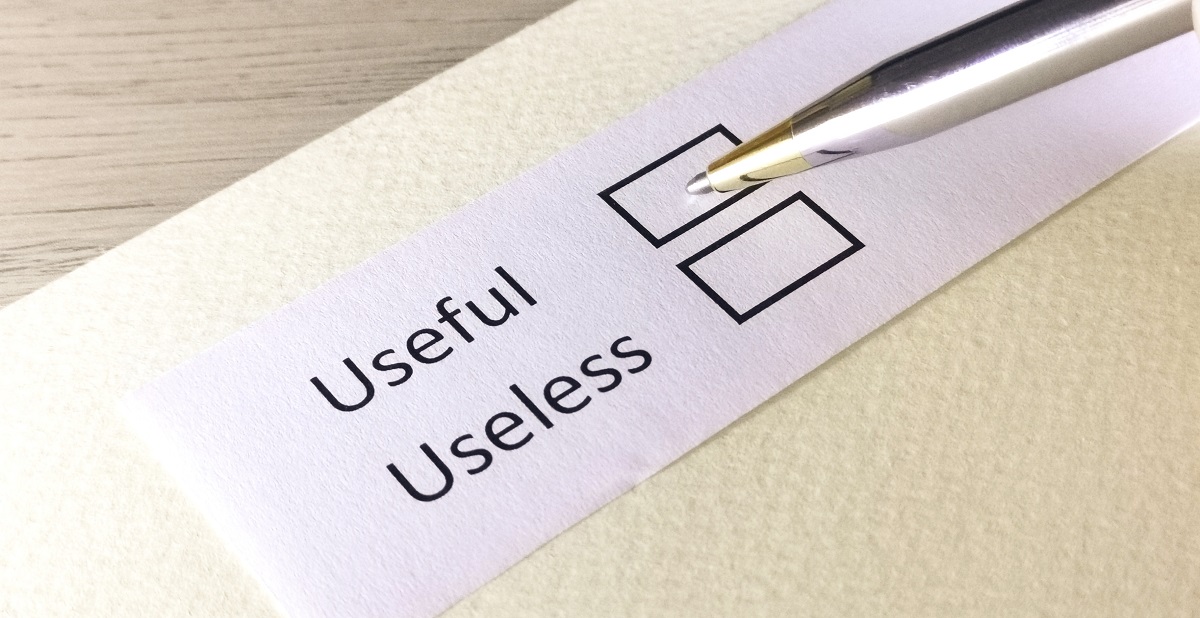 Yeexin Richelle/Shutterstock.com
Yeexin Richelle/Shutterstock.comグレーバーは冒頭で高らかに宣言している。
「本書がわたしたちの文明の心臓部を射抜く矢となることをねがっている」「嫌悪と反感と疑念が、わたしたちの社会をまとめあげる接着剤となった。これは悲惨な状態である。ねがわくば終わらせたい」
これからさらに人口に膾炙(かいしゃ)していくだろうブルシット・ジョブという言葉は、職業へのレッテル張りや分断をもたらすために用いられるべき言葉ではなく、名づけによって問題を根源的に掘り起こし、連帯をするための言葉であることは明らかだ。グレーバーは、こうも言っているのだから。
「消し去りたいと夢想しているのは仕事であって、その仕事をしなければいけない人びとではない」
では、ブルシット・ジョブを消し去った先には何があるのだろう。
この本は具体的な事例や証言も読みどころなのだが、お飾りの受付係など、女性も多く登場する。明言こそされていないが、女性の労働の歴史と現在というテーマも、本書にはこめられていそうだ。
医療費管理会社に勤めていたアニーは、おしゃべり厳禁の職場で、煩雑な書類仕事に従事させられ、上司の権力の誇示が目的と思われるミス報告の儀式を課せられる。アニーの前職は幼稚園の教諭だったが、低賃金ゆえに転職せざるをえなかった。
アニーは子どもを抱き上げたり、ハグしたり、おんぶしたり、揺らしながら寝かせたりしていた環境から、触れ合うどころか会話すらない環境へと移行したことが、自分の肉体や精神に巨大な影響を与えたと話す。
 Monkey Business Images/Shutterstock.com
Monkey Business Images/Shutterstock.comケアする仕事にある喜び。しかし、その仕事に従事すると、暮らしが成り立たなくなるというジレンマ。
デヴィッドという人物は、こう語っている。
「家賃の支払いだけのために、子どもを教育したりケアしたりするという実質のある仕事(リアル・ジョブ)からまったく無意味で屈辱的でもある仕事に移らなければならないとして、それがどのようなことか」
無意味な仕事は人を蝕む。それと表裏一体のこととして、人は他者をケアするということを求めてやまない。
グレーバーは、ケアから再考すべき領域が、実はとても広いことを指摘する。
「ほとんどの労働者階級による労働が、それをやるのが男性であれ女性であれ、実際には女性の仕事と基本的にみなされるものに類似している」「仕事はますます『生産的』労働とみなされているものから遠ざかる一方、ますます『ケアリング』労働に接近しているということである。というのも、機械に代替されることが最も考えにくいことがらからケアリングは構成されているからである」
誰かの世話をする役割を、女性は家庭でも職場でも負い、あるいは負わせられ、それは貶められてもきた。しかし、賃金の有無を問わず、人間の仕事というのは、そもそも、そしてますます、ケアなのではないかと考えさせられる。
ただ、グレーバーは、ケアリング労働を単に称揚しているわけではない。他者への愛、ケアリングの土台として、安定した制度的な保守が求められがちであるという側面についても触れている。
このように、本書はほんとうの意味で「ビジネス」書であり、人間が他者と関わりあうことの深層にまで迫る奥行きを持つ本だ。やはりグレーバーは文化人類学者だということに、何度も立ち返らされる。
ユーモアが織り交ぜられたグレーバーの文章からは、温かな人柄が伝わってくる。自身も労働者階級出身のグレーバーは、大学生などの若者たちがブルシット・ジョブに誘導される現状を、未来を壊すものとして深く憂いている。
グレーバーの未来への祈りが伝わってくるような言葉を、最後に引いておきたい。
「人間の生活とは、人間としてのわたしたちがたがいに形成し合うプロセスである。極端な個人主義者でさえ、ただ同胞たちからのケアとサポートを通してのみ、個人となる。そしてつきつめていえば、『経済』とは、まさに人間の相互形成のために必要な物質的供給を組織する方法なのである」
(なお、グレーバーのコロナ禍に際しての発言を紹介し、『ブルシット・ジョブ』のサブテキストとしても最適な論考に、片岡大右さんによる「「魔神は瓶に戻せない」D・グレーバー、コロナ禍を語る」がある。おすすめしたい)
上記の原稿を論座編集部に送った9月3日の晩、グレーバーの訃報に接した。
『ブルシット・ジョブ』を読んで何より思ったのは、こういうことを書くこの人がとても好きだ、ということだった。
グレーバーの言葉からは、頭と体と心をめいっぱいつかってこの世界を生き、これを書いている、生身の人がいるということが、たしかな手ごたえで伝わってくる。本のなかで書き手と会っているという思いを強く感じさせる。
その日は、原稿を書き終えた高揚感のまま、『ブルシット・ジョブ』を担当した同僚に、あの一文の向こうでグレーバーが考えていることを一冊で読んでみたいとか、グレーバーさんは会ったらきっとこんな人じゃないだろうかと、書き送っていた。
 デヴィッド・グレーバー(1961―2020)
デヴィッド・グレーバー(1961―2020)彼が新しい言葉を投じてくれることは、なくなってしまった。
残された本のなかで彼に出会うことは、だれにでも許されている。
それは、彼の不在の悲しみをともなうものになってしまったが、これからも彼の言葉は読む人の何かを変え、そのことが、この世界を変えていくことにきっとつながっていく。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください