ポストコロナをディストピアにしないために
2020年10月06日
『コロナ時代の哲学』(大澤真幸 THINKING「O」016号、大澤真幸・國分功一郎著、左右社)の「まえがき」には、新型コロナウイルスに関する、大澤真幸による次のコメントがある。
私たちは、生と死の全体、世界や社会のあり方の根幹に関して、これまで見たことがないものを見ており、感じたことがないことを感じている。……私たちは……経験していることを言葉にしようと努めなくてはならない。……言葉にしたことだけが……今経験していることから得つつあることを……私たちの態度のうちに定着させるからだ。……何とか言葉として捉えようと努めたことは、「うまくは語れなかった」という不充足感とともに残り、後に概念によって救いとることができる。……努めなかったときには、それはすっかり忘れられ、結局、私たちのうちにいかなる有意味な変化をも惹き起こさない。
 大澤真幸
大澤真幸一見いかにも大澤らしい、癖の強い言葉回しだが、これを単なる個人的な文体の趣味に矮小化してはいけない。ここにある「『うまくは語れなかった』という不充足感」や「それはすっかり忘れられ」といった言い回しには、「いま」と「近未来」を語る言葉であるのに、どこか、デジャヴュを見るような趣があるからだ。
そこには、発話者が背負っているこれまでに発してきたさまざまな言説の「揺らぎ」と「変遷」、たとえば「戦後」について考えてきた大澤個人の「過去」が映り込んでいるからだと思われる。このようにして発せられた多くの言葉を丁寧に積分すれば集合的な「歴史意識」になるだろう。彼が言う「言葉」とは、たとえばそういう「言葉」のことだと思う。
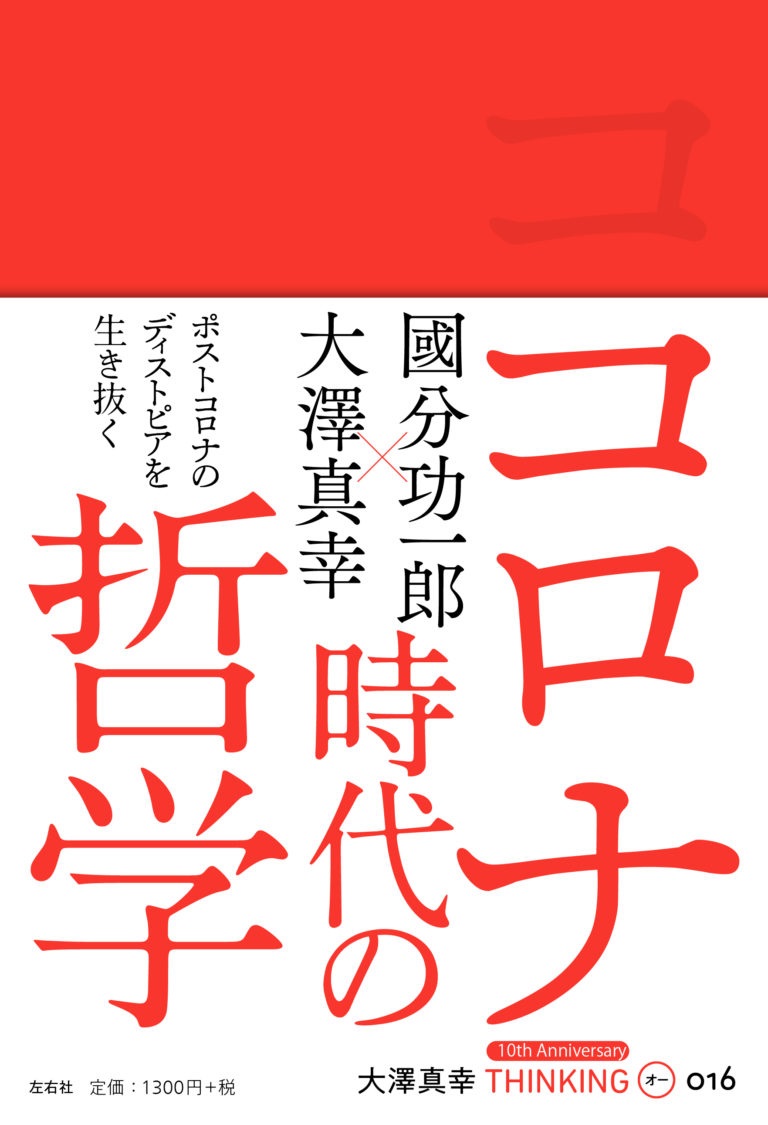 大澤真幸・國分功一郎著『コロナ時代の哲学』(大澤真幸 THINKING「O」016号、左右社)
大澤真幸・國分功一郎著『コロナ時代の哲学』(大澤真幸 THINKING「O」016号、左右社)このことから、わたしが思い浮かべたのは、本年3月末にコメディアンの志村けん氏とその親族を襲った不幸のことだった。
それまでにも、「ダイヤモンド・プリンセス号」をはじめとする由々しき事態があったにもかかわらず、SARS(重症急性呼吸器症候群、2002年)やMERS(中東呼吸器症候群、2012年)のときがそうだったように、「俺にはたぶん関係ない」と、まるで他人事のように考える、いつもながらの迂闊な心を隠せないでいたのに、彼の「死」に伴う社会的な措置を知ったときには、さすがに驚愕した。「死に目に会うことができなかった。遺体に会うことも」という実兄の悲痛な会見によって、我々は只ならぬ事態の中にいるのだと漸く合点がいったのだ。
では、この本の言説は、「まえがき」以降、どのように展開するのだろうか。構成は、「まえがき」の後に、まず「ポストコロナの神的暴力」という大澤の<論文>があり、次に大澤と國分功一郎の<対談>「哲学者からの警鐘」がくる形をとっている。
<論文>は、コロナ禍が国境を越えたグローバルな事象であることを象徴するかのように、まず新訳聖書の逸話の紹介から始まる。「ヨハネによる福音書」だけにある逸話である。
イエスが十字架上で絶命した後、マグダラのマリアが空っぽになったイエスの墓前で泣いていると、白衣の使いが現れる。その使いとの短いやり取りがあってからマリアが振り返ると、もう一人の男がいる。彼女は「何を泣いているのか。誰を求めているのか」というその男の問いに答えた後で、彼が復活したイエスだと気づいたのだろう、おそらくイエスにすがりつこうとした。それに対してイエスは「ノリ・メ・タンゲレ(私に触れるな)」と言ったというのである。この命令は、復活したイエスの最初の言葉として重視されてきたらしい。
だが、これだけではコロナ禍で我々に課される基本的な制約、つまりソーシャル・ディスタンスを守れという情報的な「コロナ対策」にほぼ等しい。
 Linda Bestwick/Shutterstock.com
Linda Bestwick/Shutterstock.comでは、大澤は、これにどんな付加価値を見つけ出すのだろうか。それは、「触れられる対象という限りでの(局在する)イエスの身体を否定することが、キリストの身体をより強力な存在へと、つまり(偏在して奇跡をなす)普遍的なものへと転換するのだ」と説明される。つまり、「いまここでは触れるな」という「ノリ・メ・タンゲレ」の戒律は、実のところ、それとは逆の「(どこであっても)身体に触れる(ことで施される)」という奇跡が根幹にあってのことなのだと。
これで、コロナ禍で招来される「新しい生活様式」には、「情報的なコロナ対策=ノリ・メ・タンゲレ」だけでは足りないこと、むしろ、触れることを排除できないし、排除すべきでもないことが示唆される。
もちろん大澤は、「ノリ・メ・タンゲレ」が及ぼす「新しい生活様式」についても抜け目なく言及する。「多くの活動は、オンラインに移し変えられるし、その方が高い効果や効用が得られる場合もあるだろう。長時間の通勤は苦痛だし、時間の無駄だ……」などと。その上で、「コミュニケーションが全体として、身体の非接触を目指しているとき、何か根本的なことが失われるのではないか」と釘を刺し、対談部分で國分が言及している話を用いて、キリストの逸話とはまた別の角度から、「情報的なコロナ対策」では不十分だと説いている。それは、「鏡像の自己認知」に関する実験に関する話である。
鏡に映る自分の姿が自分だと認識できる動物は、人間やチンパンジーなどごく少数の類人猿しかいないらしいことが、マーク・テストという実験によって確認されているという。寝ている動物の顔に印(マーク)をつけ、鏡に映った顔を見せたときに、鏡ではなく自分の顔に手をやったりするようなら鏡像の自己認知ができているとわかるというわけだ。
 GUDKOV ANDREY/Shutterstock.com
GUDKOV ANDREY/Shutterstock.comところで、自己認知ができるためには、自分では自分の全体像を見ることはできないので、生育の過程で同種の個体を見ていることが必須になるはずだ。このことを確かめるために、生まれたばかりのチンパンジーを母親から引き離し、隔離して同種の他個体を見せずに育て、鏡を見せる実験をすると、果たしてその個体は、鏡像の自己認知ができないという。
実験はさらに続く。今度は生まれてすぐに隔離して育てられたチンパンジーを3匹用意し、2匹と1匹の2組に分け、透明の壁で隔てられた隣同士の2つの部屋で育ててからマーク・テストを施す。すると、同居した2匹は難なく合格するのに、残る1匹は合格しない。つまり鏡像の自己認知ができないという。
このことからわかるのは、他者との身体接触を伴う交流の経験がないと、チンパンジーは鏡像の自己認知が可能な能力を、おそらく獲得できないということだ。そして、大澤は「これはおそらく人間も同じだろう」と言う。
以上の実験結果は、コロナ禍にあって欠かすことができないソーシャル・ディスタンスのルールに内在する、看過できない不安を惹起する。自己認識の不全な個体間に健全なコミュニケーションが成り立つはずがなく、コミュニケーションが成り立たない社会なら、コロナからは安全でもディストピアであることは明らかだからだ。従って、この不安の具現化に、どう対処するのかを考えることは、コロナ禍が続く限り人類共通の課題であり続ける。
大澤は、ウイルスが招来するディストピアというアポリア(難問)に対するには、当面はITの積極的な活用しかないことを認めている。
その一方でITの発展は、監視国家や監視資本主義というもう一つのディストピアに繋がりかねないことを、既に実現し発展途上にある中国の安全保障部門による「社会信用システム」や、アメリカを含むほとんどの先進国で行われているGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)の消費者監視などを例にあげて検討し、その上でいまの人々は、誰にも見られていないことを恐れる、つまり監視されることを望んでいるのではと言っている。
だとすれば、現在、あるいは将来のウイルス対策として監視システムや制度が導入されたとき、それを拒否するのは難しいと洞察するのである。
ではどうするのか。この事態にどう対応すればよいのか。それが直截に語られているのが國分功一郎との<対談>だ。
大澤は言う。
今回の危機の特徴は、圧倒的なグローバリティです。……人間が地球的レベルで連帯しない……自分の国だけの解決はナンセンスだということを教訓として得たことは大きい。……僕はこの危機こそは、「世界共和国への最初の一歩」になりうる、とあえて言っています。……現在の国連やWHOのような国際機関(では)……機関そのものが国民国家の闘争の場になってしまう。だから、国民国家が主権を放棄した上で形成される連帯という意味で、あえて世界共和国と言っているわけです。
「世界共和国」という飛躍に驚く人がいるだろう。しかし、この「言葉」にカントの「永遠平和のために」を思い浮かべる人も少なくはないはずだ。その意味では、冒頭で述べた「歴史意識」の裏付けのある哲学者・大澤の確かな志が感じられる「言葉」だと思うのだ。
さて、最後に、末尾に置かれた<追悼>に触れておく。アフガニスタンの地で井戸を掘り続けた中村哲は、大澤との対談のなかでこう言っていたという。――「もし真理というものがあるとすれば、それは地下水みたいなものです。どこを掘っても出てくるんですね。ただ、あちこちチョロチョロと動いていると、水は出てこない。一カ所にじっととどまって掘り続ける。……そういうことで真理は見えてくるのでしょう」。
この重い言葉が、大澤の秘めたる志に重なって聴こえてくるのは、わたし一人だけではないと思う。
 中村哲医師を追悼する壁画=アフガニスタンの首都カブール
中村哲医師を追悼する壁画=アフガニスタンの首都カブール*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください