2020年11月26日
私の郷里、福島県南相馬市小高区では、かつて新刊書店2店が併存していた。だが、東日本大震災と原発事故によって強制避難区域となり、書店はなくなってしまう。
それから5年後の2016年、南相馬市原町区に移住していた作家の柳美里さんが小高区で書店「フルハウス」を開くと宣言した。どんな店をつくろうとしているのか、開店前の2017~18年に二度、柳さんを取材した。18年4月には開店に立ち会い、その後も折々に店を覗きに行った。ただ、今年はコロナ禍のため福島に帰れず、現在の様子を見られないのを心残りに思っていたところだった。
そんなときに届いたビッグニュースである。アメリカでもっとも権威ある文学賞という「全米図書賞」の翻訳文学部門で11月18日(日本時間19日)、柳さんの小説『JR上野駅公園口』の英訳版がその賞に選ばれたというのだ。しかも、小高区と同じ南相馬市の鹿島区(旧八沢村)に生まれたという設定の主人公が登場する、地元そのものを描いた作品である。我がことのように嬉しくなった。
 店長を務める書店「フルハウス」で全米図書賞受賞を喜ぶ柳美里さん=2020年11月19日、福島県南相馬市小高区
店長を務める書店「フルハウス」で全米図書賞受賞を喜ぶ柳美里さん=2020年11月19日、福島県南相馬市小高区『JR上野駅公園口』は2014年の刊行時に読んでいた。出稼ぎ、ホームレス、天皇、震災……。曰く言い難い内容だった。最後には東京で亡くなった主人公が天空から津波に呑まれる孫娘を見るという、悲劇で終わってしまう。まったく出口のないストーリーだ。
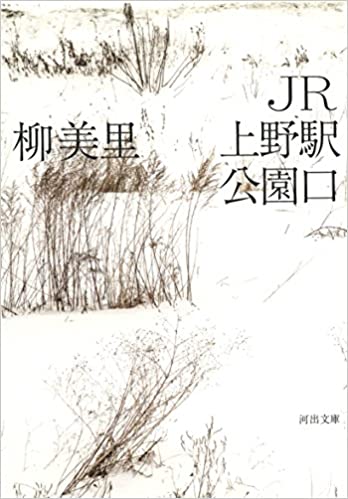 柳美里『JR上野駅公園口』(河出文庫)
柳美里『JR上野駅公園口』(河出文庫)読了時、地元の人々や私の家族・親族の人生がよぎり、感情が吹き出してきたことも思い出した。極私的な自分語りのようになってしまうが、私なりに感じ取った物語の周縁をあらためて言葉にしてみようと思う。
小説の舞台となった鹿島区(旧鹿島町)には、亡母の実家がある。たまたまだが、物語の主人公とその息子の生まれ年が伯父(母の兄)とその息子(従兄)と同じだった。主人公と私の伯父が生まれ育ったのも、合併によって鹿島町になる以前の旧八沢村だ。さらに、主人公の長男は県立原町高校を卒業し、私の従兄の母校も原町高校であった。物語の登場人物が実在していたならば、従兄と友だち関係にあり、原高にも一緒に通っていたかもしれない。けれども、主人公の長男も私の従兄も、もうこの世にはいない。他人事とは思えない設定に感情移入せずにはいられなかった。
ただ、大きく異なっていたのは、それぞれの家族が信心の対象にする仏教の宗派だ。伯父一家は、樹齢600年の大銀杏がそびえ立つお寺の檀家だった。一方、物語の一家は、天明の大飢饉(1782年~)で相馬藩(現在の相馬市から大熊町までの一帯)の農民の多くが亡くなり、相馬藩の呼びかけで北陸地方から移住してきた一向宗の門徒の末裔になる。越中(今の富山県)からやってきた僧侶の建立した寺院に帰依していた。
相馬藩と越中の一向宗を信仰する農民がつながった理由はよくわかっていないようだが、思い浮かぶのは富山の薬売り(越中の売薬)である。私の実家にも年に2回、薬売りのおじさんがやってきて、ゴム風船でつくったリンゴやカラフルな紙風船などをもらったものだ。200年以上前から、このように両者の関係が培われていたのではないだろうか。
 東日本大震災後、支援を続けてきた富山県南砺市に対して南相馬市の中学生が絵とお礼の言葉を書いた巨大紙風船=2013年2月9日、南砺市中ノ江
東日本大震災後、支援を続けてきた富山県南砺市に対して南相馬市の中学生が絵とお礼の言葉を書いた巨大紙風船=2013年2月9日、南砺市中ノ江ただ、移民の歴史をとうとうと語ってくれる親族はいたものの、関心を深めることもなく震災に至ってしまった。他方、“よそ者”の柳さんは、地元の人々の話に耳を傾け、一向宗のお寺に出向き、土地に根ざす歴史を背景に物語をしたためた。まなざしの確かさと鋭さを思わずにはいられない。
そして、東日本大震災による地震と津波、これに原発事故が重なって、今度は
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください