死をめぐる「錯覚」を解毒する
2021年01月06日
最初に個人的事情を述べることを許していただきたい。介護施設のデイサービスを週2回利用していた老母の要介護度が進み、昨年の春(2020年3月)から自宅を完全に離れて介護医療院に入ることになった。入所直前には肺炎を起こし、一時的だったがいのちの危機にもさらされた。また、直後にコロナ禍に見舞われたため、施設側は来訪者の面会を断っており、母には9カ月以上会うことができていない。
こういう事態が身近に起こると、やはり、死について考える時間が増える。コロナ禍のもとでは施設に入った家族の死に目に会えないどころか遺体にも会えない、といったニュースを耳にするにつけ、死という言葉はいっそうリアリティをもって迫ってくる。
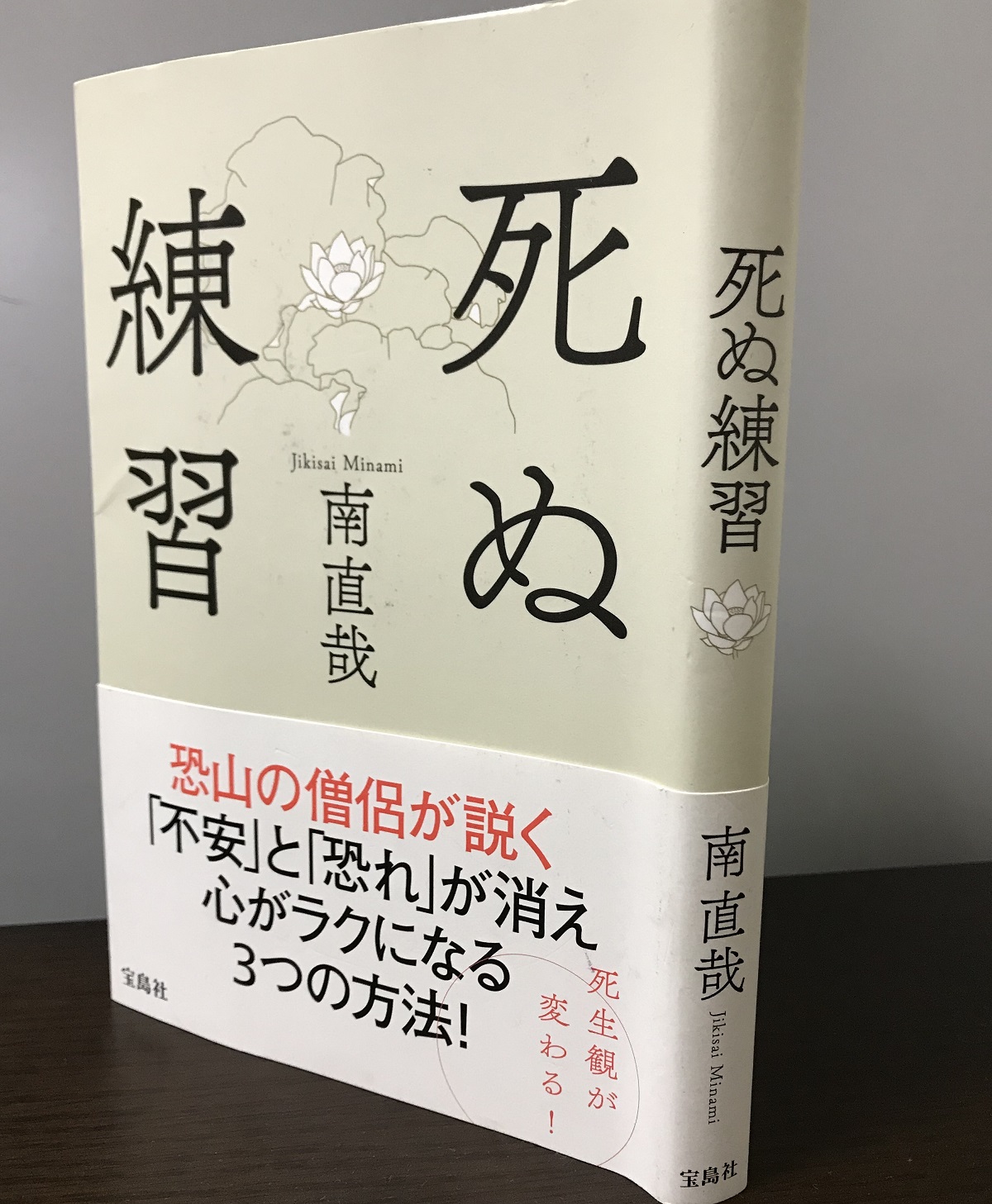 南直哉著『死ぬ練習』(宝島社)=筆者提供
南直哉著『死ぬ練習』(宝島社)=筆者提供かつて、同じ著者による『超越と実存――「無常」をめぐる仏教史』(新潮社)を読んで、僧侶としての実践に裏打ちされた言葉と、あまりにも潔い立場に感銘を受けたことがある。
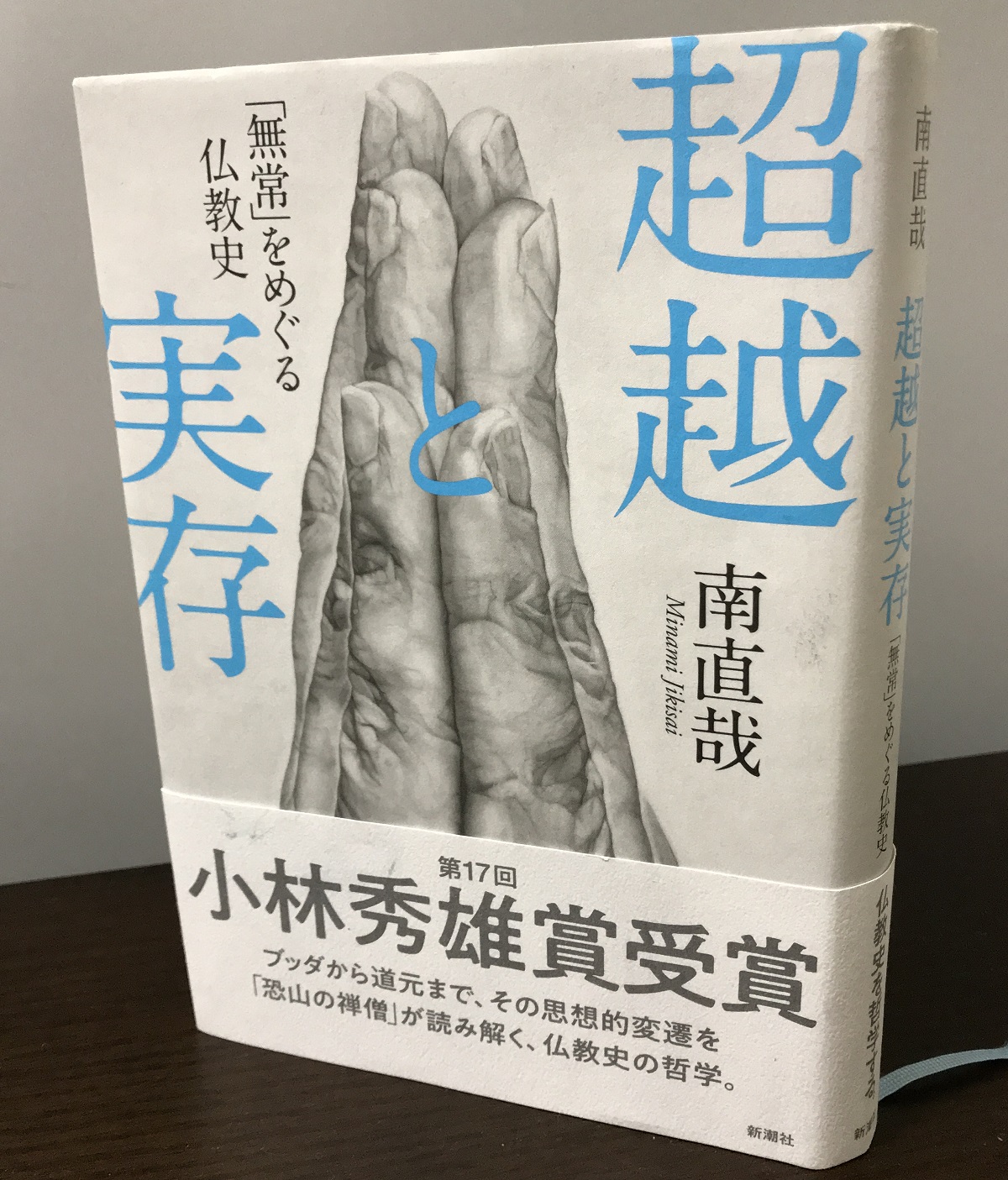 南直哉著『超越と実存――「無常」をめぐる仏教史』(新潮社)=筆者提供
南直哉著『超越と実存――「無常」をめぐる仏教史』(新潮社)=筆者提供かつての日本ではとくに、会社やムラの一員であることが個人のアイデンティティを保障する側面が大きかった。それが現代では変質し、グローバル資本に席巻された世の中を、剥き出しになった「個」として生きざるを得ない人が増大している。「無常」を観ずる行為は、そのような「個」を生き抜くときの助けになるのだと私には読め、大いに学んだ。
 僧侶・南直哉=2012年5月、青森県むつ市の恐山菩提寺で
僧侶・南直哉=2012年5月、青森県むつ市の恐山菩提寺でさて、『死ぬ練習』である。本書の内容が、タイトルから想像される「死ぬまでに人は何をすべきかという、死の準備やいわゆる『終活』のすすめ」でないことは、「はじめに」冒頭で断られる。まず、死は「絶対にわからない」(経験できない)純粋観念であり、「死に関して言葉にできるのは、途方もなく法外な何事かによって、『自分であること』が突如断ち切られるということのみである」ことが、押さえられる。
はた目には、死(涅槃)をめざして修行するのが仏教だと見られる。だとすれば仏教の修行は「死ぬ練習」とも言えるだろう。そのような仏教が、「死が何であるかまったくわからずに、ただそれに直面しなければならないわれわれ」に与える示唆があるのではないか。そうした観点で、著者が自身の体験とともに死と向き合い、死についての考えをわかりやすい言葉で披歴したのが、本書である。
死について考えを巡らせるようになった著者の原点には、小児喘息に苦しみ、何度も「終息状態」に陥ったという幼年期の経験がある。「終息状態」とは「完全に呼吸を止められて目の前が真っ赤になり、もうダメだ……という刹那に、どこかに穴が空いたかのように細い空気が肺に通る」ような、「お話にならない苦しさ」のことだそうだ。つまり、文字通りに死と隣り合わせの経験を「日常的に繰り返し」た原点によって、著者は死を問わざるを得ない性癖を身につけて成長し、現職に至ったことになる。
このような書き手が、人々はどのように死を受容するか、他者の死は生きている人にどのような影響を与えるか、「仏教における死」にはどういう特徴があるか、などについて語る言葉は直截で、容赦がない。だからこそ、読む者の拠って立つ足もとをよく照らしてくれる。
 南直哉
南直哉こうした話の需要が「厳然と、しかも大規模に」あるのは、死への不安が拭えないからであり、なぜ拭えないかと言えば、死には腑に落ちる根拠や理由がないからだ。そして根拠や理由の不在をさらに追求すれば、そもそも自己の存在というものに根拠や理由が欠けていることにも思い至る、と。
有史以来こうした根拠不在がもたらす不安に答えてきたのが、宗教である。「神」の存在を「自らに引き込むこと」で、「根拠と理由への欲望に応え」るわけだ。「一神教や浄土教の説く教説を全面的に信じることができるなら、心配は何もない」。死への不安は和らぎ、人は落ち着くことができる。
しかし、「絶対神的なものにコミットしない」一般の人々にとって、死を受容するのはそれほど簡単ではない。宗教が提供する意味やストーリーに「素直に乗れない人」たちは、死を「丸吞み」するしかない、と著者は述べる。
そして彼の経験によれば、死を「丸呑み」するには、3つほど方法があるという。1つめが「体当たり玉砕」法。これは、比較的若い世代に可能な方法である。例えば、それまで元気にバリバリ働いていた人が突然倒れ、病院を受診すると重病が発見されて「余命は長くない」と宣告されるようなケースだ。こうした人は、残された時間を仕事や学業など「何ものかに没頭」して過ごし、最期まで「精一杯生きる」ことで死期を忘れ、死に「背後から呑み込まれていく」。
2つめは「90歳超え」法で、これは文字通りである。著者によれば、「90歳を超えてから、苦しんで死ぬ人は、まずいない」。90歳を過ぎると、生命力が「よい具合に枯れて」きて、「死への感受性(死の不安)」が鈍る、というわけだ。ただ、中年以降の「規則正しい生活」や「温かい人間関係」がないと、この方法も容易ではない、という。
最後が「自分を大切にしない」法で、後にも触れるが、これが最も仏教的だと説明される。「自分を大切にしない」という文字面だけ見ると「投げやりに生きろ」という意味なの?と誤解されるかもしれない。しかし、もちろんそうではない。
生きているという状態は、そもそも他人・他者とともに生きている状態を指す。そうだとすれば、「自分と他人の間に、必ず共通の問題が生じる」。そのとき「その共通の問題に取り組んでいけばよいだろう」という意味で、「自分を大切にしない」という言葉が使われる。この「共通の問題」に取り組む際に重要な具体的実践事項については、本書で直に確かめられたい。
 恐山菩提寺 beibaoke/Shutterstock.com
恐山菩提寺 beibaoke/Shutterstock.com「自分を大切にしない」、つまり他者との共通の問題に取り組む姿勢が大事なのは、自分の死に臨む時だけではない。「大切な他者」の死を受容する場合にも、この姿勢が鍵なのだ、と読み進むうちに気づかされる。
死は「絶対にわからない」ものの、死への「意識」は誰にもある。だからこそ人は「未来」や「自由」を実感できる、と死をめぐる議論の前提に立ち戻って著者は確認する。生の「イメージの鮮明さは、死を光源にして」おり、死は生に対して決定的な力を持つ。そう語りながら、死の「意識」に強烈に影響を及ぼすのは「大切な他人の死」であることに、注意を促していく。宗教が提供する意味やストーリーには素直に乗れなくても、自らの人生で紡ぎ/紡がれた意味を噛みしめずに、人は死ねないものだ。そうした意味を紡ぎ出すには、「他人」「他者」の存在が不可欠なのだ、と。従って「自分を大切にしない」姿勢がなぜ大切なのかが、おのずと理解されてくる。
そして、ここにこそ仏教の出番がある。仏教の立場を代表する「無常」「無我」「縁起」という考えはいずれも、「常に・変わらない・そのもの自体で存在するもの」を否定する。同時に、「私」という自意識を融解させ、自己は「自己以外のものとの関係性から構成される」ありようを提示する。通常は疑わずにいる「自己」や「私」の存在を、それらが実は「他者」なしには成立しないと示すことで、死に臨んで呼び覚まされる世界が不安や恐怖だけでないことに気づかされる。こうした立場で死を考えたとき、砕いた表現でいう「自分を大切にしない」姿勢が仏教的に最も勧められる、というわけだ。
さらに、仏教における死をめぐるアイデアには「輪廻」「往生」「涅槃」があるとしたうえで、著者は前2つを潔く(!)斥(しりぞ)け、「涅槃」のみを強調する。「輪廻」「往生」というアイデアは仏教の根幹と相いれないのに対し、「涅槃」は「死のわからなさ」に真正面から向き合っているからだという。錯覚して「ある」と思い込んでいる「自己」を解体した果てに訪れる境地が「涅槃」であり、坐禅と慈悲行(「自分を大切にしない」法の実践)こそ、「涅槃」に到達するための修行(「死ぬ練習」)なのだ。
こうした文脈を踏まえると、例えばここ十数年来よく耳にするようになった「死の自己決定」という言葉も、そもそも危うい土台で発せられていると思われてくる。その問題についても、著者は最終章「死の今後」で、安楽死の議論と絡めて語っていて、示唆に富む。
同時に、「自己」に囚われず他者との関係性に目を向けさせる仏教の考えとは真逆な方向に、現代の資本と市場の論理は人々を誘導し続けている、と著者は危惧する。同感だ。自殺者が増え、リーダーは「自助」「共助」「公助」のうち「自助」を真っ先に推奨する。こうした社会では、「自己」への幻想を解毒する仏教的思考と実践が何より有効だ、との感を強めている。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください