小説の「言語」とアニメの「非言語」をめぐる《反措定(アンチテーゼ)》
2021年01月18日
もう昨年のことになるが、12月のはじめ、Twitterのタイムラインに流れてくる荒れた言葉の数々を見て、「困ったことになったな」と内心で呟いていた。
いわゆるその“炎上”は、作家の丸山健二さんがTwitter上で発信した次のような文章が引き起こしたものだった。
少年期を過ぎたならば、アニメやゲームという非現実の世界からは完全に手を引かなければならず、さもなければ、自立や自律とはいっさい無縁な、不気味極まりない子ども大人として異様にして異常な人生を送るだけならまだしも、社会全体と国家全体を尋常でない集団に仕立て上げ、暴力の狂気を迎える。
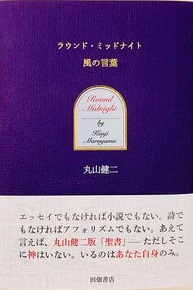 丸山健二『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』(田畑書店)
丸山健二『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』(田畑書店)困惑の主たる原因は、直後に丸山さんの新刊『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』(田畑書店)の発売を控えていたからで、それもこの本はこれから人生の荒波をくぐらなければならない若い世代にぜひ読んでもらいたいと思っていたからだ。
そして戸惑いというのは、これまで丸山さんがTwitter上でどんなに過激な言葉で体制やそれに従属して生きる者たちを批判したところで、ほとんど“炎上”したことなどなかったのだが、サブカル界隈に水を差した途端にこうである。そこに何か得体の知れない“禁忌”を見た思いがしたからだ。
もっとも、このことで初めて丸山健二がTwitterをやっているのを知った、という揶揄めいた言葉も多かった。もちろん丸山さんは自分でテンキーを打って投稿したりタイムラインを逐一チェックしたりなどしない。東京にある丸山健二事務所員、兼「いぬわし書房」(丸山さん自ら興したひとり出版社)の編集者が、ファックスで来た140字の原稿を代わりに打ち込んでいるのだ。だから炎上のことも丸山さんはその編集者を通じて間接的に耳にしているに過ぎない。
「困惑」と「戸惑い」のうち、「困惑」の方は投げつけられる汚い言葉をなぞっているうちに、解消した。少なくともここでヒステリックに反応している人々は、こちらが想定している読者層ではない。
勝手な想像であるが、「宇宙戦艦ヤマト」あたりからのアニメの世界、ドラゴンクエストあたりからのゲームの世界をリアルタイムで知っている世代と、少なくともそのひと回り下の世代、つまり40、50代のサブカルファンが中心と見た。そしてアニメと同等に文学にも興味があり、福田和也が『作家の値うち』(2000年、飛鳥新社刊)で丸山健二を酷評していたこともほぼリアルタイムで知っていた層……あたりが“炎上”の中心を牽引しているように思えた。
それから年を跨(また)いでおよそひと月、このことをつらつらと考えてみた。そして久しぶりに《反措定(アンチテーゼ)》などという大袈裟な言葉さえも思い出した。そのことを少し詳しく述べようと思う。
実を言うと、丸山さんが件のTwitterをアップした前日に、映画館で『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を観ていた。流行りもの好きでもなければコアなアニメファンでもないのに、コロナ禍のなか、しかも遅ればせながらなぜ……といえば、それはYouTubeの「VIDEO NEWS」というジャーナリストの神保哲生さんと社会学者の宮台真司さんが掛け合いでやっているチャンネルを見て、そのなかで語られる宮台さんの『鬼滅の刃』論がべらぼうに面白かったからだった。
 映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は日本の歴代興行収入で1位に
映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は日本の歴代興行収入で1位にその論を思い切りつづめて言ってしまうと、『鬼滅の刃』の基本構造は、「鬼と人間」との対立である。「鬼」というのはつまり現代のほとんどの人間、何よりも利己に生き、そのために努力し、自らのためだけの上昇志向を持つ存在を表しているのに対し、「人間」は利他に生きる。修行をして強くなろうとするのも、それで得た力によって弱き誰かを助けようとする存在である。
また、鬼がどんなにダメージを受けても死なない不死身の存在であるのに対し、人間はどんなに強くなっても儚(はかな)く脆(もろ)く、斬られれば血が出るし、命が奪われれば再生することもない。そして最後の方で煉獄杏寿郎(人間)と鬼の猗窩座(あかざ)が闘う場面で、人間にしては強い杏寿郎を鬼の世界に引き入れようとしきりに誘惑する猗窩座に対して、杏寿郎は次のような言葉を3度も繰り返す。
「君と俺とでは価値基準が違う」
この台詞を宮台氏は重くみる。負けは分かっている。破滅も分かっている。が、それがどうした。君と俺とは価値基準が違うのだ……。宮台氏が強調するのは、もはや絶望しかない、どうしようもないこの世界においても、「それがどうした」と言い続けることの貴重さである。この宮台氏の論はとても説得力があった。
 社会学者・宮台真司
社会学者・宮台真司そして、以上の論を頭に入れた上で観てさえも最後の最後でやや涙腺が緩んでしまったくらいだから(このところとみに涙腺が緩くなった。特に映画がダメだ)、評判に違わず作品としてはよく出来ているのだろう。
以上からも知れる通り、筆者は決してアニメを否定するものではない。ゲームとは縁遠いが、話題になったアニメは劇場ではなくともどこかで観ている。
しかし、そうは言ってもコアなアニメファンでもない。『鬼滅の刃』を観ても惹かれるのはあくまで「言葉のちから」にであって、そのあたりは「アニメのことはよく分からないが、スクリプトが魅力的だと思った」という神保哲生氏の感想にほぼ重なる。
 丸山健二=2013年、長野県大町市で
丸山健二=2013年、長野県大町市でそこで「反措定」である。
では丸山さんのTwitterに同意できないのであろうか? いや、あながちそうとは言えないのではないか、というのがいまのところの自分なりの結論だ。
というのも、『鬼滅の刃』を劇場に観に行った動機も、宮台さんの言葉に誘われたからであり、そして実際に観て惹かれたところも、あくまで「言葉」においてであってそれ以外ではない。言葉や批評に紐付けられないアニメ作品には興味も関心もない。そういう意味で「アニメのコアファンではない」と言っているのだ。
そういえば投げつけられた罵倒のなかでもっとも多かったのは丸山さんの「非現実の世界」という言葉に引っかかって「小説だって非現実の虚構じゃないか」という趣旨のものだった。しかしそこは強調して言いたい。言葉は現実である。だから、言葉のみで作り出した作品は、虚構であっても現実である。おそらくそこには「身体性」という問題が関わっている。
たとえば「言葉と身体性」、あるいは「言葉にとって身体とは」という設問は成り立つが、「アニメと身体性」、あるいは「アニメにとって身体とは」という設問が成り立たないことを考えてみれば自明だろう。
アニメには「身体性」がない。それについては多分、何らかの科学的な知見があるかもしれないが、おそらく言葉のみによって人間の頭脳に喚起されるイメージと、アニメによって喚起されるイメージとは、性質を異にするだろう。そしてその差は頭脳(ブレイン)だけではなく、胸(ハート)や肚(アニマル・本能)にも異なった影響を及ぼすに違いない。
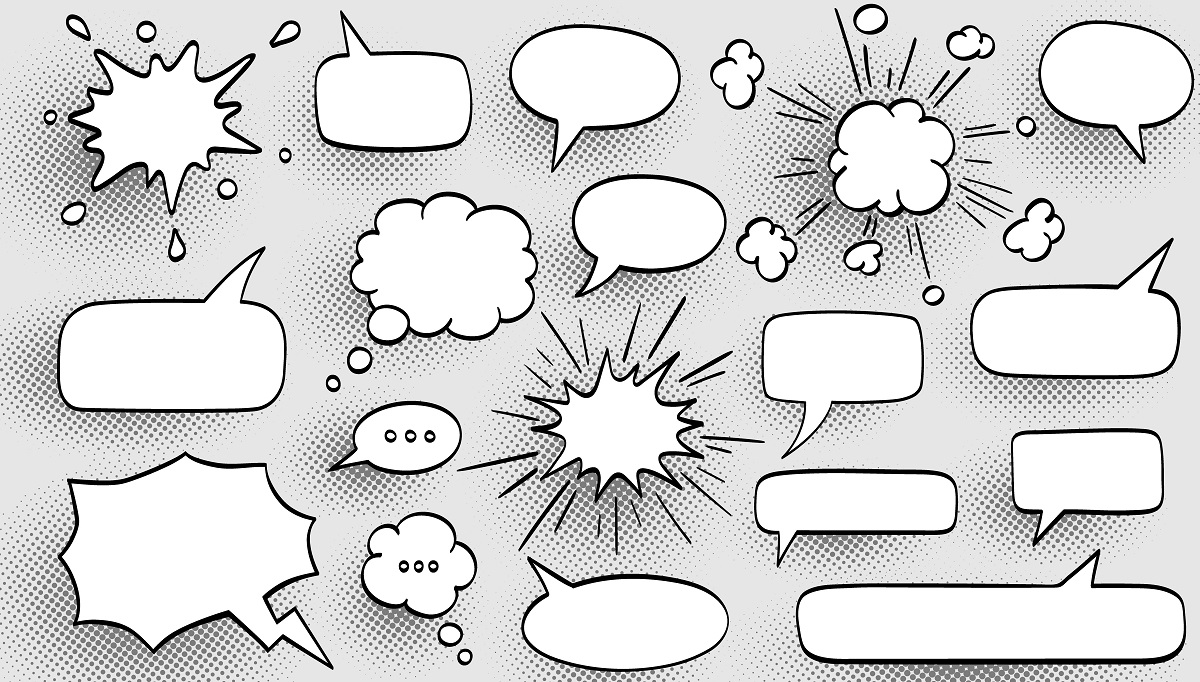 NataLima/Shutterstock.com
NataLima/Shutterstock.comここ数年ほど、二つの大学で小説創作の講座を受け持っていて、延べでいうと200人以上の学生の小説を読んできた。そのなかで共通する顕著な傾向が一つあった。それはラノベやアニメ、つまりサブカル作品のみを読んできた学生の書く文章と、スタート地点は同じであってもそこから一般の文学作品にまで手を伸ばして読んでいる学生の文章とは明らかに差があることだ。
前者の小説はまず擬音語が多い。そして会話が多く地の文が少ない。そして圧倒的に語彙が貧弱である。一方、後者は地の文でしっかりと客観描写が出来ており、語彙が豊富である。
もしこれが違う創作の授業であったら、たとえば物語のプロットをコマ割りの絵とセリフで表しなさい、という課題であったら、様相はまったく異なるだろう。語彙の乏しかったはずの学生が、格段に雄弁になるのは想像に難くない。
要するに、使用している表現ツールが違うということなのだろう。とすると、受け手と送り手の間を繋いでいるものも〈非言語化された〉何ものか、なのだろうか。
そこで思い出したのだが、あれは90年代も終わり頃のこと、ある集まりの流れで作家や編集者、それにデザイナーやカメラマンがひとつのテーブルに座る酒席があった。ほぼ全員が初対面で、そう深い話もせずにダラダラと会話をしているなかで、サブカルにやけに詳しい若い男性のデザイナーに対して、ちょっとだけ年長の女性編集者が突然、こう言って怒り出したのだった。
「あなた、さっきから『マジすか』しか言わないじゃない。もっと何とか別な言いようはないの!」
おそらくアニメファンのボリュームの大部分を支えているのは、アニメにあえて「批評的言語」を紐付ける必要のない人々だろう。感動したアニメにわざわざしち面倒臭い理屈をつけて語る必要はない。〈非言語化された〉何ものかで分かり合っていれば充分に違いない。
そこにあえて言語を使って応ずるとすれば、ごく単純なクリシェ(常套句)、たとえば「マジか」と「ヤバい」と「カワイイ」の3語があれば、事足りる。そこにあえてもう1語付け加えるならば、「泣ける」だろう。それらの言葉に別に意味を探る必要はない。いわば吹き出しの中の感嘆符の代わりなのだから。
この「言語」と「非言語」の間は、果たしてシームレスにつながっているのだろうか? あるいはそこには何らかの断絶が横たわっているのか? そしてそこに〈身体性〉はどう関わってくるのか? そのことを次回、丸山さんが突きつけた〈反措定〉も絡めて考えてみたい。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください