米中対立が激しさを増す「新冷戦」の今、必要とされるのは幾人ものケナンか
2021年03月07日
国際法の常識を無視して「領海」外での武器使用を可能にする中国海警法が施行されて1か月以上がたつ。中国の動きは、アジア太平洋の安定を揺るがしかねず、それに対してアメリカも警戒レベルを上げ続けている。両大国の覇権争いは「新冷戦」ともいわれる段階に達した。だが、そもそも中国をこうした行動に駆り立てている源泉は何なのだろうか。中国の拡張主義を抑止し、破局を避けることは可能なのか。75年前、新たな脅威として台頭したソ連について冷静な分析を下した米外交官の知恵を再読してみよう。
 来日したジョージ・ケナン米国務省政策企画局長(左)=1948年3月1日、羽田空港で、朝日新聞撮影
来日したジョージ・ケナン米国務省政策企画局長(左)=1948年3月1日、羽田空港で、朝日新聞撮影第2次世界大戦が終わって間もない1946年2月半ばのことだ。在モスクワのアメリカ大使館のナンバー2だったジョージ・ケナン(公使参事官)は風邪をこじらせて寝込んでいた。上司であるハリマン大使が不在だったため、ケナンは病床で執務を続けねばならなかった。そこに本国から一通の電報が届いた。
第2次世界大戦が終わって半年あまり。当時はまだ、ドイツと日本を相手にした大戦中の連合国同士の絆への信頼が残っていた。アメリカは戦後秩序の形成にあたってソ連の協力を求めていた。だが、緩衝地帯として東ヨーロッパ諸国に共産党政権を樹立しつつあったソ連は、アメリカ主導の国際秩序より自国の安全保障を優先していた。戦後構想の柱となる世界銀行にも国際通貨基金にも入るそぶりを見せなかった。
ソ連に対するナイーブな期待をいまだ抱いていたアメリカ財務省は、ソ連の意図をいぶかり、クレムリンが何を考えているのか、国務省を通して在モスクワ大使館の見解をただしたのだった。ハリマン大使の不在は偶然だったが、この偶然から歴史を動かすドラマが生まれる。
高熱にうなされていたケナンだったが、アメリカ国務省随一のソ連専門家として、長年蓄積してきた見解を今こそワシントンに直訴すべきだと考えた。秘書の助けを借りて、ソ連の行動の源泉を大局的に分析する8000語におよぶ電報を口述筆記させた。
これがその後、アメリカの対ソ戦略「封じ込め」の構想を生んだ「ロング・テレグラム(長文電報)」である。
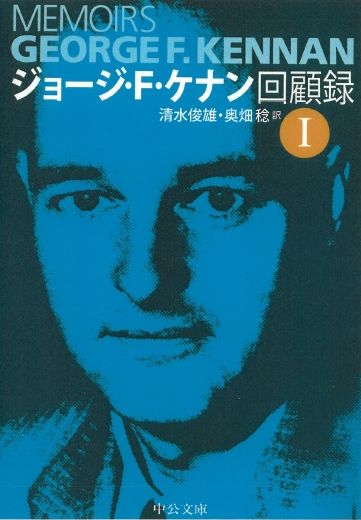 外交官生活を振り返った『ジョージ・ケナン回顧録』(中公文庫)
外交官生活を振り返った『ジョージ・ケナン回顧録』(中公文庫)卒業後は外交官になったものの、もともと学究肌のケナンは仕事になじめず、早々に辞職を考えた。だが、上司が特殊言語の習得のための研修制度があることを知らせ、ケナンは国務省にとどまった。ケナンが選んだのはロシア語だった。ロシア革命直後でアメリカはソ連と国交がなかったため、ケナンはドイツでロシア語を学び、近隣のバルト三国でロシアの観察を続けた。
1933年にアメリカがソ連と外交関係を結んだときには、ケナンは5年余りの修行を終えて、すでに一人前のロシア専門家となっていた。その後、モスクワと国務省、およびヨーロッパ諸国での勤務を経て、大戦末期の44年に在モスクワのアメリカ大使館の公使参事官の職に就いた。
ケナンは達意のロシア語で人脈を築き、鋭い観察眼で、スターリン体制の強権的な性格とそのもろさを見抜いていた。そういう彼にすれば、大戦中と同じようにソ連とうまくやっていけると考えた米政府内の見方は、あまりにもナイーブに思えた。その思いを、国務省あての46年2月の「ロング・テレグラム(長文電報)」に込めたのである。
この電報はワシントンの政界・官界で大センセーションを巻き起こした。だれもが判断に迷っていたソ連の対外行動の動機を鮮やかに読み解いていたからだ。無名の外交官は一気に時の人となった。ケナンはほどなく本国に戻り、1947年には、新設された国務省政策企画局の初代局長に任命された。
ケナンがモスクワから本国に送った「長文電報」はのちに一般向けに改訂・拡大され、有力誌「フォーリン・アフェアーズ」の1947年7月号に、「ソヴィエトの行動の源泉」というタイトルで掲載された。国務省の要職にあった筆者ケナンの名は隠され、「X」とされた(そのため一般には「X論文」と呼ばれる)。
この「X」論文から、ケナンの米ソ冷戦への処方箋(しょほうせん)を紹介する。
 いまや国際政治学の古典となったケナンの『アメリカ外交50年』(岩波現代文庫)
いまや国際政治学の古典となったケナンの『アメリカ外交50年』(岩波現代文庫)ケナンが見るところでは、ソ連の指導者たちにとっては、ロシア革命は依然進行中であり、共産党は権力を絶対化するプロセスの中にあった。諸外国がソ連に執念深い敵意を抱いている以上、共産党は、ソ連国内で無限の権力を追求する必要があると考えた。そのいっぽう、ソ連の指導者たちは共産主義というイデオロギーの正当性に揺るがぬ長期的な信頼を寄せていたため、短期的な日々の交渉では現実主義的な妥協もいとわない、と指摘する。
そうしたソ連観を踏まえて、ケナンは次のように提言した。
「アメリカの対ソ政策の主たる要素は、ソ連邦の膨張傾向に対する長期の、辛抱強い、しかも確固として注意深い封じ込めでなければならない…このような政策は、脅威とか怒号とか大げさな身ぶりで外面的『強硬さ』とかを見せることとは何の関係もない…クレムリンは政治の現実に対する反応において根本的に柔軟である…ロシアの指導者たちは人間心理に対する鋭い判断力を持っており、憤激や自制心の喪失は、力の弱いことの証拠であることを知っている…ロシアとうまく取引するコツは、いかなるときでも落ち着いて、ロシアが自らの威信をあまりそこなわないで応諾できるような道を開いておくことだ」(「ソヴィエトの行動の源泉」、ケナン『アメリカ外交50年』岩波現代文庫所収)
またケナンは、ソ連の体制内部に「やがて自分の潜在力を弱めてしまうような欠陥をその内に含んでいる」とも指摘している。注意深い封じ込めによって、長い時間をかけてソ連体制の崩壊を待つというシナリオが、そこから浮かび上がる。ソ連を軍事的に倒す必要はない、封じ込めで十分だという見解だ。
1947年、アメリカのトルーマン政権は、内戦状態にあったギリシアと、ソ連と対立していたトルコに軍事援助を表明した(トルーマン・ドクトリン)。さらに大規模なヨーロッパ経済復興援助計画(マーシャル・プラン)を始めた。その背景には、ケナンのこの青写真があった。
その後の冷戦の展開は、必ずしもケナンが想定していた通りではなかった。ケナン自身が後に認めたように、「X論文」では封じ込めの手段が明示されていなかった。
ケナン本人の念頭にあったソ連の脅威とは、外国の国内政治に浸透する政治的な影響力であった。だから、封じ込めの手段も政治的手段を想定していた。だが、実際のアメリカの冷戦政策は軍事色を帯びていき、封じ込めは軍事的封じ込めと解釈された。その結果、1962年のキューバ・ミサイル危機のように一触即発の事態もあった。
しかし、冷戦が最終的にソ連体制の自壊で幕を閉じたのは、ソ連体制の病理を診断して対処方針を描いた青写真が、冷戦の初期からアメリカ政府の中にあったことが大きかったのではないか。
では今、「中国の行動の源泉」を描ける新しいケナンはいるのだろうか。
2018年10月4日に、当時のペンス米副大統領が保守系シンクタンクであるハドソン研究所で、刺激的なスピーチを行った。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください