ワクチンの接種で、「発症」だけでなく「重症化」予防も
2021年03月22日
厚生労働省の報告(2020年11月時点)によると、新型コロナウイルス感染症の重症化率は約1.6%、死亡率は約1.0%となっている。以前に比べて低くなっているというものの、高齢者では今もなお重症化したり、亡くなったりする人は多く、30代と比べると重症化のリスクは70代で47倍、80代で71倍だ。
重症化しやすいのは高齢者だけではない。慢性閉塞性肺疾患(COPD)や糖尿病、高血圧、肥満などの持病がある人も注意が必要だとされている。
重症化すると、体内では免疫細胞が過剰にサイトカインという炎症物質を産生する「サイトカインストーム」が起こる。しかし、なぜこうした重症化が起こるのだろうか。また、重症化する人としない人とでは何か違いがあるのだろうか。免疫学を専門とする医師の宮坂昌之さん(大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授)に、重症化のカギとなる免疫について話を聞いた。
――新型コロナウイルス感染症の重症化で、わかってきたことは何でしょうか?
宮坂 世界各国の研究者が注目しているのが、“T細胞”という免疫細胞です。免疫には大きく分けると、生まれつき持っている自然免疫と、生まれた後にさまざまな病原体に曝されることで得られる獲得免疫とがあります。T細胞とは後者の獲得免疫の中心を担うリンパ球です。
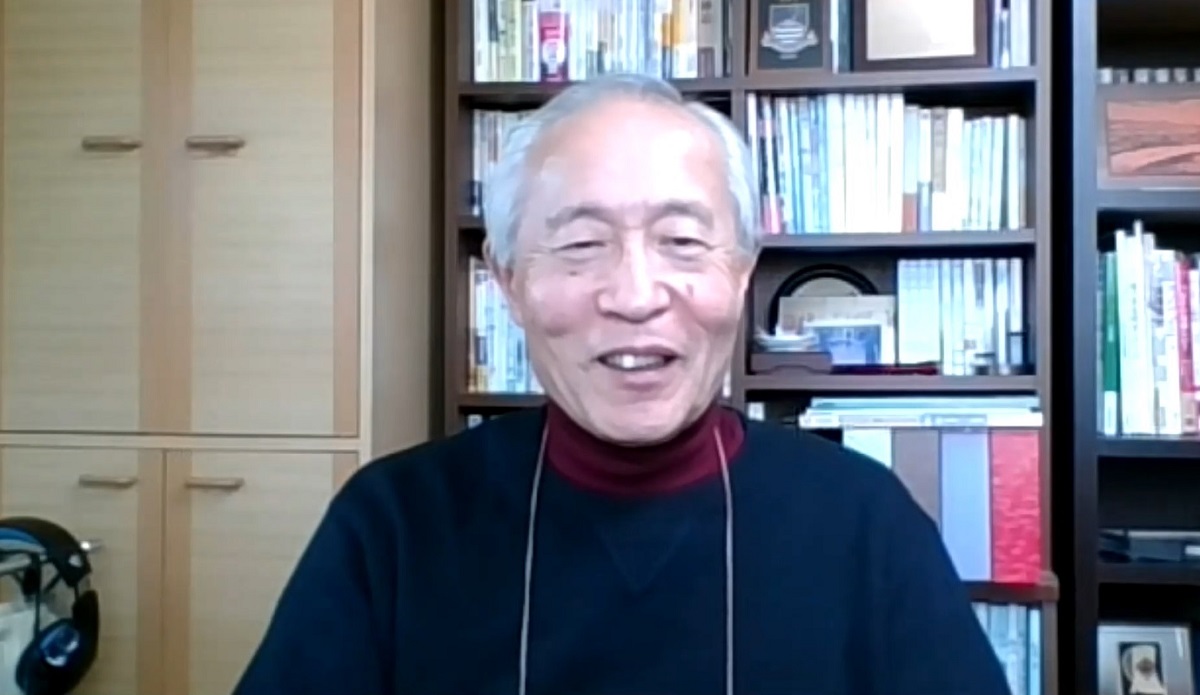 宮坂昌之・大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授
宮坂昌之・大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授ヘルパーT細胞は体内を常にパトロールしていて、敵である細菌やウイルスなどの抗原を見つけると、キラーT細胞に「攻撃せよ」と指令を出したり、B細胞という免疫細胞に抗体(中和抗体)を作らせたりしています。炎症に関わるさまざまなサイトカインを作るのも、ヘルパーT細胞です。
キラーT細胞はヘルパーT細胞の指令を受けて抗原を持つ細胞(たとえばウイルス感染細胞)を攻撃します。レギュラトリーT細胞はヘルパーT細胞、キラーT細胞とは反対の作用を持ち、免疫反応にブレーキをかけるように働きます。
司令塔のヘルパーT細胞、前線で病原菌と闘うキラーT細胞、これらの細胞をコントロールするレギュラトリーT細胞、この3者がバランスよく調整されることで、免疫システムがうまく働くというわけです。
そしてもう一つ忘れてはならないのが、メモリーT細胞の存在で、新型コロナウイルス感染症に対して重要な役割を持ちます。
多くのヘルパーT細胞やキラーT細胞は、抗原が体内から排除されるのと共に数が減っていきますが、このなかのごく一部が長い寿命を獲得し、体内に存在し続けます。こうしたT細胞をメモリーT細胞と呼びます。この細胞がいるからこそ、何カ月も経ってから再び同じ抗原に出会ってもすぐに反応し、免疫システムを作動させることができるのです。
 ワクチン接種を受ける群馬県・前橋赤十字病院の医療従事者=2021年3月19日
ワクチン接種を受ける群馬県・前橋赤十字病院の医療従事者=2021年3月19日――新型コロナウイルス感染症にT細胞が関与する研究には、どんなものがありますか?
宮坂 まず、アメリカ、オランダ、ドイツなど7カ国で報告された研究報告があります。いずれも、2019年以前の、新型コロナウイルスが存在する前に凍結していた血液サンプルを調べたところ、なんとそのサンプルの2~3割に新型コロナウイルスに反応するヘルパーT細胞が見つかりました。これはおそらく昔から新型コロナウイルスが存在していたというよりも、何か別のコロナウイルスの交差免疫(後述)によるものだと考えられます。
基本的にT細胞は一つの抗原に反応するようにできています。そのため、ふつうは新型コロナウイルスの抗原に反応するT細胞は、インフルエンザウイルスなどほかのウイルスには反応しません。ですが、例外として別のウイルスが新型コロナウイルスと共通の抗原を持っていれば、両方のウイルスに反応することができます。これを交差免疫といいます。
普通の風邪を起こす季節性コロナウイルスは、新型コロナウイルスのほかに4種類あります。これらに過去に感染した人が、交差免疫を持った可能性があるのです。
実際、季節性コロナにかかった人が新型コロナウイルス感染症にかかりにくいのか、あるいは重症化しにくいのかを調べた研究結果がアメリカから報告されています。それによると、感染予防にはあまり効果がないものの、重症化予防には効果がありそうとのことでした。
ドイツではまた、新型コロナウイルスの感染者を軽症者、中等症者、重症者にわけ、血液中のヘルパーT細胞を調べた研究結果が発表されています。血液中からは症状が重くても軽くても同じように、多くのヘルパーT細胞が見つかっていたのですが、問題はその中身でした。
軽症者の血液中のヘルパーT細胞は、新型コロナウイルスに反応性が高い“高親和性”のものが多く存在していたのですが、重症者ではウイルスに反応しにくい“低親和性”のものが多く存在していたのです。
低親和性のヘルパーT細胞はウイルスを抑制する力が弱いため、ウイルスがどんどん増殖し、それを受けて免疫暴走によるサイトカインストームが起こる――。こんなメカニズムが働いていると推測されるわけですが、今のところ、なぜ低親和性のヘルパーT細胞が増えるのか、また、どういう人が低親和性のヘルパーT細胞を持ちやすいのか、そういったことは明らかになっていません。それが解明できれば、重症化するかどうかが判定できるバイオマーカーができるかもしれないですね。
――レギュラトリーT細胞に関しての研究はありますか?
宮坂 免疫にブレーキをかけるレギュラトリーT細胞に関してはつい最近、二つの論文がほぼ同じタイミングで出ました。興味深いのは、二つが相反する内容だったことです。一つは、レギュラトリーT細胞が末梢血(血管の中を流れる血液)では増えていたという報告、もう一つは、レギュラトリーT細胞が肺の中で著しく減っていたという報告だったのです。
一般的に、感染によって激しい炎症が起こっている場所では、さまざまな免疫細胞が反応し、サイトカインを作っています。こうしたサイトカインはレギュラトリーT細胞にダメージを与えるため、その数が減って炎症にブレーキがかかりにくくなっています。ただその一方で、こうした反応は局所だけなので、末梢血ではレギュラトリーT細胞が多く存在しているのかもしれないのです。
この二つの研究が正しいとしたら、レギュラトリーT細胞が肺で少なく、末梢血で多かったのは、こうした理屈が考えられるわけです。ただ、レギュラトリーT細胞の新型コロナウイルス感染症への関与はまだわかっていないことが多いので、これからの研究報告が待たれます。
 ワクチン接種後に強いアレルギー反応を起こしたと想定した患者にアドレナリンを注射する模擬実験=2021年3月15日、秋田市保健センター
ワクチン接種後に強いアレルギー反応を起こしたと想定した患者にアドレナリンを注射する模擬実験=2021年3月15日、秋田市保健センター――ワクチンで重症化は防げるでしょうか。
宮坂 日本では2月17日から一部の医療関係者への先行接種が始まっていますが、ワクチンでも、中和抗体だけではなく、T細胞による免疫効果が期待されています。
そもそも中和抗体
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください