2021年06月21日
緊急事態宣言下では、休業した書店が少なくなかった。「本屋さんで飛沫を飛ばしている人なんかいないのに」と思う一方で、外出の理由を減らすためと考えれば仕方ない。いや、だったらなぜオリンピックはできるのだろう。オリンピックのことを考えるともやもやが膨らむ。
話がずれたが、私の住む神奈川県はまん延防止等重点措置にとどまり、本屋さんは開いていてくれた。いつも行くお店で、物々しいタイトルとインパクトのあるカバーに思わず手を取った。翻訳物でこの厚さ、読み切れるだろうか……と心配もよぎったが、まったくの杞憂だった。『BAD BLOOD──シリコンバレー最大の捏造スキャンダル 全真相』(関美和、櫻井祐子訳、集英社)。無駄をそぎ取った歯切れのいい文章と、疾走感のある場面展開で、400ページを2日で読み終わった。
著者は、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で調査報道を20年ほど続け、現在はフリーのジャーナリストであるジョン・キャリールー。本書は、同紙の記者だったときに、シリコンバレーのスタートアップ(ベンチャー企業)「セラノス」で起きていた不正を明るみに出したものだ。
まず、本書が取り上げている事件の概要を紹介したい。
セラノスは2003年、スタンフォード大学の学生だったエリザベス・ホームズのアイデアから始まった。患者が強いられる何通りもの検査を、1滴の血液を採るだけで行う検査機器を開発する、というものだ。
エリザベスは20代、大きな青い目が印象的な女性で、アップルの設立者スティーブ・ジョブスを意識していつも黒いハイネックを着ている。声は驚くほど低音だ。画期的なアイデアに彼女の風貌などもあって、投資会社が次々に投資を行っていく。
とはいえ、試作は困難を極めた。間もなく完成するはずが、実際は「中学生の工作のよう」で、不具合が多発。患者の負担を減らすため、という大義は徐々に薄れ、資金集めのための取り繕いに突っ走っていく。行われたのは明確な詐欺だ。
たとえば、投資家への資料には、でっち上げの収益見通しが示され、製薬会社への実演では、あらかじめ録画した成功場面の動画を見せていた。命にかかわるだけに悪質だ。不完全な機器を市場に出してしまえば、たとえば本来治療が必要な人に対して、「異常なし」と判断してしまうこともありえる。
 「セラノス」の創業者エリザベス・ホームズ Debby Wong/Shutterstock.com
「セラノス」の創業者エリザベス・ホームズ Debby Wong/Shutterstock.com雑誌「TIME」の表紙をエリザベスが飾ったのを皮切りに、セラノスの評価はさらに上がり、会社の要職には元国務長官のキッシンジャーや海兵隊の参謀マティス(元国防長官)などが名を連ねるように。お墨付きを得て、さらに資金が集まっていく。
あるとき、著者は知人からの紹介で、セラノスを退職した元社員と会う。そしてそこから怒涛の取材を重ねていく。セラノス側からはさまざまな妨害工作を受けたが、2015年10月15日の紙面に掲載された。見出しは「もてはやされたスタートアップの行き詰まり」。記事がきっかけで、その後セラノスは転落を余儀なくされる──。
 2018年9月に解散した「セラノス」の旧本社社屋=カリフォルニア州パロアルト Michael Vi/Shutterstock.com
2018年9月に解散した「セラノス」の旧本社社屋=カリフォルニア州パロアルト Michael Vi/Shutterstock.comなぜ中身が不十分な会社がこれほどまでに評価されたのか、事件としても興味深いのだが、私が一番印象に残ったのは別のところだ。記者が世の中を揺るがすような情報をつかんだとき、新聞に書けるのかという点だ。
著者は冒頭にも述べたように、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の記者であり、同紙のオーナーはルパード・マードックである(正確には同紙の親会社の所有者)。そのマードックは、セラノス最大の投資家だった。
オーナーが巨額の投資を行っている会社の不祥事を書くのか。実際、セラノス側はそこを突き、エリザベスは計4度、マードックに直接会って訴えた。キャリールー記者が追っている事実は間違いで、記事が表に出ればウォール・ストリートは恥をかくし、セラノスは大きな痛手を受ける、と。しかしマードックは取り合わなかった。そして記事は掲載された。
私は考えた。もし、日本で同じことが起きたらどうなっていただろう。オーナーや社長に不都合な事実を書けるだろうか。記者は書いても、会社としてGOサインを出せるのか?
この本を読んでいたころ、私はマーティン・ファクラーさんの本を作っていた。マーティンさんは元ニューヨーク・タイムズ東京支局長を務めた記者で、現在はフリーのジャーナリストとして活躍している。日本語も中国語も堪能で、政治、経済はもとより、東アジアの歴史にも精通している。
 マーティン・ファクラーさん
マーティン・ファクラーさんマーティンさんは以前、ウォール・ストリート・ジャーナルでも働いていた。私は気になったことを聞いてみた。マードックは、自分が所有する会社の記事によって巨額の損失が出ることがわかっていながら、口出しをしなかったのだろうか。
そう聞くとマーティンさんは少し驚いたように答えた。
「口出しされたと書かれているのですか」
──いえ、口出しをしたとは書かれていません。ただ、されなかった、とも明記されていなくて。
「口出しすることは考えられませんね。少なくとも私が記者だったときは、経営者側から何か言われるということはありませんでした。もしそんなことが起きたら、逆に新聞に書かれてしまうでしょう」
そう言って少し笑いながらこう続けた。
「仮に緘口令を敷いたとしても、記者というのは、それを黙って受け入れる人たちでないですしね。どこからか漏れるでしょう。そのとき、新聞の信用は地に落ちます。マードックも投資家の視点から見たとき、それはビジネスとしてよくないと考えたのかもしれませんね。
実際のところは分かりませんが、アメリカの新聞社はビジネス系と編集系がはっきり分かれています。私はウォール・ストリート・ジャーナルにいるときも、ニューヨーク・タイムズにいるときも、オーナーから何か言われたことはありませんよ」
──編集と経営の分離ですね。日本でもよく言われています。でも、たとえば今回のオリンピックを見ていても、なかなかそうとは思えなくて。アメリカで、新聞社がオリンピックのスポンサーになることはありますか。
「調べないとわかりませんが、普通はないでしょう。批判記事が書けなくなりますよ」
──日本は大手紙すべてが東京オリンピックのスポンサーです。読売、朝日、毎日、日経、産経に北海道新聞です。
「おぉ……。体制の一部です、と公言していることと同意ですよ」
──どの新聞も「編集と経営の分離」を掲げて、批判するときは批判すると言っています。朝日新聞は、五輪を中止せよ、との社説を掲載しました。
「社説や論説では威勢のいいことを言いますが、ほかの報道はどうですか。本当に知りたいことが書かれていますか」
──書かれていることもありますが、オリンピックに関しては、なぜいま開催しなくてはいけないのかはよくわかりません。
「日本の新聞社の記事は、少なからず官僚や政府の発表モノです。アクセスジャーナリズムと言われるもので、権力者側にアクセスすることでネタを取り報道するという手法です。また、記者クラブなどもそうですが、インサイダーの特権を何より重視していると私は見ています。
アクセスジャーナリズムの対極にあるのが調査報道です。独立した立場から取材して、ファクトを積み重ねて、独自のストーリーを提示することです。新聞社に求められているのは後者ではないですか。それに読者はお金を払うわけです。
アクセスジャーナリズムに頼っていては、私たちが本当に知りたい記事は書けません。オリンピックなら、『なぜオリンピックを延期、中止できないのか』『いったいいくら、どこに税金が使われているのか』なども知りたいですよね。
そもそも新聞社は、オリンピックのスポンサーとして多額のお金を払って、企業として得をしているのですか。そのお金を使って調査報道をしてほしいですよね」
──かねて、日本のアクセスジャーナリズムに警鐘を鳴らしていますね。
「きっかけは3・11です。原発の事故で、政府は20㎞圏内に退避命令を出しましたが、30㎞圏内は安全だと言い、メディアもそう報じていました。実際、その直後、20~30㎞圏内の南相馬には2万人が残っていました。私が取材に行くと、安全であるはずの南相馬には日本の大手メディアの記者は1人もおらず、いたのはフリーランスか、私のような外国人の記者だけでした。
大手メディアは『安全だ』と報じながら、みんな逃げたのです。記者のなかには、取材すべきと考えた人もいたでしょう。私も大手メディアの優秀な記者を何人か知っています。おそらく会社の判断でしょう。彼らはインサイダーとして、政府から別の情報を得ていたのかもしれません。それはわかりませんが、最低でも『政府はこう言っているが、わが社はこう判断した』と書くべきでしょう。信じられませんでした。自分の国民がいるのに記者がいないとは! 南相馬の人たちは捨てられたんです。アクセスジャーナリズムの限界だと思いました。このときのことは以前『「本当のこと」を伝えない日本の新聞』(双葉新書)に詳しく書きました」
マーティンさんとはこのあと、日本の報道機関を委縮させた朝日新聞の「吉田調書問題」について話したのだが、別の機会に記せたらと思う。最低限のことだけ言うと、日本のメディア企業は記者個々人の取材成果を生かせる組織なのか、ということだ。報道機関であることを優先させるのか、インサイダーの特権を守るのか──。記者の成果を尊重し、しっかり生かされる組織であってほしいと思う。
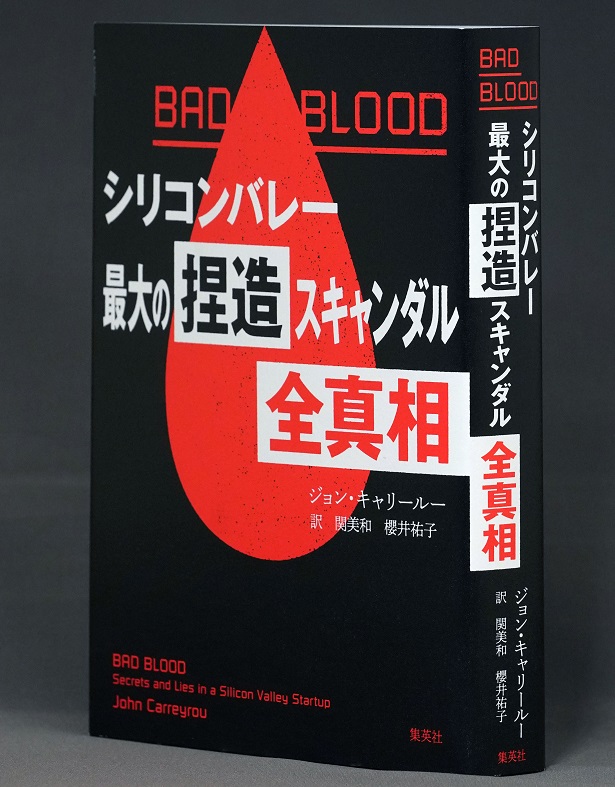 ジョン・キャリールー『BAD BLOOD──シリコンバレー最大の捏造スキャンダル 全真相』(関美和、櫻井祐子訳、集英社)
ジョン・キャリールー『BAD BLOOD──シリコンバレー最大の捏造スキャンダル 全真相』(関美和、櫻井祐子訳、集英社)しかし最後まで読み、この違和は自分の浅はかさから来たのだと知った。巻末に事実の裏付けを記した細かい字の脚注が20ページにもわたってつけられている。神の視点で書けたのは、この圧倒的な事実の積み重ねがあるからなのだ。それを知ると、この本がずっしり重い気がした。
シリコンバレーのスタートアップ企業の醜聞を追った顛末記として一気読み必至の本書だが、一記者の書いた調査報道モノとして読むとまた別の感動を覚える。記者という仕事をしている人への尊敬の念が深まり、そして事実を発表する報道機関の姿勢に打たれた。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください