デマやフェイクニュースを聞いても相手を否定せず、あとから自分で調べ直す
2021年08月06日
世界で接種が進む新型コロナウイルスのワクチンで問題になっているのが、「ワクチンデマ」。そもそもワクチンはその性質上、デマやフェイクニュースと親和性が高く、ほんの少しの真実が含まれることで人々は信用してしまいやすい(前稿)。こうしたワクチンデマやフェイクニュースから身を守るためにはどうしたらいいか。その対策や意外な落とし穴について、デマやフェイクニュースに詳しい国際大学GLOCOM准教授・主任研究員の山口真一氏に解説していただいた。
コロナワクチンを巡るデマはなぜ生じやすいのか──山口真一氏に聞く(上)
山口真一 国際大学GLOCOM准教授・主任研究員
1986年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。博士(経済学)。専門は計量経済学。研究分野は、ネットメディア論、情報経済論など。主な著書に『正義を振りかざす「極端な人」の正体』(光文社新書)、『なぜ、それは儲かるのか──〈フリー+ソーシャル+価格差別〉×〈データ〉が最強な理由』(草思社)、『ネット炎上の研究──誰があおり、どう対処するのか』(共著、勁草書房)。ほかに東京大学客員連携研究員、シエンプレ株式会社顧問、日本リスクコミュニケーション協会理事などを務める。
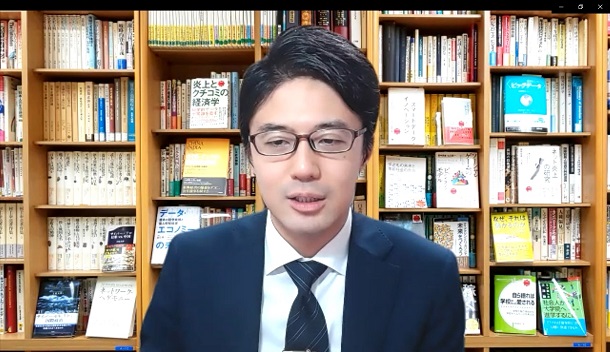 山口真一・国際大学GLOCOM准教授、主任研究員
山口真一・国際大学GLOCOM准教授、主任研究員──山口さんは、新型コロナのワクチンデマの広がり方も調べていますね。
山口 ツイッターにおけるコロナワクチンデマの拡散状況を調べました。なぜツイッターなのかというと、一点は個人発信のソーシャルメディアは人々の間でどのような情報が拡散されているか観察するのに適しているから、もう一点は日本ではフェイスブックなどに比べてツイッターのユーザーが非常に多く、情報拡散能力が圧倒的に高いからです。
これらはデマに限らずいえることで、「リツイート」という画期的な機能によるところが大きいと考えています。また、最近のツイッターユーザーは、友人とのコミュニケーションツールというだけでなく、情報収集の手段として使っている傾向が強く出ていることがわかっています。
──ニュースや情報をツイッターから入手している人が多いのですね。
山口 そういうことです。そこで、今年の3月から4月にかけて1000リツイート以上あった日本語の「ワクチン」という言葉を含むツイートを分析しました。そこでわかったのが、デマやフェイクニュースのような真偽不明な情報は、これらのツイート全体のたった4.7%しかなく、ほとんどはワクチン接種に関する正しい情報や予約に関する情報、供給が遅れていることに対する批判、ワクチンデマへの注意喚起などでした。
 PiXXart/Shutterstock.com
PiXXart/Shutterstock.com──ネット上ではワクチンデマが多いわけではなかったわけですね。
山口 割合としては、かなり少なかったことになります。興味深いのは、拡散まで考えたリツイート数になるとさらに少なく、「ワクチン」という言葉を含む投稿のリツイート数全体の4.3%にすぎなかったことです。つまりワクチンデマは我々が思うほど拡散されていなかった。これは通常のデマやフェイクニュースとは異なっている点です。コロナワクチンに関して、意外と国民は冷静に見ているのかもしれません。
──コロナワクチンでは、必ずしもネットがデマの温床になっていないと?
山口 その可能性はあります。以前私が実施したフェイクニュースの研究では、「ツイッターやユーチューブで情報・ニュースと接触しているかどうか」と「デマやフェイクニュースを信じる傾向」とは、関連がみられませんでした。といいますか、むしろインターネット歴の長い人や、ツイッターで情報・ニュースと多く接触しているほどデマやフェイクニュースにだまされにくい傾向さえみられたのです。
おそらく、ネット歴が長い人や長時間ネットを利用している人は、ネットやソーシャルメディアのニュースが玉石混交であることをわかっているのではないでしょうか。何よりインターネットやソーシャルメディアでは専門家だけでなく、いろんな人が好き勝手に発信します。ですから、そんなメディアだからウソや間違いはあるでしょうという前提で、情報の検証行動をしっかりしているのではないかと考えています。
──ネットの情報を鵜呑みにしていないわけですね。
山口 ソーシャルメディアの特徴を理解して使っているので、だまされにくいということです。反対に、ネット上のデマやフェイクニュースにだまされやすい人は、ソーシャルメディアへの信頼度が高い人、マスメディアへの不満度が高い人でした。「ソーシャルメディアの情報にはメディアが報じない真実がいっぱいある」と考えている人は、その情報を簡単に信じてしまうわけですね。
 zef art/Shutterstock.com
zef art/Shutterstock.com──ただ、新型コロナのワクチンデマが問題となる背景には、政府への不信感が影響しているようにも見えますが、どうでしょうか。
山口 すでに発表されていますが、「陰謀論を信じている人ほど政府への信頼度が低い」、あるいは「政治に対して無力感が高い人ほど陰謀論を信じやすい」という研究があります。そしてもう一つ、「日本では政府のコロナ対策に対し不満を覚えている国民の割合が高い」ことが、海外の調査で明らかになっています。そう考えると、コロナ対策に対する不満がワクチンデマの問題につながった可能性は否定できません。
ただ、コロナワクチンでいえば、政府は比較的、しっかり情報を発信しているのではないでしょうか。厚労省は接種後の副反応については都度、更新していますし、説明も割としっかりしています。
──河野行政改革担当相も積極的にコメントしています。
山口 あのような立場の人が積極的に発信すると多くの人に情報が行き渡り、少なくともワクチン接種に対して漠然とした不安を抱えている人は、その不安を払拭できるかもしれません。実際、私の分析でも、河野大臣がメディアやブログでワクチンデマを否定したことはツイッター上で大きな話題となったことがわかっています。
 noEnde/Shutterstock.com
noEnde/Shutterstock.com──先ほど、ツイッターではワクチンデマは拡散されていないという話でしたが、デマやフェイクニュースは知人から伝わるというケースも少なくありません。
山口 心理学の研究でも、専門家の話より、家族や友人、知人の話を信じてしまう結果が出ています。実は、ツイッターなどソーシャルメディアより
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください