「昔のように読めなくていい」「ペースが遅くてもいい」「読んだはしから忘れてOK」
2021年09月27日
新型コロナウイルスに翻弄されている間に夏が去り、早くも季節は秋である。まだ当分こういう状態が続くのかと考えると気分は重たくなるが、愚痴ったところで仕方がない。
むしろ、いま感染対策とともに私たちがすべきは、こうした状況下でも心を落ち着かせることではないか。せっかくの秋なのだから、できる限り穏やかに過ごしたいところである。
そこでおすすめしたいのが読書だ。
「読書の秋」だから……というベタな理由はさておいても、テレワークの浸透によって自由な時間が増えた方も少なくないはず。だとすれば、確実に過ぎていくその時間を大切に使ったほうがいい。少なくとも読書は、無目的にテレビを見たり、ネット動画を垂れ流したりして時間を浪費するよりもずっと有意義だろう。
「そうはいっても、気がつけばあまり本を読まなくなってしまったからなあ」
「本は好きなんだけど、読むペースが落ちてきた気がするんだよね」
「読んだはしから忘れてしまって、だんだん自信がなくなってきた……」
本を読もうと提案すれば、そんな声がいろいろなところから聞こえてきそうである。実際、そういう人にもたくさん会ってきた。だが、それはごもっともな話。つまり別な表現を用いるなら、そもそも「読めなくて当然」なのである。
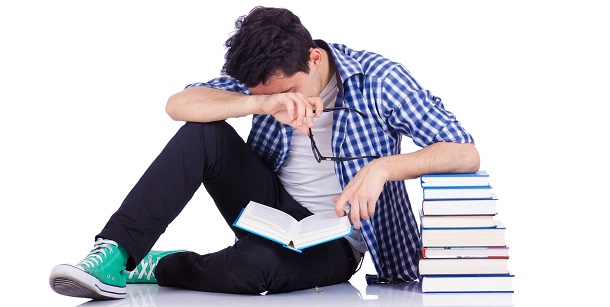 Elnur/Shutterstock.com
Elnur/Shutterstock.com私は書評家として、おもにウェブメディアで書評を書き続けている人間だ。もともと音楽ライターとしてキャリアをスタートしたのだが、30年近い時代の流れとともに、自然と書評のニーズが高まっていったのだった。取り上げているのはビジネス書が中心だが、毎日ほぼ休みなく書評を書き続け、気がつけば今年で9年目になる。また作家としても活動しているが、書評家のイメージが強くなっていったこともあり、ここ数年は読書関連の本を書く機会が増えている。
そんな立場にあるからこそ、「読めない人」の悩みが手に取るようにわかるのだ。というより、私自身も数年前までは似たようなものだった。子どものころから読書が好きで、学生時代には1日に3冊くらい読むことも少なくなかった。にもかかわらず、社会に出たら仕事に追われ、年齢を重ねるごとに、どうにも昔のようにはいかなくなっていたのだ。
書評を書くようになってからいろいろなことを解決できもしたが、とはいえまだまだ自分の“読書力”は完璧ではないと考えている。それどころか、“理想的な読書の仕方”については死ぬまで悩み続けることになるのだろうとさえ思っている。
いいかえれば、そんなものなのだ。読めなくて当然、読書ペースが落ちても当然、読んだ本の内容を忘れてしまってもまた当然。もちろん人間離れした読書能力を持っている人もまれにいらっしゃるが、むしろ、そういう人のほうが例外だと考えるべきだ。
そうすれば、「読めない」の先にある新たなスタートラインにつけるのではないだろうか? それは、私の読書に対する基本的な考え方でもある。
この夏にも、2冊の読書関連書籍を刊行した。手前味噌ながら、それらは読書になんらかのコンプレックスを抱く方のお役に立てるものではないかと自負している。そこで2回に分け、“理想的な読書の仕方”についてご紹介させていただきたいと思う。
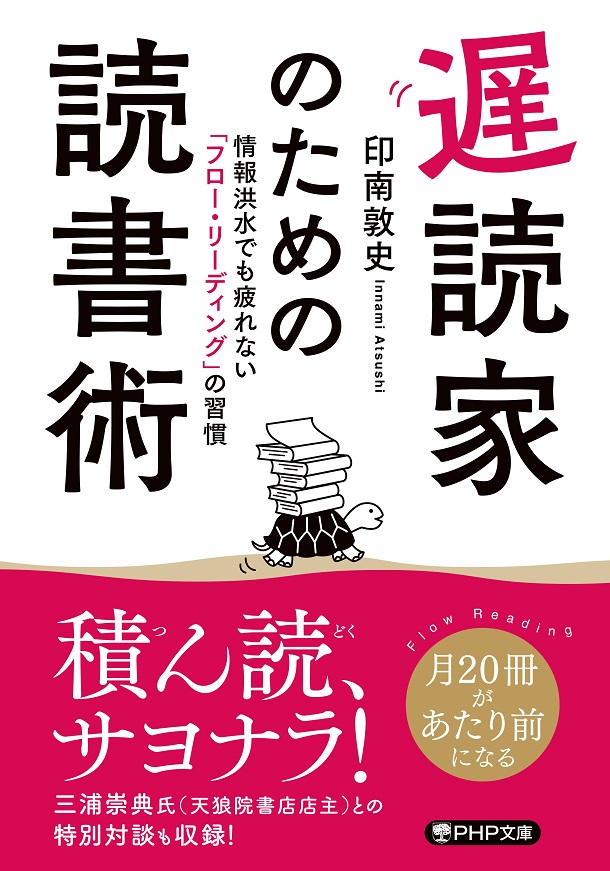 印南敦史『遅読家のための読書術 情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(PHP文庫)
印南敦史『遅読家のための読書術 情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(PHP文庫)そもそも同書は最初、担当編集者との「学生時代とくらべて、本をサクサク読めなくなったよねー」というような雑談をきっかけとして生まれたものだった。いわば前述した「読まなくなった」「読めなくなった」などの思いを共有したことから、「ひょっとすると、同じようなことで悩んでいる人は多いのでは?」という疑問に至ったわけである。
したがって、本書の基盤としてあるものは“コンプレックス”であるともいえる。もっといえば、私が伝えたいのは“読書コンプレックスは持ってよい”ということである。多くの人が読書のことで悩むのは、読書に対する自分なりの理想像を持っていて、しかしその理想どおりにいかないからだ。そのため、「自分は読めない人間なのだ……」と悩んでしまうことになるのである。が、冒頭で触れたようにそれは間違いだ。
なぜなら実際には、“読めない人”のほうが圧倒的に多いからである。逆にいえば、「理想と違って思うように読めない」状態こそが普通なのである。たとえば本書の序文にも書いたのだが、私は1ページ読むのに5分から10分の時間を費やしていたことがある。ボーッと読み進めていたら全然頭に入っていなかったことに気づき、同じところをまた読みなおし……なんてことを続けていたら、どんどん時間が経ってしまっていたのだ。
同じような経験をしたことがある方はきっといるはずだが、実はそこに重要なポイントがある。
人は多くの場合
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください