2021年11月16日
つい最近、自分の書棚で『ジャパン アズ ナンバーワン──アメリカへの教訓』(エズラ・F・ヴォ―ゲル、広中和歌子・大本彰子訳)を見つけました。1979年に日本で刊行されたこの本は、今でも1980年代の日本の経済的成功を語る時によく引き合いに出されます。パラパラとページをめくっていると、隔世の感というか、なによりも副題の「アメリカへの教訓」という今となってはあまりに皮肉な表現が印象に残りました。
「デジタル敗戦」「安いニッポン」などという言葉が飛び交う現代からみると、今は高齢者になった当時30代の団塊世代がバリバリ働いていた時代でした。「ウサギ小屋に住んで蟻のように働く」と外国人から揶揄されても「日本は世界第2位の経済大国なんだ」と社会全体が希望と活力に満ちていたあの頃が何だか嘘のようにも思えてきます。
我が国における急激な少子高齢化と人口減の危機に警鐘を鳴らした『未来の年表──人口減少日本でこれから起きること』(講談社現代新書)は、そういう「良き時代」を知っている世代にとっては衝撃的でした。2017年に作家でジャーナリストの河合雅司さんが書いてベストセラーになった新書ですが、それを読んで友人たちと話したのは、私たちのような1950年代の中庸に生を享けた人間たちには、そこで明らかにされる急激な人口減少という日本の未来像に衝撃を受けるとともに、ある種の違和感を覚えるということでした。何故なら、人口は爆発的に増え続けて、人類は食糧やエネルギー不足に悩まされるという共通認識が20世紀の後半まで存在した印象があったからです。
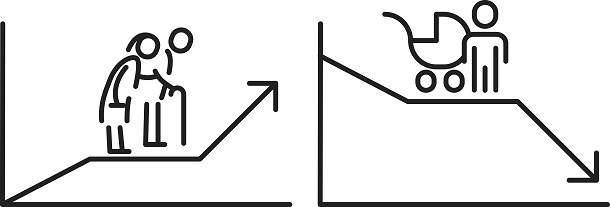 Vector street/Shutterstock.com
Vector street/Shutterstock.comいささか手前味噌になってしまいますが、光文社古典新訳文庫でマルサスの『人口論』(斉藤悦則訳)を2011年に刊行しました。人口について書かれた古典中の古典ですが、翻訳された原稿を読みながら、印象に残ったのは、第二章の冒頭にある有名な一節です。
人口は、何の抑制もなければ等比級数的に増加する。一方、人間の生活物資の増え方は等差級数的である。
こういう私の見解が正しいかどうか、いっしょに検討しよう。
この言葉はどこかでお聞きになったことがあるのではないでしょうか。簡単に言えば、人口の急激な増加に対して食糧は十分に増えないということです。私たちのみならず、20世紀を生きた人間の思考の前提になり、呪縛となっていた感があります。もちろんこの書物が書かれたのが1798年だということは忘れてはいけませんが、後で触れる中国で行われた一人っ子政策もマルサスの議論から自由ではなかったと考えるのはそれほど無理があるとは思えません。
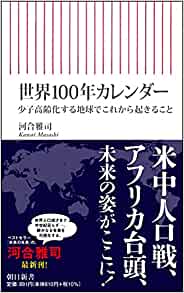 河合雅司『世界100年カレンダー──少子高齢化する地球でこれから起きること』(朝日新書)
河合雅司『世界100年カレンダー──少子高齢化する地球でこれから起きること』(朝日新書)人口増加に関しては、20世紀は人類史に刻まれる「人口爆発の世紀」であったということも知りました。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の「人口統計資料集」の2021年版で国連のデータが紹介されているそうですが、その内容を筆者の河合さんが紹介しています。
世界人口が10億人に達したのは、1800年代初め。つまりマルサスの『人口論』が書かれた直後になります。ところが、20億人に達したのは130年後の1927年。たった130年で倍になったことになります。農業の生産性が向上し、医療や衛生環境が改善されたことがその理由に挙げられています。
その約30年後、1960年には30億人。14年後の1974年には40億人になり、1987年には50億人を突破。1999年には60億人になったという驚きの記述があります。しかも特に増えていたのは開発途上国だということです。
しかし、この急激な人口爆発に変化が訪れます。1970年代前半に年平均の増加率の下落が始まり、これこそが21世紀中に迎える世界人口の減少への転換につながる予兆であり、ターニングポイントであったことを河合さんは指摘します。人口は増えていたけれど、増加率の減少が始まったということです。
しかも人口減少は日本に限ったことではなく、東アジアではすでに始まっているというのです。中国では生産年齢人口(15歳から64歳までの働くことができる世代)がピークアウトしており、韓国と台湾は2020年に人口減少に転じたというのも興味深い現象です。それでも国連の中位推計(現実的予測)では、2100年には世界人口は108億を超える数字が示されているようですが、これはかなり楽観的な見通しであるようですし、人口増加率は鈍化しているのです。
この指摘は、いままで未来の世界人口はまだまだ増え続けるのだと漠然と考えていた私には衝撃的でした。さらには同じ国連の中位推計によれば、21世紀の前半に起きる最大の変化があります。人口集積地が東アジア・東南アジアから西へ移ることです。具体的にはサハラ砂漠より南にあるアフリカ諸国の人口が2100年には世界人口の3分の1にまでなるというのですから驚きます。いままでの世界の見取り図が激変するのを目の当たりにすることになるのです。自らの想像力を駆使して未来を考えなければならない時代だと痛感しました。
こうした世界人口のバランスの変化は、世界情勢にも大きな影響を及ぼし、2100年時点の人口ランキングのトップ10はインド、ナイジェリア、中国、米国、パキスタン、コンゴ民主共和国、インドネシア、エチオピア、エジプト、タンザニアとなる。
これは米国ワシントン大学保健指標・保健評価研究所(IHME)の研究チームの予測だそうですが、全く違う世界が見えてきませんか。
 brichuas/Shutterstock.com
brichuas/Shutterstock.comさて、ここからは本書の最大の読みどころ。米中の人口がどう推移するかについて書かれた部分に触れましょう。最近の米中をめぐるニュースはきな臭いものばかりです。台湾をめぐる中国の露骨な発言も危機感を煽ります。習近平国家主席とバイデン大統領のやりとりも緊張感を増しています。
しかし、一旦政治的な出来事から離れて、本書で紹介されている人口という視点から中国をみると、ずいぶん違った印象があるのです。本書でも一章が中国に割かれています。世界一の人口大国である中国も統計数字には水増し疑惑があり、そのため共産党系メディアに中国の人口学者の分析として「早ければ2022年にもピークに達し、人口減少に転じる可能性がある」という記事が載ったことが紹介されています。一人っ子政策は、結果として中国の人口爆発を防ぐどころか、人口減少をもたらしたのです。中国政府が今年になって3人目の出産を認めることを表明したとしても、すでに手遅れの感は否めません。
中国の若者たちは、高学歴化が進み世界の若者と同じように晩婚化が進んでいるようです。また、将来の収入に対する不安から妊娠をためらう夫婦が増えているという指摘には、わが国と全く同じ事情があること、そしてそれは世界の趨勢でもあることを痛感します。私の周囲の若い夫婦からも、将来にたいする漠たる不安から子どもを持つことに逡巡していることを聞かされているからです。
国連の低位推計(悲観的予測)によれば、2100年の中国の人口は6億8405万人。しかし米ウィスコンシン大学の研究者で中国の人口問題の第一人者である易富賢研究員は、日経新聞に紹介された記事で、3億5000万人から4億5000万人と試算しているそうです。10億を超す人口大国・中国というイメージは今世紀末には終わっている可能性が大きいようです。
それでは米国はどうでしょうか。実は米国も人口増加率が鈍化しているのです。少子高齢化による「自然増加幅の縮小」と「移民の流入数の減少」が原因です。若い国家というイメージの米国ですが、高齢化は進んでいるし、出生数の減少も加速しているということです。その背景にあるのは、やはり女性の社会進出による晩婚、晩産化、若年層の所得減少、学費返済の負担増が理由として挙げられています。ただ平均寿命が延びたことと、世界トップの移民大国であるとの理由で人口減少社会にならないのです。しかしながら、移民がやってくることに危機感を抱く人々がいることは、トランプ前大統領の衰えぬ人気で知ることができます。
もう一つ、最初に私は新聞の記事で読んだ時に奇妙な感慨にひたったのですが、2020年の国勢調査で米国の白人人口が減少に転じたのです。これは国勢調査では初めてのことだそうですが、これからの米国のイメージが大きく変わっていく予兆であるという印象を受けました。
本書ではシンクタンクであるブルッキングス研究所が、2045年には全年齢でも白人人口が49.7%になると予測していることを紹介しています。しかも今後非白人のなかで増えるのはアジア系だということです。しかも2019年における米国生まれのアジア系人口の中央値が19歳という若さですから、米国のイメージを私たちは大きく変えるべき時期がきているのでしょう。
このように本書には無尽蔵ともいえるデータが採用されており、数字に弱い私などは理解するのに骨が折れた半面、とても説得力を感じました。
読み終えて思うのは、これだけ大きく変化するこれからの世界の中で、急激に人口減少が進む日本が延命可能な社会経済システムをどのように構築していくのかということです。政治の世界を見ていると、いささか心許ない印象は否めません。それにしても「新しい資本主義」という言葉の意味がよく理解できないのは私だけでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください