参画と議論なき環境では政治的な「自己効力感」は育たない
2021年11月18日
2021年10月31日に行われた衆議院選挙は、与党の自民党・公明党が過半数を制し、野党第一党である立憲民主党や、共闘を組んだ共産党は議席を減らすという結果に終わりました。投票率も55.93%と、前回よりは向上したものの戦後3番目に低く、諸外国と比べても異様に低い状態が続いています。
また、この選挙結果を受けて、立憲民主党の枝野幸男代表は辞任を表明し、11月30日に代表選が行われます。ところが、こちらはさらに盛り上がりが見られません。野党第一党が政権交代の選択肢として国民に認知されないままでは、次回の国政選挙でも投票率の向上はかなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。
そこで、どのようにして国政選挙の投票率を上げるか、とりわけ野党が、「政権に批判的であるにもかかわらず投票に行かない層」に投票所へ足を運んでもらうにはどのようにすればよいかについて、解決策を考えたいと思います。まず今回は低投票率の原因を分析することにしましょう。
 DesignRage/Shutterstock.com
DesignRage/Shutterstock.comまず、低投票率の背景として様々な要因があり得ると思いますが、「自分が投票しても社会や自分の生活環境は変わらない」という感覚が染みついてしまっている「政治的学習性無力感」が、近年多くの識者から指摘されています。
「学習性無力感」とは心理学の用語で、抵抗したり回避したりすることができないストレスの渦中に置かれているうちに、そこから逃れようとする行動すら起こさなくなってしまう心理のことです。これと似たような現象が、投票行動においても発生しているというのは、私も概ね同意します。
「無力感」という言葉の並びから、こういう心理に陥っているのは悲観的な人というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。たとえば、「(政治は変わらないのだからorコロナ対策なんて誰がやっても大変なんだから)政府への文句ばかり言っていないで、自分のやるべきことをやろう!」といったように、「サバイバル応援型の自己啓発」も、背景には政治への学習性無力感があります。
また、インターネット上でネット右翼や冷笑アカウントが頻繁に用いる「(政治は変わらないのだから)そんなに嫌なら日本から出ていけばいい」「(政治は変わらないのだから)そんなに嫌なら自分が立候補すればいいだけ」という論調も同様です。彼らは変わらないと信じ込んでいるからこそ、「変わらないことを理解していないように見える人たち」をバカにしているわけです。
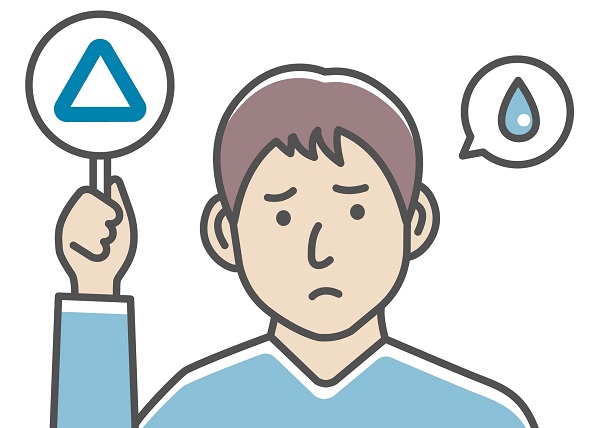 Barks/Shutterstock.com
Barks/Shutterstock.comそれにしても、この「政治的学習性無力感」の蔓延は、何が原因なのでしょうか? 近年その傾向が強まっている背景を探る前に、そもそも日本社会が無力感を与え続ける環境だということを忘れてはなりません。
その最たるものが教育でしょう。日本の学校教育では、議論を通じて皆で合意を得ることよりも、大人の言うことを黙って聞くことや、周りに合わせることが是とされる傾向にあります。一部の教師たちが独断と偏見で決めた人権侵害的な校則がいまだに存在するのは、その象徴です。
2021年11月7日放送の『日曜討論』(NHK)では、評論家の荻上チキ氏が学習性無力感の話に触れたのち、政治アイドルの町田彩夏氏は、声を上げれば社会を変えられると思えるのは、中高での生徒会自治に関与した経験のおかげという旨の話をしていました。私はこのようなものを「政治的自己効力感」と呼んでいるのですが、残念ながら、そのような経験を積める環境はほんの一握りなのが現状です。
たとえば、「目安箱の設置」は生徒会でよく提案される取り組みかと思いますが、生徒会に意思決定権限や自治権限が与えられていないため、ほとんど利用されないまま廃れることが多いと思います。
職場も同様の傾向にあります。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください