2022年04月13日
“沖縄の映画”と聞いて、あなたはどんな作品を思い浮かべるだろうか?
年配の方なら、1953年公開の『ひめゆりの塔』(監督:今井正、製作:東映)を知っているかもしれない。沖縄戦の実態を広く伝えたこの作品は多くの観客を動員し、どん底にあった東映を救ったといわれる。今井監督は、1982年に同じ水木洋子の脚本で沖縄ロケによるリメイク作品(製作:芸苑社)もつくっている。
 『ひめゆりの塔』(1982年版)の撮影現場。今井正監督(左)と主演の栗原小巻=那覇市南風原
『ひめゆりの塔』(1982年版)の撮影現場。今井正監督(左)と主演の栗原小巻=那覇市南風原また、1968年には舛田利雄監督による『あゝひめゆりの塔』(製作:日活)、1995年には神山征二郎監督による『ひめゆりの塔』(製作:東宝)もつくられた。戦後沖縄映画の一つの軸が「ひめゆり=反戦平和」にあったことは間違いない(いうまでもなく、それらの大作はすべて本土の作品である)。
ただ日本映画の好きな人なら、復帰前後から1980年代にかけて、沖縄映画にもう一つの(「ひめゆり映画」とは無縁の)濃厚な傾向が見え隠れすることに気が付いていただろう。
沖縄ヤクザ映画、とでもいうべきものである。
たとえば、復帰直前の1971年には、『博徒外人部隊』(監督:深作欣二、製作:東映)という奇妙な作品がある。主人公は零落した「組」のリーダーである郡司(鶴田浩二)。地元横浜ではもうどうにもならないと思い切った彼は、沖縄への侵出を目論み、手下たちにこんな科白を吐く。「戦後の日本のように、新しく縄張りをつくれる場所が一つだけ残っている」。彼が地図で示したのは沖縄だった。
こうして郡司は数名の配下と共に那覇へ乗り込み、「本土の食い詰め者」と嘲られながらもシマの強奪を進めていく。礼節ある侠客が似合う鶴田の、傍若無人の振る舞いにはいささか辟易するものの、この“本土から押し入るヤクザ集団”というプロットは強力で、このカテゴリーの「型」のように働いていく。その展開を少しだけ見ていこう。
深作映画といえば『仁義なき戦い』(製作:東映、1973)だが、上記の作品はどうにも噴飯ものだった。ところが、中島貞夫監督の『沖縄やくざ戦争』(製作:東映、1976)は、本土ヤクザの侵出という同一テーマを扱いながら、地元ヤクザ同士の対立抗争へ視点を置き、深みを獲得している。軸になるのは、中里(松方弘樹)と国頭(千葉真一)というコザ(現沖縄市)の義兄弟同士の煮詰まった緊張関係。また彼らコザの「組」と那覇の「組」との一触即発の背後に、侵出の機会を窺う本土ヤクザも見え隠れし、スピーディな場面転換と相まってひりつくような切迫感がある。
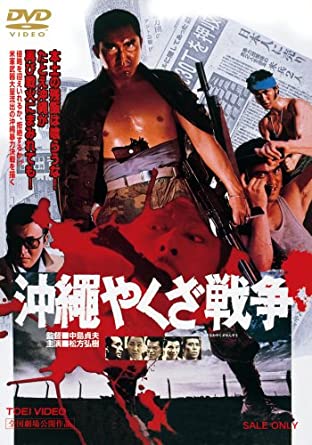 中島貞夫監督『沖縄やくざ戦争』(DVD)
中島貞夫監督『沖縄やくざ戦争』(DVD)沖縄vs本土の暴力抗争劇はこの作品をもってピークへ達した感があるものの、その後も多くの追随作品を残した。秀作とは言いにくいが、『沖縄10年戦争』(監督:松尾昭典、製作:東映、1978)は直系の作品と言っていいだろう。再び松方・千葉が共演したが、前作のような精彩はなく、銃撃戦もどこかおざなりである。
後年、このジャンルと「型」を復活させたのは北野武だ。監督第2作『3×4X10月』(製作:バンダイ/松竹富士、1990)では、同じ草野球チームの若者二人が銃を買うために沖縄へ向かう。ひょんなことから彼らが勤めるガソリンスタンドがヤクザと抗争する羽目になり、武器調達が必要になったという不思議な設定だ。彼らは沖縄でヤクザの二人組(うち一人が北野)と意気投合し、銃を買い付けて戻ってくるのだが、東京での銃撃戦も含めその一部始終がスタンド店員の妄想だったというオチがついている。
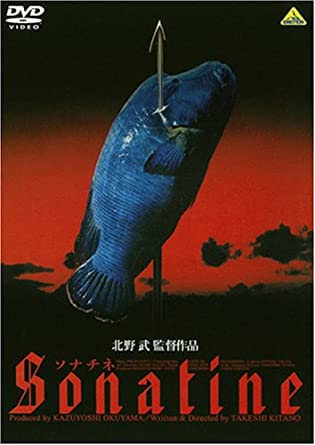 北野武監督『ソナチネ』(DVD)
北野武監督『ソナチネ』(DVD)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください