2022年04月28日
一つの時代からある世代の文化が生まれるのか、それとも一つの世代がある時代の文化をつくるのか──このニワトリとタマゴの問題はなかなか難しいが、私はぎりぎりのところで世代先行の方に加担したい。
なぜなら、「全共闘世代」の前に全共闘文化はないし、「オタク第一世代」の前にオタク文化は存在しなかったはずだからだ。
1960年代の学生が、眼前の小さな疑義を起点に国家権力の企みを告発しなければ、党派を必要としない運動の文化は出現しなかった。また、アニメのマニアが、作者さえ意図していない物語の背景を空想しなければ、権威を求めない趣味の文化は登場しなかった……。
とやや声高なイントロダクションで今回紹介するのは、1989年8月に刊行された『事典版 おきなわキーワードコラムブック』(まぶい組編、沖縄出版)という出版物である。
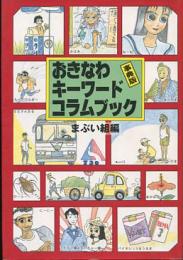 まぶい組編『事典版 おきなわキーワードコラムブック』(沖縄出版)
まぶい組編『事典版 おきなわキーワードコラムブック』(沖縄出版)ただ「いろいろな人」とはいうものの、「一九六〇年代から一九八〇年代に生まれた、もしくは青春を迎えた人々に捧げる」書物であるため、「項目に年代的な偏りがある」こと、書き手に「地域的な偏りが若干ある」ことを認めてほしいということわりが付いていた。
つまり同書は、最初から“沖縄の同世代による沖縄像の発見”という明確な目的を持っており、その確信犯的な戦略によって編まれたと考えて良いだろう。
結果からいえば、『事典版 おきなわキーワードコラムブック』は話題の本になった。『沖縄タイムス』に連載された喜納(きな)えりかのコラム「沖縄県産本のあゆみ」によれば、「若者たちが同時代的な沖縄を活写したこのショートコラム集は、キーワードの立て方や文章のクオリティーも相まって社会現象ともいえる大ヒットを巻き起こした」のである(「充実期の1980年代、おきなわキーワードコラムブックと沖縄大百科事典」2015年11月12日)。
 bluehand/Shutterstock.com
bluehand/Shutterstock.com同書に収録されたキーワードは433本。ランダムにいくつかを拾い上げてみようか。
「あい!」「あがー」「味くーたー」「熱こーこー」「いいはずよ」「いっせんまちやー」「御願不足」「うちあたい」「A&W」「オキコワンワンチャンネル」「沖縄キリスト教短期大学」「沖縄ジャンジャン」「沖縄独立論」「ガーブ川の世界」「開南のバス停」「共同売店」「ぐそー」「コーヒーシャープ」「桜坂通り」「さしみやー」「真剣―ん?」「センエンナーのおじさん」「だからよ」「登野城漁港」「奈名子のドリームコール」「ビーチパーティー」「南大東島行きの飛行機」「民謡研究所」「わじわじー」。
凡例には、「方言」「風物」「食べ物」「レトロ」「人物のようなもの」などのジャンルが設けられているが、これを参照しつつ、私の目であえて分類すれば、①沖縄の日常風景に埋め込まれたモノ・コト・ヒト、②沖縄人の言動の特徴を示す言葉や概念、③若い沖縄人の記憶に残った事象・人物・場所、④その他(立項意図が不明なものを含む)というところだろうか。
それぞれのキーワードを紹介する余裕はないが、③がこの本らしくて面白い。「登野城漁港」のように「自分は何度しのぶとあの護岸をデートしたことか」みたいな個人的経験が盛り込まれていたり、「奈名子のドリームコール」のように特定の人物(この場合はラジオ番組のパーソナリティ)のいかにもの語りが再現されていたりするからだ。
「一九六〇年代から一九八〇年代に生まれた、もしくは青春を迎えた人々」は、こうしたキーワードに胸を衝かれたことだろう。キーワード群には、都市化とリゾート化の波をいちどきに被ったこの時期の心象風景が多く含まれていた。
執筆者は70名以上に上る。その一覧を見ると出生年は1960年代に集中しており、これが“年代に偏りがある”ということわりの理由なのだろう。ちなみに「まぶい組」の「級長」は、1963年に那覇で生まれた新城和博である。
想定されたコア読者が、この執筆者陣と同様の年恰好だったことは明らかだ。本土復帰を記憶し、1980年代の沖縄で青春を送った若者たち。1冊の本を通して復帰世代とは異なる沖縄へのこだわりを共有した彼らを、私は「おきなわキーワード」世代と呼んでみたい。彼らこそ、「内なる沖縄ブーム」をつくり出した主要なジェネレーションだと思うからだ。
彼らが30代を迎えた1990年代は、多くのことが重なり合って起きた10年間だった。
1995年、大田昌秀による革新県政の足もとで、米兵による少女暴行事件が発生した。全島的な抗議運動の中から、日米地位協定の見直しと米軍基地の整理縮小を求める声が湧き起こり、翌年の県民投票では基地反対が多数を占めた。
一方この時期に「沖縄ブーム」は最初のピークを迎えている。復帰20周年に合わせて復元された首里城、NHKの大河ドラマ『琉球の風』が観光客を呼び寄せただけではない。大ブレークした安室奈美恵が、本土の少女たちの憧れの眼差しを集めたのは、復帰運動以来の大衆的高揚のさなかだった。
「まぶい組」の新城は、著書『うちあたいの日々──オキナワシマーコラム集』(1993)で、この頃出会った人々との交友を記している。その大半が「オキナワポップシーン」にかかわる同世代の人々である。
たとえば石垣島出身の新良幸人(あらゆきと)は、八重山高校で1学年下の大島保克(おおしまやすかつ)と並ぶ八重山民謡の唄者(うたさー)だ。ライブを追いかけ、「プロデュースやマネジャーじみたことまでしてしまったから、自分でもふと『なんでかねー』と思ったりする」打ち込みようだった。
 八重山民謡の歌手・新良幸人
八重山民謡の歌手・新良幸人R&Bバンド「The Waltz(ザ・ワルツ)」を率いるローリー(現・ローリー・クック)もその一人。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください