中野慶『小説 岩波書店取材日記』を読む
2022年05月04日
岩波茂雄が1913(大正2)年に古本屋からスタートし、翌年に夏目漱石の『こゝろ』を出版して軌道に乗り、戦前戦後の日本の出版界を牽引してきた岩波書店は、来年創業110年目を迎える。
 中野慶『小説 岩波書店取材日記』(かもがわ出版)
中野慶『小説 岩波書店取材日記』(かもがわ出版)小説は、大学で史学と労働経済学を学んでコンサルタント会社に就職した主人公の女性が、1か月の研修先として岩波書店を指定され、「労使関係に注目して、戦後の軌跡をたどる」という課題を課せられる。
上司から、まずこれを読めと与えられたのが、安倍能成の『岩波茂雄伝』(岩波書店)。さらに「変化球」だと言って手渡されたのが、「先々代社長」の大塚信一『理想の出版を求めて──編集者の回想1963─2003』(トランスビュー)と、団塊世代の編集者だった小野民樹の破天荒な青春記『60年代が僕たちをつくった』(幻戯書房)の2冊。彼女に対応し案内役を買って出たのは、労働組合委員長を務めたこともある同社の現役専務という設定だ。
初日に専務に社内を案内されていた時、階段上に高齢の著者が現れ専務は丁重に挨拶し、ケインズやガルブレイスについて書かれている理論経済学のI先生ですと彼女に紹介する。「労使関係について取材するとは、どういう視点なのですか」とI先生に聞かれ、「吉野源三郎さんが初代委員長を務めた労働組合にも注目しています」と答える。
I先生とは、言わずと知れた伊東光晴。専務が先生は『君たちはどう生きるか』を受け継ぐ本も書かれていると彼女に言い、巻末の注では『君たちの生きる社会』(ちくま文庫)が紹介される。このように、小説とは言いながらも、本文中で話題になるいわゆる岩波文化人の数やエピソードも多く、登場する著作の注が60点にも及ぶ一種の教養小説のようでもある。
専務は彼女の取材目的に合わせて、社内の様々な人物やOBを紹介し、そのインタビューを通して、岩波書店の戦後の歴史と、それに絡んだ独特な労使関係が浮かび上がってくる。
多くの企業では、パートや派遣比率を高めて正社員を削減し、査定の強化で従業員を選別したり、労働組合の力を弱めようとするが、岩波書店では「1980年代でも派遣社員は皆無、アルバイトも少数、ほぼ全てが正社員で差別のない労働条件を獲得した。出産・育児のための条件も整い、両性が定年まで勤務するのは当然」だった。
1957年生まれの著者は、岩波書店で夜間受付を経て編集者になったので、新入社員の時から社員の顔と名前をすべて知っていたという。それが作品に描かれる社内の人間関係に対する観察眼にもつながったのだろうか。また戦後の労働組合運動の歴史にも詳しく、電産型賃金体系への疑問を入社早々から表明し、岩波労組の執行委員も務めていたというから、その視点からの会社や組合に対する著者自身の考えも、登場人物の口を通して披瀝されていく。
 岩波書店創業者の岩波茂雄
岩波書店創業者の岩波茂雄戦後初期から女性差別を否定し、戦後の賃金体系で世間標準の学歴差別を否定し続けてきた。中卒高卒組の中で格別に優秀な人が多かったとも。賃金は長らく物価水準に連動するスライド制が維持され、インフレが激化した70年代には抜群の効果を発揮したという。だから70年代までは業界内で屈指の賃金水準が維持された。その一方で、労働時間や仕事の内容を評価しない平等主義は世間一般と乖離していると著者は見る。
岩波労組の初代委員長が吉野源三郎だったということは、本書の中で度々語られる。吉野の後の2代目委員長になった塙作楽(はなわ・さくら)の『岩波物語──私の戦後史』(審美社)によると、塙は共産党幹部の伊藤律の口利きで戦後間もなく岩波に入社し、吉野とともに1946年1月創刊の「世界」の編集に関わる。
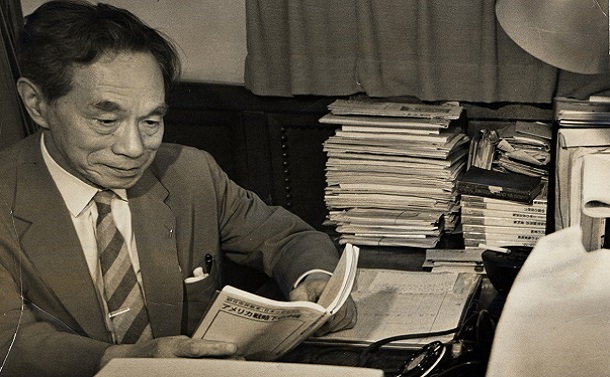 岩波書店の看板雑誌「世界」の創刊時の編集長で、岩波労組の初代委員長でもあった吉野源三郎
岩波書店の看板雑誌「世界」の創刊時の編集長で、岩波労組の初代委員長でもあった吉野源三郎「世界」は岩波茂雄の学生時代からの友人・安倍能成を最高責任者としてスタートするが、安倍が文部大臣に就任したため吉野が編集長となる。新雑誌「世界」の編集長が、結成された組合の委員長にされたのだ。しかし組合結成2か月後に、部課長制度が新設され、部課長は非組合員になったため、委員長は吉野から塙に。伊藤律の勧めで共産党に入党させられた塙をはじめ、社内に入党者が増え、かなりの人数にまで膨れ上がったと、塙は自著で書いている。そのため、岩波書店の「細胞」は、地区委員会を離れ、共産党中央委員会直属の組織に変わったと塙はいう。
それが後に、原水爆反対運動の分裂を受けて組合も揺さぶられることにつながったのだろう。70年代には、組合の執行部派と批判派の攻防戦もあり、吉本隆明の名を冠した「Yシフト」というのがあって、「批判しない。論争しない。ガチンコ対決は吉本崇拝者を勢いづかせる。この組合の土俵に乗ってもらおう」というスタンスだったという。いささか冗談ぽいが、それなりのリアリティーもある。
理想の出版社を求めてきたものの、「少なからぬ人がアパシーにとらわれている。過密労働は軽減されず、短期間で辞めていく編集者も出てきた」とも著者は登場人物に言わせる。「最大の欠陥は全社に浸透した放牧の思想。放し飼いで良い。職場は組合まかせで管理や教育を軽視してきた」とも。
専務は、会社の姿勢を象徴するかのようなエピソードを挙げる。「長らく誕生日には全社員とOB・OG等の自宅に福砂屋のカステラが贈られた。その昔は長野県出身の苦学生のために夜間受付という職場もあって、嘱託の肩書きと高給も保証されていた。(中略)温かな会社だと信頼されている。創業者と後継者の意思。人間を大事にする職場をめざすという労使の合意で実現してきた」と。
そういえば、この本の著者も長野県出身で、夜間受付をしていた。また、講談社も社員の誕生日祝いをやっていたし、小学館も子どもの誕生祝いに五月人形やお雛様を社長夫人が自宅に届けに来ていた時代もあった。日本の出版社は、似たり寄ったりの家族主義的な社員とのつながりを重視してきていたのだろう。
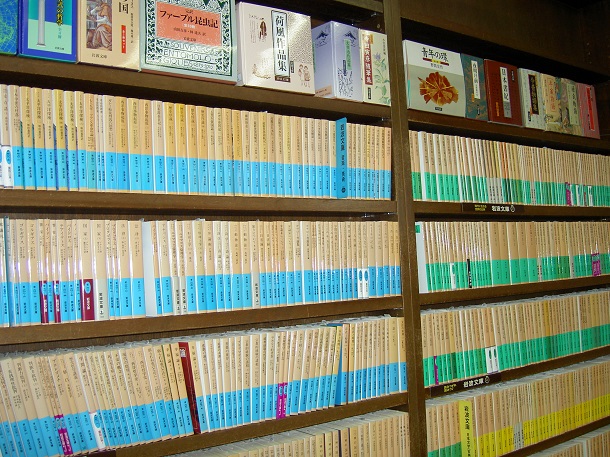 1927年創刊の岩波文庫
1927年創刊の岩波文庫岩波書店は、90年代後半には史上最高の売り上げを達成したという。それは日本の出版界の絶頂期とも重なる。しかし、2000年代初頭まで年間約700点の新刊を出していて、長時間労働が日常化して在職中に亡くなる優秀な編集者もいたという。著者は2015年当時の岩波書店を舞台に、新人コンサルタント女性の目を通して、経営が組合を気にし過ぎて抜本的な改革が遅れがちな現状に苛立ちを表明しているようでもある。
とはいえ、2代目社長の岩波雄二郎の前では「売れ筋」という言葉も禁句で、役員といえどもベストセラー志向を許さなかったという、利益至上主義とは無縁の社風を著者はこよなく愛しているからこそ、退職後の古巣に危機感を抱き、それを小説化したのだろう。
ちなみに、2021年6月に発表された岩波書店の決算公告(第72期、2020・4・1~2021・3・31)によると、純利益は7億3028万円の赤字となっている。2月21日、アカデミックな「岩波文化」に対置された講談社の、昨年度(第83期、2020・12・1~21・11・30)の決算が発表された。売上高は1707億7400万円(前年比17.8%増)、当期純利益は155億5900万円(同43.0%増)と大幅増益だった。
集英社や小学館なども同様に、コミックを中心にした電子出版が好調で、いずれも増収増益が見込まれる。それにしても、岩波書店の年間7億円を超える赤字はただ事ではない。それもあってか、昨年6月1日付で、それまでの岡本厚社長から坂本政謙社長(就任時56歳)に経営がバトンタッチされ若返った。
 2021年に就任した坂本政謙社長
2021年に就任した坂本政謙社長岩波書店はコミックこそ持たないものの、膨大な書籍の蓄積がある。戦前からの「岩波文庫」「岩波新書」をはじめ、アカデミズムの英知を集めた様々な「岩波講座」シリーズや、「広辞苑」という日本を代表する辞典がある。一時期の学生たちを魅了したオピニオン雑誌「世界」もある。その岩波書店が大幅な赤字だとは? 「全社に浸透した放牧の思想」「職場は組合まかせで管理や教育を軽視してきた」ことや、会社側と組合側の代表が出席する月1回の経営協議会で、人事や経理や経営方針などあらゆる問題が報告されるという組合重視の経営が災いしているのか?
そればかりが原因だとは思えない。返品不可の買い切り制に安住し、営業も編集も書店や読者との直接的な接点を持ちにくかったのではないか。また、一時期までマンガを俗悪と否定してきたような岩波文化の高級志向が、同社の出版物全体に影響を与えていはしないか。とともに、岩波講座や「世界」などが売れなくなってきているのは、大学生が本を読まなくなってきているのと同様に、日本社会全体の脱知性化と無縁ではないようにも思える。
70年代以降の管理教育の強化や、学力偏重の教育の在り様、政府の露骨な学術会議人事への介入に象徴されるように、アカデミズムへの拒否感が醸成されつつあることなども遠因であろう。
坂本政謙社長は、同社で初めての直木賞を受賞した佐藤正午の『月の満ち欠け』の主人公と同じ青森県八戸市の出身で、作品のロケハンにも付き合うなど、佐藤がこの作品を完成するのに深くコミットした担当編集者でもあるという。これまでなかったタイプの新社長により、創業110年を迎える岩波書店がどう変容していくのか、その手腕に大いに期待したい。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください