2022年05月23日
外国人の友人たちと話した後にいつも自分に言い聞かせていることがあります。先ほどの彼、彼女の意見を普遍化してはいけないということです。フランス人の友人であろうと中国人の友人であろうと、彼らの意見は彼らのもので、フランス人や中国人を代表するものではないということを肝に銘じておくべきだと思っています。
中島恵『いま中国人は中国をこう見る』(日経プレミアシリーズ)もたくさんの中国人に取材して書かれた本ですが、この傾向性は見事に克服されていると思います。著者はあとがきでこう述べています。
いつものことだが、本書には富裕層や有名企業の経営者、農民工など、日本メディアの「常連」はほとんど出てこない。私がこれまで信頼する誰かに紹介されたり、たまたま巡り合った人など、「ごく普通の中国人」が中心だ。
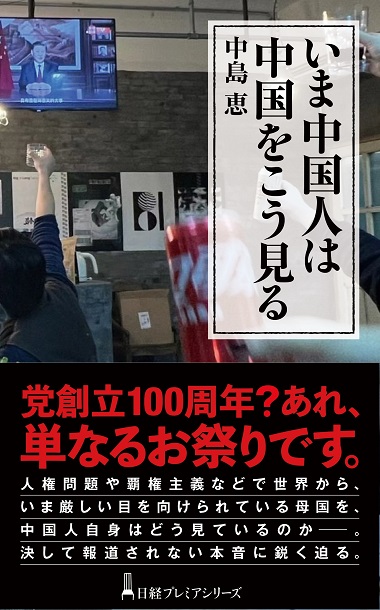 中島恵『いま中国人は中国をこう見る』(日経プレミアシリーズ)
中島恵『いま中国人は中国をこう見る』(日経プレミアシリーズ)ちょうど1年前に、本欄で『内側から見た「AI大国」中国──アメリカとの技術覇権争いの最前線』(福田直之著、朝日新書)を取り上げました。それはデジタル大国・アメリカを脅かすほどに成長した中国のIT企業に関する優れたレポートでしたが、本書と併せて読んでみるとより深く中国の現在の姿が浮かび上がることと思います。
『内側から見た「AI大国」中国』は、米中激突の深層に鋭く迫る好著
本書は2021年の7月1日に天安門広場前で行われた中国共産党創立100周年を記念する祝賀式典についてのコメントから始まります。文化大革命時代の毛沢東を彷彿とさせるような(といっても今の若い世代には通じないでしょうが)、習近平国家主席の演説する映像を鮮明に憶えている方も多いと思います。この時の参加者のひとりの感想が紹介されます。
正直いって退屈でした。早起きしたので眠たかった。内心では、早く終わらないかなあ、なんて不謹慎なことを考えていたのです。
まあ、こういう人間もいるだろうな、とは思うものの、あの映像からはちょっと想像もできないのは間違いないことでしょう。
さて、第1章は中国のゼロコロナ政策の中身についての証言で構成されています。その徹底したやり方を読んでいると彼我のあまりの違いに驚きを禁じ得ません。そしてゼロコロナを可能にしている社会の同調圧力の高さも著者が指摘する通り並大抵のものではないことが分かります。
 「コロナ対策でしばらく営業停止」との紙が貼り出されたスーパー=2022年3月30日、上海市
「コロナ対策でしばらく営業停止」との紙が貼り出されたスーパー=2022年3月30日、上海市中国の「近所の目」は日本よりはるかに厳しい。
強いリーダーシップの証として、政府の進めるゼロコロナ政策ですが、支えている要因のひとつが庶民の同調圧力であることを知ると複雑な気持ちになります。しかしそれだけではないことも別の証言から分かります。アメリカでなぜ80万人以上が犠牲になったのか理解に苦しむというある男性の意見もあります。
どんなに正義を振りかざしても、どんなに自由が大事でも、命あっての物種でしょう? 私はこれまでアメリカに憧れていた気持ちがあったのですが、コロナによって吹き飛んだ。アメリカへの憧れや幻想はガラガラと音を立てて崩れ落ちました。
ここには重要な問題提起があるように思います。アメリカという国の思想的な背景を日本を含めたアジア諸国が理解する困難さが露呈しているように思えてならないのです。
第2章では激変する中国社会のことが語られます。在日中国人女性が著者に語った言葉が心に残りました。
日本人が考える中国人の幸福は、ネットに習近平氏の悪口を堂々と書けることかもしれませんが、私たちはそうは思いません。
毎年収入が上がって生活が安定し、去年よりも今年、今年よりも来年はもっといい生活が送れること、これが中国人にとっていちばんの幸せなんです。
豊かになると同時に中国人のマナーが飛躍的に向上していると著者は指摘します。30年ぶりに日本から中国に戻った女性と著者の会話も興味深いものがあります。日本よりも格段に便利なネットスーパーに感動し、生活費の安さに驚くのです。北京郊外の観光地で公衆トイレがとてもきれいでトイレットペーパーが完備されていたという記述には私も驚きました。個人的にも中国での公衆トイレ問題はなかなか大変な思い出があったからです。もう10年以上前のことですから自分の古い印象を更新すべきなのでしょう。
 Vikky Mirs/Shutterstock.com
Vikky Mirs/Shutterstock.comさて、第3章では、日本でもメディアに頻繁に登場するようになった「共同富裕」というスローガンについて触れています。何か時代が逆に動いているように感じる人も多いかと思います。20世紀の共産主義の理想が21世紀の今、もう一度叫ばれることに驚きを隠せないと語っていた友人を思い出しました。
この「共同富裕」の一環として「双減政策」が実施されました。「宿題を減らす」「学外教育(学習塾)の負担を減らす」という掛け声のもと2021年夏、大手の学習塾チェーンが突如閉鎖されました。格差の激しい教育の分野がやり玉に挙げられたのです。
私が特に興味深く読んだのは、第5章の「Z世代」の中国の若者たちです。最近よく耳にする「Z世代」とは1995年頃から2010年頃までに生まれた若者を指すのですが、中国の人口のなんと20%がその世代に属するのだそうです。
中国では現在活躍中のアイドルたちの間だけでなく、Z世代を中心とした一般の若者の間で「昭和」ブームが巻き起こっており、ほかにも音楽(LPレコード)、ファッション(アイドル風の衣装)、写真(コスプレ撮影)、食べ物(居酒屋)などさまざまな分野に広がっている。
著者が取材した、こうした事情に詳しい30代の中国人男性は、中国の若者がアニメやドラマを通じて、日本の昭和の雰囲気や風情を感じ取っているのだと分析します。政治権力とは別のところで、サブカルを通じて親近感をもつというのは非常に今日的ですし、この傾向は今後ますます広がっていくのではないでしょうか。
そしてこういう流れが、実は社会を変革する大きな要因になることを東西対立の象徴であったベルリンの壁崩壊から私たちの世代は学んでいます。旧ソ連・東欧圏の若者たちはロックなどさまざまなサブカルから西側に対する認識を新たにしたことはよく知られています。中国のZ世代の若者の日本語学習が、アニメやドラマ、音楽やゲームなどサブカルの影響から始まることも多いことに触れられています。
そして米中対立がメディアでは連日のように報道されていますが、世界で最もアメリカ留学を望んでいるのは中国人だということも事実として知っておくべきことだと本書に教えられました。
もうひとつ、「タンピン主義」についての興味深い記述があります。タンピンとは中国語で「寝そべる」というほどの意味だそうですが、ロシアの作家イワン・ゴンチャロフのオブローモフ主義と同じで「何もしない」で横になったまま過ごすことだそうです。若者たちの、結婚しない、子どももいらない、最低限しか働かない、もちろん家もクルマもいらないという低欲望型のライフスタイルを指すそうです。
中国といえばアグレッシブに働く巨大IT企業の従業員を連想する向きも多いと思いますが、すでに成熟した資本主義国家である日本と同じような感性を持った若者たちが出現しているのは大変面白い現象だと思います。中国のSNSには「タンピン主義」に共感する声が大量に書き込まれているそうです。
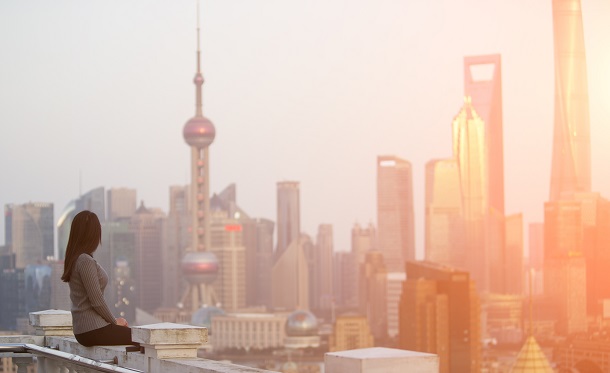 Yaorusheng/Shutterstock.com
Yaorusheng/Shutterstock.comまた、日本製品に対する印象の変化にも驚きました。2015年の中国人の爆買いブームを記憶している方も多いでしょう。そんな時代もとうに過ぎ去っているようです。
かつての中国人にとって、日本製品は「憧れの的」「日本製品を持っていたら自慢できる」といった存在だったし、日本人デザイナーのブランドというだけで価値があった。だが、Z世代の若者は日本製品に対して、そうしたイメージは悲しいくらい持っていない。
彼らが生まれた1990年代後半以降、その成長過程は日本製品の存在感が失われていった時期とぴったり重なる。
時代は凄まじいスピードで変化していることをまざまざと思い知らされる記述です。逆に周囲の若い世代に聞き、中国製のコスメを日本の若者が使っていることを知りました。そしてそれは第6章のメディアについても同じです。著者が取材したある中国人のコメントは完全なる言論統制という中国のイメージを変化させます。
中国政府は『人民日報』などの主流メディアを中心にして、世論の動向を誘導することを狙っていますが、今は「すき間」があちこちにあって、完全に情報統制することは難しくなっていると思います。すき間ができた理由は、中国の国際化、そして国境を飛び越えるネットの存在です。
今迄の本書の内容からは容易に想像がつくことではありますが、案外、完全な情報統制が可能であるというイメージが残っているのではないでしょうか。ネットは新しい情報源としてさらに激しく中国社会を変えていくことでしょう。
本書のエピローグによるとコロナ禍が始まる直前の2019年には日本を訪れた中国人は過去最多の959万人にのぼったそうです。もちろんその後、中国人の観光客は激減しましたが、2021年10月には日本映画『おくりびと』が大ヒットしたこと、2020年に杭州と上海に日本の蔦屋書店がオープン、同じ年に上海に「ロフト(LOFT)」もオープンしたことなど、これからの日中関係を考えるうえで象徴的な出来事に思えます。
本書を読了して、コロナ禍が終息したら、すぐにでも中国に行ってみたいという気持ちになりました。新しい時代を肌で感じるために。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください