2021年の大作で女性監督はゼロ、意思決定の場のバランス是正を
2022年09月06日
世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数で、日本は今年も146カ国中116位という低さだった。先進国はもちろん、東アジア太平洋地域19か国においても日本は堂々の最下位。タイやインドネシア、韓国、中国、そして軍事政権の弾圧が続いているミャンマーも、日本より順位が上である。
特に政治分野は139位、経済分野は121位で、非常に格差が大きいという結果。女性国会議員、女性閣僚、女性管理職の少なさや、男女の所得格差などが顕著である。つまり、日本で社会をとり仕切るのも、大きな金を動かすのも、依然としてほぼ男性。世界の潮流から取り残されていると言える。
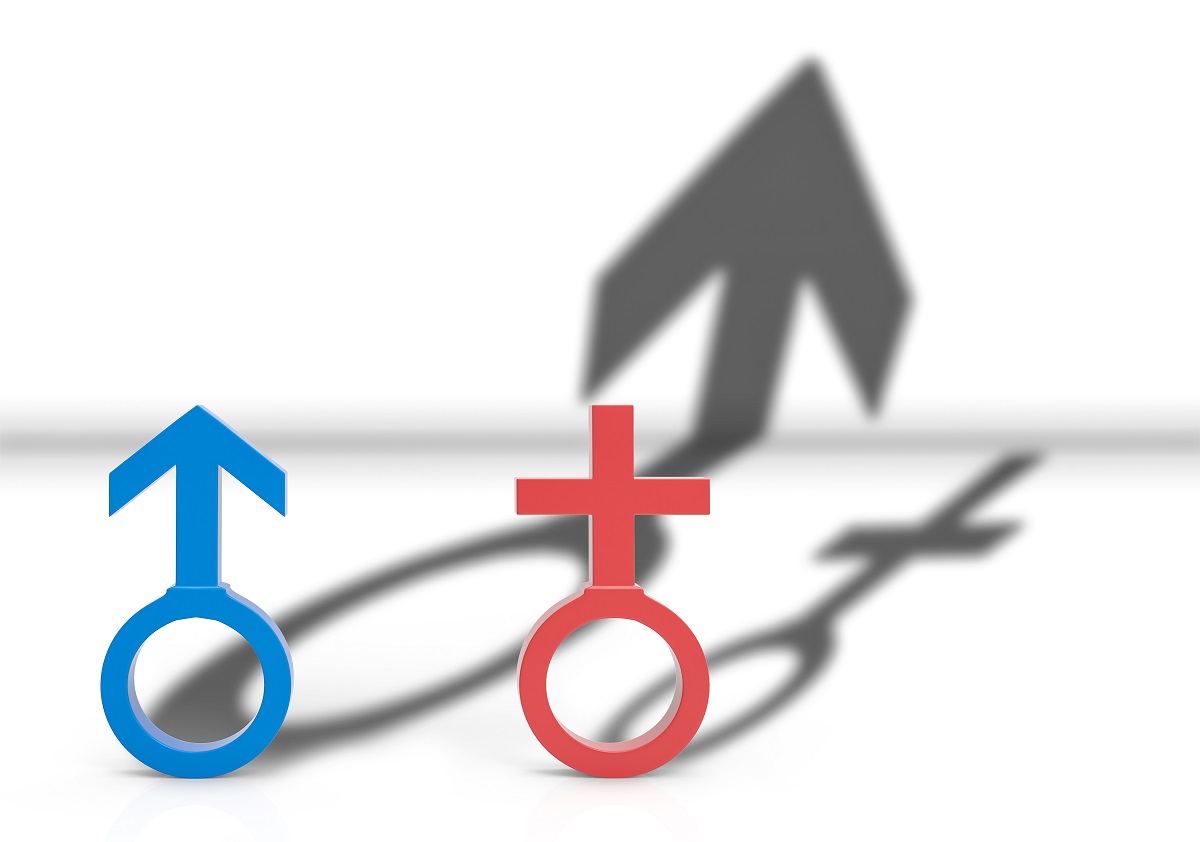 PATARA/shutterstock.com
PATARA/shutterstock.com非営利の一般社団法人Japanese Film Projectの調査によれば、2021年に劇場公開された映画471本の中で、女性監督の作品は57本、約12%だった。さらに松竹、東宝、東映、KADOKAWAの大手4社が製作・配給した実写映画に限って見てみると、40本中0本、女性監督0%という結果。また、この4社における役員・執行役員の女性の数は、合計102人中わずか6人のみである。
映画制作の現場では、「最近は女性スタッフが増えた」という声をよく聞く。だが具体的に中身を見ると、監督やプロデューサーや脚本家など、作品の意思決定に関わるポジションはやはり圧倒的に男性が多い。また、撮影、照明、録音、演出など各部署のスタッフも、技師やチーフと呼ばれる上位ポジションは男性で、下に付く助手は女性、という構図が多く見られる(一方で、衣装やメイクなど、昔から女性がメインで担ってきた部署は、賃金が低く設定されていたり、現場での立場が弱いという指摘がある)。
これは決して「男性の方が能力が高い」ことを表しているのではない。映画の現場がこうなっている大きな原因は、過酷な労働環境だ。昨今の映画は、とにかく「予算がない」が合言葉のように言われている。少ない予算で作るためには、限られた人数と日数で、一人一人がガッツリ頑張るしかない。早朝6時前に集合し、22時に帰れるのは早い方、深夜に解散し、わずかな睡眠をとり、また翌朝働く、といった現場は珍しくないし、私自身も幾度も経験した。休憩時間や休日を潰して準備に充てる、といった光景もよく見られる。
 gnepphoto/shutterstock.com
gnepphoto/shutterstock.com現在、映画スタッフの大多数はフリーランスであり、労働基準法が適用されず、最低賃金や時間外労働のルールがない。大抵、仕事のオファーは「期間は○ヶ月で、ギャラは○円」という超ざっくりした口約束でされることが多い(そもそも私のようなキャリアの浅い監督の場合、納品するまでギャラを提示されないことも多い)。
契約書がなく、業務の細かい取り決めもないので、当然、長時間労働が常態化する。実質的に機能する労働組合もなく、労働者の権利を主張できるような状況ではない。仕事を与える側/もらう側という非対等な関係性においては、細かいことを言うと今後仕事を失うかもしれない……という心理も少なからず働く。閉鎖的で上下関係のある社会で、ハラスメントも起きやすい。予算がないことの皺寄せが、立場の弱いスタッフに際限なくのしかかってくる。
若いうちは「映画が好き」「映画に関わりたい」という情熱でどうにか頑張っていても、出産や子育てなどの事情が出てくると、連日連夜続く現場で働くことは難しくなる。特に女性は、家事、育児、介護など、無償ケア労働を担わざるを得なくなることが多い。せっかくアシスタントで経験を積んでも、上のポジションに上る前に業界を去ってしまう優秀な女性が沢山いる。
個人的な話をすると、私は2014年に妊娠した。その時お世話になっていた女性プロデューサーにその旨を告げると、「え、妊娠しちゃったの?」「せっかく監督してこれからって時だったのに…」と残念がられたことを鮮明に覚えている。祝福してくれるだろう、と決めてかかっていたので、とても驚いた。そして「天野さん、もう映画は撮れないと思うよ」と、はっきりと言われた。その時は、意味が全く分からなかった。育児の大変さや映画業界の構造を理解していなかったのだ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください