お寺のトラブル、地獄の説き方から旧統一教会問題まで
2022年10月18日
読者の皆さんは、『月刊住職』(興山舎)という雑誌を知っているだろうか?
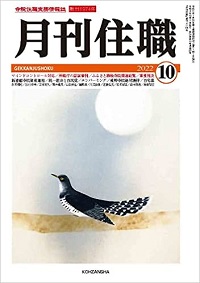 『月刊住職』(興山舎)2022年10月号
『月刊住職』(興山舎)2022年10月号雑誌名もなかなかインパクトがあるが、掲載されている記事のタイトルはさらに強いインパクトがある。一般の人にとってはカルチャーショックを感じるようなものばかりで、このタイトルを見て、SNSなどで「攻めてる」と話題になっているのだ。
バックナンバーから、いくつか目を惹くタイトルをピックアップする。
「ポケモンGOの襲来に各寺院はどう対処すべきか、問題はあるか」(2016年9月号)
「この夏の読経に使える住職のためのマスク選び」(2020年8月号)
「ゆうちょも大銀行も硬貨の預け入れ有料化にお寺も大憤慨!」(2022年3月号)
「お寺でも始まっている参詣ポイント制って何なのか」(2022年8月号)
「現代人に『地獄』を説法するのに必要なのは何か」(2022年9月号)
記事内容はある程度想像できるものもあるが、「そんなことがあるのか?」「お坊さんはそんなこと考えているのか?」という内容ばかりであろう。
中でも本年9月号の「現代人に『地獄』を説法するのに必要なのは何か」という見出しは、特に強烈なインパクトがある。どうにも不穏な気配すら感じるのも事実だ。
日本仏教では伝統的に、説法で地獄について語ることが多かったが、現代では地獄を語る僧侶は少なくなっている。その中で、あえて地獄を説くことについて考える記事である。
地獄という思想の歴史、地獄に関する様々な逸話、地獄に関する絵本や紙芝居、地獄を語ることへの僧侶自身の様々な意見、地獄を説くことのメリットとデメリット、そして説くためのノウハウなど、多面的に地獄について書かれている。
記事を通して一貫しているのが、僧侶自身が、どうやって地獄の思想と向きあうかということである。説法で地獄の話題に触れるべきかどうか、触れるとすれば、どのように語ればいいのかを考えるための材料となっている。
おどろおどろしい内容が書いてあるようにも見えるが、内容はいたってまじめである。しかも記事には、地獄の話題が脅しにならないようにする配慮の必要性も説いている。
決していかがわしい内容の記事ではない。人がよりよく生きていくために、地獄という考え方を、どう活かすかを大まじめに考える記事なのだ。
他の記事タイトルも、一般人から見ると、カルチャーショックを感じるものばかりだ。
「ポケモンGOの襲来に各寺院はどう対処すべきか、問題はあるか」は、ゲームアプリの「ポケモンGO」が流行った時、勝手にポケストップ(ポケモンのアイテムを入手できる場所のこと)がお寺の境内に設定されることがあり、それにどう対処したらいいかという内容である。ある日、突然、お寺の境内に人がたくさん集まりだし、みな黙ってスマートフォンを操作している、という光景を目にし、何がおきているのか全くわからない、というお寺も少なくなかったようだ。
 西本願寺の阿弥陀堂門に掲げられたポケモンGOの使用禁止を伝える看板=2016年7月、京都市下京区
西本願寺の阿弥陀堂門に掲げられたポケモンGOの使用禁止を伝える看板=2016年7月、京都市下京区「この夏の読経に使える住職のためのマスク選び」は、僧侶が読経をする時に、息苦しくならないようなマスク選びの記事である。お経は、参列者のほうに向かって唱えることは少ないものの、大きな声を出すため、参列者に配慮してマスクをつけたまま唱える僧侶がほとんどである。ただ、長時間お経を唱えていると、息苦しくなったりする。特に夏の読経は、暑さも加わり、熱中症の危険性すらある。夏でも快適に読経できるマスク選びは、僧侶にとっては重要な問題なのだ。
「ゆうちょも大銀行も硬貨の預け入れ有料化にお寺も大憤慨!」は、ここ数年、金融機関が、硬貨の預け入れに手数料を徴収するようになってきたことに対する、お寺の対応に関する記事だ。ゆうちょ銀行は手数料を徴収していなかったのであるが、今年1月から徴収することになった。お寺によっては、賽銭など大量の硬貨が集まるケースがあり、今後、手数料が大きな負担となってくる可能性があるのである。
「お寺でも始まっている参詣ポイント制って何なのか」は、小売店などで商品を買うと貯まるポイント制度を取り入れるお寺が増えており、その取り組みに関しての記事である。全国的なお寺離れが進む中、お寺に来てもらう動機づけとして注目されているようである。中には、浄土宗のように、宗派が先頭にたって取り組むケースもある。浄土宗の寺院をお参りするたびに、「参礼寺(まいれいじ)ポイント」が貯まっていき、特典と交換できるという仕組みである。
どれも一般社会ではそんなに珍しい話ではないが、それがお寺での話ということになると、俄然、刺激的な話題に見えてくるのである。
『月刊住職』は、A5版で180〜200ページの月刊誌である。表紙の一番上には「寺院住職実務情報誌 創刊1974年」と書かれている。寺院住職の実務情報誌というのは、この月刊誌の特徴をよくあらわしている。住職というのは宗教者であるが、法的には宗教法人の代表役員であり、株式会社でいうところの代表取締役でもある。つまり宗教者と実務者の両面を持っている。つまり、単なる宗教者ではなく、法人運営を担う住職として仕事をしていくために必要な情報を提供しているということになる。
こういう月刊誌なので、編集者は僧侶が
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください