2022年10月20日
あるロシア文学者から聞いたのですが、今年の2月にロシア軍がウクライナ侵攻を始めた時に、今年度のロシア文学の履修者が少なくなると悲観したそうです。あにはからんや、予想に反して例年よりたくさんの学生が講義に出席したといいます。これを聞いて今の若者たちがロシアは怖い国だという従来のイメージではなく、逆にどういう国か知りたいという気持ちが強いことに安堵しました。
しかし一般的な日本人が、ロシアという国は理解不能、謎の大国だという印象をもっていることも否定できません。私はロシアの大衆の素顔が報道からはあまり見えてこないことが問題ではないかと感じていました。
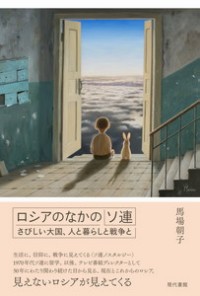 馬場朝子『ロシアのなかのソ連──さびしい大国、人と暮らしと戦争と』(現代書館)
馬場朝子『ロシアのなかのソ連──さびしい大国、人と暮らしと戦争と』(現代書館)著者の馬場朝子さんはNHKのディレクターとしてソ連、ロシアに関する40本以上の番組制作に携わった経歴の持ち主です。しかも馬場さんは1970年から6年間、ソ連・モスクワ国立大学文学部に留学していたのです。NHK退職後の2012年から5年間再びモスクワに住んだといいますから、激しく変化する政治や社会と庶民の変わらぬ暮らしぶりも熟知しています。
現在のロシアでは50歳以上の人は「ソ連人」として教育を受けているという著者の指摘から、ソ連のシステムへの一部回帰を志向するプーチン大統領が支持される要素があることが分かります。第一章では、まず著者が留学したソ連時代の話が披露されます。「利益」という言葉さえ必要のない世界では、モスクワ大学でも教授と清掃員も給料はたいして変わらず、医師や教師の給料がもっとも低いレベルだったという記述には驚きを禁じ得ませんでした。
そういう平等の感覚に70年も慣れた人たちが、市場経済に翻弄されたこともよく理解できます。しかも現在のロシアでは収入の地域格差は60倍にもなるそうです。ちなみに日本は2倍です。人々がモスクワを目指すというのはよく分かります。しかし著者はロシアの友人たちに資本主義における自由競争の説明をしながら、格差そのものに違和感を覚えるロシア人の感覚の方が正常なのかもしれないと考えます。これは私には大変重要な視点ではないかと思えました。
 danielo/Shutterstock.com
danielo/Shutterstock.com第二章ではロシアの大国思想についての興味深い記述が続きます。ロシアの大国思想の裏にある歴史的な背景の解説は説得力があります。13世紀にモンゴルのチンギス・ハンに征服され、その後もポーランド、スウェーデン、フランスのナポレオン、ナチス・ドイツと、周辺の国々から攻め込まれながらも、その都度、戦って勝利してきた偉大な祖国という概念があるということです。
そのためソ連時代の一番大切な記念日だった11月7日の革命記念日に代わり、現在では5月9日の大祖国戦争戦勝記念日が大きな祝賀行事になったと言います。大祖国戦争とは第二次世界大戦のことですが、前述したように50歳以上の人々は生粋のソ連人として、アメリカと対等であった栄光の時代の記憶に支えられています。ウクライナ侵攻を支持しているのもこの層が多いということです。
 戦勝記念日に、第二次世界大戦を経験した親族の写真を掲げて歩く市民=2022年5月9日、モスクワ
戦勝記念日に、第二次世界大戦を経験した親族の写真を掲げて歩く市民=2022年5月9日、モスクワ
ロシア人が価値を置く「力への信望」は、国だけでなく個人にも向けられる。とくに男性はマッチョが良しとされる。プーチン大統領も、ことあるごとに自慢のボディーを披露する。
プーチン大統領が柔道をしたりしてマッチョぶりを見せつける報道をテレビで見た記憶がありますが、それもこういう背景があってのことだったと分かります。
第三章は「民主主義」の話から始まります。著者はロシアでは人々の間で民主主義が否定的なニュアンスで使われることがあり、聞き間違いかと思ったと書いています。しかしその理由を知ると納得できるのです。「民主主義」という言葉は、ソ連崩壊後に、「なんでも自由なことが民主主義」という極めて不完全な形で理解されたため社会に大混乱を招いたからなのです。
ソ連崩壊後のエリツィン時代(1991~99)、つまりプーチン大統領の登場する前に起きた社会の急激な変化が原因となっていることを著者は指摘します。企業の民営化のおかげで弱肉強食の激しい富の争奪戦が始まり、日本でも知られるようになった新興財閥である「オリガルヒ」が生まれ、町にはカジノが林立し、成金たちが高級車に乗って自らの富を誇示していたというのです。テレビで民主主義者たちが、自分たちが目指すのは完全に自由な社会だと言い、格差拡大すらも肯定されました。これではソ連時代にノスタルジーを感じる人が多くなるのも分かります。
著者は忘れられない光景があると書いています。モスクワから郊外にある空港までの道を少し走ると、深い森の木立の両側に10メートルおきに女性が立っていたのです。
外はマイナス二十度の寒さ。車が通るたびに、コートの前を開けてミニスカートの足を見せる。食べられなくなって街娼になった女性たちの列だった。こんな悲しい光景を生む新生ロシアの民主化とはなんだろうと切なかった。
いかに大きな混乱にロシアの女性たちが巻き込まれていたかを物語るエピソードです。そしてこういう社会の混乱を生んだ「民主化」に対して否定的なニュアンスで語る人たちがいるのがよく理解できます。
長年、過酷な環境下でロシアを支えてきた女性たちだが、近年ロシアの若い女性から「金持ちと結婚して専業主婦になるのが夢」という言葉を聞くようになった。
女性も働くのが当然であったソ連時代が嘘のような話です。しかも国連の2011年の統計によれば、離婚率が6割と世界一だということにも驚きました。ちなみに旅行サイト「ホテルズ・ドットコム」によると世界30カ国の年平均休暇日(年次休暇、祝日を含む)はロシアがトップで40日。離婚率と休暇が世界一と聞くと複雑な感慨を抱いてしまいますが、このようなエピソードの中にロシアを理解する鍵があるようにも思います。
ウクライナ侵攻の後、マクドナルドは閉店、ユニクロもなくなり、外国の銀行のカードも使えなくなるという制裁措置がロシアに加えられ、突然襲ってきたこの生活上の危機をロシア人はどう受け止めているのか。半年経った時点での著者の知人たちへのインタビューは非常に新鮮です。
年金暮らしの老婦人は、町は平静を保っているし、カフェもレストランも賑わっていて日常生活には支障がないという。旅行会社の経営者もヨーロッパや日本からの観光客が来なくなって大変だけれど、中国と中央アジアからの客でどうにか会社を回していると言います。ユニクロのフリースをまとめ買いした女性は都会に住んでいる人々にとっては輸入品が手に入らないことで不便を感じてはいるが、地方に住んでいるあまり豊かでない人たちは輸入品に頼る生活をしていないので、変化はないと言います。
 撤退した米スターバックスの店舗を引き継いでオープンしたロシア資本の「スターズ・コーヒー」。本格的な開店初日は客が殺到した=2022年8月19日、モスクワ
撤退した米スターバックスの店舗を引き継いでオープンしたロシア資本の「スターズ・コーヒー」。本格的な開店初日は客が殺到した=2022年8月19日、モスクワ
小さな危機には自分で対処し、大きな危機にはそんなものだと粛々と受け入れる。そんな風にロシアの人たちは危機対応能力を、ソ連時代から引き継いで磨いてきた。というか磨かされてきた。
この文章の通りの対応なのです。また、政治的な反対運動もあることは日本のメディアでも報じられていますが、1991年のソ連崩壊後の報道の自由ぶりはすさまじかったと著者は回想しています。日本でも実現したことのないような完全な自由を獲得していたのです。しかし2000年のプーチン大統領の誕生後は報道も自由を制限されるようになりました。ロシアでの取材のなかで著者が自分は日本のジャーナリストだと自己紹介すると「あなたは何度、命の危険を感じたことがありますか」と聞かれます。著者がそういうことはないと言うと、ああたいしたことはないなという顔をされたというエピソードからも、ロシアのジャーナリストたちの過酷な状況は容易に推察できます。
第四章の「ソ連・ロシアの戦争」では前述した大祖国戦争から始まります。ソ連の第二次世界大戦での死者は2700万人。世界で一番多い犠牲者をだしています。本書では、ソ連時代にウクライナの小さな村に行って村民の集まりを覗いた時のことを紹介していますが、大祖国戦争で男性の多くが亡くなり参加者が女性ばかりだったといいます。
現在は戦闘状態にあるロシアとウクライナですが、実は切っても切れない関係なのだということです。そもそも両国の発祥はキエフ公国であることからも分かりますが、ロシア革命後の1922年にソ連に編入され、その崩壊とともにウクライナは独立したのです。長い歴史のなかで民族は混じり合い両国に友人や親せきを持つ人が多いのです。ロシア料理でボルシチを食べたことのある人も多いでしょう。実はウクライナが発祥の地なのだそうです。
著者がウクライナやロシアの友人や知人たちの生の言葉を紹介していますが、その中の一人の言葉が胸に残りました。ウクライナに住むこの女性はロシア人の友人たちから大丈夫かとメールが届き、この友人と爆撃してくるロシア兵の両方がロシア人であることを嘆きます。あるいはモスクワで貿易会社を経営するロシア人は、これはロシアの戦争ではない。プーチンの戦争だ。受け入れられないと言います。
 モスクワ中心部の広場で開かれたウクライナ侵攻への抗議集会で、「戦争反対」「ウクライナは敵じゃない」などと声を上げる男性。この直後、治安部隊に拘束された=2022年2月24日、モスクワ
モスクワ中心部の広場で開かれたウクライナ侵攻への抗議集会で、「戦争反対」「ウクライナは敵じゃない」などと声を上げる男性。この直後、治安部隊に拘束された=2022年2月24日、モスクワ本書のように多くの市井の人々に取材して、ジャーナリスティックな視点からロシアのことを描いた本は貴重です。ソ連とロシアの両方の世界で生活した著者ならではのエピソードが満載の内容は、毎日のニュースで消費されていく情報としてではなく、より本質的なことを知るために役に立つ一冊だと思います。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください