混迷し続けるアメリカを知るための道案内となる近刊の新書と古典的作品
2022年11月18日
11月8日投票のアメリカの中間選挙は、超大国の社会的分断を改めて危惧する結果となった。上院はかろうじて与党・民主党が過半数を維持したが、下院では共和党が議席を伸ばして、多数派を奪還。予想されていたレッド・ウェーブ(共和党の大勝)は起きず、バイデン大統領は「民主主義にとって良い日」と安堵(あんど)したが、保守対リベラルの対立は激化する一途だ。
いまやアメリカ人は、政治信条ごとに異なる「パラレル・ワールド」に住んでいる。多様にしてひとつであるはずのアメリカの国民統合自体が危ういのだ。「理念の共和国」はどこへ行くのか。道案内となる2冊の本を紹介する。
連載「三浦俊章の現代史の補助線 書評×時評」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。
 中間選挙の結果を受け、支持者から歓声を受ける笑顔のバイデン米大統領(左)と妻のジルさん=2022年11月10日、ワシントン
中間選挙の結果を受け、支持者から歓声を受ける笑顔のバイデン米大統領(左)と妻のジルさん=2022年11月10日、ワシントン一冊目は、この8月に出たばかりの岩波新書、『アメリカとは何か 自画像と世界観をめぐる相克』である。
著者の渡辺靖氏は、もともとはハーバード大学で博士号を得た社会人類学者。軽快なフィールドワークで、ポピュリズム、ナショナリズムの台頭を追い、アメリカ社会の分断状況を分析してきた。現場ルポと新しい文献の紹介をミックスした渡辺氏の著書は情報量が多く、今回の本も現状を俯瞰(ふかん)する上で、まずお勧めしたい本である。
特に第1章「自画像をめぐる攻防」は、米国流の「リベラル」と「保守」がどう形成されてきたかという歴史的な見取り図を示したうえで、オバマとトランプを位置づけ、さらに右派と左派のポピュリズムの潮流にも切り込む。この章を読むだけでも頭が整理され、なぜ今のような深い分断がアメリカ社会に生じているのか、理解する一助になるだろう。
アメリカの将来について著者は、楽観主義と悲観主義の双方を戒め、バランスを取ろうとしているが、行間からしみだしてくるのは、暗い見通しだ。
たとえば、評者が特にショックを受けたのは、次のような個所である。
「対立や分断がここまで深化した民主主義国家が協調メカニズムを回復した事例はなかなか思い浮かばない。世論の裂け目からナチスが台頭したドイツが民主主義国家に生まれ変わった例はあるが、それは戦争(敗戦)という大きな代償を伴うものだった」(38ページ)
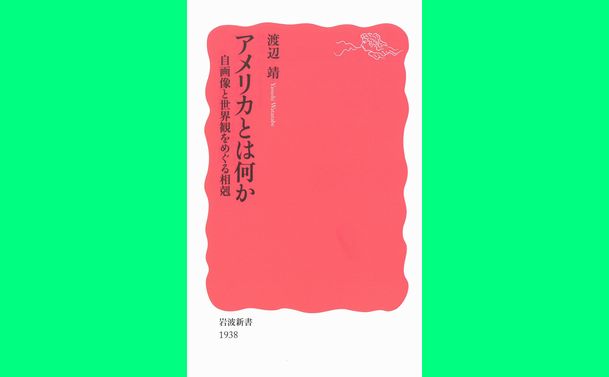 『アメリカとは何か 自画像と世界観をめぐる相克』(渡辺靖、岩波新書、860円+税)
『アメリカとは何か 自画像と世界観をめぐる相克』(渡辺靖、岩波新書、860円+税)折よく、今回の中間選挙から3日後の11月11日、日本記者クラブで開かれた研究会で、著書の渡辺氏の話を聞く機会があった。(日本記者クラブのHPで視聴可能)
渡辺氏は、かつて共和党のレーガン大統領の好敵手だった民主党のティップ・オニール下院議長の「あらゆる政治はローカルだ」という言葉を紹介した。それは、すべての政治はローカルな問題をめぐる対立であり、そのうえに国政(ナショナル・ポリティックス)があるという考えだが、今ではそれが真逆になったという。
共和対民主、保守対リベラルの対立は、首都ワシントンだけではなく、地方政治に及んでいる。地域の候補者の対立も、ローカルな争点ではなく、バイデンとトランプの対立を通して語られる。人々は、自分たちの息子や娘が、ライバル政党の支持者の子弟と結婚することを好まなくなった。日常生活までイデオロギー対立が浸透しているという。
今後、白人の人口比率が下がり、社会の人種的多様性が増すことで、アメリカのリベラル化が進むという見方もあるが、渡辺氏は、人口構成だけでは政党支持は説明がつかず、むしろ「レッド」(共和党支持)と「ブルー」(民主党支持)の対立がこのまま併存し、アメリカは曼陀羅(まんだら)のような状態になるのではないかという見通しを述べた。
 集まった支持者を前に、2024年大統領選への立候補を表明したトランプ前大統領(右)と妻のメラニア氏=2022年11月15日、フロリダ州パームビーチ
集まった支持者を前に、2024年大統領選への立候補を表明したトランプ前大統領(右)と妻のメラニア氏=2022年11月15日、フロリダ州パームビーチアメリカとは何か、という問いは実は古い。多様性を抱えながら国民統合を果たしてきたアメリカ自身が、観察者に対して、たえずその問いを発してきたともいえる。アメリカを研究することは、この問いに答えようと試みることである。
2冊目に紹介するのは、渡辺靖氏の著書とまったく同じタイトルのアメリカ研究の古典的作品。現在は平凡社ライブラリーで刊行されている『アメリカとは何か』(斎藤眞)である。
同書は、戦後日本のアメリカ研究をけん引してきた故斎藤眞氏(1921~2008年、東大教授、国際基督教大教授などを歴任)が一般読者向けに書いた論文やエッセーをまとめたものだ。1981年に岩波書店から出された『アメリカ史の文脈』の新版であるが、アメリカをめぐる様々なトピックを歴史の文脈でとらえようとした斎藤氏の手法を考えると、むしろ改題前のタイトルの方が的確かもしれない。
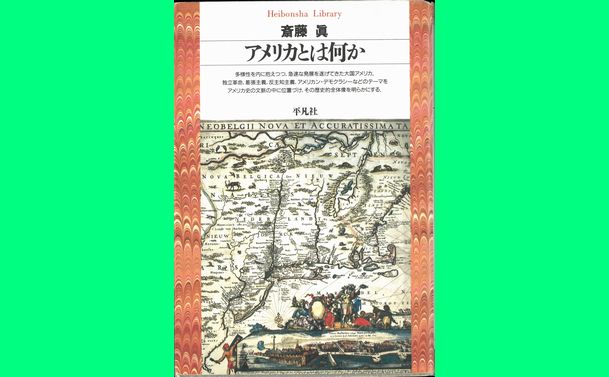 『アメリカとは何か』(斎藤眞、平凡社ライブラリー、1165円+税)
『アメリカとは何か』(斎藤眞、平凡社ライブラリー、1165円+税)平凡社版の「解説」で、斎藤氏の指導を受けた古矢旬・北大名誉教授が「短く大きなことを話すのは嫌いではない」という斎藤氏の信条を紹介しているが、この本はまさにその見本のような作品である。
冒頭に置かれた「アメリカ社会理解の前提―時間・空間・人間・転機」という論文はわずか7ページだが、そこで展開される独自の視座、魅力的なレトリックは、単なる学者の文章を超えて、ひとつの芸術作品を見るようだ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください