2022年11月30日
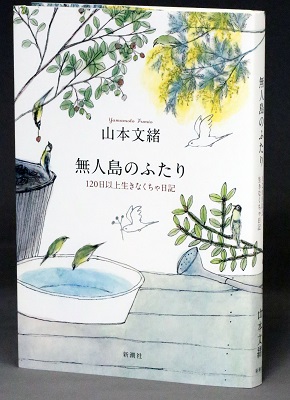 山本文緒『無人島のふたり──120日以上生きなくちゃ日記』(新潮社)
山本文緒『無人島のふたり──120日以上生きなくちゃ日記』(新潮社)この本に何が書かれているかは、おおむね分かっている。すぐにでもページを開いてそれを確かめるべきところだが、先ほどから手を出しあぐねている。
本のタイトルは『無人島のふたり』。「120日以上生きなくちゃ日記」という副題がついている。ちょうど去年の今頃にがんで早世した作家・山本文緒の闘病記である。なぜ読むのを躊躇(ためら)っているのか。それを語るには、編集者としてその作家と密に付き合った時期、30年ほど前に時間を遡る必要がある。
 jakkapan/Shutterstock.com
jakkapan/Shutterstock.com横浜の駅ビルにある喫茶店にひとり残され、編集者はただ呆然としていた。一体何があったのだろう。先ほどまで対面に座って穏やかに話をしていた作家はいきなり無言のまま席を立ち、去って行った。飲みかけのコーヒーカップだけが、虚しく目の前にあった。
作家と編集者はここ1年以上かけて、書き下ろしの長編小説の刊行を準備していた。それはおそらく双方にとって重要な作品になるはずのものだった。その小説のタイトルは『眠れるラプンツェル』。集英社のコバルト文庫の書き手として活躍してきた作家が大人向けの小説に挑んだ5作目だった。
編集者はある出版社でずっと純文学の雑誌の編集をしていたが、会社の経営方針が上場に向けて大きく舵を切り、とにかく売れる本を作れという切迫した環境のなか、たった一人でエンターテインメント小説の分野への鉱脈を見つけることを厳命されていた。
とはいえ何の人脈もなく、交際接待費ゼロの職場環境で、大手出版社の編集者たちの間に分け入って既存の売れっ子作家を捕まえるのは到底叶わぬことだった。そこで着目したのが、当時純文学にも少女小説にも児童文学にも、そしてエンターテインメントにも収まりきらない一群の女性作家に書き下ろしの長編小説を依頼することだった。もし成功すれば、字義どおり「中間小説」の新しい路線ができるはずだった。
山本文緒というその作家を知ったのは、雑誌で文芸時評をお願いしていた北上次郎氏が『パイナップルの彼方』と『ブルーもしくはブルー』という二つの作品を激賞していたからだった。それらを一読してたちまち魅了された。軽快でいて女性の内面をリアルに、また細やかに描く作家の筆致は新鮮で、何より小説の巧手だった。
書き下ろしの依頼は即受け入れられ、作品を介した濃密な日々が始まった。同じくコバルト文庫の書き手から編集者の属する文芸誌の新人賞を受賞して再デビューした角田光代の担当が彼だったことが、二人の関係をより近くした。「あの時は、そんなこともありか! って、みんな色めきたったんですよ」、そう言って楽しそうに笑いながらビールのジョッキを傾けた、それもまた横浜の駅ビル屋上にあったビアホールだった。
仕上がった原稿を読んだ時には、興奮した。その前に集英社から出した『あなたには帰る家がある』もよかったが、それを凌ぐ出来と確信した。ところがいざ刊行の段になって、上層部からさまざまな干渉があった。
まず、タイトルを変えろという。それは断じて肯じ得なかった。作品のタイトルは著者のものであり、百歩譲っても著者と編集者のものであるとの主張が、また上層部の癇に障ったらしかった。仕事が個人に着くことは、会社の最も嫌うところだったのだ。
タイトルの件は作家に告げずに、頭を丸めて上司に懇願するという古典的な手段に出て何とか免れたが、次には8000部初刷り予定だったのを7000部に落とせといってきた。さすがにそれには逆らえなかった。また編集者には、どうせすぐにも重版できるだろう、という自信があった。
作家がいきなり席を立ったのは、そのことを告げた瞬間だった。正直、そこまで作家が腹を立てるとは思っていなかった編集者は、あまりのショックに小一時間動くことができなかった。作家とはその後、二度と会うことはなかった。
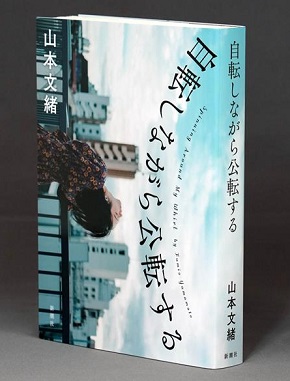 山本文緒『自転しながら公転する』(新潮社)
山本文緒『自転しながら公転する』(新潮社)そんな矢先、作家の訃報に触れて耳を疑った。58歳。あまりに早すぎる死に、編集者は再び呆然とした。横浜の駅ビル喫茶店でひとり取り残された時の気持ちが蘇った。これで本当に、二度と会うことが叶わなくなったのだ。
 2001年1月、直木賞を受賞した山本文緒(中央)。同時受賞の重松清(左)、芥川賞を受賞した堀江敏幸と
2001年1月、直木賞を受賞した山本文緒(中央)。同時受賞の重松清(左)、芥川賞を受賞した堀江敏幸と意を決して手を伸ばし、襟を正して繙いた『無人島のふたり』は、想像以上の、いや、想像を絶する内容だった。
胃の不調を感じて病院を訪れた著者は、検査の結果、膵臓がんだと告げられる。それもステージ4bで、もはや助かる余地がない、と。途中から頁をめくる手がしばしば止まった。十数年前に、身近な者を看取った自身の経験と重なったからだった。
彼女は子宮頸がんだったが、診断を受けたときにはすでにステージ5だった。そこから4ヶ月後に亡くなったのだが、最後にはやはり緩和ケアを受けた。思わぬスピードで進行するがん細胞、ジェットコースターに乗っているような、日常と非日常がめまぐるしく交錯する日々……この本に記されている病状についての諸々は、手に取るように分かった。
だから、驚愕したのはそこではなかった。自分の状態、および周囲の人びとのひとつひとつを克明に、客観的に著そうとする著者の強靭な意思に圧倒されたのだ。この日記は亡くなる9日前まで書き続けられている。それがどれだけ驚異的なことかは身近にがん患者を看取った者ならだれでも実感するだろう。
今日から手書きで書いているこの日記をパソコンでテキストに打つ作業を始めた。/打ってみると手書きの日記は、下書きの下書きの下書きくらいひどいので、このまま活字で発表されたらと思うと冷や汗が出る。
この日記が本になるということが決まる前に書かれた文章である。「言葉を記す」ことについての作家の並々ならぬこだわりをここに見る思いだ。それに、書くだけではない。病床にあって、同時代の作家の作品を実によく読んでいる。ふと漏らす感想に、凡百の書評を凌ぐ“つかみ”があるのだ。
もうすぐ死ぬとわかっていても、読みかけの本の続きが気になって読んだ。/金原ひとみさんの『アンソーシャル ディスタンス』、死ぬことを忘れるほど面白い。
最近体調が思わしくないせいか新しい本を読む気がせず、テレビで映画化のことを知った村上春樹の『女のいない男たち』を再読。ほとんど内容を覚えていなかった。(中略)春樹さんの本から気持ちが離れて久しいけれど読んでみればやはり巧さに唸る。
夜、夫が気晴らしに何か本を読んでくれるというのでちょうどアマゾンから届いていた角田光代さんの『おやすみ、こわい夢を見ないように』を音読してもらう。確か姉と弟が造語でおやすみを言い合う好きなシーンがあって、そこがもう一度読みたかったのだ。/造語は「ラロリー」で、意味はタイトル通り。夫とも「じゃあねラロリー」「また明日ねラロリー」と言い合って眠った。
そして、以下の文章に触れる時、「本を読む」という行為の本質を知らされて胸を突かれるのだ。
未来のための読書がなくなったらもう何も読みたいものはないのかもと思ったけれど、私の枕元には未読本が積んであるコーナーがあって毎晩その中からその日の気分に合わせて本を選んでいる。未来はなくとも本も漫画も面白い。とても不思議だ。
この本にはきらりと光るディテールがぎっしりと詰まっているが、最も読む者の心に迫るのは、タイトルの由来にもなっている「夫」との関係だろう。お互いを尊重しあってあえて別居結婚を続けてきたふたりが、強い精神のきずなで結ばれていたことが如実に知れる。
驚くのは夫も妻も実によく「泣く」ことである。そしてそのことを臆さずに記す作家の抑制の効いた筆が、ふたりの心情を十全に伝える。不謹慎かもしれないが「こんなに幸福な別れがあったのか」とも思う。読みながら、看取った〈身近な人〉とは決していい関係ではなかった自分を激しく悔やむ瞬間がしばしば訪れた。
本のちょうど中ほど、在宅医療の先生の訪問を受けた時の場面で、ちょっとクスッとした。
普通のお医者さんとは違うのでたっぷり1時間世間話まじりにいろんなことを話した(最終的には夫の新車自慢まで聞いてもらった)。/その中で私が自分のことを「意外にわたし頑固なところがあってなかなか柔軟にできないことが多いんですよね」と言ったら「意外じゃないですよ! 頑固だから今こうしてここにいるんじゃないですか! いいことです!」と笑われた。/確かに……と私と夫は納得。
クスッとしたのち、「そうか、そうだったんだ」と妙に腑に落ちるところがあった。
喫茶店にひとり取り残されたあの時、考えてみれば、勤めていた会社を辞め、離婚をした直後でもあって、山本さんは独り筆一本で生きていく覚悟を固めた時期だったのだろう。その矢先に削られた初刷部数は、部数の問題以上に気持ちを殺がれたに違いない。その強靭な意思と激しさ。それがここでいうところの「頑固さ」だったのだ。
本書の中ではさまざまな担当編集者がお見舞いに訪れる記述が頻出する。そのくだりに触れるたびに、そういう関係にはなり得なかったわが身の不運をかこつと同時に、また純粋に読者として本書に出会った幸運を深く噛み締めた。
本書は今後、図らずも同じ病にかかった人びと、いや、いまや日本人の二人に一人ががんになると言われている時代においては、万人の必読書になるだろう。また私にとっては……遺された山本文緒の全作品を読み返すための道しるべとしてずっと在り続けるに違いない。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください