『千代田区一番一号のラビリンス』『無人島のふたり』『戦争日記』……
2022年12月22日
*本や出版界の話題をとりあげるコーナー「神保町の匠」の筆者陣による、2022年「私のベスト1」を紹介します。
井上威朗(編集者)
森達也『千代田区一番一号のラビリンス』(現代書館)
上皇ご夫妻を「キャラクター」として描き切った、後世の出版史年表に載せるべき歴史的な企画です。ですが、(仕方ないことではありますが)作者がお二人に直接に会うことができず、ラブレターのような形で物語を仕上げてしまったがために、本作をエンタメとして「ベスト1」だと称揚することはできません。
それでも、読みはじめたら止まらない娯楽性の高い仕掛けが満載な上に、作者の長きにわたる取材と問題意識の醸成が読みやすい形で織り込まれているので、2022年で最高の挑戦をやり遂げた野心作だと思っています。「面白さ」と「モチーフ」との関係をどう考えればいいのか、漫画編集者である当方としても示唆に富む読書体験ができました。
 『千代田区一番一号のラビリンス』(現代書館)の著者・森達也
『千代田区一番一号のラビリンス』(現代書館)の著者・森達也大槻慎二(編集者、田畑書店社主)
山本文緒『無人島のふたり──120日以上生きなくちゃ日記』(新潮社)
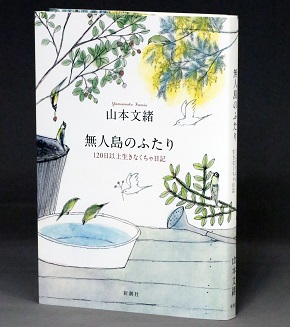 山本文緒『無人島のふたり──120日以上生きなくちゃ日記』(新潮社)
山本文緒『無人島のふたり──120日以上生きなくちゃ日記』(新潮社)この本の読者はおそらく老若男女を問わず、自分が著者と同じ立場に立ったらどうするかを実感として突きつけられるだろう。つまり、平易で何のけれん味もない文章が、それだけ「内面のリアリズム」を顕わす術を獲得しているわけで、単に闘病記というだけでなく、この作家が到達した境地を、身を賭して示している。その意味で、まさに作家の「スワンソング」にふさわしい作品だと思う。
また、明日死ぬかも分からない状態に陥っても、人は本を読みたくなる存在なのだと著者は教えてくれてもいて、それは依然きびしい環境にあって「本づくり」に携わる人間にとっては大きな救いであった。出来得ればそういう風に読まれる本を1冊でもいいから作ってみたいと、切に思わせた。
山本文緒『無人島のふたり』を読んで──その強靱な意思と激しさ
駒井稔(編集者)
オリガ・グレベンニク『戦争日記──鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々』(奈倉有里ロシア語監修・解説、渡辺麻土香、チョン・ソウン訳、河出書房新社)
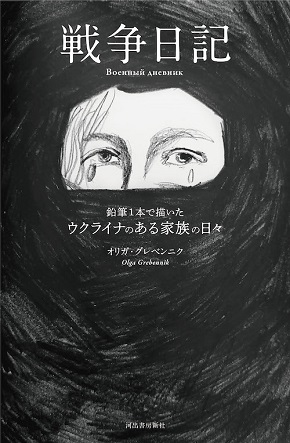 オリガ・グレベンニク『戦争日記──鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々』(奈倉有里ロシア語監修・解説、渡辺麻土香、チョン・ソウン訳、河出書房新社)
オリガ・グレベンニク『戦争日記──鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々』(奈倉有里ロシア語監修・解説、渡辺麻土香、チョン・ソウン訳、河出書房新社)ウクライナの絵本作家、イラストレーター、アーティストとして活動してきた著者は、この本を鉛筆1本で書き上げたのです。突然の攻撃から逃れ、夫を残したまま子供だけを連れて、国を離れるまでの悲劇的な時間を文章と絵で再現しています。そのリアルさは「戦争は絶対悪である」ということを、強く感じさせる内容になっています。走り書きのような文章とそれを具体的に描いた絵を併せて読み進めていくと、この出来事が遠い国の話ではなくなり、その臨場感に圧倒されます。まさに『戦争日記』なのです。
今野哲男(編集者・ライター)
豆塚エリ『しにたい気持ちが消えるまで』 (三栄)
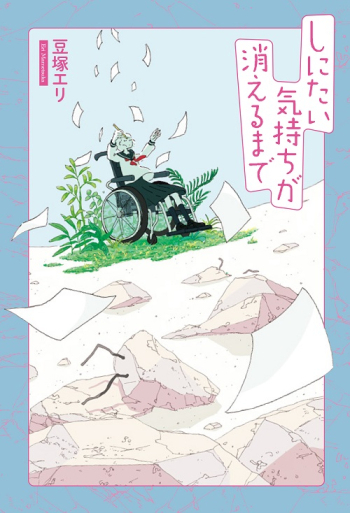 豆塚エリ『しにたい気持ちが消えるまで』 (三栄)
豆塚エリ『しにたい気持ちが消えるまで』 (三栄)著者が「投身自殺」にまで追い込まれて選んだ決意は、「生きるために死ぬ」という背理の裏に「身体が生きたがる」という想定外の事実を持っていた。たとえ無意識にせよ、それが著者の潜在的な認識だったことは、本書の各所に見つけだすことができる。当時16歳だった彼女に、たとえ商業的な出版であれ、ここまで書かせることができた不思議、これを「私」は「詩的な跳躍」と呼んだ。この本にあるそういったジャンプを肯定する著者本来の力である。その証拠に……などと、やぼなことはもう言うまい。前述の原稿で触れた荒井由実(松任谷由実)の「ひこうき雲」と本書本文との比較で、「私」にとっては、もう十分な証拠だったのだから。
佐藤美奈子(編集者、批評家)
小川哲『地図と拳』(集英社)
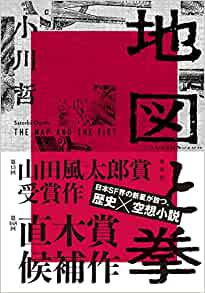 小川哲『地図と拳』(集英社)
小川哲『地図と拳』(集英社)圧倒的だったのが、小川哲『地図と拳』である。日露戦争開戦前から太平洋戦争に至る日本の近現代史が、「満洲」にある架空の理想郷「李家鎮=仙桃城」をめぐって錯綜する、複数視点によるストーリーを通して浮かび上がる。大河小説を読む醍醐味とともに、言葉と観念が歴史をつくっていくスリル、怖さを味わった。
もう一作、触れずにいられないのが島田雅彦『パンとサーカス』(講談社)だ。日本の戦後史と近未来を舞台に、もはやこちらが現実では? と感じさせる物語。新聞連載中から目が離せなかった。
中嶋廣(元トランスビュー代表)
ベスト1と言いながら、双方譲らず2冊挙げることになった。
鷲見洋一『編集者ディドロ──仲間と歩く『百科全書』の森』(平凡社)
まず文体。「です・ます体」を用い、「注」は付けず、参考資料・文献一覧も省略する。その結果、900ページの本が飛ぶように読める。ディドロを中心とする18世紀のフランスが生き生きと蘇り、ポリフォオニックで複眼的、独創的な世界が出現する。鷲見洋一は歴史を叙述する新しい文体・方法を見出したのだ。そういう能書きは別にして、とにかく一度本を開けばたちまち惹きつけられ、閉じることができないほど面白い。
紅谷愃一『音が語る、日本映画の黄金時代──映画録音技師の撮影現場60年』(河出書房新社)
黒澤明や今村昌平、石原裕次郎や高倉健に信頼され続けた録音技師の60年の回想。私はこの書物を読んで、映画の見方がガラリと変わった。映画音楽は一部に過ぎない。サウンドデザインとしての音は、意識されにくいのだ。これまでの映画批評は、実に半分しか見えていなかったのだ。もう一度最初から、全部の映画を観なおしたい。そう思わせる本だ。この本が、私が生きている間に出て本当によかった。
 『音が語る、日本映画の黄金時代──映画録音技師の撮影現場60年』(河出書房新社)の著者・紅谷愃一(べにたに・けんいち)
『音が語る、日本映画の黄金時代──映画録音技師の撮影現場60年』(河出書房新社)の著者・紅谷愃一(べにたに・けんいち)野上暁(評論家、児童文学者)
游珮芸・周見信『台湾の少年』(倉本知明訳、岩波書店)
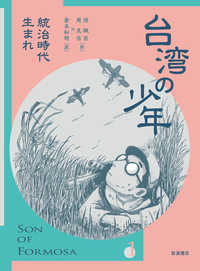 游珮芸・周見信『台湾の少年1 統治時代生まれ』(倉本知明訳、岩波書店)
游珮芸・周見信『台湾の少年1 統治時代生まれ』(倉本知明訳、岩波書店)実在の人物を主人公に、第1巻の『統治時代生まれ』は柔らかなタッチの鉛筆画、第2巻の『収容所島の十年』は墨ベタを基調にした木版画調、第3巻の『戒厳令下の編集者』では、2色をうまく生かすなど、激変する時代に沿って作画の手法を描き分けるテクニックも素晴らしい。第4巻の『民主化の時代へ』も楽しみだ。
堀由紀子(編集者・KADOKAWA)
鈴木エイト『自民党の統一教会汚染──追跡3000日』(小学館)
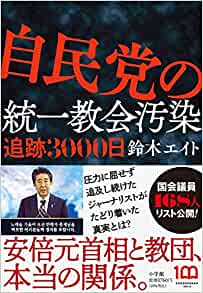 鈴木エイト『自民党の統一教会汚染──追跡3000日』(小学館)
鈴木エイト『自民党の統一教会汚染──追跡3000日』(小学館)内容もさることながら、ハードボイルドモノが好きな私には、著者の取材ぶりが胸アツだった。多くのメディアが「面倒なもの」と宗教問題から距離をとってきたなかで、一人問題意識を持ち続け、ときに危険な目にあいながらも追いかけ続けた。本人は暑苦しさとは無縁の淡々とした書きぶりなのだが、そこがまたたまらなく魅力的なのだ。
松澤隆(編集者)
國分功一郎『スピノザ──読む人の肖像』(岩波書店)
哲学の「意味」ではなく「妙味」に溢れた快著。多くの方が挙げるだろうから他書を、とも当初考えた。しかしこの一冊を忘れるのは、やはり無理。次のような一節にも出会ったし。<なぜ人々は悪魔を仮定するのであろうか、そんな必然性は全くないのに、とスピノザは述べている……確かに必然性はない、だが、それはしばしば要請される>(「要請」に圏点あり)。必ずしも著者の本意に合致しないかも知れないが、今年ほど「要請される」魔力に慄(おのの)いた年はない……。
もちろん本書の真の価値は、世相への連想だけではない。難解なテキストを、平易あるいは安易に読み解くのではなく、思索の経緯も自問も誠実かつ簡勁に示してくれるのが、魅力だ(つねに感興と沈思をもたらす著者の講演と同様に!)。『エチカ』についての評価、<言葉を用いて、言葉が到達し得る限界にまで、我々を連れてきてくれたのである>とは、読了した我々が、著者への感謝に代えたい一節。
 國分功一郎『スピノザ──読む人の肖像』(岩波書店)の著者・國分功一郎
國分功一郎『スピノザ──読む人の肖像』(岩波書店)の著者・國分功一郎高橋伸児(「論座」編集部)
蓮實重彦『ジョン・フォード論』(文藝春秋)
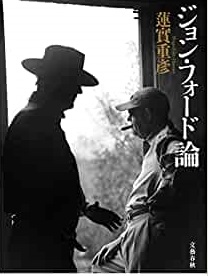 蓮實重彦『ジョン・フォード論』(文藝春秋)
蓮實重彦『ジョン・フォード論』(文藝春秋)最近は映画をスマホで早回しして「ストーリー」だけを追う行為が当たり前のようになっているというが、映画はまず画面を凝視することからしか始まらないという原点回帰を迫る本でもある。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください