『何が記者を殺すのか』『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』
2022年12月28日
8月31日、斉加尚代監督『教育と愛国』へ「JCJ大賞」が贈られた。「JCJ賞」は、今年で65回を迎えた賞で、日本ジャーナリスト会議(JCJ)が1958年以来、年間の優れたジャーナリズム活動・作品を選定して、顕彰してきた。
映画『教育と愛国』は、大阪の毎日放送が、月1本、最終日曜日の深夜0時50分から関西で放送している「MBSドキュメンタリー『映像』シリーズ」で、斉加が撮った『映像'17 教育と愛国〜教科書でいま何が起きているのか』(2017年7月30日放送)の映画版である。2022年5月から3ヶ月あまりで、3万5000人が劇場に足を運んだという。
 毎日放送のディレクター、斉加尚代=2022年5月、映画『教育と愛国』を上映中の「第七藝術劇場」(大阪市淀川区)
毎日放送のディレクター、斉加尚代=2022年5月、映画『教育と愛国』を上映中の「第七藝術劇場」(大阪市淀川区)その斉加が劇場公開を1ヶ月後に控えた今年の4月、ペンをも駆使して上梓したのが『何が記者を殺すのか──大阪発ドキュメンタリーの現場から』(集英社新書)である。第一章「メディア三部作」で、斉加は『教育と愛国』を含めた、「MBSドキュメンタリー『映像』シリーズ」の3本の番組を振り返っている。
三部作の最初の作品は、『映像'15 なぜペンをとるのか~沖縄の新聞記者たち』(2015年9月27日放送)。企画のきっかけは、作家百田尚樹の発言「沖縄のふたつの新聞社は潰さなあかん」、そしてそれに先立つ大西英男衆議院議員(東京16区)の「マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だ。経団連に働きかけてほしい」などの発言であった。百田に名指しされた2社のうち、琉球新報本社の記者たちの日常を密着取材した。
2作目は、『映像'17 沖縄 さまよう木霊~基地反対運動の素顔』(2017年1月29日放送)。
「どこつかんどんじゃ、このボケ、土人が……」
沖縄本島北部の米軍施設〈ヘリパッド〉建設工事に抗議する住民側に向かって大阪弁で毒づいた機動隊員のこの差別発言が、きっかけであった。大阪府知事も沖縄及び北方対策の特命大臣も、機動隊員の肩を持つ。思えば、沖縄の2新聞社を潰せと言った百田尚樹も、大阪出身であった。沖縄の問題は、大阪の問題でもある。斉加は再び沖縄に向かった。
三部作の第3弾『教育と愛国』の舞台は、大阪と東京。「教育勅語」の再評価や「日の丸」「君が代」への敬意の強制、そして教科書の内容や採択など、教育現場へのあからさまな介入の当事者への取材を、果敢に行っている。
 斉加尚代『何が記者を殺すのか──大阪発ドキュメンタリーの現場から』(集英社新書)
斉加尚代『何が記者を殺すのか──大阪発ドキュメンタリーの現場から』(集英社新書)“『バッシング』では、ベージュのセーターを着て自身を何度も登場させました。意図的に顔を晒したのには理由があります。……差別と偏見を煽りバッシングの波を作り出すブログ主宰者と電話でやりとりする場面にもベージュで出演しています”(P.141)
斉加がベージュのセーターにこだわったのは、視聴者に、自分が誰かを強調するためだ。映像に顔を晒し、実名を書き込み、衣服までも同一にすることによって、誰がこのドキュメンタリーを撮っているのかを、明確にしたのである。
“その後、私自身が映っている画面や実名がネット内に挙げられ、批判や中傷の対象になります”(P.141)
「デマやヘイトを発信する人たちに接すれば、自分も槍玉にあげられるだろう」と予想し、それまでの取材で目の当たりにしたネットバッシングの実態を捉えるために、自らをいわば「餌」にしたのである。
「今回は伝えるために満身創痍になってもいい」
予想通り、取材を積み重ねるに従って、バッシングが殺到した。斉加を「ブラック記者」として拡散するアカウントが次々に増える。かねての計画どおり、斉加は、SNS上の自らへの攻撃の分析を専門家に依頼、その結果浮かび上がってきたのは、「ボット(ツイッターで同じような内容を作成・投稿する自動投稿プログラム)」の関与であった。
2018年12月16日、遂に電波に乗った『映像‘18 バッシング〜その発信源の背後に何が』には、次のテロップが流された。
“当番組は放送前、ネット上で一部の人々から標的にされた。
先月末から6日間、取材者を名指しするツイートの数は5000件を超えた。
その発信源を調べるとランダムな文字列のアカウント、つまり「使い捨て」の疑いが、一般的な状況に比べ、3倍以上も存在した。
およそ2分に1回、ひたすらリツイート投稿するアカウントも複数存在した。
取材者を攻撃する発言数が最も多かったのは「ボット」(自動拡散ソフト)の使用が強く疑われる。
つまり、限られた人物による大量の拡散と思われる”(P.224~225)
斉加尚代の勇気と胆力、行動力には脱帽する。斉加の覚悟、勇気、胆力を生み持続させる力、即ち「自分を惹き付けてやまないテーマ」を、彼女は迷いなく明言する。
「テレビジャーナリズムの可能性を諦めない!」
地球環境危機への鋭敏な感性とともに晩年のマルクスのノートを読み込んで発表した『大洪水の前に──マルクスと惑星の物質代謝』(角川ソフィア文庫)で世界的な注目を浴び、新書大賞2021を受賞した『人新生の「資本論」』(集英社新書)で多くの読者の賛同を得た斎藤幸平も、「学者は現場を知らない」「実践なき机上の空論だ」との批判を向けられてきたという。
だが、その研究の根には「資本主義が生み出す貧困や環境破壊に対する怒り」がある。その「怒り」こそ、斎藤幸平の「自分を惹き付けてやまないテーマ」である。理論はその行動を生み出し支えるためのものなのだ。
“理論と実践とは対立しないと考えるからこそ、私の方がもっと実践から学ばなければいけない” (『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』P.4)
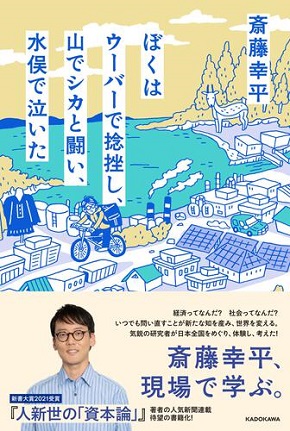 斎藤幸平『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)
斎藤幸平『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)自らウーバー・イーツの配達員を経験、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください