「鬼とは何か」を現代に問う小さな物語
2023年01月20日
トンコハウス制作、堤大介監督の新作シリーズ『ONI~神々山のおなり』(全4話)が2022年10月21日からNetflixによって世界各国31言語で配信中だ。2023年1月17日には「アニメーションのアカデミー賞」と称される「第50回アニー賞」の「テレビメディア」6部門にノミネートされるという快挙が報じられた(各賞発表は現地時間2月25日)。
物語は、様々な妖怪や神々が暮らす神々山に、100年に一度恐ろしい怪物「ONI」が襲撃するという「鬼月」が迫るところから始まる。天狗先生の指導のもと、学校で元気に修行に励む主人公の少女おなりとクラスメイトたち。マイペースで不思議なおなりの父「なりどん」には誰も知らない秘密があった……。
 『ONI~神々山のおなり』 ©2022 Tonko House Inc.
『ONI~神々山のおなり』 ©2022 Tonko House Inc. 2016年に行われた「トンコハウス展」(※)には、「未来」と題されたコーナーに幾つもの企画案が展示されていた。2017年の巡回展からは、堤監督による鬼の親子と思われる絵が追加されていた。それから5年。現代日本を舞台とした長編ファンタジーは世界で好評を博している。
(※)以下を参照のこと
「トンコハウス展 『ダム・キーパー』の旅──未来志向の創意あふれる短編アニメーション展示」(「論座」2016年4月22日)
本年1月21日からは大規模な企画展「ONI展」が開催される。昨年12月28日からは、展示とイベントの充実を図るべくクラウドファンディングも実施中だ。
堤大介監督に作品制作の経緯から技術的達成、物語に込めたメッセージに至るまで広範に伺った。
(記事後半で物語の結末に触れている箇所があります。作品を未見の方はご注意下さい)
トンコハウス・堤大介の 「ONI展」
2023年1月21日(土)〜 4月2日(日)
PLAY!MUSEUM
〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟クラウドファンディング
『ONI』を通して、アニメーション制作の概念を変える“きっかけ”をつくりたい!
堤大介(つつみ・だいすけ)
1974年、東京生まれ。ニューヨークのSchool of Visual Artsを卒業後、LucasArts Entertainment Companyに勤務。ブルースカイ・スタジオで『アイス・エイジ』(2002年)、『ロボッツ』(2005年)、『ホートン ふしぎな世界のダレダーレ』(2008年)の色彩設計・コンセプトアート等を担当。2006年、ピクサーに移籍し『トイ・ストーリー3』(2010年)、『モンスターズ・ユニバーシティ』(2013年)でアートディレクター(色彩・照明)を歴任。2014年、短編アニメーション『ダム・キーパー』を自主制作。ロバート・コンドウと共同で監督を務め、世界の国際映画祭で20以上の賞を受賞、2015年米国アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた。後に2人が中心となってトンコハウスを設立、米国カリフォルニア州バークレーと日本の石川県金沢市にスタジオを構える。2020年アニー賞ジューン・フォーレイ賞(功労賞)受賞。『ONI~神々山のおなり』(2022年)は初の単独長編監督作品となる。
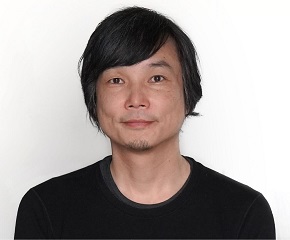 堤大介監督
堤大介監督堤 2022年に48歳になったのですが、ここ数年は経験したことのない強烈な出来事が続きました。世界の時間が止まったようなコロナ禍を経て、過激な思想を持った人たちの発言力が高まっていきました。世界中がまるで闇に覆われてしまったように暗いニュースばかりの中で、どうしたらこの作品を日本と世界の人たちに見てもらえるのか、伝えるためにどうすべきなのかと、みんなで何度も話し合いました。
──本作は可愛らしい神々の冒険ファンタジーとしても鑑賞出来ますが、マイノリティの人権や人と自然との関係性といった社会的テーマも含まれ、多層的な群像劇になっていますね。
堤 必ずしも社会的なメッセージを込めたいと思っているわけではないのですが、現代社会に生きている以上は、そうしたテーマが入ってきて当然ですよね。アニメーション映画の制作には大勢のスタッフが関わりますが、『ONI』のストーリーに関しては、ぼくと(脚本の)岡田麿里さんが中心となって延々と話し合いながら進めていきました。
──2019年にドワーフ(スタジオ)で制作されたパイロット版『ONI』はストップモーションでした。3DCGで制作された経緯を伺いたいのですが。
堤 当初は漫画的な誇張を採り入れたコンパクトな作品を構想していて、おなりのデザインも「雷神になりたい少女」として肌も赤く塗っていました。その後、ドワーフさんと話し合いを重ね、コマ撮りでは難しいシーンが多いことが分かりました。脚本が進むにつれ、より複雑でドラマチックな広がりを得ていく中で、2020年の時点で、CGで制作することを決めたんです。
──日米のトンコハウスを母体として、CGは日本の各社で制作されたそうですね。
堤 幸いコロナ禍でも仕事が止まることなく進められました。ハリウッド大作のスペシャルエフェクトを担当されてきたMEGALISさんがCG全般を、『ダム・キーパー』(2014年)、『ムーム』(2016年)でも協力してくれたアニマさんとマーザ・アニメーションプラネットさんにキャラクターアニメーションを中心に担当していただきました。大所帯でしたが、監督と責任者間だけのやり取りにはしたくありませんでした。スタッフみんなが「自分たちの作品」と呼べるものにしたかったのです。
週2回のオンライン・ミーティングに何十人も集まって、みんなでワンショットずつ討議する。それがとても楽しくて、最後の方は本当に一つのチームにまとまっていきました。各社の才能あるスタッフが、予算と時間の制限された中でもクオリティを落とすことなく、粘りに粘って素晴らしい映像を作り上げてくれました。
 ©2022 Tonko House Inc.
©2022 Tonko House Inc.──滑らかな従来の3DCGとは異なる、独特の動きの硬さがあります。「ストップモーションのようだ」という評価も聞かれますが、むしろ日本のリミテッドアニメーション風のCGに挑戦した作品なのではないかと思います。
堤 それは嬉しい評価です。ぼくは、1970年代から1980年代に日本で放送された「テレビアニメ」で育ちました。宮崎駿監督の『未来少年コナン』(1978年)などは、少ない動画枚数でも美しく見せることに成功しています。それは一つ一つのポーズの美しさや絵の持つ力だと思います。日本でCGアニメーションを作って世界で勝負するのであれば、圧倒的にその力だろうと。ディズニーの滑らかさやポーズの作り込みは素晴らしいですが、日本の2Dアニメーターの絵作りはそれと同等に素晴らしいと思います。
制作当初にスタッフを集めてこう言いました。「ぼくらが目指すのは80年代日本のアニメだ。それは限られた予算と時間を逆手にとって美しいものを作るというマインドであり、そのための工夫を学ぼう」と。トンコハウスはピクサー出身者が多いスタジオです。だからこそ、ディズニーやピクサーと異なる道を行くことに意義を感じています。
──ローアングルや俯瞰、奥から手前の一瞬の移動などに、日本的特徴を感じました。天狗先生の羽根の動きなど「第1話」と「第4話」を比較すると試行錯誤の積み重ねが垣間見えるようでした。
堤 おっしゃる通り、作りながら技術を発展させていきました。最初は苦労しましたが、次第に動きの硬さを感じさせないポーズを作り出せるようになりました。結果として日本ならではの美しいアニメーションが出来たと自負しています。
一番嬉しかったのは、ピクサー、ディズニー、ドリームワークスといったアメリカの主要スタジオのアニメーション・スーパーバイザーの人たちから「アニメーションが良かった!」というコメントをもらったことです。今回大きな手応えを得たので、今後もこの方向を詰めていきたいですね。
──動きを制限することでレンダリング(データ生成・出力)の時間と予算を削減出来るという利点もありますね。
堤 それも重要です。リミテーションをアドバンテージに変えることは、どんな現場でも大切だと思います。「動きが硬くて見にくい」という声も聞きますが、スムーズな動きであっても演技の基礎が失敗している映画もあります。演技を疎かにしないことの方が大切だと思っています。
 ©2022 Tonko House Inc.
©2022 Tonko House Inc.──キャラクターデザインが秀逸です。おなりの眼は小さな黒丸で白眼がなく、鼻もありません。そこは大きな眼を描く日本風のデザインとは異なりますね。
堤 日本を舞台にした作品で、登場人物はアジア人なのに大きな眼のキャラクターばかり登場することに違和感がありました。ぼくとロバート(・コンドウ)は、最初から黒眼だけのデザインにずっとこだわってきました。でも、それまで携わってきたメジャーな作品では「それをやっちゃダメだ」と言われていたのです。『ダム・キーパー』制作時にも「これでは表情や演技が描けないだろう」と言われました。そのたびに「眼が小さくても演技は出来る」と言い続けてきました。今回も同じようなバトルが
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください