エンパシーの力で、「考える」を鍛える
2023年04月25日
新学期が始まりました。新型コロナウィルスによる重苦しい空気に覆われた3年間を経て、ようやく「普通」の学校生活が戻ってきたと感じている子どもたち、学生たちは少なくないでしょう。この先、何が起こるか分からない――それを痛感した3年間でもありました。こんな予測不能な時代を幸せに生きるために、教育の場には、どんな発想が必要でしょうか。劇作家・演出家にして、「人生相談」の名回答者でもある鴻上尚史さんに聞いてみました。
僕は昨年(2022年)、15年間続けてきた「虚構の劇団」を解散しました。そこでは俳優やスタッフを育てようと、ずっと若い人たちと付き合ってきました。
そんな彼・彼女らとの会話の中で、年々増えてきた言葉があります。
「そんなことしていいんですか?」
 鴻上尚史
鴻上尚史「なんで、もっと広く使わないの?」と尋ねたら、返事はこうでした。
「そんなことしていいんですか?」
こんなこともありました。芝居の小道具で竹の釣り竿を買ってきたのですが、長すぎて、俳優がうまく使えず、もてあましています。僕が「短く切ればいいじゃないか」と声を掛けると、びっくりした表情で言われました。
「そんなことしていいんですか?」
オーディションのために、小さな劇場を借りた時のことです。客席の後ろにオペレーションルームがあるのですが、その劇場は、オペルームと客席との間にガラス戸が二枚はまったような窓があり、ちょっと舞台が見えにくい構造でした。並んで座った音響と照明のスタッフ二人は困って、代わりばんこに、せわしなく窓を開け閉めして、舞台の様子をのぞいていました。簡単に取り外しできる窓だったので、僕が「窓をはずせば見やすいよ」と言うと、二人が同時に言いました。
「そんなことしていいんですか?」
彼・彼女らは、いまあるルールにどう従うかということにはすごく長けています。でも、現状を疑ったり、変えたりするという発想の訓練がなされていないのです。僕は大学でも教えていますが、学生たちにも同じことを感じます。しかも、「優等生」ほど、その傾向が強いのです。
これは、若者たちの責任でしょうか。
 MaDedee/Shutterstock.com
MaDedee/Shutterstock.comまるで、教育の最上位目標が「ルールを守らせること」のようになっているのです。為政者からすれば、こういう教育を受けた国民はコントロールしやすいでしょう。でも、それで僕たちは幸せになれるでしょうか。
ルールを守らせることを一番にするのではなく、自分の頭で考え、自分の行動を決めてゆくことの出来る人間を育てる方向に教育をシフトさせなければいけない。そうでなければ、日本社会そのものが危ない。僕が、そんな問題意識を共有している一人が、横浜創英中学・高校校長の工藤勇一さんです。
工藤さんは2014年から20年まで千代田区麴町中学の校長を務め、学校の「当たり前」を見直し、生徒を学びの当事者にする改革で、大きな成果を挙げました。『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』(講談社現代新書)という本で対談しました。
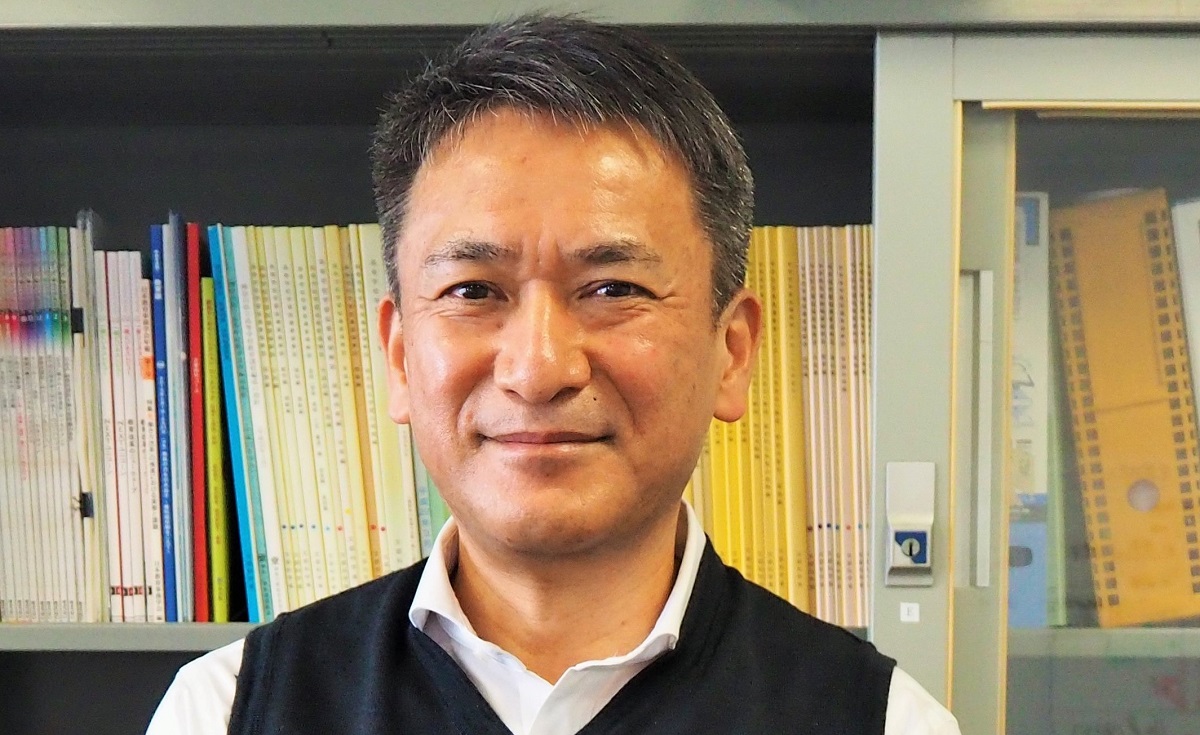 横浜創英中学・高校校長の工藤勇一さん
横浜創英中学・高校校長の工藤勇一さん「最も重要なことは何か」を考えさせる発想です。
こう言うと当たり前のようですが、この国の教育には、いろいろな場面で「何が一番大事か」を考える訓練が欠けていると思います。大人たちは自分の成功体験をもとに、「今までのやり方を守っていればいい」という教育をやってきて、その結果、多くの子どもたちに「ルールは守る」けれど「現実に対処できない」思考を植え付けてしまったと思うのです。
予想不可能な時代に、自分の頭で考えない人が多くなるのは、国家レベルの危機といえるでしょう。誰にも予想がつかないのだから、現実を常に検証し続け、おかしな方向へ行きそうになったら、みんなで意見を出し合って、修正していく必要があります。
 Daniil Khailo/Shutterstock.com
Daniil Khailo/Shutterstock.com人が生きていて一番大事なことは何か。それは、幸せになることでしょう。でも、日本では、「世間」に生きる人に対する、よく言えば「気遣い」、悪く言えば「忖度」が第一になっていて、まず、相手が何を求めるかを考えがちです。それが過剰になると、「ひとに迷惑をかけるな」という〝呪いの言葉〟に支配されてしまうのです。それは、とてももったいないことです。
自分にとって何が幸せか、それを維持するにはどうしたらいいかを、それぞれが考える。そのために必要な「土壌」――例えば、危険のない町であったり、平和であったり――をどう作ればいいのかと発想を広げてゆけるといいでしょう。そのためには、自分の頭で考える訓練を小学校から始めることだと思います。
ものを考える訓練として、ある状況をシュミレーションしてやってみる、という方法があります。僕は演劇人なので、これから演劇の手法を例に挙げますが、別に演劇だけが有効だと言っているわけではありません。他のジャンルでもいろいろ考えられると思います。ただ、ここでは自分に身近な手法で話を進めたいと思います。
工藤先生の依頼で創英中学校で、こんな授業をしました。
課題は、『シンデレラ』の物語。継母はシンデレラに、とてもつらく当たります。どうして継母はあんな態度をとったのか、考えてみましょう、という問いです。
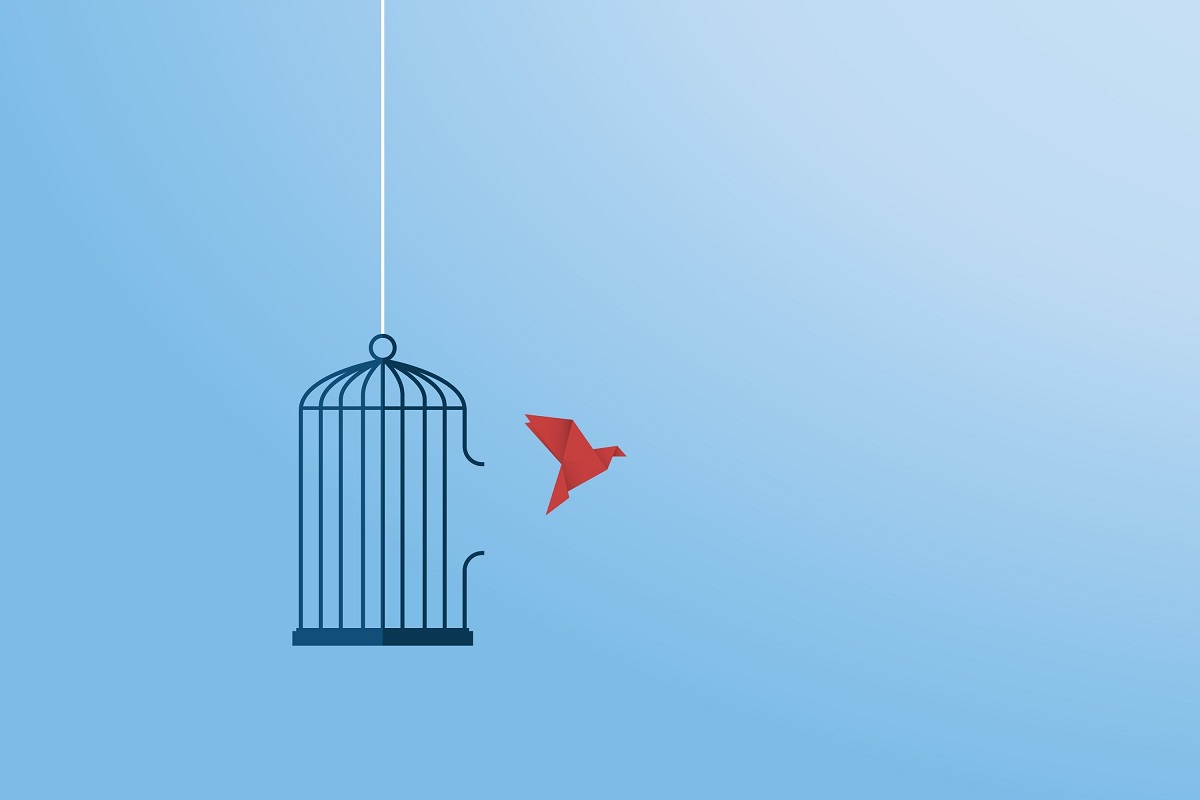 MaDedee/Shutterstock.com
MaDedee/Shutterstock.comシンパシー(sympathy)とエンパシー(empathy)という言葉があります。
シンパシーは「同情心」です。「シンデレラがかわいそう」という同情はシンパシーです。「自分の嫌いなことを人にするな」や「自分の好きなことを人にしなさい」は、シンパシーです。
一方のエンパシーは「共感力」と訳されたりしますが、「相手の立場に立てる能力」です。その人に共感する必要はありません。もし自分が継母ならば、なぜシンデレラをいじめるのだろうかと考えることです。
エンパシーを持つという体験は、自分とはまったく違う考えや感情を持った相手の立場でものを見ることで、「考える」の良い訓練になります。
中学生たちからはいろいろな意見が出ました。
「継母にとっての再婚相手であるシンデレラの父親がとてもひどい人で、その怒りを娘にぶつけたのでは」「実の娘とシンデレラの容姿の差が大きいので憎しみの感情が生まれた」「一人『敵』を作ることで家族をまとめようとした」などなど。こういうエンパシーの能力を磨くには、演劇の手法はとても有効です。
ほかにも、例えばスポーツで、あるケースを想定し、最も有効な練習方法は何かを考えてみる、といったことも、エンパシーを磨く練習になるかもしれません。
素材ややり方はたくさんあるでしょう。どんな方向からでもいいのです。こうした訓練を積むことで、子どもも大人も、「しょうがない」と考えることを諦めないようになるといいと思います。その積み重ねが、僕らが先行きの見えない時代を生き抜くための力になるはずですから。(構成:山口宏子)
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください