2014年08月18日
研究者が研究の成果を論文の形で公表するという習慣が生まれたのは、それほど昔の話ではない。
確かに、科学者の学会というと、誰もがイギリスのロンドン王立協会を想起するかもしれない。この協会は一七世紀に誕生した、現存する学会としては最古のものの一つで、その機関誌は、協会の創設とほぼ同時期の一六六五年に、当時この協会の秘書役であったオランダ人のヘンリー・オルデンブルグ(Henry Oldenburg 1618〜77)によって、私的に始められ、今日まで続く学術雑誌の祖とも言われている。
しかし、考えてみると、この時代に「科学者」という社会的存在はあり得なかったことも指摘せざるを得ない。
言葉の上だけから考えても、イギリス語の「科学者」、つまり〈scientist〉という語彙は、ウィリアム・ヒューエル(William Whewell 1794〜1866)が造語して使用し始めるまでは、存在しなかったのであり、その意味では、王立協会に集った人々を、安易に「科学者」と呼ぶことは時代錯誤を犯すことになる。
また、内容的にも、機関誌であるPhilosophical Transactions を実際に調べてみると、およそいろいろな種類の言説が雑多に集められており、現在の学術ジャーナルの面影はない。
近現代の科学者の代表のように思われるチャールズ・ダーウィン(Charles Darwin 1809〜82)も、王立協会の機関誌に寄稿しているが、彼の最大の研究成果である生物進化論の学説を一八五九年に公表したのは、不特定多数の読者を想定した『種の起源』という書物の形においてであった。
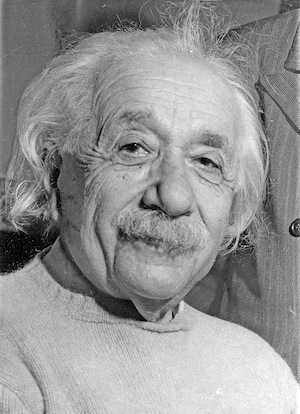 アインシュタイン博士=AP
アインシュタイン博士=AP同時に、一九世紀後半には、個々の専門領域の研究者のみが集まって作る専門学会、別の言い方をすれば「科学者共同体」も次々に形成されたから、当然ながら、学会誌という論文発表の媒体も新たに生まれたことになる。
この半世紀は、現代の科学研究に関する諸制度が、ほぼ全面的に整えられていく時期に当たっており、科学者共同体の内部で、研究による新しい知識の生産から、その活用、あるいは評価、褒賞などが自己完結することになる。
評価に関しても、一つには、専門化が激化すればするほど、当該の研究結果の良否は、当該の専門家仲間以外に容よう喙かいすることができなくなる、という理由から、またもう一つには、科学者共同体は外部からの介入を極度に嫌い、すべてを自分たちの手で行おうとする独立の主張から、当然のように「ピア・レヴュー」という形式が確立したのである。
この「独立」の問題には、科学者は極端に神経質になるようで、例えばボルティモア事件はその良い例になるだろう。
この事件は、一九七五年にノーベル生理学・医学賞を受賞したボルティモア(David Baltimore 1938〜)の研究室で起こったスキャンダルで、彼も共著者の一人である、Cell誌に発表された論文に関して、同じ研究室の同僚から、疑惑を訴えられたことに始まる。一九八六年のことであった。
当初、研究室ヘッドであるボルティモアらは、この訴えを黙殺したので、提訴者は最終的には下院議員のディンゲル(John Dingell 1926〜)を動かし調査委員会が組織された。このときボルティモアは、全米の研究者に檄を飛ばし、「第二のガリレオ事件」として、厳しく反対するように促すキャンペーンを張った。つまり科学の世界に政治が介入するのを断固阻止しよう、というのであった。
余談だが、全米科学アカデミー(NAS)の当時の会長フランク・プレス(Frank Press 1924〜)が、危機感を募らせ、若い研究者の卵に、研究者としての躾を説いたパンフレット On Being a Scientist の編集、刊行を思い立つきっかけの一つが、この事件であった。このパンフレットの初版は一九八九年に刊行されている。
科学者の「独立」に関しては、私自身、苦い経験がある。
一九八五年、筑波で開かれた科学万博で、日本IBM社のパヴィリオンの一階モールに、科学技術の歴史を彩る写真などを展示する企画があり、そのお手伝いをすることになった。
現代を象徴する出来事の一つとして、「アシロマ会議」を取り上げた。最終案が固まったとき、アメリカのIBM社に、表敬的な意味もあったのだろう、その案を提示した。
するとアメリカの学術コンサルタントと称する人物から、アシロマ会議に関して強烈な異議が返ってきた。遣り取りがあったが埒らちが明かないので、直接出向いて折衝することになった。
その段階で初めて判ったのだが、相手はハーヴァードの教授で、ニュートン研究で知られるコーエン(I. B. Cohen 1914〜2003)、当然旧知の人物だった。
他の点でも議論はしたが、ほとんど半日を費やして結局折り合えず、日本IBM社の担当者は、もともと、頭も資金もすべて日本IBM社の負担なのだから、と言ってくれたので、アメリカIBM社は本企画には一切関わりがないという断りを明記することで、帰ってきたのである。いろいろとコーエンは文句を言ったが、主要なポイントの一つは、アシロマ会議が認めたIRB制度にあった。
もともとアシロマ会議というのは、いわゆるリコンビナントDNA、つまりDNAの組み換え技術が、原理的にはほぼ完成した一九七五年に、その将来に危惧を持った専門家たちが世界中からカリフォルニアのアシロマに集まって、一種研究の規制措置をガイドライン化することを定めた会議であった。
その規制措置は大まかに言って三つある。一つは実験生物(主として大腸菌)に処理を施して、生体内では繁殖できないようにするという生物学的封じ込め、もう一つは実験生物の危険度に応じて、扱う実験室の防護の程度(P1〜P4)を定めるという物理学的封じ込め、そしてIRB制度の三点である。
IRBは〈Institutional Review Board〉の略語で、日本では通常「倫理委員会」と意訳されているが、研究機関内に設けられた審査委員会である。
要するに、この分野の研究者は、実験材料、実験手法その他を明記した実験計画書を、自分が所属する研究機関のIRBに提出し、その許可を得て初めて当該の実験に取り掛かることができるという制度である。
問題はIRBの構成にあった。
IRBのメンバーのうち、当該の専門領域の専門家は半数を超えてはならない、という規定が定められた。言い替えれば、そのメンバーの半数以上は「非専門家」によって占められるべき組織がIRBなのである。
ちなみに、この取り決めは、日本でもガイドラインとして受け入れられているが、日本のIRB制度では、この条件を厳密な意味では満たしていない事例も見受けられる。
話を戻すと、コーエンは、このIRB制度は、やはり研究の「独立」に対する重要な侵害であって、認めるわけにはいかない、と言うのだった。彼は自分の背後にはアメリカ物理学会が付いている、という、およそ議論の筋道からはかけ離れたことまで持ち出して、引き下がろうとはしなかったのである。
いずれにしても、科学者共同体が、研究に関するすべてを自分たちの手に掌握しておきたい、という欲求を強く抱いていることは、以上のような出来事からもわかるだろう。
しかし、二〇世紀後半からは、科学者共同体の内部に限局されているはずの科学的知識を、国家行政や産業が、自分たちの目標実現のために、こぞって利用し始めたのである。
その典型はマンハッタン計画であったが、ライフサイエンスの世界は、医療と直接繋がるために、産業を含めて、科学的知識の利用が極めて活発な領域の一つとなっている。
つまり、すでに、科学者共同体の「独立」は、出口のところで完全に崩れ去っているのだ。しかも、現代のように研究に巨大な資金が必要になり、研究の大規模化に伴い、研究資金は当然、科学者共同体内部で調達できるはずもなく、外部社会からの援助を仰がなくてはならない。
その点で入り口においても、「独立」というきれいごとは通用しない事態に立ち至っている。
『ネーチャー』と『サイエンス』が、現在、世界の研究者たちが、自分の論文を掲載してもらいたいと願う、最も重要な媒体であることは、周知だろう。
『サイエンス』は、それでもアメリカの全米科学振興協会(AAAS)が刊行しているジャーナルだが、『ネーチャー』に至っては、普通に市場でも購入できるジャーナルである。
もともと『ネーチャー』が刊行された際には、論文を掲載する媒体というよりは、むしろ啓蒙的な役割をもって任じていた。つまり科学的知識を一般の人々に行き届かせることが、自らの使命であると考えていたのである。その意味では、現代社会における通常の科学ジャーナリズムと、大きな違いはない、あるいはなかった、というのが真実だろう。なお、このような性格から、現代の研究者の中に、敢えて『ネーチャー』などは一切相手にしないと宣言する勇気ある人物も現れている。昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカのシェックマン(Randy Schekman 1948〜)である。
ただ、初期から『ネーチャー』の編集部には、「問題提起」(polemic)という意図もあったようで、あえて定説でないような言説も掲載し、誌上で論戦が行われるのを督励するような空気があった。
そうした啓蒙的なジャーナルが、論文発表媒体へと移行するのは、やはり領域の専門化の進展が働いていたことは明らかだろう。
そしてそこにもう一つの因子が絡む。
それが完全に因果関係で結ばれていると主張するつもりはないが、少なくとも状況的な関わりはあるはずである。
その因子とは、被引用度であり、インパクトファクターである。
ユージン・ガーフィールド(Eugene Garfield 1925〜)が一九六〇年代の初めに創設したISI(Institute for Scientific Information)によって刊行されることになった『被引用度索引』(Science Citation Index)は、恐らく創始者の思惑を遥かに上回る結果をもたらした。
ある特定の論文が、他者の論文のなかで引用される回数を、単に数え上げる、という児戯に等しい方法で計上される被引用度は、その論文の学問的重要性を示す客観的尺度として、猛威を振るい始めたからである。
しかも、その被引用度を基礎に、そこから算出されるインパクトファクターは、論文誌の使命を制するほどの意味を持つようになっている。
インパクトファクターとは、ある年間に、特定のジャーナルに掲載されたすべての論文の被引用度を単純加算した上で、その数値を、論文の総数で除する、要するに、年間の論文の平均被引用度なのだが、たったそれだけの値が、論文誌の重要度の客観的尺度として、決定的な意味を持つようになって、まだそれほどの時間が経っているわけではない。
ただ研究者の履歴書に添える業績リストは、まず査読付き単著論文、次に共著論文、総説など序列的なカテゴリーに分類されるが、個々の論文には、必ず被引用度を付する、という習慣が国際慣行になるのは、今から二〇年ほど前からであろうか。
そしてその論文が掲載された論文誌のインパクトファクターを乗じながら、その業績リストの重要度の「客観的数値」が、いとも簡単に算出する習慣もまた、現在では定着している。
そもそも被引用度そのものが、必ずしも当てにならない。
例えば、親しい仲間、利害関係を共有する仲間の論文はお互いに引用し合う、しかしライバルの研究者の論文は決して引用しない、などという戦略が、たちまち広がるし、論文誌のインパクトファクターも、人気投票のような趣もあって、論文内容や研究者の資質を真に反映したものになるとは限らないのは、ほとんど自明である。
それにもかかわらず、現在そうした数値が決定的な役割を果たしている背後には、やはり極度の専門化があると考えざるを得ない。世界でもほんの数十人だけが、専門家として存在するような、極端に小さな科学者共同体さえある現実のなかで、ある業績をどう評価するか、ということに、誰もが自信が持てなくなり、「客観的」指標にすがりたくなるのも、無理はないかもしれない。
もう一つの問題は、論文の査読という点である。
私も、海外からも査読を依頼されることがあるが、それは一つには、人間関係で、あまり面倒がないと思われているからと推測されることも多い。
科学者共同体といえども、先輩、同僚、後輩などの人間関係のなかで、査読が公平に行われるのを妨げる要素も決して少なくない。それが露骨に表れる場合さえある。査読者バイアスという言葉さえある。ある特定の論文誌の査読者は、ある特定の研究志向に対してのみ好意的で、別の志向には極めて厳しい、というような事態はままあることになる。それが更なる新しい共同体へと分裂させるきっかけにさえなる。
そうした研究を巡る険しい状況のなかで、一般の報道機関が、科学研究の成果をどのように報道すべきか。そこに大きな困難があることは目に見えている。
 多くの報道陣が集まる中、会見する理化学研究所の小保方晴子氏ら=2014年4月9日
多くの報道陣が集まる中、会見する理化学研究所の小保方晴子氏ら=2014年4月9日もっとも、科学報道ではないが、少し前に起こった偽作曲家の事件も、パターンとしてはよく似ていたと言える。
どちらも、マスメディアが、刺激的、感動的な物語をセンセーショナルに作り上げ、一転、手のひらを返すような否定的な物語を、もう一度センセーショナルに打ち出す。同じ話題で、二度「もうける」と言っては失礼かしら。
もうずいぶん前になるが、科学の世界で、新しい発見と称するものを、論文の形で「ピア」(同僚)に問う前に、メディアに発表する傾向が増していることを警告した記事を書いたことがある。
今回の理研の事件は、『ネーチャー』誌に論文が発表された後のことだから、これには当てはまらないが、科学者の側が積極的にメディアを利用して自分たちの「業績」を喧伝しようとした点では、変わりはない。
 会見する小保方晴子氏=2014年4月9日
会見する小保方晴子氏=2014年4月9日すでに繰り返し述べてきたように、もともと、科学研究は、基本的には専門家の集まりである科学者共同体の内部で自己完結する営為であった。
研究による新しい知識の生産、生産された知識の(論文という形での)ジャーナルへの蓄積、蓄積された知識の流通、流通する知識の利用・活用、あるいはそうした知識の評価、などが、科学者共同体内部でのみ行われ、外部社会には漏れ出ない、というのが特徴であり、それが技術や工学との顕著な違いであった。今「あった」と過去形で書いたが、確かに現代では、この特徴はむしろ希薄になっていて、少なくとも「知識の利用・活用」は、明らかに共同体の外で行われるようになっている。
行政や産業が、その最たる利用者である。利用者は、学術上の良否よりも、実際の使い勝手や、その活用効果から判断する傾向がある。
かつて科学的知識は、公共的(communal)とされ、誰もが(ただし、研究者仲間に限る)自由に利用できるはずのものであったが、今では「知的財産権」のような主張が科学の世界にも入り込んでいる。
今回の事件でも、そうした点が、問題を難しくしていることも無視できない。きちんとした情報がすべて明かされているとは限らないのである。
その点を考えれば、先に書いたように通常のメディアに対して、科学上の知識に関して相応の「見識を備える」よう求めることは、ないものねだりではないか、という批判は当然あり得るだろう。
 会見で頭を下げる佐村河内守氏=2014年3月7日
会見で頭を下げる佐村河内守氏=2014年3月7日聴いた音楽はムード風であり、それ自体として必ずしも「悪い」ものではないと思ったが、ベートーヴェンの「再来」など、冗談としか思えない話で、私が新聞のデスクであったり、テレビジョンのプロデューサーであったら、文字通りの「際(きわ)物(もの)」として、取材は一切認めなかっただろう。これは後知恵で言うのではない。
理研の例では、正直なところ半信半疑で、半信半疑であれば、裏切られる可能性に十分備えた取材、あるいはニュース化をすべきだろう、と考えていた。
いずれにしても初期の騒ぎは、どちらもあってはならないものだった。そして、それだけの判断は、ごく当たり前の常識を備えていれば、自ずから生まれるものだったはずである。
もう一つ、メディアの立場で考えておいてよいのは、そうした際に、自分たちだけで判断するのではなく、複数の適切な専門家に相談することだろう。
もちろん、新聞なりTV局なりは、それなりにコメントを求める専門家を抱えているはずで、そんなことはとっくの昔に実行していると言われるだろう。
しかし、実際には、それが十分に機能していないことは明白ではないか。
ここには二つの問題がある。
一つは、メディア側が、専門家のコメントを求める際、多くの場合、すでに自分たちのなかで引きだしている結論を補強したり、強化したりする発言を期待しており、専門家のコメントのなかから、そうした部分だけを取り出したり、極端な場合には、発言内容にはないことまで「捏造」して、メディアが発表することさえある、という点である。
そういう経験を何度か繰り返すうちに、メディアの取材には決して応じない、という頑なな姿勢に入ってしまう専門家を、私は何人も知っている。
いきおい、紙面や画面には、メディアでの露出を至上の価値とする一部の専門家と称する人々のみが、活躍することになる。
もう一つの問題は、専門家は一般に、研究仲間以外の人々とのコミュニケーション能力を著しく欠いているという点である。
最近日本でも「サイエンス・メディア・センター」という組織が生まれており、経済基盤はなかなか整備できていないが、活動を始めている。
しかじかの問題には、コミュニケーション能力も含めて、適切な対応をしてくれるはずの専門家のリストを持ち、メディアとの間の媒介機能を果たそうとする組織である。
このように考えてみると、事態は全く絶望的ではない。
辛抱強く、よりよい道を探し出す努力を続けること以外に、選択肢はない、というまことに平凡な結論を以て締め括りとしたい。
◇
村上陽一郎(むらかみ・よういちろう)
東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授。
1936年生まれ。東京大学教養学部教養学科卒(科学史・科学哲学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。上智大学理工学部助教授、東京大学教養学部教授、同先端科学技術研究センター教授、東洋英和女学院大学学長などを経て現職。 著書は『安全学』(青土社)、『科学史の逆遠近法 ルネサンスの再評価』(講談社学術文庫)、『知るを学ぶ あらためて学問のすすめ』(河出書房新社)、『エリートたちの読書会』(毎日新聞社)など多数。
※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』8月号から収録しています。同号の特集は「科学報道はどう変わるべきか」です
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください