公正な報道と調査報道に取り組み言論の自由を掘り崩すものと対峙せよ
2015年03月23日
朝日新聞は2014年、自ら引き起こした報道の過ちをめぐる問題で未曽有の危機に立たされました。雑誌や新聞では猛烈な朝日バッシングが連日のように展開され、メディアの分断状況も深刻化しています。海外メディアからは、日本の言論状況を憂慮する声も聞かれます。今回の一連の問題を経て、朝日はどう生まれ変わるべきか。「リベラルな言論」が復権する道はあるのか─。徹底討論しました。
(司会は『Journalism』編集長・松本一弥)
松本 慰安婦報道と慰安婦報道検証、東京電力福島第一原発事故をめぐる吉田調書問題、さらには池上彰さんのコラムの掲載を見送った池上コラム問題の三つが重なり、朝日新聞は昨年、痛恨の極みといえる事態に陥りました。
すでにいろいろな方からご指摘いただいているように、朝日の上層部は組織防衛に走りすぎたあまり、「読者に対する誠実さ」という最も肝心な視点が欠落した結果、長年の読者と社会からの信頼を著しく裏切ってしまい、その後、朝日は「反日」「売国奴」などといった激しいバッシングを浴びました。
また、戦後の朝日がどこまで「リベラルなジャーナリズム」を展開できたかについては厳しい検証が必要だと思いますが、かぎ括弧(かっこ)付きの「保守主義」が台頭する中、いわゆる「リベラルな言論」までもが脅かされ、批判を浴びる事態に一部でなりつつあると認識しています。
過ちは過ちとして、朝日が厳しい批判を受けるのは当然ですし、私たちはそれを真摯(しんし)に受けとめ、反省しなければなりません。同時に、歴史修正主義的な言論やヘイトスピーチのような排外主義が跋扈(ばっこ)する中、リベラルな言論がこのまま後退していいとは、私は考えません。
本日は朝日の一連の「失敗の本質」がどこにあったのかという問題にとどまらず、感情的な誹謗中傷の応酬ではない、本来的な意味での「公共圏」といいますか、自由闊達な言論空間がどうすればこの国に蘇よみがえるのかといった点も視野に入れつつ、お話をいただければと思います。
この雑誌は、取締役編集担当直属の機関である朝日新聞社ジャーナリスト学校が発行していることから、編集担当直属の雑誌という位置づけになっています。その意味で発行に伴う軸足は朝日本体に置いていますが、今回の事態は「ジャーナリズムの根幹が問われた問題」にほかなりませんから、一切のタブーを排して朝日問題を徹底検証する必要と責任があると考え、様々な立場の方の多様な論考で構成する「朝日問題特集」をつくることにしました。
まず最初に、慰安婦報道と慰安婦報道検証についてのご意見からうかがいたいと思います。
 半藤一利さん(左)と苅部直さん(撮影=吉永考宏)
半藤一利さん(左)と苅部直さん(撮影=吉永考宏)
松本 どうぞ。
半藤 私は40年以上、雑誌ジャーナリズムに身を置いた者ですので、私自身もこの40年間の間にいくつかの過ちを犯し、相手方と折衝して謝るなど、いろいろな経験をしてきました。その経験から言うと、朝日新聞がこの三つの問題を一緒くたにして会見をし、「謝ったのか、謝らなかったのか」という問題以前に、誰に対して、何を謝っているのかが非常にはっきりしないということを私は痛感したんです。
一つ例を挙げますと、大江健三郎氏が昭和36(1961)年の「文學界」1、2月号に書いた小説をめぐる「セヴンティーン事件」(注1)というのがありました。当時、私は月刊「文藝春秋」編集部におりましたので部外者ではあったのですが、会社の大問題でしたので、それに少し参画したのです。
あの時は文春に右翼がものすごい勢いで抗議に来まして、その折衝で連日のように大騒ぎになりました。
その直前、昭和35年には「中央公論」12月号に載った深沢七郎氏の「風流夢譚」という小説がきっかけになった「風流夢譚事件」(注2)が起きていました。結果的にあちらはこじれまして、36年2月に嶋中社長邸で殺傷事件が起きるという事態になりました。そのため雑誌ジャーナリズムは、文春問題と中公問題で冬の季節を迎えたように震撼としていたんです。
あの時、私の会社が取った態度が非常に印象的で、今でも記憶に残っているのです。文春は「文學界」3月号誌上で陳謝したわけですが、ただその陳謝の仕方が、対象をはっきりと特定していて、「これに対しては陳謝する」ということを明確にしたんですね。
 半藤一利氏(撮影=吉永考宏)
半藤一利氏(撮影=吉永考宏)
「謹告 小誌一、二月号所載大江健三郎氏『セヴンティーン』は山口二矢氏の事件にヒントを得て、現代の十代後半の人間の政治理念の左右の流れを虚構の形をとり創作化し、氏の抱く文学理念を展開したものである。が、しかし、右作品中、虚構であるとはいえ、その根拠になつた山口氏及び防共挺身隊、全アジア反共青年連盟並びに関係団体に御迷惑を与えたことは率直に認め深くお詫びする次第である」
このわび状を「文學界」誌上に載せまして、これで騒ぎがすっとおさまったという経緯がありました。
私は非常に大事な点だと思うのですが、「文學界」としては決して大江さんの文学作品を全否定しているわけではなくて、認めているのです。その意味で、文春の立場は、はっきりしている。
しかも文春は、読者は陳謝の対象にはしなかった。そういうやり方で、「私たちはきちっと正しい文学活動をしたのだ」ということを証明したのです。私はこの時、ジャーナリズムが訂正して陳謝する場合は相当慎重に考えて、きちんとやらなければいけないということを痛感しました。
それと比べると、今度の朝日さんは、三つの問題を一緒くたに、しかもごちゃまぜにしてしまっている。それぞれの問題は対象が全然違いますから、やっぱりこういう問題をガチャガチャやると、ジャーナリズムはかえって自分の立場を失って、自分で自分の首を絞めることになるのではないかと思います。
新聞というのはあまり謝ったりするのに慣れていないのかなということも思うのですが、これからの問題もありますから、朝日さんはきちっとした態度をとらないと非常にいけないんじゃないかということを、雑誌記者としての長い経験上、ほんとうに感じました。これだけは最初にはっきりと言っておかなきゃいけないなというふうに思ったので、余計なことを申しましたけれども。
松本 半藤さんがご指摘になった今の点、苅部さんはいかがですか。
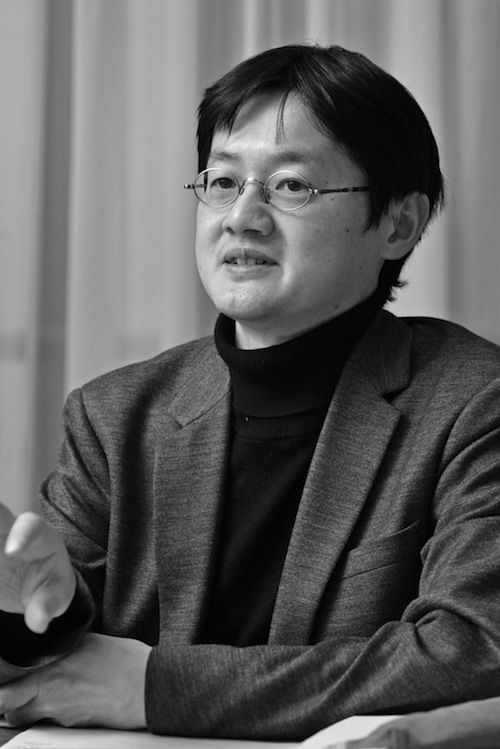 苅部 直氏(撮影=吉永考宏)
苅部 直氏(撮影=吉永考宏)
批判が殺到するのも、読者が朝日新聞に対して期待しているからそういうことが起こると考えたほうがいい。そもそも信頼できないメディアだったら、批判もしませんよね。この騒動の直後、朝日の記者の人たちが自信をなくしたようすなのが、かわいそうだと思いました。ネガティブな現象とばかりうけとめなくてもいいでしょう。ここ、ゴシック体で強調したいくらい(笑)。
その上で申し上げますが、三つの問題のうち、池上問題と残りの二つでは重大度が違います。ジャーナリズムにとって一番致命的なのは池上問題でしょう。また慰安婦問題についても、長年にわたって報道してきたことを、なぜ今になって訂正するのかという問題を含みますから、これと吉田調書問題との違いもあります。
まず慰安婦報道検証については、何で今になってそんなことをやるのか、不思議に思っていたのですが、第三者委員会の報告書に、つまりは経営問題だったと書いてあったので納得しました。朝日バッシングに対して対抗しなければいけないという意図だったと。そうであれば、第三者委員会も指摘するように、読者の方を向いていないと言われても仕方がないでしょう。読者にとっては、やはり唐突に思える検証記事だった。
しかもタイミングが悪い。韓国で反日世論が高まり、慰安婦問題に関する責任追求が厳しくなっている時に検証紙面を出すのは、外国から見れば、朝日が日本社会の右派勢力に屈したとか、政府の責任を否定する姿勢を明らかにしたという風にとられてしまいますよね。
ほかの問題に関しても言えることですが、今や日本の新聞を読むのは日本人だけではありません。外国人で日本語が読める人は海外にも少なくないし、新聞社の英語のウェブサイトもあります。日本の外でも読まれるという意識を欠いているところに、危機感を覚えました。
松本 外岡さんはいかがですか。
 外岡秀俊氏(撮影=吉永考宏)
外岡秀俊氏(撮影=吉永考宏)
やはり一番の問題は池上コラム問題なのですが、池上コラム問題がなぜ起きたのかを考えると、要するに慰安婦報道で間違っていたのに謝らない、しかもそれを指摘されたことを封じようとしたという二重の構造になっているわけですね。
まず、間違ったことを謝らなかった。それはなぜなのか、あるいはなぜ放置してきたのかについて、結局、追い込まれて第三者委員会に依頼して検証するという体裁をつくらざるを得なかったわけです。自分たちはなぜ、このことを今まで長年にわたって放置してきたかについての内省というか、「誰が何を考え、どうしたのか」を検証しようという意志といいますか、凄すごみをいまだに感じないんです。だからその意味で朝日の人たちの危機感というのはまだまだ甘い。
私は、朝日問題というのは朝日特有の問題もありますけれども、やっぱり活字メディア全体が今置かれている状況、つまり優位性が失われてきていて、多メディア化している、影響力も低下して経営基盤も空洞化しているという中で起きた問題なわけです。
つまり二重の危機の中に起きている問題で、それに関して、「読者に対して失った信頼を具体的にどうやって回復していくのか」についての本気の訴えかけもいまだに感じられません。
松本 信頼回復と再生のための計画を具体化していく途上ではありますが。
半藤 外岡さんは朝日新聞のOBだからお聞きしたいのですが、朝日の対応はなぜこんなに遅かったのですか? 吉田証言がかなりデタラメだというのは相当前にわかっていましたよね。
苅部 1992年、秦郁彦さんが産経新聞に書いた記事で指摘されていた。
半藤 そう、秦さんの記事で明確になったわけです。にもかかわらず、あれからずっと、訂正しない状況を引っ張ってきて、なぜ今、訂正するのか。こんなに引き延ばしてから訂正したというのは、社内事情がかなり複雑だったのですか?
外岡 私は2006年から07年にかけて、ゼネラルエディター兼東京編集局長という職にありました。編集局長は、それまで1人だったのを2人制にして、1人はマネジメント、もう1人は紙面に全面責任を負うという形にしました。
私は、その紙面に責任を負う役回りだったので、その間、慰安婦問題を放置した責任を問われる1人ではあるのです。その年は、ここにいる松本が中心になって、朝日新聞の戦争責任を正面から取り上げる「新聞と戦争」という長期連載をやっていたんです。
半藤 おやりになりましたよね。非常に立派なものでしたね。
外岡 あれも、週刊文春さんとか週刊新潮さんなどにずっと指摘されながら、検証できていなかった問題です。戦後60年たって、当時取材していた記者が少なくなるという中、あの連載をやるというところにようやくこぎつけたのです。
 松本一弥編集長(撮影=吉永考宏)
松本一弥編集長(撮影=吉永考宏)
編集委員でキャップ役を務めた藤森研さん(現・専修大学教授)や、編集委員の上丸洋一さんらとともに取り組んだ「新聞と戦争」の検証作業は1年以上にわたって続けました。
デスクを務めた私は、「この仕事は歴史をフィールドにした調査報道だ」と位置づけ、デスクワークにあたっては(1)徹底的な取材をする中で集められたファクトだけをもとに冷静に描く(2)イデオロギーはもとより情緒的な部分はすべて排除する(3)現在の地点から過去を単純に断罪しない―ことを自らに課しました。
ただ、当事者や関係者がまだご存命ということもあって「自分の先輩たちの過去をなぜそこまで厳しく検証するのか」という、社内の目に見えない〝抵抗〟や〝圧力〟は相当なものがありました。
外岡 そこはやはり基本的には日本的組織じゃないですけれども、身内をかばうとか先輩をかばうとか、でも最終的には自分自身の保身があるんですよ。
自分を守るために、要するに「くさい物にふたをする」ということになってしまう。それがほんとうは「間違っている」ということは頭ではわかっていても、それを内部からはなかなかきちんと指摘できないという体質がやっぱりあるのだと思います。
それと、ある意味で日本の新聞はわりとそうだったと思うんですけれど、「紙面に間違いはない」という無謬(むびゅう)神話のようなものを広げたし、自分たちもそんな体裁を繕ってきた。だから、新聞はよほどのことがない限りは謝らないんだという、長い間の組織風土のようなものができたのです。
半藤 これは朝日新聞だけじゃなくて文藝春秋でもありまして、私が役員になっているころでしたけれども、何か大きなミスをやった。これをしっかりと後世のため、後輩のために、「どうしてこういうことが起きたのか」ということを検証して残していこうじゃないかと、役員会では必ず決議をするんです。
ところが、実際にはやった試しがない。これはやっぱり、日本的組織というのはそれをやると責任者が出ちゃうんですよね。責任者が出るということについては、日本的組織というのは何か、かばうというようなところがある。
それは私の中にはあまりなかったんですけれども、私としては「責任は責任としてちゃんと負ってもらえばいいじゃないか」ということを思っていたんですが、太平洋戦争の時の参謀たちと同じようなものですから。何かそういう体質が文春の中にはありましたので、朝日にもすごくあるのかなと、勘ぐったのです。
外岡 やっぱりそういう体質というのは非常に根深いという感じがしますね。
だからそこの部分に手をつけることなく今回の問題を終わらせてはいけないと私は思うんです。そこはやっぱり、朝日に今いる人たちに一生懸命頑張ってほしいと思います。朝日は世間には頭を下げたかもしれないけれど、自分たちでは「ほんとうの危機にある」ということをまだ自覚していない。それをわかってほしいと思います。
松本 その点に関連して、この際、「失敗の本質」に迫る意味でもうかがっておきたいのですが、外岡さんは「慰安婦問題を放置した責任の一端は自分にもある」といわれます。しかし以前に私がたずねた時は、そうした事態を打開するべく具体的なアクションを起こそうとしたということではなかったですか?
外岡さんは、私に対して「吉田証言がウソだというのは以前からわかっていた。その誤りを正さないのが朝日の弱点になっていると考えて、社会部と政治部のデスクに対し、慰安婦問題と教科書問題の検証をしてほしいと頼んだ。ところが何度働きかけてもデスクたちは言葉を濁して暗黙の抵抗を続け、結局うやむやになってしまった」とはっきり話されていました。実際のところはどうだったのでしょうか。
外岡 何が原因だったのかはわからないんですけれども、ものすごい抵抗があったのです。ただ、取材した記者たちがまだ社内にいたりして、あまりにも〝距離が近すぎる〟から検証は難しいということなのだろうと思っていました。
だけど、本来はそういう人たちの責任問題とは別に、やっぱり言論の責任問題はあるのですから、そこをきちんとさせないと、いくら慰安婦問題のことを展開しても「あの報道はうそじゃないか」というふうに指摘されると、その足場が崩れてしまうのです。だから「自分がいる間にきちんとさせたい」という気持ちは持っていたのですが、結局できませんでした。
半藤 外岡さんがいたころは、経営者からの圧力はなかったのでしょうか。
外岡 いや、それはないです。「新聞が戦争をいかに煽ったのか」ということについても、徹底的に検証してくれという話でしたから。
半藤 ああ、そうですか。その辺、編集は自由だったわけですね。
外岡 多分、上から言っても、私がいうことを聞かないだろうと幹部は思っていたのではないでしょうか。
苅部 戦争責任問題について、右派メディアに載る記事や文章には、たしかに感情的なクズ記事も多いのですが、先にふれた秦郁彦さんの92年の文章のような、実証的な批判が載ることもある。そういう文章については、産経新聞だからと言って無視するのでなく、ちゃんと耳を傾けなければいけなかった。それなのに、産経に合わせて記事のトーンを変えると負けになるというような意識が、朝日の側にあったのではないですか。
しかもそれ以前に、担当されている記者の方々が、慰安婦問題についてきちんと知っていなかったのかもしれません。吉田証言を否定したとしても、慰安婦制度それ自体を批判するための証拠がゼロになるわけではないから、それはそれとして問題を追及していけばいいでしょう。何が問題なのかについて定見をもっていないから、吉田証言を否定すれば、慰安婦制度の問題性を全面否定することになってしまう、と過剰に警戒する姿勢に陥ってしまったような気がするんです。
外岡 今回、原発問題と、それから歴史認識問題にじかにかかわる内容について、一連の問題が起きたというのは非常に象徴的だと思います。
要するに、イシュー(問題)自体が政治化されてきているわけですよね。そういう中で、朝日の幹部の人たちは、この件が政治的に利用され、「これで謝ると相手に屈したことになってしまう」と考えたのではないか。そういう政治的な力学の中で発想していったのかなという気がします。
それは、誰に対して何を謝るかという問題につながるのですが、結局のところ、終始そのことがわからなかったというのが、朝日が読者に対して目が向かなかった理由ではないかと思うのです。
だから、別に右派勢力とか批判勢力に頭を下げるのではなくて、自分たちが今まで放置してきた誤りについて、きちんと頭を下げるということであれば、誰にもそんなに気兼ねをする必要はないし、そこから出直せばいい話なのです。
それが、変に政治的な打算や計算が働いたから、池上さんの話まで封じ込めてしまうというふうになってしまった。だからどう考えても、
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください