2022年02月21日
「ブラジャーって古くなっても捨てにくい……。そんなあなたに、知ってほしいキャンペーンがあります」
これは、ブラジャーのリサイクルに関する記事の見出しです。下着メーカーのワコールが、古くなったブラジャーを店頭で回収し、布やワイヤーなどのパーツを生活雑貨に再利用するという取り組みを紹介しています。
10年以上前から毎年実施されている取り組みなので、新聞であればニュース性はないと判断されるネタかもしれません。一つの企業の取り組みを紹介するのは広告記事ではないか、と眉をひそめるデスクもいるかもしれません。また、内容を正確に表現するなら「ワコール、使用済みの下着を今年もリサイクルへ」などのタイトルが適当でしょう。
ところがこの記事、このタイトルのおかげで、驚くほどよく読まれているのです。
ブラジャーは多少形が崩れてもまだ使えるので、捨てるタイミングを見極めにくいものです。布とワイヤーを分別しなければなりませんし、丸裸でゴミ袋に入れるのは気が引けます。「捨てにくい」というのは多くの人に〝あるある〟だったにもかかわらず、あまり知られてこなかったお悩みでした。それを代弁した見出しだったため、この記事はよく読まれたのでしょう。もしかしたら「ブラジャー」という単語から、果てしない想像力を働かせて思わずクリックしちゃったよ、という人もいるかもしれませんが。
ともかく、ワコールによると、2020年度のキャンペーンでは約22万枚のブラジャーが回収されたそうです。記事が多くの人に読まれ、SNSでシェアされ、そのうち一部の人が行動を起こせば、廃棄物が減り、資源の有効活用につながります。ネタの選び方、記事のつくり方、読者への届け方によって、メディアが社会に貢献するインパクトが大きく変化する一例として、この記事を紹介させていただきました。
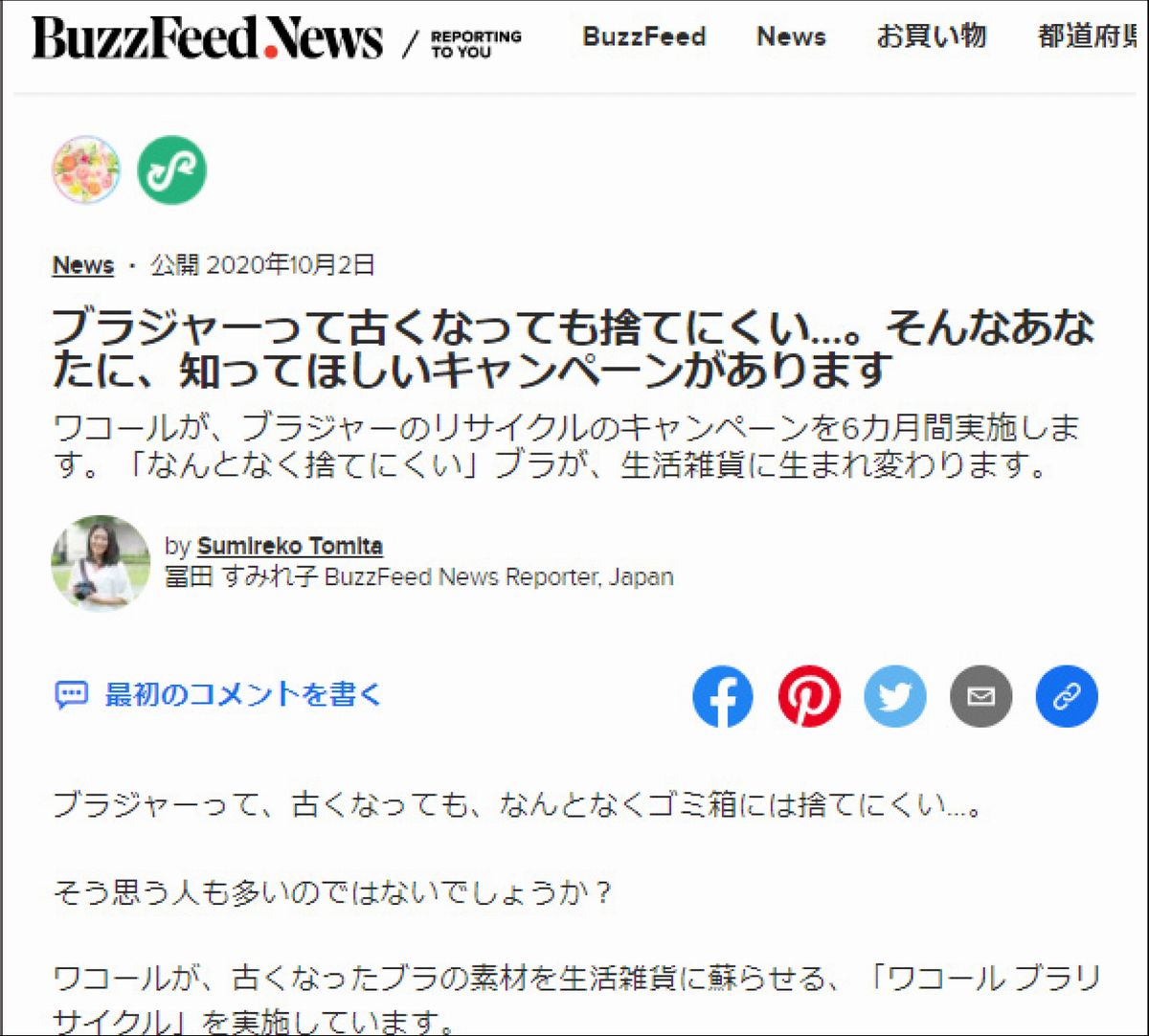 BuzzFeed Newsが伝えたブラジャーのリサイクルの記事
BuzzFeed Newsが伝えたブラジャーのリサイクルの記事BuzzFeed Japanでは、どんなテーマを取り上げるときにも、読者への扉をこちらから開くことを常に意識しています。記者の中には、特定の分野において高い専門性をもった記者もいます。それでも、「そのテーマ、あなたは関心あるかもしれないけど、読者は興味ないよね?」「そもそも知りたいとも思っていないかもしれないよね?」「書き方が独善的になっていない?」といった問い直しから始めます。
もともと関心がある層ではなく、無関心層や未認知層にタッチポイントをつくるにはどうすればよいか、という角度から、コンテンツの内容や構成、見出しを考えているのです。これは、私がBuzzFeed Japanに入社したときに最も発想の転換を迫られたことの一つでした。
私は毎日新聞の記者として5年間、行政や警察の取材をしたのち、ニュース週刊誌AERAで約9年間働きました。AERAの記者だったころは、女性の生き方や働き方を主に取材していました。たった10年ほど前ですが、当時はまだ、育児休業を取得した女性が、職場復帰してからの働き方に悩んで離職を迫られていたようなころでした。共働きの夫に、いかに家事を〝手伝って〟もらうか、保育園の入園を勝ち取るための「保活」でどんな作戦を立てればいいのか、といった記事が人気でした。
想定読者は、都心部で働く30代の高学歴・高キャリアの女性たち。職場でも家庭でも「正解」がわからない彼女たちに「悩んでいるのは自分だけじゃない」と思ってもらえるような共感性のある企画を毎週のように連発するため、必然的にテーマはどんどん狭く・深くなっていき、当事者の溜飲を下げるような企画が多かったように思います。
一方、インターネットメディアのアプローチはまったく異なりました。インターネット上の拡散を重視するバイラルメディアとして誕生したBuzzFeedは、たくさんの人が集まっているところ(プラットフォームやSNS)に記事を届けにいくというスタイル。誰もが無料で読むことができ、いったん拡散されると、どこまでも広がっていきます。
読者はミレニアル世代が中心というデータはありますが、配信先のプラットフォームやSNSの特性によって少しずつ異なります。Twitterでは40代の男性が多めだったり、Instagramのフォロワーは20代がほとんどだったり。なので、もともと媒体にもテーマにも関心のない人たちがいつどんなときに目にするかわからない、という前提で記事を書いています。
記事と読者は一期一会。まず、見出しで興味をもってもらうことができなければ、読者への最初の扉は開けません。私たちの競合は新聞、テレビ、インターネットメディアだけではありません。1台のスマホ上でも、NETFLIX、YouTube、TikTok、Instagram、ゲームアプリなどさまざまなサービスと可処分時間を奪い合わなければならず、いかにクリックしてもらうかがとても重要になります。
冒頭のブラジャーの記事は、いま多くの企業が取り組んでいるSDGsの一環でもありますが、見出しに「SDGs」や「リサイクル」と入れると、もともと環境問題に関心のない人はまずクリックしません。できるだけ間口を広くするという狙いも、あのタイトルには含まれていたのでした。
17年からは特集企画をスタートさせました。#MeToo、国際女性デー、LGBTQ、ファクトチェックなど、テーマ別に特設ページを設け、継続的に発信しています。量的なインパクトや回遊のチャンスを生み出すためです。こうした取り組みが結果的に、それまで社会課題に関心のなかった人や、若い世代の人たちが、ジェンダーや環境、政治などに関心をもつきっかけになっています。
ここで、「社会課題の解決のためっていうけど、結局はページビュー(PV)を稼ぐためなんでしょ?」という声が聞こえてきそうです。答えはもちろん、その通りです。ページビューが多いということは、すなわちたくさんの人が記事に関心をもってくれたということ。心をこめて書いた記事は、できるだけ多くの人に分け隔てなく読んでいただきたいです。
せっかくなので、メディアビジネスについても触れておきたいと思います。
BuzzFeedはオンライン専業メディアで、購読制でも課金制でもないため、すべての記事を読者に無料で提供しています。
マネタイズ(収益化)の柱は、PV数に連動した収入(広告費・プラットフォーム配信費)と、ネイティブ広告の売り上げです。最近ではアフィリエイトやライセンスビジネス、コンテンツ受託制作などの新しいビジネスも始めています。
先ほど説明した「無関心層や未認知層にタッチポイントをつくる」という私たちの強みは、ネイティブ広告を制作するときにも発揮しています。その商品を見たことも探したこともない大多数の人に商品を知ってもらい、関心をもってもらうきっかけをつくる役割を担います。
例えば、広告記事を「クイズ形式」にしたり、画面上で写真をスライドすることで2枚の写真を比較できる「スライダー機能」を駆使したりと、ユニークな手法で興味をそそり、最終的に「これは◯◯の広告だったのか」と落とし込み、商品の認知度やイメージを向上させます。目指すのは、「企業が届けたいメッセージ」と「読者に読まれる工夫」がちょうど重なる領域のコンテンツをつくり、潜在層に訴えかけること。テレビCMなどとは異なるポジションを担っています。
私たちのユニークな手法に注目した企業から、商品やサービスを宣伝したいというだけでなく、企業のブランドイメージを向上させたいというニーズもいただいています。多くは社会課題の解決につながる内容で、特集企画などで力を入れてきたテーマと方向性がマッチすることも増えてきました。
性的マイノリティーを含むすべての従業員を包摂する企業文化を紹介したい。生理の悩みに寄り添うサービスが生まれた経緯を伝えたい。男性社員の育児休業を推奨し、自社だけでなく業界や社会を変革したい――。企業の担当者と話していると、自社のビジネスの範囲内、または延長線上で、本気で社会変革を目指しているということがわかり、胸が熱くなります。
 BuzzFeed Japanのオフィスの様子
BuzzFeed Japanのオフィスの様子人の役に立つ仕事がしたい。自分や大切な人の幸せな未来のために働きたい。自社の商品やサービスを通して社会をよりよくしたい。それぞれがひとりの生活者でもある企業人の、健全な社会活動だと思います。
そんな働く人たちの熱い思いを広めたくて、20年3月に企画したのが、就職や転職を考えている学生や社会人向けのイベント「未来をつくる仕事のこと〜就活で聞けないリアル〜」です。若い世代に、未来をよくするために働いている大人たちがいることを知ってもらい、仕事を選ぶときの参考にしてもらえたらと、OB訪問のイベント版のようなスタイルを考えました。
取材などでお付き合いのあった企業にイベントの企画書を送り、営業の担当者とともにプレゼンに出向き、イベントの趣旨に共感してくださった13社から協賛・協力をいただくことができました。残念ながら、新型コロナウイルスの感染拡大によって会場での開催こそ叶いませんでしたが、オンラインでイベントを配信することができました。
このイベントを機に、私自身は企業とのコラボレーションをより積極的に推進したいと考えるようになりました。組織改革のタイミングで「BuzzFeed Japan News」の編集長を退任し、20年11月からは別媒体である「BuzzFeed Japan」の編集長(Head of Content)になりました。
「BuzzFeed Japan News(いわゆる黒のバズフィード)」がニュース部門としてビジネスと分離した行動規範があるのに対し、生活情報などを発信する「BuzzFeed Japan(いわゆる赤のバズフィード)」では行動上のファイアウォール(制限)はありません。部門の中には、編集記事を制作するチームのほか、ネイティブ広告を制作するチーム、アフィリエイトコンテンツを制作するチーム、企業のオウンドメディアの受託制作に携わっているメンバー、企業の広報担当と関係を築き、ときに広告を受注してくるメンバーらがおり、編集とビジネスを両立して運用しています。
もちろんコンテンツに関しては、編集と広告を混同させることがあってはなりません。広告費や制作費をいただいているコンテンツは明確に分離し、スポンサード表記やPR表記をつけ、プラットフォームへの配信も制限します。行動上は並走しているからこそ、よりハイレベルな倫理観のもと、厳格な運用体制を敷いています。
BuzzFeed Japanが創刊したばかりで小さな組織だったころは、黒と赤が媒体として分かれておらず、統一した価値基準が求められたこともありました。企業とのコラボレーションに価値をおきたいというと、社内で肩身の狭い思いをしたこともあります。黒と赤が媒体として分離されたことで、取材としてやったほうがよい場合、ビジネスとしてやったほうがよい場合を明確に舵取りできるようになり、それぞれで最大のインパクトを生み出すことができています。
さらに、21年5月にハフポスト日本版と合併したことによって、テキスト系のメディアは3媒体となり、月間のユニークビジター(UV)は延べ5900万人となりました。
ハフポスト日本版はSDGsについて積極的に取り組んでいるメディアです。生配信番組「ハフライブ」で毎月、季節の話題をもとにSDGsについて話し合ったり、SDGsガイドブックを無料配布したりしています。
SDGsの情報を積極的に求める人に向けたハフポスト、SDGsと言われてもピンとこない人に向けたBuzzFeed、と情報発信の棲み分けができています。特に広告においては、両媒体の特性を生かして役割分担をすることで、未認知層から顕在層までさまざまなレイヤーの人たちに、広くリーチすることができるようになりました。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください