長谷部恭男 早大教授に聞く
2022年05月02日
海外の研究者との幅広い人脈を持ち、米国の大学でも教鞭をとるなど、日本を代表する憲法学者の一人として知られているのが、長谷部恭男・早大教授だ。長谷部教授が最近、英語の論文集『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)を出版した。タイトルを日本語に訳すと「まっとうな立憲国家に向けて 日本の立憲主義の軌跡」。近代立憲主義を受け入れ、発展させてきた日本がいま直面している課題を、「主権」「憲法上の借用」「戦争権限と国家緊急権」「司法と憲法の論理」を柱に描いている。今年は日本国憲法の施行から75年。改憲勢力が勢いづいた政界では憲法改正が声高に語られ、一部メディアも作られた土俵の上で踊っている。しかし、冷静に考えたい。改憲を論じる前に向き合うべき憲法上の問題があるのではないか。ジャーナリズムはそれを伝える責務があるのではないか。まっとうな憲法報道のために何を考えるべきか、長谷部教授に話を聞いた。(聞き手 朝日新聞編集委員・豊 秀一)
――『Towards a Normal Constitutional State』というタイトルに込めた狙いを教えてください。
長谷部 Normalということばは「標準的」とも「正常な」とも訳すことができます。私の意図としては、「正常な」に力点があります。「まっとうな」と言い換えてもいいでしょう。正常な国家と異常な国家があります。異常な国家の典型は全体主義国家です。公と私の区分を認めず、個々人が心の中で何を考えるかさえ、国家がすべて支配しようとします。
 長谷部 恭男(はせべ・やすお)
早稲田大学法学学術院教授、東京大学名誉教授
長谷部 恭男(はせべ・やすお)
早稲田大学法学学術院教授、東京大学名誉教授――国家が公と私の区分をきちんとできているということ。つまり、立憲主義が確立されているかどうかがその基準になるということですね。今の日本の現状をどう診断されていますか。
長谷部 立憲主義ということばには、大きく分けて2通りの意味があります。一つは、憲法によって政治権力を縛るという最低限の意味です。もう一つは、さまざまな価値観・世界観を抱く人々が社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う国家を実現するという、より濃厚な意味です。近代立憲主義と呼ばれることもあります。戦後の日本では、研究者も西洋で立憲主義が生まれた歴史を真剣に研究してこなかったこともあり、後者の側面が軽視されてきたように思われます。もっとも最近では、前者の最低限の意味もかなり怪しくなってきていますが。
――前者についていえば、安倍晋三政権による集団的自衛権に関する憲法9条の解釈変更とか、臨時国会召集義務を定めた憲法53条後段を平然と無視するとか、憲法に縛られない振る舞いが散見されるといったことでしょうか。
長谷部 そうですね。
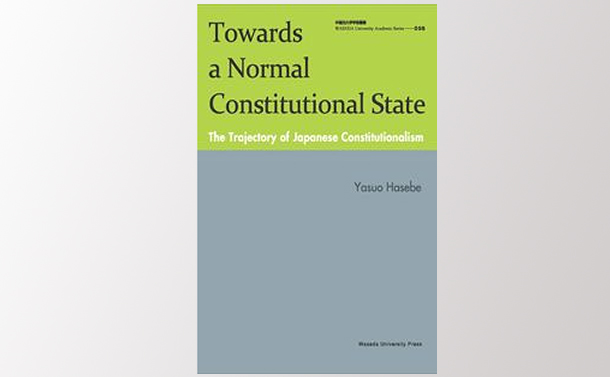 長谷部恭男教授の新著『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)の表紙
長谷部恭男教授の新著『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)の表紙――立憲主義に反する振る舞いが目立つ一方で、憲法9条を変えて自衛隊を明記すべきだとする主張や、新型コロナウイルスなどの危機に対応するために緊急事態条項を憲法に新設すべきだといった主張が繰り返されます。自民党は改憲を訴えるために全国行脚(あんぎゃ)も始めました。とにかく憲法を変えたいという意思は伝わってくるのですが、中身をみると、改正の必要性が合理的に示されているようには思えません。
長谷部 新著にも書きましたが、新型コロナウイルスの感染拡大をコントロールし、防ぐという公共の福祉の実現のためにやむを得ない限度で、法律で人々の活動に制限を加えることに憲法上の問題はありません。感染症対策のために憲法を改正し、緊急事態条項を設けるべきだという一部政治家の主張に根拠はありません。あまり深く考えもせずに、戦争などの危機にあたって憲法に例外状態を作る、つまり国家緊急権を政府に与える緊急事態条項を憲法に書き込もうと考えているとしたら、とても危険です。ナチス独裁に道を開いたワイマール憲法の経験が示しています。緊急事態という言葉の中身を整理し、丁寧に伝えることがメディアに求められているのではないでしょうか。
――新著で、安倍政権による憲法9条の解釈変更は、憲法の基本的な価値への攻撃であり、自滅的であると指摘されています。どのような視点で9条をめぐる議論を報じていくことが大切でしょうか。
長谷部 フランスの政治哲学者、ジャン・ジャック・ルソーは、戦争における攻撃目標は、敵国の社会契約、つまり憲法だと言っています。言い換えれば、国を守るということは、つまるところ憲法を守ることです。人々の命や財産を守ることだけが大事だというのであれば、自分たちの命をかけて戦うことは合理的とは言えません。どのような社会を危険を冒してでも守りたいのか、ということを真剣に考えるべきだと思います。安倍政権による憲法9条解釈の変更に問題点が大きいのは、そうした真剣な問いかけがないまま、立憲主義という核心的価値を攻撃したという点にあると考えています。
――どのような社会を守るのかという点では、戦争中に特攻隊員として出撃して亡くなった人々は何のために命を落としたのかということを、考えざるをえません。
長谷部 特攻隊は、爆弾を装着したままパイロットもろとも体当たりする生還を期さない作戦です。そんな状況にまで追い込まれていたのであれば、日本国民の命を守るのが大切であったのなら、降伏するべきでした。それでも戦争を続けたのは、天皇制を守るためでした。そこで守ろうとしたのは、天皇を頂点とする国を愛することが一人ひとりの内心に強制され、異論を唱えれば非国民として排除されるという、公私の区別のない「異常な国家」でした。第2次世界大戦は、公私の区別のない全体主義と、公私を区別する立憲主義(リベラルデモクラシー)との戦いだったのです。
――ロシアのウクライナ侵略に世界中から注目が集まっています。プーチン大統領は、リベラルデモクラシー体制を目指すウクライナの現在の政権を変える意図を明確にしています。この戦争は、ロシアによるウクライナの憲法原理への攻撃と見ていいのでしょうか。
長谷部 そうですね。現在のロシアは、典型的な全体主義国家とは言えないかもしれませんが、国民に供与される情報を統制し、ある程度の生活水準の維持と引き換えに、ロシアの栄光ある伝統の復活を目指す現政権への忠誠を求める権威主義国家ではあります。ヨーロッパ流の立憲主義国家を目指すウクライナの現政権を倒して自国の勢力下に置こうとしているわけですから、体制変更を恐れるウクライナの人々が必死で抵抗するのは当然でしょう。
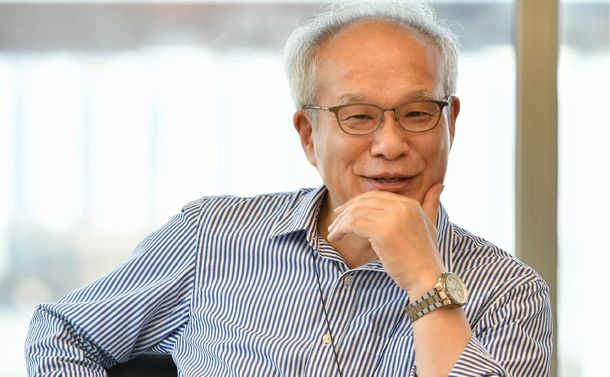 座談会で発言する長谷部恭男・早大教授
座談会で発言する長谷部恭男・早大教授――最近、国民の命を守るために、敵基地攻撃能力を持つことが必要だということを言い始めている一部の政治家がいます。ウクライナ危機に乗じて、「核共有」の議論をすべきだとも言い出しています。この点はどう考えたらいいでしょう。
長谷部 国民の生命と財産を守ることは、政府の第一の役割であることはいうまでもありません。だからといって、敵基地攻撃能力を持つと威勢のいい物言いをすることが本当に国防に資するかはよく考えたほうがいいでしょう。そもそも、敵基地攻撃能力を保有することで、「現実的」に考えて何を「抑止」するというのでしょうか。イスラエルが核兵器を保有していることは公然の秘密ですが、第4次中東戦争ではそれでも亡国の危機に瀕するところでした。米国が軍の警戒体制をDefcon(Defense Condition)4から3に引き上げ、大陸間弾道ミサイルの発射も準備されましたが、何とか米ソを巻き込んだ核戦争は回避されました。
戦後の世界各地で起きた限定戦争を見ても、結局ものを言ったのは、抑止ではなく、前線の勝敗でした。どのような状況を想定してどの程度のコストをかけて防衛力を整備するのか。特定の「能力」を持つことがかえって周辺諸国の軍備増強をもたらさないか。「敵というのは我々のことか」という構えを他国にとらせるリスクをどう考えるのか。様々な要素を冷静に考える必要があります。憲法9条との関係では、従来の急迫不正の侵害行為に対する必要最小限の「対処」を超えて敵の攻撃の「抑止」をはかろうとするもので、専守防衛の域を超えているのではないかという懸念も生じます。しかし、ここで考えなければならないのは、憲法9条に違背するかどうか以前の問題なのです。
――ロシアがウクライナを侵略している現実が、日本国内の9条論議に示唆(しさ)を与えることはありますか。
長谷部 9条は国家間に対立が生じたとき、双方が対等な立場で、いずれの主張に理があるかを「決闘」によって決着をつける戦争、つまり「国際紛争解決の手段としての戦争」を放棄し、そうした戦争の遂行能力である「戦力」を否定することに眼目があります。同じく国際紛争解決の手段としての戦争を違法化した不戦条約(1928年)も、自国への急迫不正の侵害に対処するための自衛権の行使は排除していません。9条も立憲主義を基底とする現在の日本の政治体制を守るために必要最小限で実力を行使することを認めていることを、思い起こさせてくれていると思います。自衛隊の存在を憲法に書くために9条を改正すべきだという一部の政治家の主張がありますが、それを額面通り受けとめるとすると、まったく必要性の欠けた見解だと言わざるをえません。
――日本の憲法論議が不思議に見える一つに、国家が頭の中にある約束事に過ぎないという基本的な視点が共有されていないことがあります。例えば、自民党の憲法改正草案の前文は「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家」という書き出しで始まります。右派の団体の改憲案に見られる傾向ですが、単数の民族、土地、血のつながりでできているものを国家と考えているかのような印象を受けます。
長谷部 日本という社会に長い歴史があり、固有の文化があることは確かでしょう。相撲とか短歌とか歌舞伎とか。ただそうしたものと、国家は区別しなければなりません。憲法が想定している国家は、人々が約束を取り結んでできた国家、つまり、「res publica(共和国)」のことを言います。この世には、相互に両立しない、どちらがより善いか悪いかを判定する共通の物差しもあり得ないような多様な価値観・世界観を抱く人々が現に存在します。人々をその価値観・世界観によって不当に差別しない社会を構築しようとすれば、社会全体の利害にかかわる公の問題と、個々人が自分で判断すべき私の問題とを切り分け、国家の役割を公の問題に限定する必要があります。「res publica」とは、公の事柄を扱う仕組みでもあります。
――ただ、そうした考えがなかなか日本社会、そしてジャーナリズムの世界ですら、十分に浸透していない気がします。
長谷部 歴史や文化があるということと、国家とを混同し、同一視してしまうとやっかいな問題が生じます。国家が個々人のものの考え方まであれこれ評価して、多数派にとって気にいらないことを言う人に対しては「非国民」だというレッテルを貼る態度に流れがちです。自分の世界観・歴史観は正しい、誰もがそうした世界観・歴史観を抱くべきだというのは、人としては自然の心情ですから、そのまま放っておくと、近代立憲主義はすぐに壊れてしまいます。
――実際、明治憲法で近代立憲主義を採用しながら、天皇機関説事件などを経て、日本の立憲主義は壊れてしまいました。日本は他国に例のない万世一系の神聖な王朝が続き、さかのぼると神に至るすぐれた国柄であるといった神権的国体論が猛威を振るいました。
長谷部 よく皇室の長い伝統とかいいますが、明治時代に人為的に作られたものです。憲法上の制度としての天皇主権は、君主制原理と呼ばれる19世紀のドイツの国々からの直輸入で、舶来品です。天皇をありがたい伝統と国民が思わされているのも、当時の伊藤博文たちがキリスト教にかわるものとして意図的に広めたものに過ぎません。
――伊藤といえば、憲法草案を審議する枢密院で、「(欧州のような宗教がない)我が国に在りて機軸とすべきは独り皇室あるのみ」と話したというのが有名です。
長谷部 伊藤たちが皇室を利用した背景は、『明治革命・性・文明――政治思想史の冒険』(渡辺浩著、東京大学出版会)を読むとよく理解できます。それによると、明治の岩倉使節団が欧米を回った際、文明国である欧米の人々がキリスト教を深く崇敬しているように見えることに疑問を抱きます。キリスト教の内容は荒唐無稽の愚かしいものにしか思えないのに、どういうわけか、と。使節団が至った結論は、宗教とは、欧米の指導者たちが「愚民ヲ使役スル」「権謀」であり、「仮面」だったということです。世間的な道徳を一般大衆に教え、安定した社会をつくるための手段として機能しているとみたわけです。そこで日本はどうするかというときに、宗教のかわりに当時の指導者が見つけたのが皇室でした。天皇がいないと国が成り立っていかないからと、キリスト教のかわりに天皇への崇敬を教育として広めたわけです。やがて、伊藤たちの意図を離れて、国体論が自己展開していって、為政者がコントロールできなくなります。公私の区別がついになくなり、戦争に突入していったわけです。
――日本国憲法で天皇は象徴になり、国民が主権者となりました。天皇は「象徴」に過ぎないにもかかわらず、メディアによって特別の価値を持つ存在として扱われ、国民主権の原則と緊張関係をはらんでいるように思います。「陛下」や「さま」という敬称使用をメディアがまずやめることが、天皇制を冷静に報じていく一歩になるような気がしていますが、いかがでしょうか。
長谷部 天皇制という「特権」と「固有の義務」のある一種の身分制と、すべての国民を平等に扱うという現憲法の基本原理との間に緊張関係があることは確かです。それでも天皇制が、紆余曲折がありながらも、抽象的な約束ごとにすぎない「日本国」の象徴としての役割を果たしてきたことについては、歴代の天皇や皇族の「象徴であろう」とする努力の積み重ねという点もあると思います。こうした天皇制を支えるエスプリ・ドゥ・コールが失われれば、天皇制の将来は危ういでしょう。この問題は、周囲が心配してもきりのない話です。皇族の人たちが次々皇室から「脱出」をしたり、世間から皇族に期待される行動や態度を示すことをやめ始めたりしたら、制度は持続しないと思います。それを考えると、報道にあたって敬称をやめるかどうかは、むしろ2次的なことなのかもしれません。
――改憲論議の前に、目の前で様々な統治機構上の憲法問題が起きています。例えば、7条解散をめぐっては、ときの政権が都合のよい時にいつでも解散権を公使し、政権の延命の手段として使っています。ところが、日本のメディアの多くは、疑問を持たずに解散権を「首相の専権事項」と表現しています。憲法53条後段で定められた内閣の臨時国会召集義務が平然と無視されるという明白な憲法違反が繰り返されているのに、問題視する報道が少ないのも気がかりです。
長谷部 首相の判断一つで解散時期が決められるという政治制度は、ヨーロッパ各国を見渡しても分かる通り、かなり特殊な制度です。憲法53条の規定にもかかわらず、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上」の要求を無視して臨時国会を召集しないことは、明白な憲法違反でしょう。その時々の党派間の対立のレベルを超えた、すべてのプレーヤーが共通して守るべきルールがあるという観念が蒸発してしまっているのではないでしょうか。記者たちが日本だけを見ていると当たり前のように映ることでも、海外の運用にも目を向けたりしながら、視野を広げることも必要ではないでしょうか。
――統治機構の問題に関して、社会部で司法を担当していた者として、自分の反省も込めてお伺いします。最高裁が憲法問題に積極的に踏み込まないこともあって、権力分立における司法の機能をどう考えるかという視点からの報道が弱い気がしています。
長谷部 これは、最高裁が自分たちの役割が何だと考えているかという自己意識とも関係しています。藤田宙靖(ときやす)・元最高裁判事は著書の中で、最高裁の裁判官たちは、自分たちの第一の役割は、個々の事件に適切な解決を与えて、当事者を救済することだと考えていると述べています。おそらくそうなのでしょう。すごく困っているかわいそうな人たちがいないと思われる事件については、踏み込んだ判断をしないし、結果、メディアも報道に力を入れないことになります。ただ、最近の最高裁は、法制度の改革が必要だというシグナルを出しても国会がそれに応えないという問題では、積極的な判断を下す姿勢を見せています。典型は非嫡出子法定相続分違憲決定ですね。
――米国を見ると、故ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事など顔の見える裁判官がいて、憲法の番人として「アイコン」になっています。日本はときに「顔もない名もない司法」といわれ、存在感が薄いです。憲法の考え方が社会に根づかない一因ではないでしょうか。
 大学のイベントで演説する米最高裁の故ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事=2019年9月、ワシントン
大学のイベントで演説する米最高裁の故ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事=2019年9月、ワシントン――米国では連邦最高裁のスティーブン・ブライヤー判事が引退することを表明し
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください