戦争の「盾」~ジャーナリズムの責任~(5)
2023年03月28日
都内の大学で、戦争とジャーナリズムについての講義を10年近く続けている。扱うのは第1次世界大戦からイラク戦争までの約100年で、どのような戦争が起きたのか、メディアはそれをどう伝えたのか、がテーマである。毎年、講義を始めるにあたって次のような話をしてきた。
「第2次世界大戦が終わってからの時代は、人類の歴史の中で、まれな繁栄と安定の時代でした。米ソの間で冷戦はあったのですが、二つの超大国同士が正面から戦うことはありませんでした。しかし近年、その戦後の平和を支えてきた国際秩序がきしみ、世界は再び不安定になりつつあります。過去100年の戦争の歴史を学ぶことは、これからの時代を生きるみなさんにとって不可欠の教養と言ってよいでしょう」
年を追うに従って、開講の辞が現実味を増してきた。昨年2月にロシアがウクライナ侵攻を始めたことで、私の恐れは決定的になった。
 ウクライナ軍とロシア軍が戦った通りには破壊された装甲車両が残り、焼け跡が黒くついていた=2022年4月8日、ウクライナ・キーウ近郊ブチャ
ウクライナ軍とロシア軍が戦った通りには破壊された装甲車両が残り、焼け跡が黒くついていた=2022年4月8日、ウクライナ・キーウ近郊ブチャ国境を突き破って進む戦車、崩れる建物、逃げまどう人々。現地からの映像に言葉を失った。この大規模な地上戦は、どこまで世界を揺さぶるのだろうか。
昨年私が行った講義は、こうしたウクライナの戦争の展開と同時進行だった。ただし授業では、直接戦争の解説はせずに、これまでの戦争の歴史を学ぶことに徹した。なぜならば、ウクライナで起こっていることのほとんどは、20世紀の戦争に何らかの先例があり、過去を学ぶことが、現代を深く知る助けとなるからだ。
たとえば、近現代の戦争を貫く三つのポイントをあげてみよう。
ひとつは、多くの戦争が、相互の恐怖心や相手の意図の読み違いから偶発的に始まっていること。次に、戦争という異常な環境の中で、人間の判断力がマヒし、一般市民の虐殺が繰り返されること。そして、戦争の最初の犠牲者は「真実」であること。指導者は不都合な真実を隠そうとするし、メディアも愛国心にあおられ、自国が始めた戦争について批判的に考えることは難しくなる。
いずれも現代の戦争に当てはまることではないか。
以下、この原稿で展開するのは、ウクライナ侵攻から1年の時点で、困難な時代を生きる若者たちにどうしても伝えたいメッセージをまとめた架空の講義である。実際の講義のように時系列ではなく、歴史から学ぶべき教訓を柱にすえて、多少時間軸を行き来しながら進めてみる。講義の中で取り上げる書籍や映画は、最後に詳しく情報を再掲載する。
では、しばし講義にお付き合いください。
みなさん、こんにちは。きょうは戦争の歴史について話をします。昨年のロシアによるウクライナ侵攻以来、報道やSNSの世界では悲惨な映像があふれていています。「もう見たくない。戦争の話はうんざり」という声も聞きます。一方、「なぜこんな戦争が起きたのだろうか。世界はまた戦争の時代に突入するのだろうか」という不安も聞こえてきます。両者とも、もっともな反応でしょう。また、昨年の授業では、第2次世界大戦の映像を見た学生から、「昔もウクライナと同じことがあったのですね」という感想も聞きました。ちょっとびっくりしましたが、戦争の歴史に関心を持つきっかけになればよいことです。
この講義のねらいは、そういう様々な感想を持つ学生のために、戦争というものを考える視点を提供することです。みなさんは高校で世界史や日本史を学んだことがあるでしょうから、「戦争についてはだいたい知っているよ」と思う人もいるかもしれません。しかし、受験のための歴史の勉強には、大きな落とし穴があります。
それは歴史をすべて因果関係の連鎖で理解してしまうことです。この戦争が起きたのは、こういう原因があったからだ、という具合です。こうした歴史理解だと、すべて起きたことは起こるべくして起こった、必然だったということになってしまいます。しかし、実際の歴史上の出来事は、決定をした指導者の思い込みや価値観など様々な要因で決まります。極度の緊張下で迷った末の決定だったり、偶然が絡んだりすることも多いのです。
第1次世界大戦の始まりを描いた『八月の砲声』(バーバラ・タックマン)という優れたノンフィクションがあります。その中に、2人のドイツの指導者が、開戦後出会ったときに、1人が「なんで戦争が始まったのだろう」と問い、もう1人が「それがわかればねえ」と答える場面があります。第1次世界大戦は、だれもあのような大戦争を求めていなかったにもかかわらず、互いの意図の読み違いと軽率な判断が重なって起こったのです。
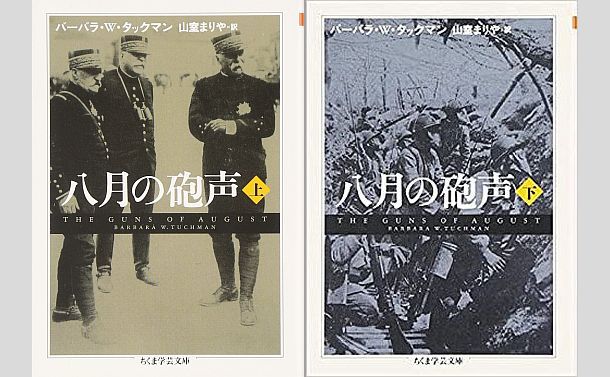 『八月の砲声』(バーバラ・タックマン著、 山室まりや訳、ちくま学芸文庫)
『八月の砲声』(バーバラ・タックマン著、 山室まりや訳、ちくま学芸文庫)第1次大戦は、史上初めて全貌が映像に記録された戦争です。映画は誕生してまもない若い技術でしたが、各国が記録用として、国民の愛国心を鼓舞するための宣伝用として、さかんに活用しました。残っている映像からは、開戦に熱狂する民衆の姿が見て取れます。19世紀初頭のナポレオン戦争以来、ヨーロッパ大陸全体を巻き込む戦争はありませんでした。戦争は、勇ましい英雄物語として美化され、若者は、自分たちもその伝説に参加できると思って、興奮したのでした。イメージしていたのは、まず大砲で撃ちあい、騎兵隊が突入し、勝敗がすぐさま決まる戦争でした。第1次大戦が1914年夏に始まったとき、各国とも数週間の戦争を想定していました。
だが、戦争は4年以上続きました。兵士たちを待っていたのは、ロマンあふれる冒険ではなく、鉄条網と機関銃、そして最後には戦車と毒ガスの洗礼でした。ナポレオンの時代から1世紀の間に、欧州各国では政治の民主化と産業革命が進み、徴兵制に基づく巨大な国民軍と恐るべき殺傷能力を持つ兵器が生まれていました。それが何をもたらすかについて、指導者も国民も想像できなかったのです。
戦争は、前もって思い描いたような道筋をたどりません。コントロールが効かなくなり、終わらせることが極めて難しくなります。こうした戦争の本質を表す「戦争の霧(Fog of War)」という言葉があります。歴史の授業で学ぶ過去の戦争は、原因も経過も結果もきれいに整理されていますが、戦争の当事者には周りの状況もわからないし、見通しも立ちません。実際の戦争とは、霧の中を手探りで進むようなものなのです。
1960年代にアメリカのケネディ、ジョンソン両政権で国防長官を務めたロバート・マクナマラ(1916~2009年)という人物がいます。
彼が国防長官になってまず直面した重大事件は、1962年のキューバ危機でした。始まりは、アメリカの「裏庭」とも言うべきカリブ海のキューバに、革命家フィデル・カストロの率いる社会主義政権が誕生したことです。ソ連はキューバでミサイル基地の建設を始めました。アメリカ全土がソ連のミサイルの射程距離に入ってしまいます。
アメリカ軍首脳はキューバ攻撃を主張しました。核弾頭がキューバに持ち込まれないうちに叩いてしまおうという作戦でした。ケネディ大統領は迷いましたが、結局軍部の提言を退け、代わりに米軍艦船によるキューバの海上封鎖を選択します。そのうえで粘り強い交渉でソ連の基地撤去を実現しました。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください