廃刊となる「法と経済のジャーナル」へのレクイエム
2023年03月28日
朝日新聞社のインターネット新聞「法と経済のジャーナル Asahi Judiciary(AJ)」廃刊にあたり、創設からかかわった者として、末筆ながら、「AJと私の13年」を振り返らせていただきます。正直に言うと、AJが13年も続くとは思っていませんでした。続いたこと自体が「奇跡」だと考えています。
 AJ創刊に関する2010年6月18日の社内会議資料の一部
AJ創刊に関する2010年6月18日の社内会議資料の一部朝日新聞の編集担当役員だった吉田慎一さん(その後、テレビ朝日ホールディングス社長で退任)から、そういう提案があったのは2009年春。
朝日新聞では翌10年4月からインターネット上の情報発信をデジタルメディア「アサヒコム」のほかにも拡充し、新たなウェブマガジンのプラットフォームを創設する計画があった。そこに載せるウェブマガジンのひとつとして、法律や経済関係のコンテンツを扱うマガジンを作れないか、という話だった。
当時、私は朝日新聞の夕刊連載「昭和報道検証」でロッキード事件を取り上げるため、田中角栄元首相の番記者だった吉田さんに何度か話を聞きに行き、問われるまま、経済事件取材を通して見えた護送船団体制の崩壊、それに伴う「市場化社会・法化社会」の到来などを話していた。
それが吉田さんの頭にあったのかもしれない。「うまくいけば、スピンオフしてその会社の社長になってもいいんじゃないか」とも言われた。
※ ※ ※
おもしろいと思った。社長になることにはまったく関心がなかったが、ウェブジャーナルというフロンティアに興味があった。
経済事件記者として長年、企業が絡む紛争の代理人、弁護人を務める弁護士や企業法務関係者を取材してきた。特に、独占禁止法や証券取引法(現金融商品取引法)の整備が進み、「法化社会」化が顕著になった2000年代、企業法務を扱う大手のローファーム(渉外弁護士事務所)は情報の宝庫だった。
同時に、その世界では、裁判関係の情報に対するニーズが膨れ上がっていた。そこをターゲットにした情報誌を立ち上げれば、双方向でより深い情報源を開拓でき、より深い調査報道記事や解説記事を書けるのではないか。さらに、関連情報商品(裁判資料)などを扱えば、法曹界や企業法務で固定読者を獲得できるのではないか――と考えたのだ。
しかも、そのメディアでは、どうやら編集権が自分のものになりそうだ。つまり、書きたいことが好きなだけ書ける。それはとても結構なことではないか、とも思った。
さっそく、「相棒」の奥山俊宏記者に連絡をとった。奥山記者とは90年代初めから経済事件などの調査報道を一緒に行ってきた。09年3月から、ロッキード事件に関する米国の機密指定解除資料の収集や関係者のインタビューなどいくつかのミッションを持って米国のアメリカン大学に留学中だった。
奥山記者も興味津々だった。9月に帰国するのを待って、2人で具体的な立ち上げ作業を始めることにした。
※ ※ ※
ロッキード事件の報道検証取材と並行して、朝日社内でマガジンのコンセプトの整理、ビジネスモデルの構築準備を進めた。マーケットリサーチ、記事商品作成、発信のデジタル技術の習得。詳細は省くが、吉田さんが敷いたレールに沿ってどんどん、話は具体化していった。名前は「法と経済のジャーナル(AJ)」と決めた。
 AJ創刊に関する2010年6月18日の社内会議資料の一部
AJ創刊に関する2010年6月18日の社内会議資料の一部専従(本社業務と兼務)は私と奥山記者の2人。私は10年11月に60歳定年(当時)を迎えるため、奥山記者がマガジンの責任者になった。私は、自分のコラム「事件記者の目」を持ち、最大手のローファーム・西村あさひ法律事務所の有志の弁護士さんに定期的に法律関係の時事コラムを書いてもらう「西村あさひのリーガル・アウトルック」の編集を担当することになった。それ以外の業務はすべて奥山記者が行うことになった。
しかし、正直に言うと、構想段階で、AJはすでに挫折していたと思う。AJは朝日の傘下にあるとはいえ一応、課金ビジネスを営む独立採算の組織である。赤字経営はできない。そのためには読者獲得のための営業をしなければいけない。ところが、私にはその気がない。奥山記者も同じだった。つまり、AJはビジネスマインドがない2人に委ねられて船出したのである。
とはいえ、2010年7月21日の最初の紙面(画面)は相当気合を入れて作った。ニュース解説記事が売りの「深掘り」では、当時まだ燻っていた鳩山由紀夫前首相の政治資金問題を掘り下げ、「検察、憲法の大臣不訴追特典を意識 昨年暮れの鳩山氏の取り調べ見送りで」を掲載した。これは奥山記者との共作だった。
さらに、それに関連して私のコラム「事件記者の目」で「鳩山前首相本人の量的制限違反容疑と相続税法違反容疑 憲法の不訴追特権が外れた今こそ検察は捜査でけじめを」を掲載した。処分当時の検察幹部や国税幹部に何度も確認取材をした。
それに証券取引等監視委員会の佐渡賢一委員長インタビュー「『検察支配』からの解放で監視委が活性化」(4回連載の1回目)。この連載は、「よくあそこまで本音を引き出しましたね」と旧知の日経新聞記者から褒めてもらった。
実は、佐渡委員長のインタビューと前後して、この年6月に検事総長を退官したばかりの樋渡利秋さんのロングインタビューも行った。これは、その直後に大阪地検特捜部の検事による証拠改竄事件が発覚したのを受け、樋渡さんから「ちょっとタイミングが悪いので記事はしばらく待って」と要望があり、お蔵入りにした。
樋渡さんはその不祥事の舞台となった村木厚子元厚労省局長の無罪事件、さらに東京地検特捜部が同様の不祥事を起こした小沢一郎元民主党代表が政治資金規正法違反に問われた事件の捜査を検事総長として指揮していた。そろそろ、蔵のカギを開けねばならない。
※ ※ ※
本来、「記者の目」は軽いタッチの短文のコラムにするつもりだった。ところが、いざ、書き始めると、何をどう書いても、どんどん長くなる。文章センスがないことを改めて思い知り、「文章修行」はあきらめた。
毒を食らわば皿まで。紙幅に制限のないウェブメディアの特性を生かして納得がいくまで長文の連載記事を書くことにした。読者にはご迷惑だったかもしれないが、その「成果」が「特ダネ記者が今語る特捜検察『栄光』の裏側」(14~15年、22回)、「警察・検察 vs.工藤会」(16年、8回)、「オウム真理教事件の教訓」(18年、4回)、「関西電力元副社長・内藤千百里の証言」(19~20年、8回)だった。
「深掘り」でも、同様のスタイルで「金丸事件:特捜部長と金庫番が語る20年目の真実」(2012~13年、10回)を連載した。これらは、単行本を上梓するとき、執筆のベースとなった。
「西村あさひのリーガル・アウトルック」の原稿は当初、いただいた原稿に、私が編集部としてのリードをつけ、本文も、一般読者が読みやすい表現に書き直し、筆者の確認を得て掲載していた。
当初は毎週1回掲載だった。専門的な法律問題も多かった。一から勉強しないとわからないテーマもあった。原稿を読み込み、リードをつけるのは簡単な仕事ではなかった。しまいには「千本ノック」を受けているような感覚になった。
リーガル・アウトルック原稿の一部は、その後、「会社を危機から守る25の鉄則」(14年5月、文春新書)として出版された。
西村側で窓口になってくださったのは、独禁法問題の有数の専門家である川合弘造弁護士だ。2006年のリーニエンシー制度導入のころから取材でお世話になっていた。マガジンのコンセプトをお伝えし、所属弁護士さんに交代で時事の法律問題での寄稿をお願いしたところ、快く引き受けていただいた。
川合さんは、太田洋、梅林啓、有吉尚哉弁護士とともに、原稿執筆のほか、西村あさひ所属弁護士への原稿発注手配、つまりデスク役を担ってくださった。いずれも企業法務界で知らない者のいない超売れっ子。超多忙の中でのご協力だった。本当にお世話になりました。感謝します。
営業はしない、書きたい記事だけを書く。いわば殿様商法。原稿の大部分は無料で読めるようにした。予想通り、業績は今ひとつだった。購読者は500人あまりで頭打ちに。多大な利益を朝日新聞社にもたらしたとはまったくいえない。冒頭で、「続いたことが奇跡」と書いたのはそのためだ。
ただ、AJは朝日新聞のデジタルプラットホームを使って編集や情報発信を行ってきた。その経費がいくらかは考えたこともなく、実質的にはタダ。寄稿の原稿料も社員は基本ゼロ。社内の情報資材も自由に使えた。外部筆者の原稿料も1本1万円とか5千円とかにしてもらった。その結果、購読者からの定期収入で、おそらく毎月、数十万円の黒字が出ていたはずだ。しかし、私自身はその計算をしたことが一度もない。
AJ「本体」の記者は私と奥山記者だけ。デスクはいない。それぞれの原稿のチェックはお互いにやろうね、ということでスタートした。奥山記者は私の原稿をきちんとチェックしてくれたが、私は奥山記者の原稿をほとんど見なかった。奥山記者の取材力、表現力を信頼していたからだ。
社論と違う記事も時々、出るが、本紙の部数や世論形成力に悪影響があるわけでもない。そういうこともあって、私が知る限り、2017年秋に朝日を退社するまで、社内ではほとんどAJが関心の対象にならなかったと思う。
AJは、ある種、朝日社内での独立空間だった。私は最後まで、本社のどの部門のだれがAJの運営に責任を持っているのか知らなかった。知りたいとも思わなかった。
AJは、私や奥山記者が朝日本紙で書ききれなかった素材を展開する場となっていった。奥山記者は原発事故や内部告発関係でいい記事をたくさん出した。
あまり本紙で記事を書いていない私はストレスを溜めていなかったが、安倍・菅政権による検察首脳人事への介入問題は印象に残る。
2016年9月の法務・検察の幹部人事で、当時の法務事務次官が、官房長の黒川弘務氏を地方の検事長に出し、刑事局長の林真琴氏を自分の後任にする人事案を官邸に打診したところ、黒川氏を事務次官にするよう求められ、やむなく受け入れたことをキャッチした。
当時の菅義偉官房長官らは黒川氏の危機管理・調整能力を高く評価。黒川次官にこだわったのは、政権を安定的に維持すべく、黒川氏を検察のトップである検事総長に起用する布石とみられた。
1970年代から半世紀にわたって、時の政権は、検察を抱える法務省の人事案について口を挟むことは少なくとも表面上はなかった。検察権力ウォッチをテーマにしてきた私にとっては、大ニュースと思えた。
旧知の元検察担当記者が政治部に配属されていた。共同取材で記事にしないかと打診すると「やりましょう」と応じた。しかし、朝日の上層部は「裏付が難しいのではないか」と報道に消極的で話は立ち消えとなった。
ならば、とAJの「記者の目」で「官邸で覆った法務事務次官人事 検察独立の『結界』破れたか」(16年11月22日)を発信した。それを皮切りに、黒川、林両氏の検事総長レースのゴールとなる2020年を見据え、人事の節目で政治介入に警鐘を鳴らす解説記事を書いた。
安倍官邸は、黒川氏を検事総長に起用するため、東京高検検事長だった黒川氏について無理筋の定年延長人事を強行。筋悪の検察庁法改正とも相まって世論の厳しい批判を受ける中、黒川氏が賭け麻雀事件発覚で辞職。結局、林氏が検事総長に就任したのは周知のとおり。その顛末は書籍「安倍・菅政権vs.検察庁」(2020年、文藝春秋社)にまとめた。
私は、毎日新聞で1973年から91年まで約18年間、朝日新聞で1991年から2017年まで約26年間、ほとんど第一線で報道に携わり、フリーとなった今も、同様の活動を続けている。振り返れば、記者になってから今月末でまる50年ということになる。
毎日では新聞記者としての基礎を作っていただいた。朝日では、バブル崩壊後の大型経済事件や構造利権がからむ調査報道の場を与えていただいた。そして、朝日の最後の7年間とその後現在までAJで自由に羽ばたかせてもらった。AJは私にとって第三のふるさとだ。
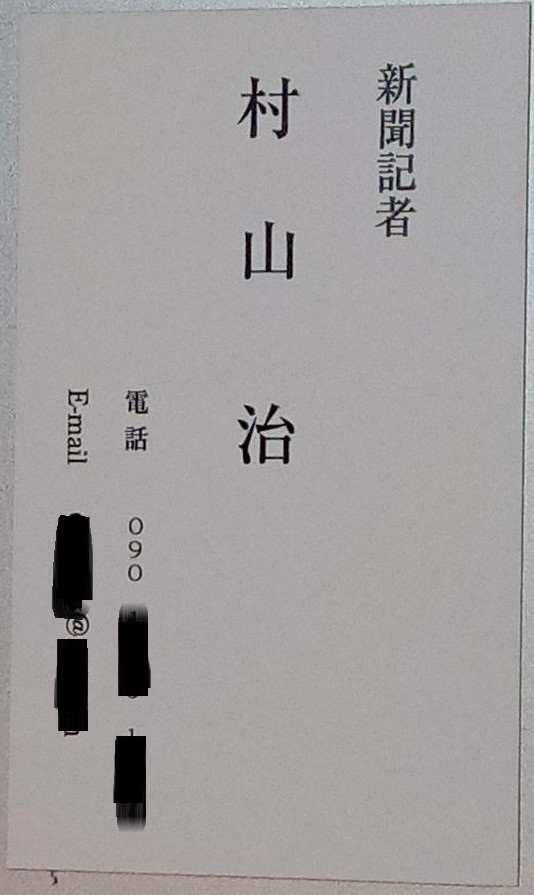
第一、第二のふるさとは「紙のビジネスモデル」の崩壊で疲弊し、見る影もなくなった。第三のふるさともそのあおりで廃刊になった。しかし、AJはなくなったわけではない。奥山記者がいる。紙面(画面)づくりに関わっていただいた多くの寄稿者がいる。読者(視聴者)のみなさんがいる。私もいる。
奥山記者は大学教授に転じたが、今も新聞記者である。私が「新聞記者」などと胸を張っていられるのは奥山記者のおかげだ。朝日を退職したあとも、取材、報道でアドバイスを受け、校閲までやっていただいてきた。私にとって、まさに奥山記者といる空間がAJなのである。
だから、さよなら、とは言わない。みなさま、今後ともよろしくお願いします。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください